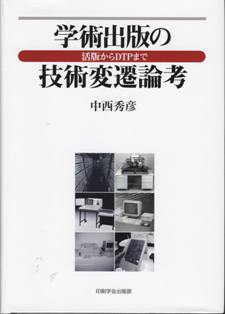「AKB48と“印刷”」 -久保野 和行―
日本古来の芸能に落語があるが、その中でも「風が吹いたら桶屋が儲かる」。荒唐無稽のこじ付け話のストリー展開であるが、妙に納得する、だから落語と言えるのかもしれない。これと似た話をこれからするわけだが、その主人公はAKB48である。
つい最近、ギネス世界記録に認定された「最も多くのポップシンガーがフィーチャーされたビデオゲーム」がある。これで思い出されるのが2009年に出版された「もし高校野球の女子マネジャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら」(作家:岩崎夏海 ダイヤモンド社)が大ブレイクしました。

私自身、これまで多くのドラッカー本は読んだことはあるが、書店に並んだものは、表紙がアニメタッチのマンガ本スタイルに腰が引けたが、購入し一気に読みきってしまった。著者の岩崎氏の、その後のインタビュー等での発言で、AKB48そのものにプロジェクトに関わってきた体験がベースになっている。登場人物が、現実のアイドルに結びつく面白さが共鳴してベストセラーになった背景が良く分かる。
ここでチョットしたエピソードをご紹介します。
お正月に孫(小学校6年生)が来た時に、「もしドラ」を間違えてマンガ本と勘違いして、私の本棚から取り出したが、表紙のアニメから想像していないほどの活字の羅列に驚いて止めるかと思っていたら、あにはからんや最後まで読破してしまった。
感想は面白かったの一言である。本当かなァーと、チョット疑問に思い尋ねると、ドラッカーもマネジメントは良く分からないが、ドラマのストリーは理解したようだ。
岩崎氏が最初に手にしたドラッカー本、「エッセンシャル版マネジメント基本と原則」(P・F・ドラッカー著 上田惇生訳 ダイヤモンド社)。ビジネス界に最も影響力がある思想家として知られる。東西冷戦の終結、高齢者社会の到来をいち早く知らせるとともに「分権化」「目標管理」「経営戦略」「民営化」「顧客第一」「情報化」「知識労働者」「ABC会計」「コアコピタンス」など、主なマネジメントの理念と手法を考案し、発展させた人です。そのような偉大な人物の書いた本からヒントを得て、分かりやすい内容に脚色して展開した物語が「もしドラ」本です。

幾つかの著作物の中で2002年5月に出版された「ネクスト・ソサエティー:歴史が見たことのない未来が始まる」(ダイヤモンド社)がある。

興味を引いたのが政治にコントロールが利かなくなる。国民がダイレクトに情報キャッチできる環境が現出されると表現している。そのドラッカーが自らの出時目を語る文章がある。
私の名前のドラッカーはオランダ語で印刷屋を意味する。先祖は1510年ころから1750年ころまで、アムステルダムで印産業をやっていた。印刷業では長い間何も変化がなかった。16世紀始め以降19世紀にいたるまで、印刷業ではイノベーションといえるものは何もなかった。
偉大な経済学者のロジックの原点が、もしかしたら印刷業の発想DNAの起点かも知れないと考えると、妙に印刷人としてワクワク感を抱いてしまう。同床同夢の勝手な感覚に陶酔して、流行のアイドルAKB48に私自身が親近感を感じた。(終)