市場から消えた新規格のフィルム(2)ラピッドシステムフィルム
印刷図書館クラブ
印刷人のフィルム・フィルムカメラ史探訪 VOL-15
印刷コンサルタント 尾崎 章
1963年3月にイーストマン・コダックが製品発表、同年5月より販売を開始した「コダパック・カートリッジ」とネーミングしたフィルムカートリッジを使用する新フィルムシステム「インスタマチック」は、フィルムをカートリッジ化する事によって「フィルム装填・巻き戻し」の煩わしさを解決した画期的システムとしてカメラ・フィルム業界はもとより需要家層からも大いに注目を集めた。

アグファ ラピッドフィルム
このコダック「インスタマチック」に対抗して当時の西独・アグファは翌年1964年5月にフィルム簡易装填方式「ラピッドシステム」を発表、業界一位のコダックと二位・アグファがフィルム簡易装填市場で対峙する事になった。
*西独・アグファは、1964年7月にベルギーのゲバルト社との合併を実施、社名をアグファ・ゲバルトとしている。
ダブルマガジンのラピッドシステム
アグファは、1937年に同社初の35mmフィルムカメラ「カラート」を発売、この機種にフィルム供給・フィルム巻取り用にカラートマガジンと名付けた共用マガジンを使用するダブルマガジン方式を採用している。

ダブルマガジン方式のラピッドフィルム
「ラピッドシステム」は、このカラートマガジンをベースにフィルム感度設定機能等々の付加機能を追加したものでカラートマガジン仕様の旧型カメラへの適合性も有していた。

ラピッドマガジンと感度端子の無いカラートマガジン(左端)
フィルム巻取り軸の無い「ラピッドシステム」のマガジンには長さ24インチ(約62cm)の35mm(J135)フィルムが収納され、撮影済みフィルムは巻取り側にセットされた同型のマガジンに収納される方式で空になったラピッドマガジンはフィルム収納用として再利用する簡易装填方式である。
撮影枚数は、画面サイズ24×24mmで16枚撮り、24×36mmで12枚撮り、24×18mmのハーフサイズで24枚撮りが可能であった。
フィルム価格は、アグファカラーCT18(カラーリバーサル 1966年 国内価格)が750円でネガカラーフィルム、モノクロフィルムがラインナップされた。
アグファが「ラピッドシステム」用としてフィルムと同時に発売した専用カメラは、コダック「インスタマチック」用カメラと同様に写真ビギナー層を対象とした簡易カメラで、例えば、「アグファ ISO RAPID IF」カメラは、40mm f8の単玉(1枚)レンズ、固定焦点、シャッタースピード1/40秒(単速)、お天気マークと併せてf8とf11を選択する仕様で有った。

アグファ ISO-RAPIDカメラ
同様に富士写真フィルム(当時)が1965年6月に「ラピッドシステム」用として発売した「フジカ PAPID-S」も40mm f11の単玉レンズ、固定焦点、シャッタースピード1/30 1/125秒の2速を御天気マークで切り替える発売当時価格4500円の簡易型カメラである。
このアグファ「ラピッドシステム」に対しては、ツアイス・イコン、ローライ、ライカ、フォクトレンダー、ブラウン、イルフォード、フェラニア等々、ヨーロッパのフィルム及びカメラ15社がラピッドシステム採用の意思表明を行っている。しかしながら、多くがコダックとアグファの両陣営に参加する二股対応を採っており、ラピッドシステム発売開始直後の1964年7月時点でラピッド陣営に参加した3社より6機種のカメラが発売されるにとどまった。
ラピッドシステムの国内対応
国内のフィルム及びカメラ各社はコダック「インスタマチック」に加えて写真需要拡大にアグファ「ラピッドシステム」が寄与すると判断、日本ラピッド会が結成され14社がこれに参加している。
*日本ラピッド会参加企業名(当時)
旭光学、オリンパス光学、キャノン、小西六写真、コーワ、三協精機、東京光学、日本光学、富士写真フィルム、ペトリカメラ、マミヤ、ミノルタカメラ、リコー、ヤシカ
富士写真フィルムは、1965年6月にネオパンSS,ネオパンSSSのモノクロネガフィルム、フジカラーN100(20EX 320円),フジカラーR100(20EX 650円)のネガカラー及びカラーリバーサルフィルムのラピッド判を発売、同時に前述の「フジカRAPID-S」とセレン露出計内臓「フジカRAPID-S2」の2機種を発売して体制を整えている。

フジカラピッド S2
「フジカ RAPID-S2」はフジナー28mmf2.8レンズ(3群3枚)シャッター速度1/30~1/250秒、セレン光電池によるプログラムEE機構、ソーンフォーカス焦点調節 等々当時の35mm普及型カメラと同等の性能を有していた。
この「フジカ RAPID-S2」はカメラ基本性能以外に元・東京芸術大学教授:田中芳郎氏によるカメラデザインが注目を集めた。本機は田中氏が得意とした人間工学に基づいたシンプルデザインの名機で、当時の富士写真フィルム製カメラは田中デザインを多くの製品に採用していた。代表例としては女性向けハーフサイズカメラの傑作「フジカミニ」、小中学生向けの初心者カメラ「フジペット」「フジペット35」、高級レンジファインダー機「フジカ35」等々を挙げる事が出来る。

ブジペット

田中デザイン・フジカカメラ
「フジカ RAPID-S2」(発売当時価格13,000円)はカメラを保持しやすい横長デザインが人気を集め「ハーモニカ・カメラ」の愛称が付けられた程であった。
小西六写真(当時)は、1965年6月にラピッドフィルム・コニパンSSラピッドフィルムとラピッドフィルムカメラ「コニカラピッドM」の発売を行っている。「コニカラピッドM」は、32mmf1.8の高級仕様レンズ、スプリングモーターによる自動巻き上げ等を採用していたがフィルムと共に殆ど市場で見かけない程度の展開にとどまっている。
インスタマチック 対ラピッドシステム
日本ラピッド会加盟した14社は、コダック「インスタマチック」優先か、アグファ「ラピッドシステム」優先かで対応が分かれた、また、日本ラピッド会に加盟した14社の中で日本光学、旭光学等、5社が具体的な対応を見送っている事からも「コダック対アグファ」の見極めが当時としては難しかった事が推定される。
「リコーオートハーフ」でハーフサイズカメラ市場を得意市場化していたリコーは、35mmフィルムを使用するラピッドシステム優先を決めて1965年6月に「リコーEEラピッドハーフ」(発売当時価格14.000円)を発売してハーフサイズカメラ市場強化を試みている。
同様にキャノンも人気商品のハーフサイズカメラ「デミ」のラピッドシステム版として1965年6月に「デミラピッド」(発売当時価格16000円)を発売している。30mmf1.7の高級仕様レンズを搭載したハイスペック機として普及機主体の他社製品との差別化を図っている。
続いてキャノンは同年10月に「デミ」と並ぶスプリングモーターによる自動巻き上げ機能を搭載した人気カメラ「ダイヤル35」のラピッド版として「ダイアルラピッド」(16.000円)の発売を行っている。
しかしながら、キャノンはコダック「インスタマチック」の優勢が明確化した事より「ダイアルラピット」以降のラピッドカメラ展開を中止している。

マミヤ・マイラピッド
中判サイズカメラを得意とするマミヤも「マミヤ・マイラピッド」(16.400円)を1965年5月に発売、武骨なデザイン・中判サイズカメラの同社が発売した洗練されたデザインと5群5枚構成・32mmf1.7レンズ搭載のハイスペック仕様が注目を集めたが、コニカ同様に「最初で最後」のラピッドカメラ製品になっている。

ヤシカハーフ17EE RAPID
大衆機を得意としたヤシカは、1965年6月に「ヤシカハーフ17EE RAPID」(16.500円)
を発売、キャノン、マミヤ等と同様に大口径f1.7レンズを搭載した本機はヤシカフェイスのクロムメッキが綺麗な高級感を持ったラピッドカメラであった。しかしながら、販売は前述リコー、マミヤ等と同様に低迷、1機種のみの市場参入に止まっている。
富士写真フィルムは、1965年12月にキャノン「ダイアルラピッド」を追随する形でスプリングモーターによる自動巻き上げ機能を搭載した「フジカRAPID-D1」(16.000円)の追加発売を実施したが、世界的規模でコダック「インスタマチック」優勢が明確化された事より富士写真フィルムも当該市場からの撤退へと方針変更を余儀なくされている。

フジカラピッド D1
結局、日本ラピッド会加盟14社の中でラピッドカメラを発売した加盟社は、オリンパス、キャノン、小西六写真、富士写真フィルム、マミヤ光機、ミノルタカメラ、ペトリカメラ、
ヤシカカメラ、リコーの9社にとどまった。
ラピッドシステムの終焉
1964年5月に「コダックインスタマチック」を追撃する形で製品化されたアグファ「ラピッドシステム」は、①35mmフィルムを使用 ②カメラメーカー側で画面サイズを選択可能 ③リーダーペーパー無のフィルム平滑性 ④フィルム位置をカメラ側で決められるフォーカス対応性 ⑤インスタマチック方式よりカメラの小型化が可能となる等の特徴を有していた。
しかしながら、ラピッドシステムに対する国内外市場の反応は鈍く販売は低迷、「巨人・コダックの敵にはなれず」という状況に至っている。
コダックは「インスタマチックカメラ」発売1年半後、すなわち「ラピッドシステム」発売年である1964年末までに600万台の販売成果を挙げアグファ「ラピッドシステム」を圧倒した。当時、国内カメラ各社の年間生産総数が320万台弱で有った事から見ても、コダック「インスタマチックカメラ」の快進撃ぶりを判断する事が出来る。
国内では発売初年及び次年度である1964~1965年にかけてカメラ各社が「ラピッドシステム」対応製品展開を実施したもののミノルタカメラ等5社が1機種の市場投入にとどまり、2機種を製品化したキャノン、富士写真フィルム、オリンパス等が1966年より新製品投入を見送り国内市場は約2年間で終息を迎える事になった。
コダックは、126フィルム「インスタマチックフィルム」126フィルムカメラ「インスタマチックカメラ」発売7年後の1970年に開催された「大阪万国博」に生産累計5000万台・記念カメラを寄贈し、コダック製品による当該市場席巻を世界にアピールした。
コダックに敗退したアグファは、1972年に126フィルムカメラ「アグファマチツク50」と4種類の126フィルムを発売して「インスタマチック」陣営への参加を行い、1978年までに11機種の126フィルムカメラを発売している。

ライトパンカラーⅡ・RAPID
アグファ、富士写真フィルム、小西六写真等のフィルム各社がラピッドフィルムの販売から撤退した後も「ライトパン」ブランドで各種短尺フィルムビジネスを展開していた愛光商会(東京・港区)がネガカラーフィルム「ライトパンカラーⅡ ラピッド」(1977年当時 12EX \430)の供給を継続したが、1983年前に生産を終了している。
以上
印刷図書館クラブ
印刷人のフィルム・フィルムカメラ史探訪 VOL-15
印刷コンサルタント 尾崎 章
1963年3月にイーストマン・コダックが製品発表、同年5月より販売を開始した「コダパック・カートリッジ」とネーミングしたフィルムカートリッジを使用する新フィルムシステム「インスタマチック」は、フィルムをカートリッジ化する事によって「フィルム装填・巻き戻し」の煩わしさを解決した画期的システムとしてカメラ・フィルム業界はもとより需要家層からも大いに注目を集めた。

アグファ ラピッドフィルム
このコダック「インスタマチック」に対抗して当時の西独・アグファは翌年1964年5月にフィルム簡易装填方式「ラピッドシステム」を発表、業界一位のコダックと二位・アグファがフィルム簡易装填市場で対峙する事になった。
*西独・アグファは、1964年7月にベルギーのゲバルト社との合併を実施、社名をアグファ・ゲバルトとしている。
ダブルマガジンのラピッドシステム
アグファは、1937年に同社初の35mmフィルムカメラ「カラート」を発売、この機種にフィルム供給・フィルム巻取り用にカラートマガジンと名付けた共用マガジンを使用するダブルマガジン方式を採用している。

ダブルマガジン方式のラピッドフィルム
「ラピッドシステム」は、このカラートマガジンをベースにフィルム感度設定機能等々の付加機能を追加したものでカラートマガジン仕様の旧型カメラへの適合性も有していた。

ラピッドマガジンと感度端子の無いカラートマガジン(左端)
フィルム巻取り軸の無い「ラピッドシステム」のマガジンには長さ24インチ(約62cm)の35mm(J135)フィルムが収納され、撮影済みフィルムは巻取り側にセットされた同型のマガジンに収納される方式で空になったラピッドマガジンはフィルム収納用として再利用する簡易装填方式である。
撮影枚数は、画面サイズ24×24mmで16枚撮り、24×36mmで12枚撮り、24×18mmのハーフサイズで24枚撮りが可能であった。
フィルム価格は、アグファカラーCT18(カラーリバーサル 1966年 国内価格)が750円でネガカラーフィルム、モノクロフィルムがラインナップされた。
アグファが「ラピッドシステム」用としてフィルムと同時に発売した専用カメラは、コダック「インスタマチック」用カメラと同様に写真ビギナー層を対象とした簡易カメラで、例えば、「アグファ ISO RAPID IF」カメラは、40mm f8の単玉(1枚)レンズ、固定焦点、シャッタースピード1/40秒(単速)、お天気マークと併せてf8とf11を選択する仕様で有った。

アグファ ISO-RAPIDカメラ
同様に富士写真フィルム(当時)が1965年6月に「ラピッドシステム」用として発売した「フジカ PAPID-S」も40mm f11の単玉レンズ、固定焦点、シャッタースピード1/30 1/125秒の2速を御天気マークで切り替える発売当時価格4500円の簡易型カメラである。
このアグファ「ラピッドシステム」に対しては、ツアイス・イコン、ローライ、ライカ、フォクトレンダー、ブラウン、イルフォード、フェラニア等々、ヨーロッパのフィルム及びカメラ15社がラピッドシステム採用の意思表明を行っている。しかしながら、多くがコダックとアグファの両陣営に参加する二股対応を採っており、ラピッドシステム発売開始直後の1964年7月時点でラピッド陣営に参加した3社より6機種のカメラが発売されるにとどまった。
ラピッドシステムの国内対応
国内のフィルム及びカメラ各社はコダック「インスタマチック」に加えて写真需要拡大にアグファ「ラピッドシステム」が寄与すると判断、日本ラピッド会が結成され14社がこれに参加している。
*日本ラピッド会参加企業名(当時)
旭光学、オリンパス光学、キャノン、小西六写真、コーワ、三協精機、東京光学、日本光学、富士写真フィルム、ペトリカメラ、マミヤ、ミノルタカメラ、リコー、ヤシカ
富士写真フィルムは、1965年6月にネオパンSS,ネオパンSSSのモノクロネガフィルム、フジカラーN100(20EX 320円),フジカラーR100(20EX 650円)のネガカラー及びカラーリバーサルフィルムのラピッド判を発売、同時に前述の「フジカRAPID-S」とセレン露出計内臓「フジカRAPID-S2」の2機種を発売して体制を整えている。

フジカラピッド S2
「フジカ RAPID-S2」はフジナー28mmf2.8レンズ(3群3枚)シャッター速度1/30~1/250秒、セレン光電池によるプログラムEE機構、ソーンフォーカス焦点調節 等々当時の35mm普及型カメラと同等の性能を有していた。
この「フジカ RAPID-S2」はカメラ基本性能以外に元・東京芸術大学教授:田中芳郎氏によるカメラデザインが注目を集めた。本機は田中氏が得意とした人間工学に基づいたシンプルデザインの名機で、当時の富士写真フィルム製カメラは田中デザインを多くの製品に採用していた。代表例としては女性向けハーフサイズカメラの傑作「フジカミニ」、小中学生向けの初心者カメラ「フジペット」「フジペット35」、高級レンジファインダー機「フジカ35」等々を挙げる事が出来る。

ブジペット

田中デザイン・フジカカメラ
「フジカ RAPID-S2」(発売当時価格13,000円)はカメラを保持しやすい横長デザインが人気を集め「ハーモニカ・カメラ」の愛称が付けられた程であった。
小西六写真(当時)は、1965年6月にラピッドフィルム・コニパンSSラピッドフィルムとラピッドフィルムカメラ「コニカラピッドM」の発売を行っている。「コニカラピッドM」は、32mmf1.8の高級仕様レンズ、スプリングモーターによる自動巻き上げ等を採用していたがフィルムと共に殆ど市場で見かけない程度の展開にとどまっている。
インスタマチック 対ラピッドシステム
日本ラピッド会加盟した14社は、コダック「インスタマチック」優先か、アグファ「ラピッドシステム」優先かで対応が分かれた、また、日本ラピッド会に加盟した14社の中で日本光学、旭光学等、5社が具体的な対応を見送っている事からも「コダック対アグファ」の見極めが当時としては難しかった事が推定される。
「リコーオートハーフ」でハーフサイズカメラ市場を得意市場化していたリコーは、35mmフィルムを使用するラピッドシステム優先を決めて1965年6月に「リコーEEラピッドハーフ」(発売当時価格14.000円)を発売してハーフサイズカメラ市場強化を試みている。
同様にキャノンも人気商品のハーフサイズカメラ「デミ」のラピッドシステム版として1965年6月に「デミラピッド」(発売当時価格16000円)を発売している。30mmf1.7の高級仕様レンズを搭載したハイスペック機として普及機主体の他社製品との差別化を図っている。
続いてキャノンは同年10月に「デミ」と並ぶスプリングモーターによる自動巻き上げ機能を搭載した人気カメラ「ダイヤル35」のラピッド版として「ダイアルラピッド」(16.000円)の発売を行っている。
しかしながら、キャノンはコダック「インスタマチック」の優勢が明確化した事より「ダイアルラピット」以降のラピッドカメラ展開を中止している。

マミヤ・マイラピッド
中判サイズカメラを得意とするマミヤも「マミヤ・マイラピッド」(16.400円)を1965年5月に発売、武骨なデザイン・中判サイズカメラの同社が発売した洗練されたデザインと5群5枚構成・32mmf1.7レンズ搭載のハイスペック仕様が注目を集めたが、コニカ同様に「最初で最後」のラピッドカメラ製品になっている。

ヤシカハーフ17EE RAPID
大衆機を得意としたヤシカは、1965年6月に「ヤシカハーフ17EE RAPID」(16.500円)
を発売、キャノン、マミヤ等と同様に大口径f1.7レンズを搭載した本機はヤシカフェイスのクロムメッキが綺麗な高級感を持ったラピッドカメラであった。しかしながら、販売は前述リコー、マミヤ等と同様に低迷、1機種のみの市場参入に止まっている。
富士写真フィルムは、1965年12月にキャノン「ダイアルラピッド」を追随する形でスプリングモーターによる自動巻き上げ機能を搭載した「フジカRAPID-D1」(16.000円)の追加発売を実施したが、世界的規模でコダック「インスタマチック」優勢が明確化された事より富士写真フィルムも当該市場からの撤退へと方針変更を余儀なくされている。

フジカラピッド D1
結局、日本ラピッド会加盟14社の中でラピッドカメラを発売した加盟社は、オリンパス、キャノン、小西六写真、富士写真フィルム、マミヤ光機、ミノルタカメラ、ペトリカメラ、
ヤシカカメラ、リコーの9社にとどまった。
ラピッドシステムの終焉
1964年5月に「コダックインスタマチック」を追撃する形で製品化されたアグファ「ラピッドシステム」は、①35mmフィルムを使用 ②カメラメーカー側で画面サイズを選択可能 ③リーダーペーパー無のフィルム平滑性 ④フィルム位置をカメラ側で決められるフォーカス対応性 ⑤インスタマチック方式よりカメラの小型化が可能となる等の特徴を有していた。
しかしながら、ラピッドシステムに対する国内外市場の反応は鈍く販売は低迷、「巨人・コダックの敵にはなれず」という状況に至っている。
コダックは「インスタマチックカメラ」発売1年半後、すなわち「ラピッドシステム」発売年である1964年末までに600万台の販売成果を挙げアグファ「ラピッドシステム」を圧倒した。当時、国内カメラ各社の年間生産総数が320万台弱で有った事から見ても、コダック「インスタマチックカメラ」の快進撃ぶりを判断する事が出来る。
国内では発売初年及び次年度である1964~1965年にかけてカメラ各社が「ラピッドシステム」対応製品展開を実施したもののミノルタカメラ等5社が1機種の市場投入にとどまり、2機種を製品化したキャノン、富士写真フィルム、オリンパス等が1966年より新製品投入を見送り国内市場は約2年間で終息を迎える事になった。
コダックは、126フィルム「インスタマチックフィルム」126フィルムカメラ「インスタマチックカメラ」発売7年後の1970年に開催された「大阪万国博」に生産累計5000万台・記念カメラを寄贈し、コダック製品による当該市場席巻を世界にアピールした。
コダックに敗退したアグファは、1972年に126フィルムカメラ「アグファマチツク50」と4種類の126フィルムを発売して「インスタマチック」陣営への参加を行い、1978年までに11機種の126フィルムカメラを発売している。

ライトパンカラーⅡ・RAPID
アグファ、富士写真フィルム、小西六写真等のフィルム各社がラピッドフィルムの販売から撤退した後も「ライトパン」ブランドで各種短尺フィルムビジネスを展開していた愛光商会(東京・港区)がネガカラーフィルム「ライトパンカラーⅡ ラピッド」(1977年当時 12EX \430)の供給を継続したが、1983年前に生産を終了している。
以上










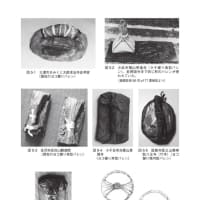
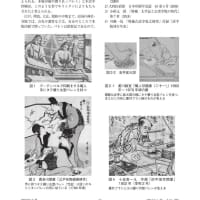
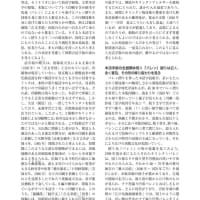

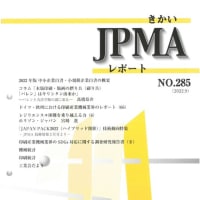





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます