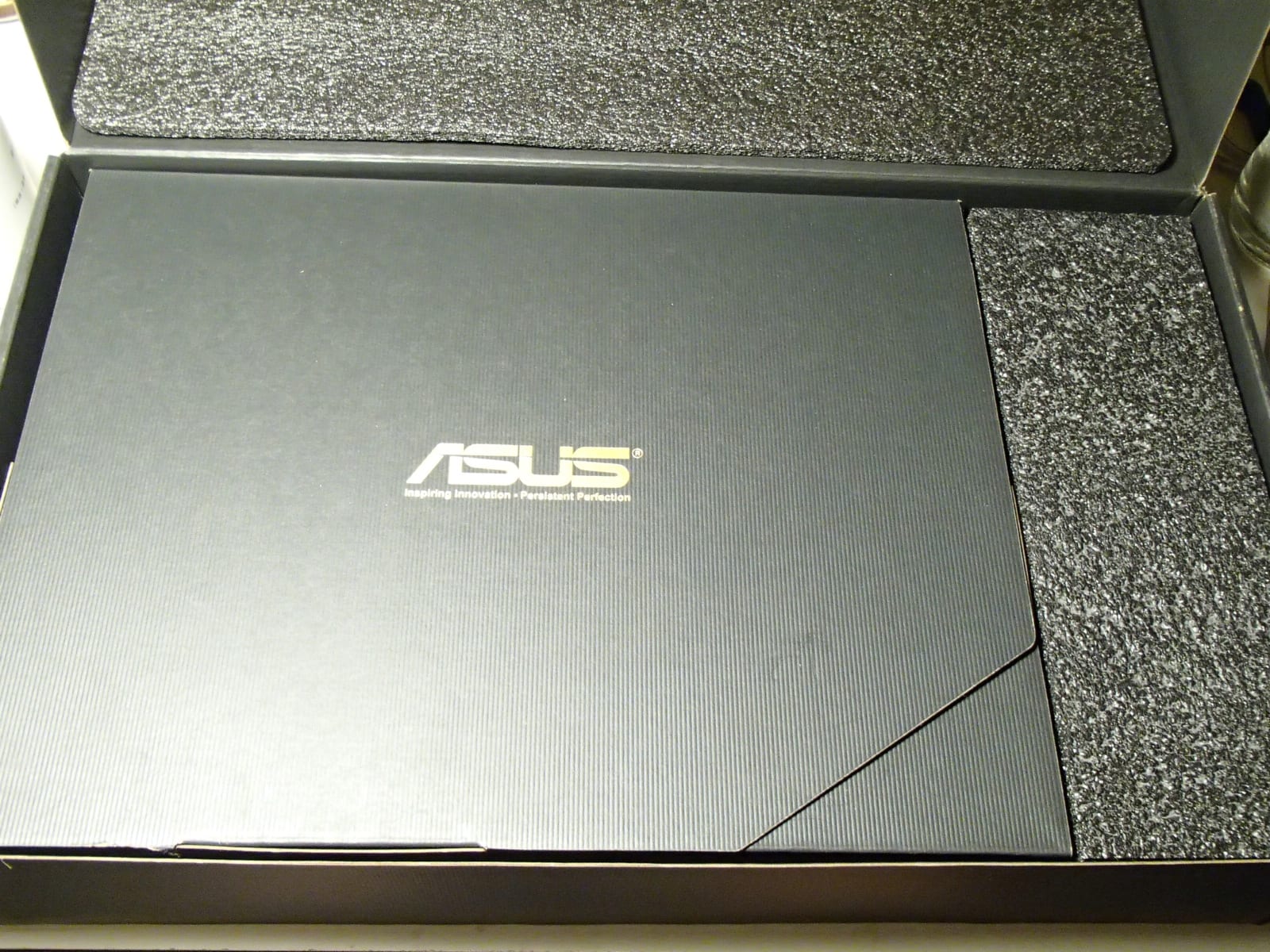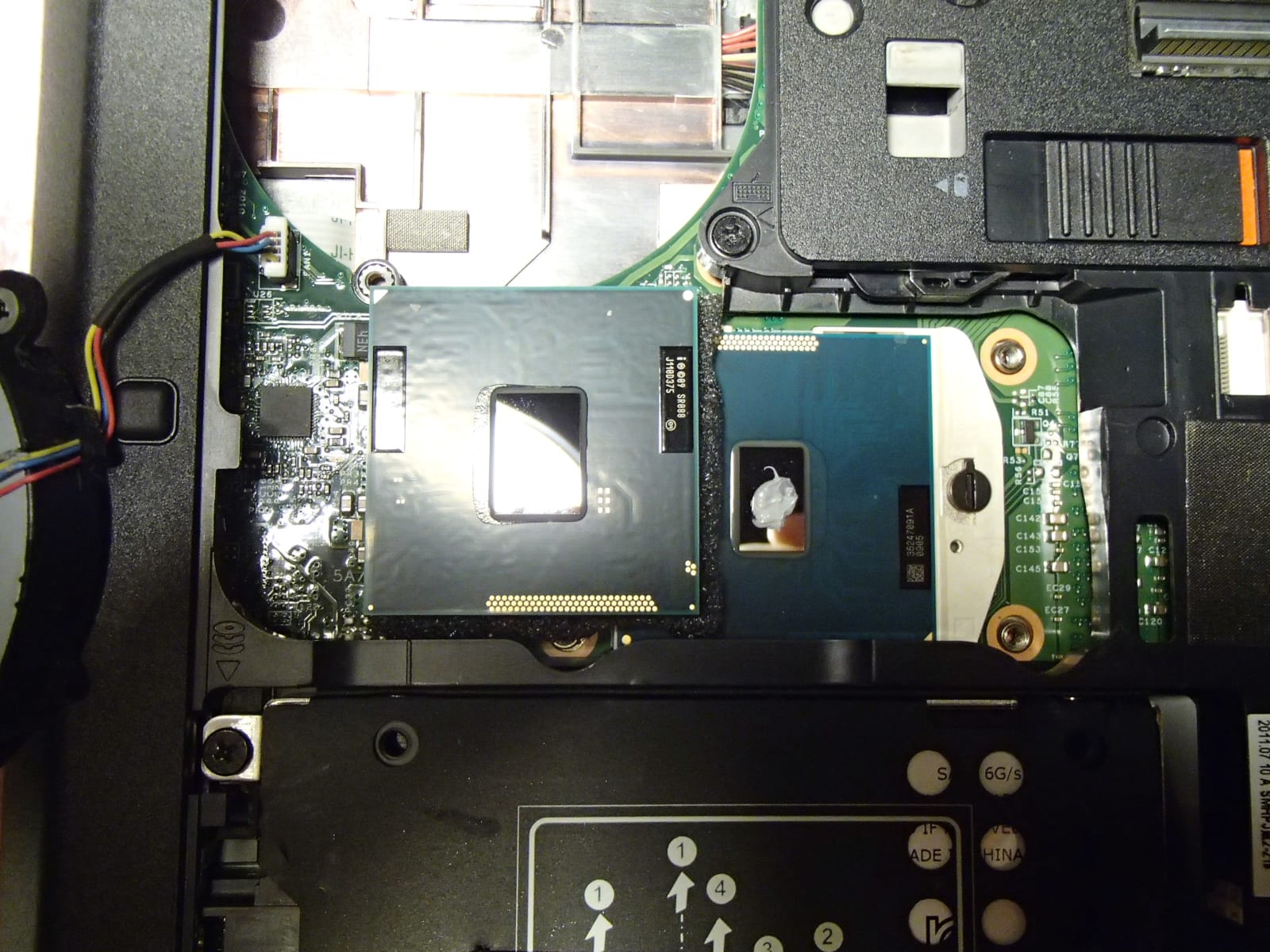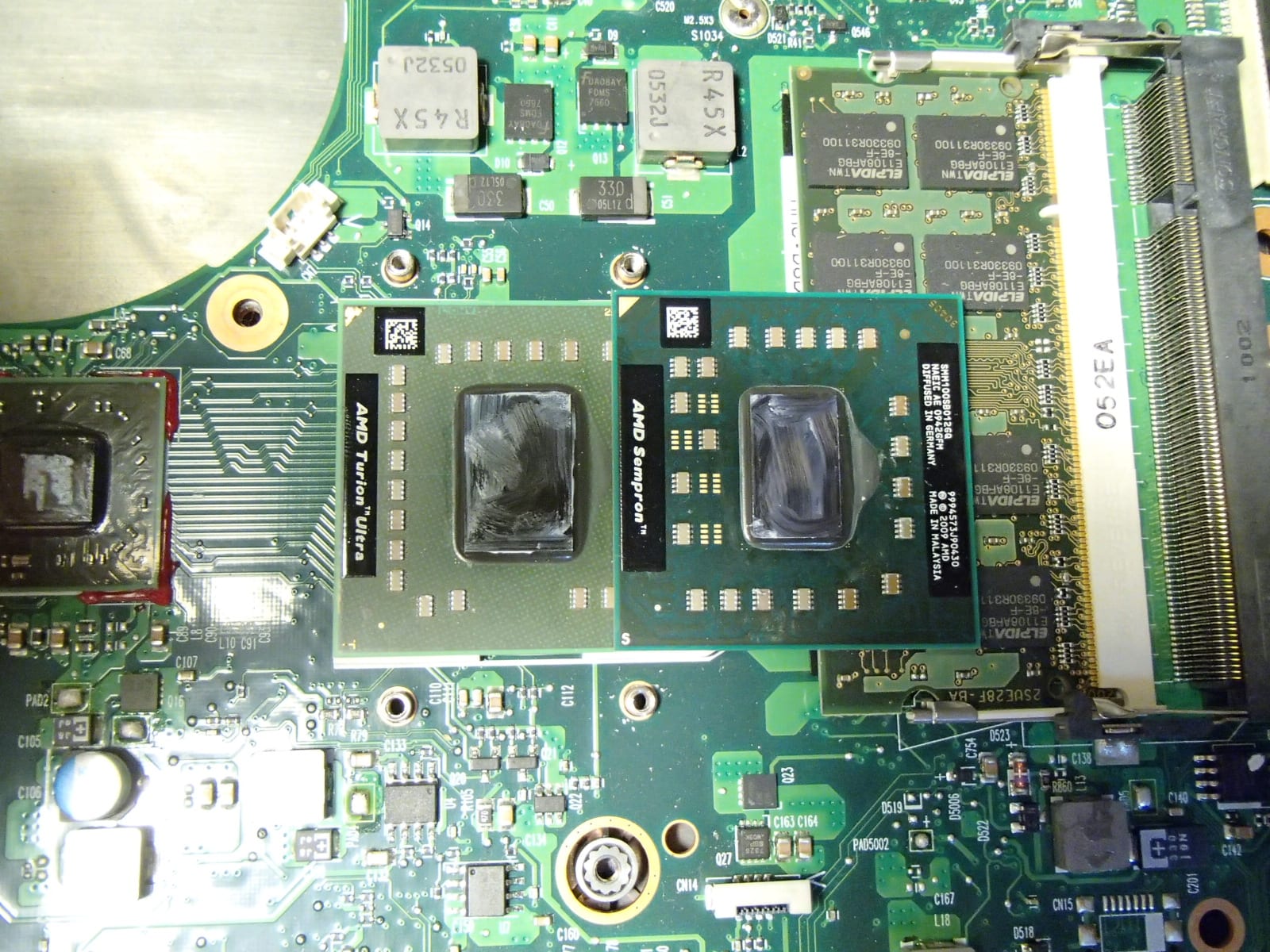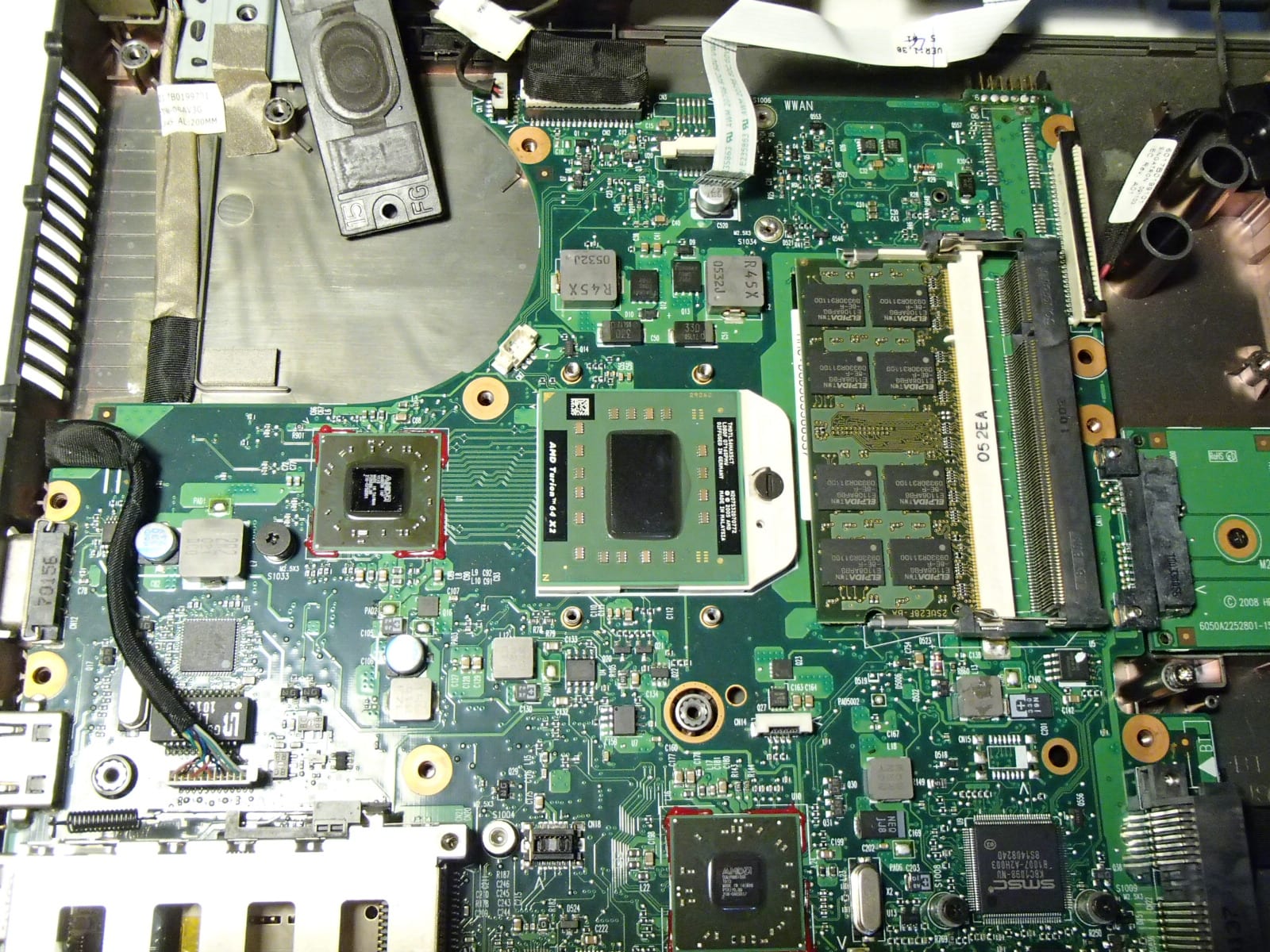以前、FreeStyle2の上位互換で書いた、左右分離式キーボードを買ってみました。
Sculpt Ergonomic Mouseがやっぱり重くてもういいかげんペンタブで操作したい
+
いちいちキーボードを動かすのはイヤ
+
ペンタブはできればLサイズを使いたい
↓
Metias Ergo Pro & 1.5mの4極ケーブル
箱の容積の割には結構重量があります。約1.7kg。

重さのせいか取っ手付き。



付属品

左

左裏

右

右裏

Lサイズを挟むための要、1.5mの4極ケーブル。左は付属のブリッジケーブル。

大丈夫かなと思いましたが、読み通りブリッジケーブルは3.5mmのオーディオケーブルと互換性があります。

無事接続完了。
Lサイズを挟めました。
なお、Mサイズまでならギリギリ付属のケーブル(43cm)でも足りると思います。

ペンタブとの相性は非常に良いです。
キーボードを手元に持ってくる必要も、手を伸ばす必要も、体をひねる必要もありません。
「そのままの姿勢で打てること」は左右分離式ならではの素晴らしい利点ですね。
こちらは使っていたKINESIS Freestyle2の20inch(+VIP3KIT)
Freestyle2は、左右キーボードを繋ぐケーブルが20inchの方でも、
Mサイズが(正確に言うと13HDが)挟める大きさの限界でした。
(13HDとFreestyle2。スタンドで少し13HDを浮かせて、ケーブル長を稼いでいます。)

なので、Lサイズ(XLもイケるかも。とは言ってもキーボード配置が肩幅以上になるので相当苦しいとは思います。)が挟めるのは、ケーブル交換ができるMetias Ergo Proのメリット①。
あ、あとErgodoxというオープンソースの左右分離式キーボードも同様に4極のオーディオケーブルが使えるみたいです。
(追記)
XLを挟みました。

たしかに肩幅以上ですが、意外なことに使いにくくはありません。
この追記部分もXLを挟んだ状態で打っていますが普通に打てます。
特にXLはキーボード置き場に困るサイズなので、同様にお困りの方は一度検討してみてはいかがでしょうか。
ただ一点、XLは厚みが邪魔して、後述のようにハの字チルトで「寄せる」ことはできませんでした。
キーボードの間を縮めたい場合には一工夫要ります。
メリット②はネガティブチルト。
通常時

ネガティブチルト

キーボードの「奥側に」傾けられる機能です。

これは素晴らしい機能で、「キーに指が吸い込まれる」かのような打ち心地になります。
指先が少し重くなる、というと語弊がありますが、
ファーストインプレッションで書いているキーが重いこと、バックスペースキーが遠いことも気にならなくなります。
メリット③はハの字チルト

20度くらいでしょうか。
Freestyle2+VIP3KITと違って角度は1種類。
手首が楽になるのはもちろん、ペンタブに「寄せる」こともできます。

ただし、ネガティブチルト⇔ハの字チルトは選択式。
同時利用不可。どちらかを選ぶ必要があります。
使ってみた感想は・・・
・静音が謳われていますが、思ったより静音ではないです。カシャカシャ鳴ります。若干静かな茶軸?黒軸や赤軸の方が物によっては静かかも。
・今の今までHHKだったせいか、バックスペースキーが遠いです。
・剛性はかなりあります。ハードパンチャーな方もたわみとは無縁でいられると思います。
・キーは正直重い・・・かも。これから馴染めば評価が変わるかもしれません。
・パームレストの低反発クッションの劣化が怖い。汗吸いまくり。Freestyle2は替えクッションが販売されているのでErgoProも販売希望。
とファーストインプレッションはこんなところです。
左右分離式だと、
ペンタブ以外にも、キーボードの間に本を置けたり、

タブレットPCを置けたりと、
実は使ってみるとかなり便利だったりします。
現行だと値段が高いものしかない上に(Freestyle2もErgoProもErgoDoxもTron配列のアレもね・・・)、
ある種の「キワモノ感」もあって、
今はまだ一般受けしそうとはお世辞にも言えない状況だと思いますが、
普及価格帯まで降りてくる製品が出たら、
もしかしたら左右分離式が注目される時代が来るかもしれませんね。