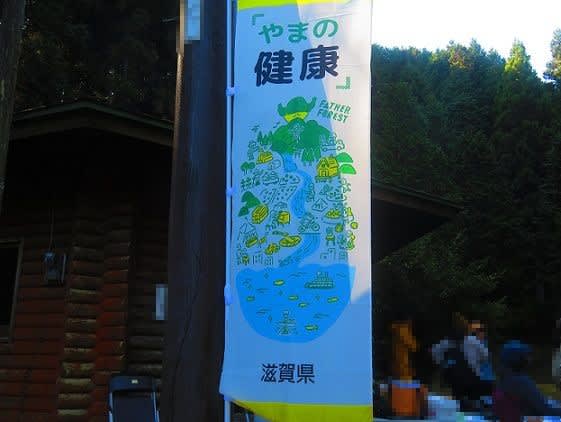2017年、和歌山県東牟婁郡太地町にある太地町立くじらの博物館訪問記を再録しています。
捕鯨の歴史やクジラの標本を展示している博物館本館を見学した後は、屋外でイルカショー見物です
過去記事<捕鯨の町 太地くじらの博物館(2017年)>

イルカショーでお馴染みのバンドウイルカは北極圏や南極を除く全世界の海洋に生息する最もポピュラーなイルカですね。
以前はハンドウイルカ(半道海豚)と言う和名で呼ばれていましたが、今はバンドウ(坂東)イルカの方が世界的にも一般的なようです。

こっちはカマイルカ(鎌海豚)。
バンドウイルカと違ってグレーとホワイトのツートンカラー。背びれの形に鎌のような切れ込みの深い曲線があるのが名前の由来です。


小さいプールを全速力で泳ぎ、ハイジャンプするイルカたち。
壁にぶつかっちゃったりしないのかなって心配になってしまいます
ショーはいたってオーソドックス。それでもイルカたちのアクティビティはとても高いので楽しめました。
博物館という施設であることから、パフォーマンスだけでなくイルカの身体の特徴や能力の紹介にかなりの時間を割いているのも、他の水族館のイルカショーと一線を画してるポイントだと思います。

くじら博物館のメインイベント、クジラショーまではまだ1時間あります

外はかなり暑いから、先に水族館マリナリュウムに行ってみましょう(笑)
つづく
更新の励みです、ポチっとお願い!