
この時期に“クリスマス”と言ったら、庭に出てくる“バラの花”。
クリスマスの時期に花開くので、そんな名前が付いたらしいが、そうでない
季節に咲く種類にまで広げてしまったので、ややこやしくなった。

最初は、ヘレボラス・ニゲルという種類にのみクリスマスローズという呼称を与えていたが、
春咲きのオリエンタリスを含めての総称になってしまった。
確かに、店先ではヘレボラス・ニゲルとか、ヘレボラス・オリエンタリスといった名前よりも、
クリスマスローズの方が通りはいい。

何れにしても、ここでは本当のクリスマスの頃、花たちは厚い雪の下なので、ニゲルと
いえども咲くことはできない。
ここの庭の一角、オリエンタリスを中心に、クリスマスローズが密集する場所がある。
最初は、簡単な石垣を積み、数株を植えたに過ぎなかったが、こぼれ種で増え始め、
今では一面畑のようになっている。
見えている枝は、チシマザクラという匍匐性の高山性のサクラだ。

その、チシマザクラの根元も、このところの暖気で雪解を迎え、冬眠?していた面々が
雪の中から首をもたげ顔を出す。
日焼けしていない、黄色みを帯びた花芽が初々しい。

こういった画像を見ると、雪が解けてからゆっくり花芽を伸ばすのではなく、しっかりと
雪の下でその準備が進められていることが、解る。

朝方は、まだ大方が雪に押さえつけられていたチシマザクラの枝(本当は幹)も、午後には
ほとんどが起きあがってきた。

お隣のニレの木の根元では、株を分けて移植したのが花をつけるようになった。
根開きが早い分花柄が伸びて、もう花がほころんでいる。
もう少し雪が解けて落ち着いたら、花柄摘みならぬ病葉(わくらば)刈りが待っている。
去年伸びた古い葉っぱを取り除いてやるのだ。
古い葉っぱの下には、実生から育った小さな苗がたくさん育っていることだろう。
早春のクリスマスは、雪解とともにやってくる。



















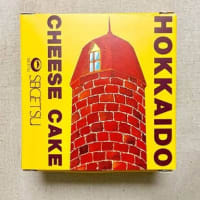
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます