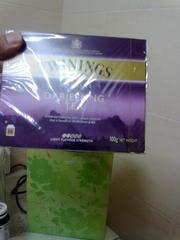本日も夜更かしをしてしまいました。
どうも深夜でないと仕事も研究も集中できないので仕方がありません。
本日月曜日は昼に一件用事があり、あとは夜の講義があるだけです。
ですから、これから昼前まで休もうと思っています。
私の研究生活にコーヒーは欠かせません。

さて、先日久々に大学院時代の仲間と連絡をしました。
仲間と言っても私の先輩にあたる方で、研究分野も異なります。
ですが大学院研究室で良くお会いし、酒も何度も飲み語りあった仲です。
私とは同時期、今年9月大学院を修了し、既に某大学の専任となっています。
というより、大学院在籍中から現在の職にあり、私と同じ社会人学生でした。
だからこそ、先輩であっても比較的身近な存在として話せたのでしょう。
スカイプで一時間程話したのですが、話題は先日行われた大学院修了式に及びました。
一番印象的だったのは、僕らと同時期に博士課程を修了した中国人留学生Yさんの話でした。
元々、中国の著名な銀行で銀行員をしていたYさんは一念発起、日本へ留学。
そこから日本語を学び、大学院の修士、博士と6年間を千葉大で学びました。
日本へ来る以前から既に家族もおり、家族とは離ればなれになりつつも、ただ博士号取得を目指しました。
その間、中国へ帰ることはほぼなく、博士課程在籍時は一度も帰っていなかったと聞いたことがあります。
私は研究室でYさんと会うと、よく近所の中国料理店へ誘い、食事や酒を飲み、研究の話をしました。
そして、いよいよ博士論文を書き上げ提出しようとしていた矢先、Yさんのお父様が亡くなりました。
私は当時、中国から日本へ戻り、大学院の研究室でYさんのすぐ近くの席で論文を書いていました。
ですが、Yさんは何も話さずにただ黙々と自身の博士論文を書いていました。
その集中力と執念のようなものに当時は全く気づけませんでしたが、その事実を知りすぐに言葉が出ませんでした。
そういう深い“思い”や“期待”を背負って博論を書いている仲間がいたことを今回初めて知ることが出来ました。
ちなみに修了式にはYさんのご家族がわざわざ日本までいらしたそうで、式の後は皆で食事会を開いたそうです。
一生忘れられない食事会であっただろうと推察します。
なお、大学院の場合、論文提出時期が年に二回設けられており、どちらで出すかで修了時期が異なります。
私と先輩の場合、論文を今年2月に出した関係で修了は今年9月となりましたが、3月修了もあります。
通常は3月修了する学生が多く、9月修了は比較的少数になります。
今回もそうで、特に博士課程の修了生となるとその数は本当にわずかとなります。
9月28日にあった大学院修了式では、式に参加した所属研究科の博士課程院生は4人だけ。
もっとも、私のように参加できなかった院生が何人いるかは把握していませんが…
そしてこれは先輩から送られてきた写真。
大学院の全研究科の修了式後、各研究科の修了院生と教員だけで撮ったもの。

皆、長い博論との格闘を終え、一区切りをつけたせいか顔が晴れ晴れとしています。
本来は私もここに入っているはずでしたが、それが叶わなかったのは少々残念です。
ですが、有難いことに?大学院から修了生のコメントを依頼をされ、それが最近大学院のHPに載せられました。
集合写真は撮れませんでしたが、その代わりと考えようと思っているところです。
http://www.shd.chiba-u.jp/message-mimura
どうも深夜でないと仕事も研究も集中できないので仕方がありません。
本日月曜日は昼に一件用事があり、あとは夜の講義があるだけです。
ですから、これから昼前まで休もうと思っています。
私の研究生活にコーヒーは欠かせません。

さて、先日久々に大学院時代の仲間と連絡をしました。
仲間と言っても私の先輩にあたる方で、研究分野も異なります。
ですが大学院研究室で良くお会いし、酒も何度も飲み語りあった仲です。
私とは同時期、今年9月大学院を修了し、既に某大学の専任となっています。
というより、大学院在籍中から現在の職にあり、私と同じ社会人学生でした。
だからこそ、先輩であっても比較的身近な存在として話せたのでしょう。
スカイプで一時間程話したのですが、話題は先日行われた大学院修了式に及びました。
一番印象的だったのは、僕らと同時期に博士課程を修了した中国人留学生Yさんの話でした。
元々、中国の著名な銀行で銀行員をしていたYさんは一念発起、日本へ留学。
そこから日本語を学び、大学院の修士、博士と6年間を千葉大で学びました。
日本へ来る以前から既に家族もおり、家族とは離ればなれになりつつも、ただ博士号取得を目指しました。
その間、中国へ帰ることはほぼなく、博士課程在籍時は一度も帰っていなかったと聞いたことがあります。
私は研究室でYさんと会うと、よく近所の中国料理店へ誘い、食事や酒を飲み、研究の話をしました。
そして、いよいよ博士論文を書き上げ提出しようとしていた矢先、Yさんのお父様が亡くなりました。
私は当時、中国から日本へ戻り、大学院の研究室でYさんのすぐ近くの席で論文を書いていました。
ですが、Yさんは何も話さずにただ黙々と自身の博士論文を書いていました。
その集中力と執念のようなものに当時は全く気づけませんでしたが、その事実を知りすぐに言葉が出ませんでした。
そういう深い“思い”や“期待”を背負って博論を書いている仲間がいたことを今回初めて知ることが出来ました。
ちなみに修了式にはYさんのご家族がわざわざ日本までいらしたそうで、式の後は皆で食事会を開いたそうです。
一生忘れられない食事会であっただろうと推察します。
なお、大学院の場合、論文提出時期が年に二回設けられており、どちらで出すかで修了時期が異なります。
私と先輩の場合、論文を今年2月に出した関係で修了は今年9月となりましたが、3月修了もあります。
通常は3月修了する学生が多く、9月修了は比較的少数になります。
今回もそうで、特に博士課程の修了生となるとその数は本当にわずかとなります。
9月28日にあった大学院修了式では、式に参加した所属研究科の博士課程院生は4人だけ。
もっとも、私のように参加できなかった院生が何人いるかは把握していませんが…
そしてこれは先輩から送られてきた写真。
大学院の全研究科の修了式後、各研究科の修了院生と教員だけで撮ったもの。

皆、長い博論との格闘を終え、一区切りをつけたせいか顔が晴れ晴れとしています。
本来は私もここに入っているはずでしたが、それが叶わなかったのは少々残念です。
ですが、有難いことに?大学院から修了生のコメントを依頼をされ、それが最近大学院のHPに載せられました。
集合写真は撮れませんでしたが、その代わりと考えようと思っているところです。
http://www.shd.chiba-u.jp/message-mimura