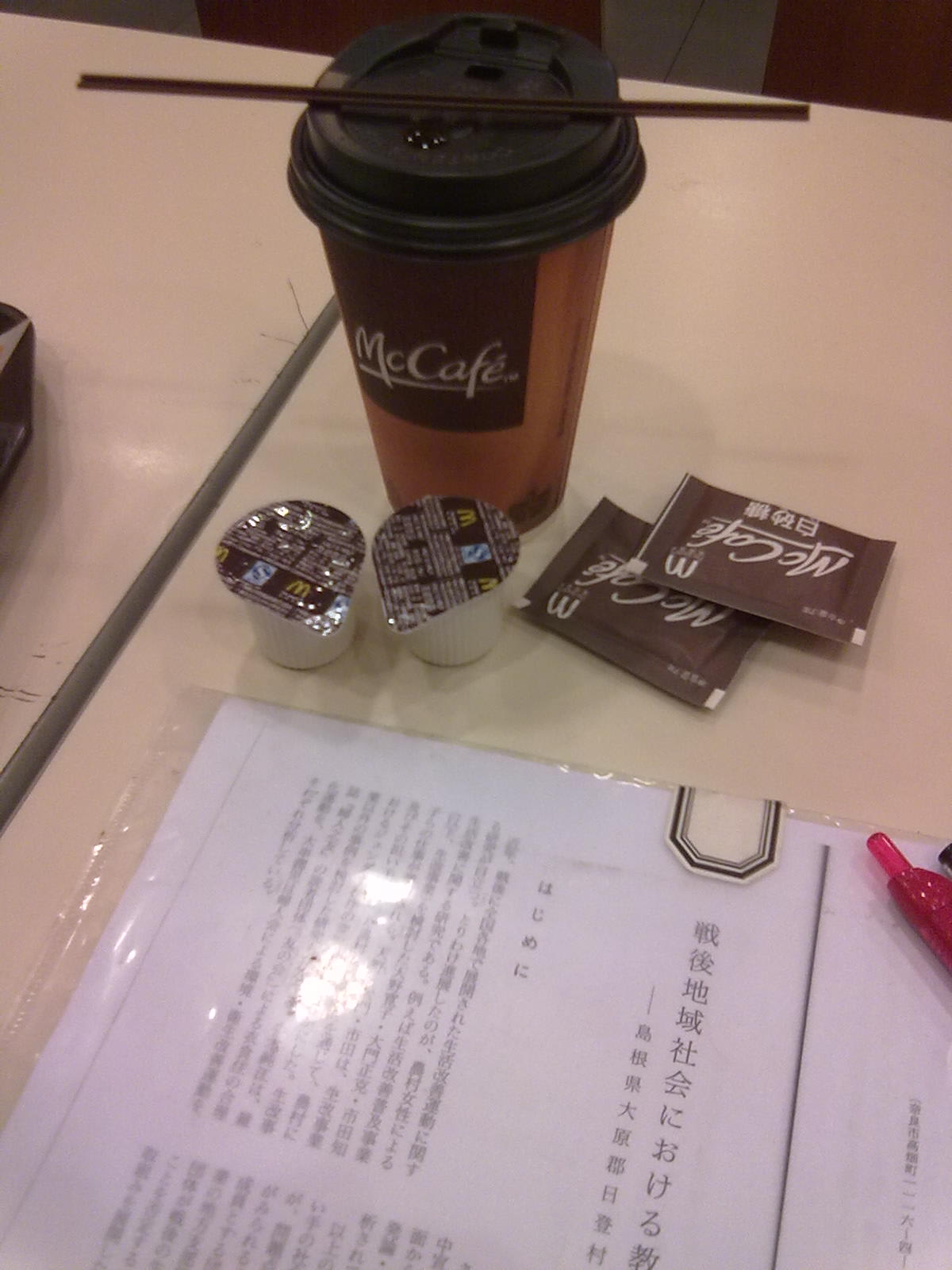<今日は夕方から二年生達、野球クラブの面々と野球をしてきました。ただ、この写真は今日のではなく、他の日に撮ったものですが…>
私は好きなスポーツは、特にサッカー、それに野球、水泳です。
いずれも学生時代に学んだ経験があり、それらに関心が深いからでしょう。
中国に来て以来、主にサッカーのみで他はする機会はほぼ皆無でした。
というのも、水泳をやる場所は大変少なく、野球場などは見たこともありませんでした。
(なお、この話は安徽省時代の話です…今の上海ではなく)
しかし、上海に来てからはこれらのスポーツをする機会にも恵まれています。
こういう点は、さすが国際都市上海という感じがします。
一般的に「中国に無い」とされるものが、上海にはあります。
ところで毎週火曜日15時半より、二年生達との日本語コーナーを実施しています。
そこでは主に、日本語での交流をしているのですが今日は違いました。
…何故か、今日は会話ではなく野球をすることになっていたのです。
(私が皆に提案したのかもしれませんが、覚えていません…)
ともかくそんなことで、学生達と新校舎のグラウンドへ向かいました。
そこには、大学の野球クラブの面々もいて、すでにキャッチボールが始まっていました。
その光景を見た瞬間、私は一気にテンションがマックスになりました(笑)
中国で本格的な野球に出会えたこと、自分もそれが出来ること、そして素晴らしい野球をする環境があること…
どれもがその理由ですが、何より好きなスポーツが出来ることが最高の喜びでした。
聞くと、この野球クラブチームはかなりの強豪だそうで、上海の大会で優勝を果たしたそうです。
そうした彼らの様子を見ていたのですが、確かに野球の動きは慣れている感じでした。
…が、日本では決して上手な方ではなく、平均よりも少し上という印象でした。
そうした点から、やはり日本における野球のレベルは高いのだと実感しました。
私は野球が相当久しぶりでしたが、最近運動を続けているせいで体は軽く感じました。
そして、
・キャッチボール
・遠投(60メートル程度)のキャッチボール
・バッティング
・ピッチング
などを時間を忘れて二時間程楽しみました。
高校時代、毎日のように遅くまで練習していた時代を懐かしく感じました。
日本語科の学生達は野球の素人だったらしく、グラウンドの隅で仲良くミニキャッチボールをしていました。
何故か日本語科の男子学生よりも、女子学生の方が関心をもっていた感じがしました。
(二年の男子学生は比較的おとなしめというのも関係あるのでしょうが…)
野球クラブの面々は、何故か私に関心を持ってくれたらしく、
「M先生」 「すごいね!」 「大丈夫、大丈夫」 「もっともっと」
など、片言の日本語で私に色々と話しかけてくれました。
そんな友好的なムードだった為、久々の野球を満喫することができました。
帰り際、クラブの学生達から、
「先生、毎週末野球をやりましょう!いいですか?」
と言われたので、
「もし時間があれば参加するよ。でも次回も必ず来るから」
と言い残し、グラウンドを後にしました。
何でも彼らは毎日のように、この活動があるそうです…(凄い元気)
私自身は仕事の合間の気分転換として、また参加できれば良いと思っています。
私は好きなスポーツは、特にサッカー、それに野球、水泳です。
いずれも学生時代に学んだ経験があり、それらに関心が深いからでしょう。
中国に来て以来、主にサッカーのみで他はする機会はほぼ皆無でした。
というのも、水泳をやる場所は大変少なく、野球場などは見たこともありませんでした。
(なお、この話は安徽省時代の話です…今の上海ではなく)
しかし、上海に来てからはこれらのスポーツをする機会にも恵まれています。
こういう点は、さすが国際都市上海という感じがします。
一般的に「中国に無い」とされるものが、上海にはあります。
ところで毎週火曜日15時半より、二年生達との日本語コーナーを実施しています。
そこでは主に、日本語での交流をしているのですが今日は違いました。
…何故か、今日は会話ではなく野球をすることになっていたのです。
(私が皆に提案したのかもしれませんが、覚えていません…)
ともかくそんなことで、学生達と新校舎のグラウンドへ向かいました。
そこには、大学の野球クラブの面々もいて、すでにキャッチボールが始まっていました。
その光景を見た瞬間、私は一気にテンションがマックスになりました(笑)
中国で本格的な野球に出会えたこと、自分もそれが出来ること、そして素晴らしい野球をする環境があること…
どれもがその理由ですが、何より好きなスポーツが出来ることが最高の喜びでした。
聞くと、この野球クラブチームはかなりの強豪だそうで、上海の大会で優勝を果たしたそうです。
そうした彼らの様子を見ていたのですが、確かに野球の動きは慣れている感じでした。
…が、日本では決して上手な方ではなく、平均よりも少し上という印象でした。
そうした点から、やはり日本における野球のレベルは高いのだと実感しました。
私は野球が相当久しぶりでしたが、最近運動を続けているせいで体は軽く感じました。
そして、
・キャッチボール
・遠投(60メートル程度)のキャッチボール
・バッティング
・ピッチング
などを時間を忘れて二時間程楽しみました。
高校時代、毎日のように遅くまで練習していた時代を懐かしく感じました。
日本語科の学生達は野球の素人だったらしく、グラウンドの隅で仲良くミニキャッチボールをしていました。
何故か日本語科の男子学生よりも、女子学生の方が関心をもっていた感じがしました。
(二年の男子学生は比較的おとなしめというのも関係あるのでしょうが…)
野球クラブの面々は、何故か私に関心を持ってくれたらしく、
「M先生」 「すごいね!」 「大丈夫、大丈夫」 「もっともっと」
など、片言の日本語で私に色々と話しかけてくれました。
そんな友好的なムードだった為、久々の野球を満喫することができました。
帰り際、クラブの学生達から、
「先生、毎週末野球をやりましょう!いいですか?」
と言われたので、
「もし時間があれば参加するよ。でも次回も必ず来るから」
と言い残し、グラウンドを後にしました。
何でも彼らは毎日のように、この活動があるそうです…(凄い元気)
私自身は仕事の合間の気分転換として、また参加できれば良いと思っています。