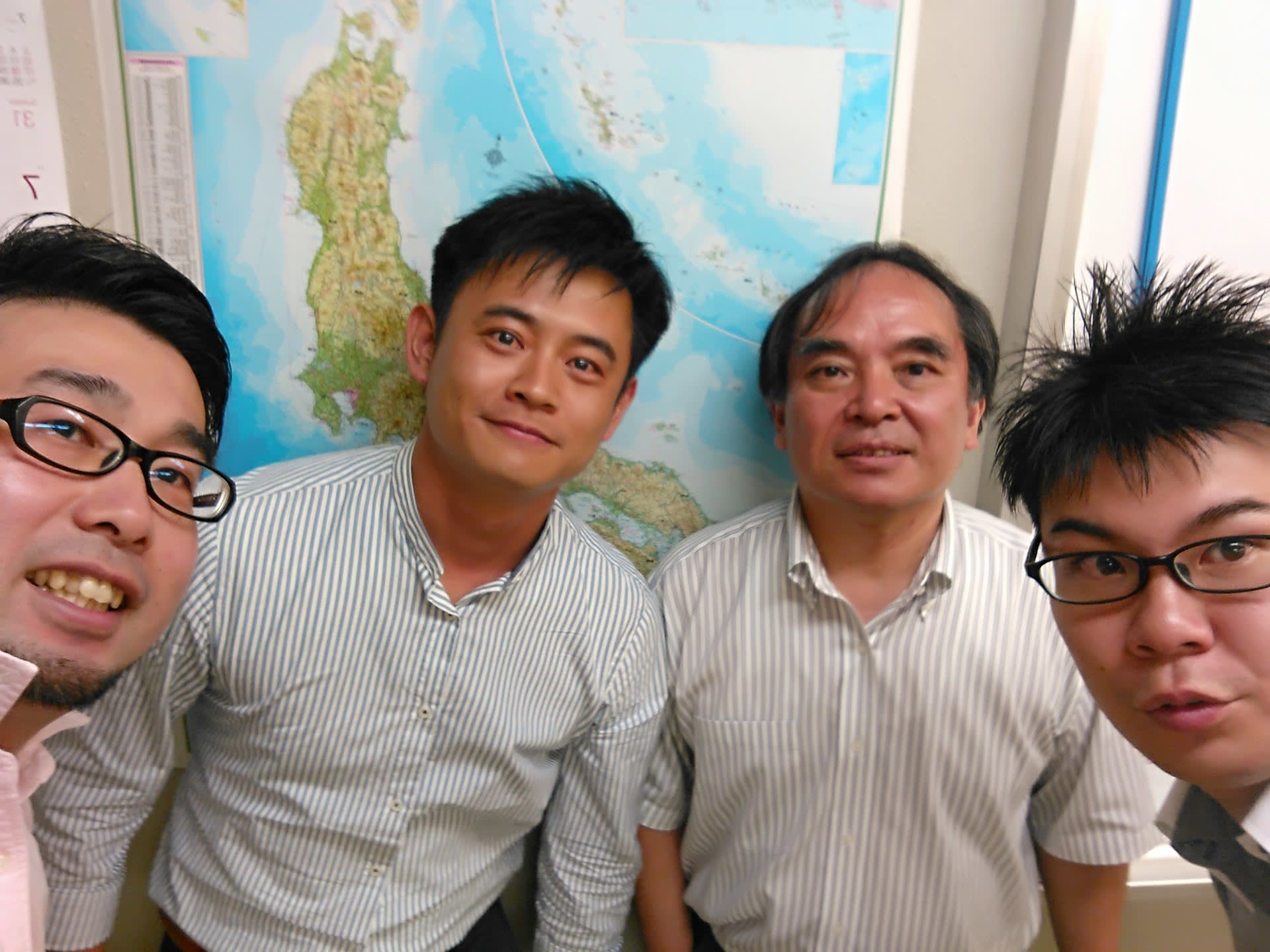10月22‐23日、これまで進めてきた日本事情テキストプロジェクトに関して報告をする機会を得ました。
研究会の会場は、天津にある天津外国語大学です(これで二回目の訪問)。
研究会名は、「国际化视野中的日汉语言对比及翻译研究国际研讨会会议」とやや長め。
その報告要旨をさきほど事務局に送ったのですが、それをここにも掲載しておきます。
__________________________________________
題目:現代中国の大学生に向けた日本事情テキストの共同制作
現代中国の大学における日本語教育関連科目の中に、日本事情(或いは、「日本概況」や「日本文化と社会」)がある。本科目では日本について、社会・文化・歴史・経済・政治などを幅広く学生に教授し、かれらの日本理解を深め、かつ、多角的な日本理解を進めることを主な目的としている。さらに、本科目は学生の日本語習得においても少なくない学習効果が期待できる。
これまで中国国内において、日本事情の大学テキストは数多く出版されてきた。しかしながら、それらのテキストには依然、少なくない課題もみられ、改善の余地が残されている。それらの課題は、①記述内容の公平性、②内容の構成面、③使用されている日本語水準、④学生の学習ニーズの把握、⑤学習内容を発展・深化させる工夫、などであったと考える。日本事情は日本語科学生に対して、有意義な内容を多く含む科目でありながら、上記、日本事情テキストにおける課題が一つの要因となり、教育的効果が十分には上げられていない状況も見られた。その一方で、教師側が日本事情テキストを使用せず、全て自らプリント・関連資料を準備して教えるとなると、教師の負担は重くなり、現実的とはいえない面もある。報告者はこれまで7年半、中国の大学で日本語教育に携わってきたが、その中で日本事情テキストを巡る課題に直面し、その過程で、解決の糸口を新たな日本事情テキストの共同制作に求めるようになった。
本報告では、現代中国の大学における従来の日本事情テキストの現状と課題を整理した上で、2014年1月以降、報告者が主導となって進めてきた日本事情テキストの共同制作の過程、さらに、我々の日本事情テキストを作る上で核に据えてきた幾つかの制作方針についても報告したいと考えている。
__________________________________________
当日得られたレスポンスなどは、後日、この空間で御紹介したいと思います。
なお、10月に報告させて頂く内容は私個人の成果ではなく、2014年以降、共同して進めてきたプロジェクトメンバーの協力によるものです。
今年8月5日(金)に千葉大で実施した会合が最近の活動なのですが、14年以降、毎年夏・冬は定期的に集まり、意見交換を交わしてきました。
メンバーの協力のお陰で、本プロジェクトはゆっくりではありますが、確実に進んでいます。
2014年1月の会合以降、毎年夏・冬に二度実施してきた会合とその後の執筆作業を経て、現時点では日本語原稿はほぼ書きあがりました。
今後はイラスト・写真の挿入、日本語水準の微調整を経て、中国語への翻訳作業を関係者にお願いし、中国語原稿を作成していきます。
ここまでの作業を来年7月には終えた後は、中国の出版社へ原稿を渡して「原稿チェック」、そして出版という流れになります。
現状ではまだやるべき事が残されており、外部意見もほしいので、10月の研究会で有益なコメントがもらえることを期待しています。
会合後の懇親会の様子
①

②
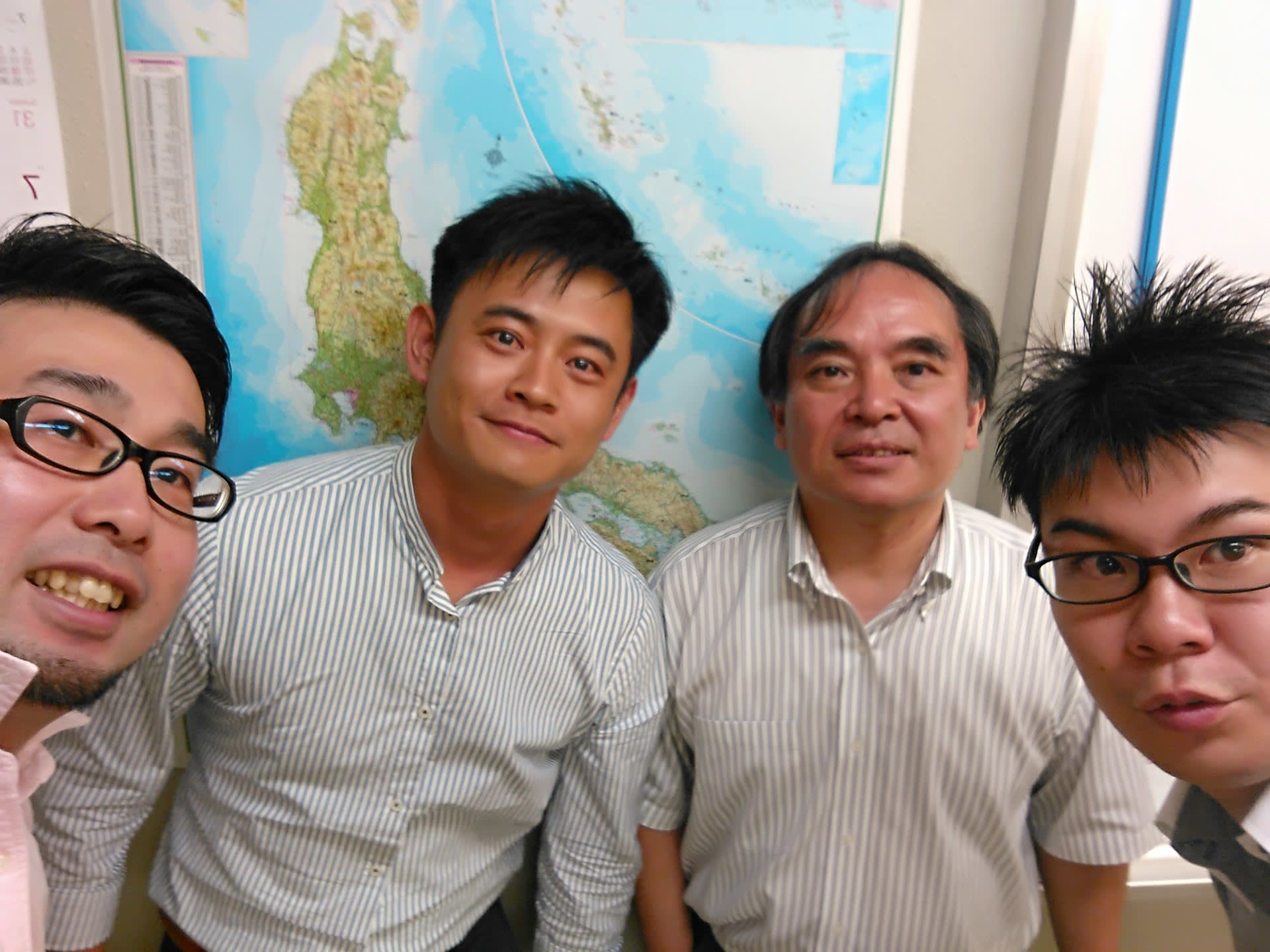
研究会の会場は、天津にある天津外国語大学です(これで二回目の訪問)。
研究会名は、「国际化视野中的日汉语言对比及翻译研究国际研讨会会议」とやや長め。
その報告要旨をさきほど事務局に送ったのですが、それをここにも掲載しておきます。
__________________________________________
題目:現代中国の大学生に向けた日本事情テキストの共同制作
現代中国の大学における日本語教育関連科目の中に、日本事情(或いは、「日本概況」や「日本文化と社会」)がある。本科目では日本について、社会・文化・歴史・経済・政治などを幅広く学生に教授し、かれらの日本理解を深め、かつ、多角的な日本理解を進めることを主な目的としている。さらに、本科目は学生の日本語習得においても少なくない学習効果が期待できる。
これまで中国国内において、日本事情の大学テキストは数多く出版されてきた。しかしながら、それらのテキストには依然、少なくない課題もみられ、改善の余地が残されている。それらの課題は、①記述内容の公平性、②内容の構成面、③使用されている日本語水準、④学生の学習ニーズの把握、⑤学習内容を発展・深化させる工夫、などであったと考える。日本事情は日本語科学生に対して、有意義な内容を多く含む科目でありながら、上記、日本事情テキストにおける課題が一つの要因となり、教育的効果が十分には上げられていない状況も見られた。その一方で、教師側が日本事情テキストを使用せず、全て自らプリント・関連資料を準備して教えるとなると、教師の負担は重くなり、現実的とはいえない面もある。報告者はこれまで7年半、中国の大学で日本語教育に携わってきたが、その中で日本事情テキストを巡る課題に直面し、その過程で、解決の糸口を新たな日本事情テキストの共同制作に求めるようになった。
本報告では、現代中国の大学における従来の日本事情テキストの現状と課題を整理した上で、2014年1月以降、報告者が主導となって進めてきた日本事情テキストの共同制作の過程、さらに、我々の日本事情テキストを作る上で核に据えてきた幾つかの制作方針についても報告したいと考えている。
__________________________________________
当日得られたレスポンスなどは、後日、この空間で御紹介したいと思います。
なお、10月に報告させて頂く内容は私個人の成果ではなく、2014年以降、共同して進めてきたプロジェクトメンバーの協力によるものです。
今年8月5日(金)に千葉大で実施した会合が最近の活動なのですが、14年以降、毎年夏・冬は定期的に集まり、意見交換を交わしてきました。
メンバーの協力のお陰で、本プロジェクトはゆっくりではありますが、確実に進んでいます。
2014年1月の会合以降、毎年夏・冬に二度実施してきた会合とその後の執筆作業を経て、現時点では日本語原稿はほぼ書きあがりました。
今後はイラスト・写真の挿入、日本語水準の微調整を経て、中国語への翻訳作業を関係者にお願いし、中国語原稿を作成していきます。
ここまでの作業を来年7月には終えた後は、中国の出版社へ原稿を渡して「原稿チェック」、そして出版という流れになります。
現状ではまだやるべき事が残されており、外部意見もほしいので、10月の研究会で有益なコメントがもらえることを期待しています。
会合後の懇親会の様子
①

②