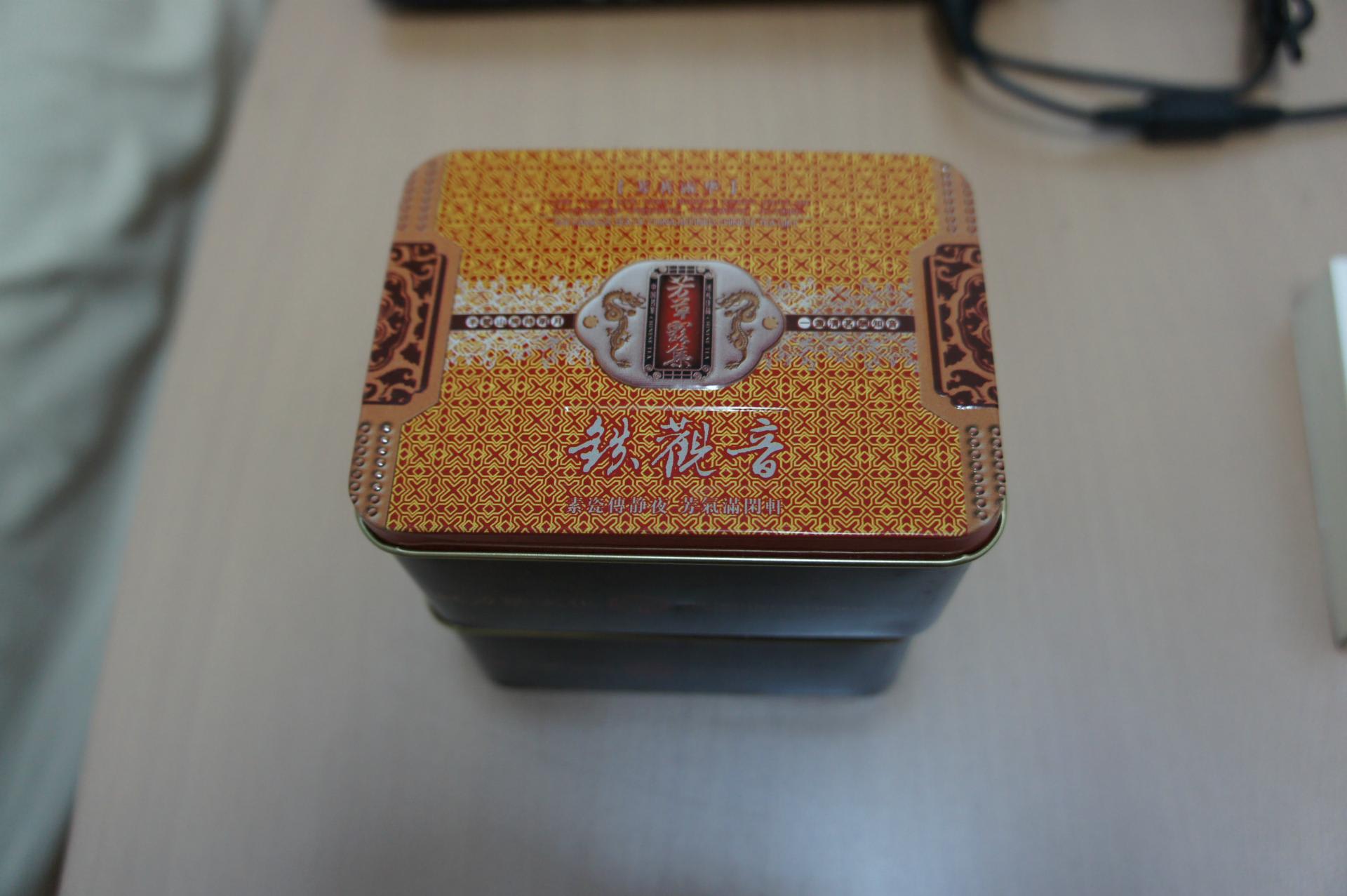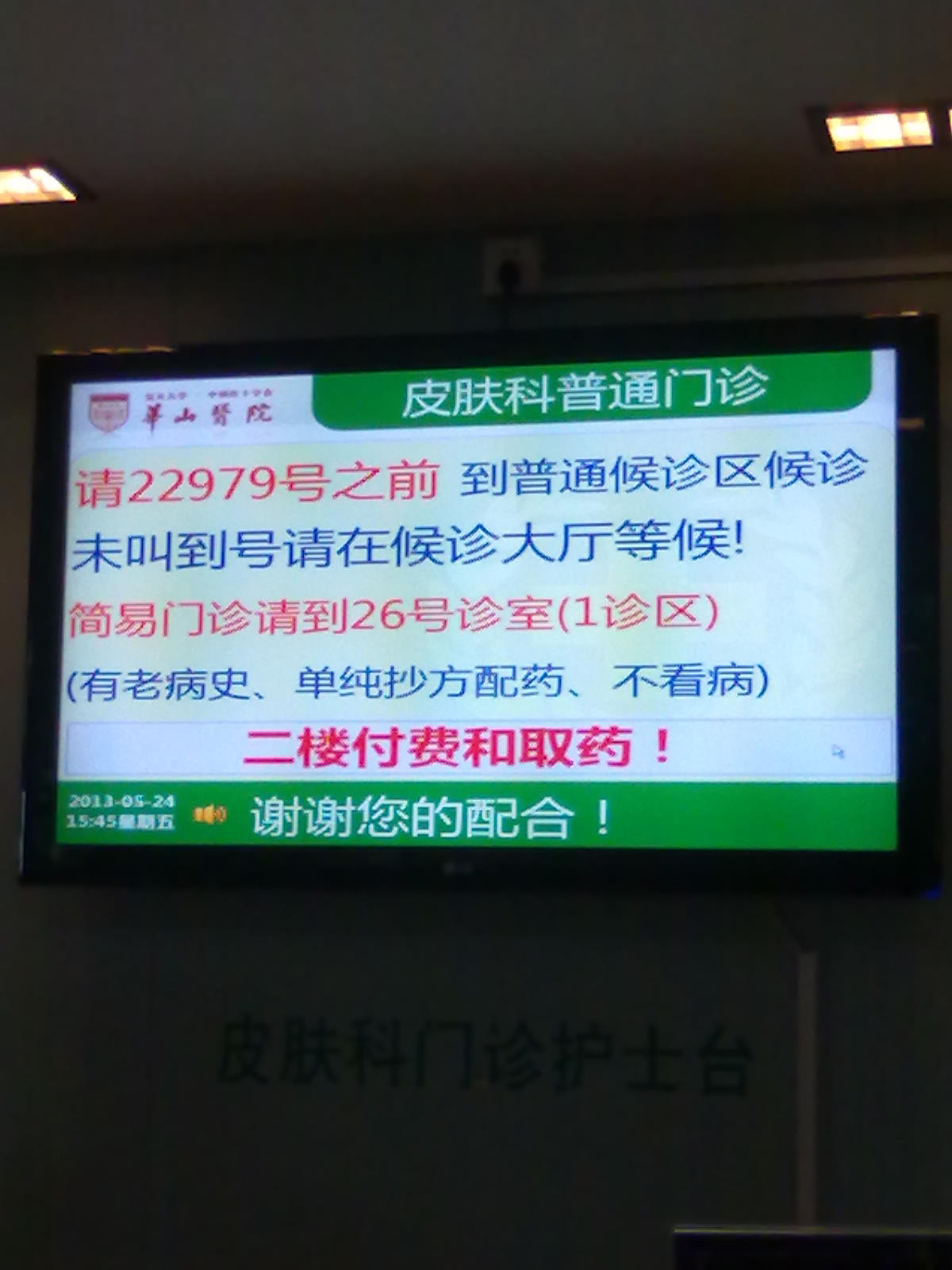「中国はコネ社会」などとよく言われることがあります。
「コネ」は「関係」と言い換えてもいいと思いますが、この評価や認識は私自身もかなり正確な指摘だと考えています。
こうした中国社会の背景には、公や社会制度に対する信頼が低いということが大きく関係していると言われます。
自国の公や社会制度が十分に信頼できないものだ、と中国の人々が認識しているからこそ、
中国では組織よりも人と人との関係に重点を置くようになっているのが実態です。
そうした具体例を日本と中国の比較を通して、今回は紹介したいと思っています。
まず、一つの例として挙げたいのが、日本人の会社組織に対する考え方と、中国人のそれとの違いです。
日本人は会社組織で様々な案件が動くので担当者が誰であったとしても、組織の方針や意志は不変であることが普通です。
だからこそ、担当者が誰であろうと、また人事異動で誰に変ろうとも、まずは会社組織の一員として対します。
何より日本の場合、「○○会社という大手の社員だから信頼できる」などというように、
まずは組織そのものを信頼するという傾向が強いことが特徴です。
一方、中国人の場合、日本とは対照的です。
すなわち、中国人は担当者が変われば組織も変わると考えることが多いものです。
だからこそ、担当者が人事異動で動く際には、「あなたは今度どこに?」と聞いてくることが多いようです。
日本では「後任はどなたですか?」と次の担当者を尋ねるのが一般的だと思います。
ここからも、中国人は会社組織そのものを信頼するというよりも、
社員一人との関係を重視していることが伺え、信頼できるものは組織ではなく人であることが理解できます。
私は中国生活5年ですが、この間、自然に人と人との関係を重視する生き方を身につけていくようになっていきました。
具体的には、自身の研究支援を中国で受ける場合、誰に頼めばもっとも案件が動くか、
仕事の環境を改善する為には誰に依頼すればいいのか、など様々な問題を組織に頼らずに、
個人的に「この人だ」と考えた人に依頼をし、各問題を解決するように心がけたものです。
もちろん、このためにはきちんと日頃から多くの人間との信頼関係を築いていく事が何よりも大切です。
ともかく、この方が迅速に、かつ高い確率で物事が動くので効果的でした。
中国人との信頼関係の築くために私が気をつけたことは二つあります。
一つ:誠実に仕事に取り組み、ごまかさない。
二つ:依頼を簡単に断らずに、可能な限り引き受けて精一杯やってみる。
ということでした。
一番目は日本でも世界でも共通することだと思いますが、二番目も中国では結構重要なことだと思います。
すぐに「できない」という人間を中国人は信頼してくれません。
まずは「やってみる」という熱意、その姿勢を見せ、実際に何とかやりとげていく人間を信頼します。
もちろん無理難題は断った方がいいのかもしれませんが、大抵の要求は出来るものです。
実際、厳しい要求を引き受け見事にやり遂げた時は、相手との強い信頼が生まれます。
日本と中国、組織を信頼する国と、もう一方は個人個人を信頼する国。
本当に対照的な国だと思います。
しかし、どちらの国でも「信頼」を何よりも重視して関係が構築されているのは同じことに気づきます。
要は、国のあり方が違うために、その「信頼」の構築形態が異なっているだけにすぎないと私は思います。
「コネ」は「関係」と言い換えてもいいと思いますが、この評価や認識は私自身もかなり正確な指摘だと考えています。
こうした中国社会の背景には、公や社会制度に対する信頼が低いということが大きく関係していると言われます。
自国の公や社会制度が十分に信頼できないものだ、と中国の人々が認識しているからこそ、
中国では組織よりも人と人との関係に重点を置くようになっているのが実態です。
そうした具体例を日本と中国の比較を通して、今回は紹介したいと思っています。
まず、一つの例として挙げたいのが、日本人の会社組織に対する考え方と、中国人のそれとの違いです。
日本人は会社組織で様々な案件が動くので担当者が誰であったとしても、組織の方針や意志は不変であることが普通です。
だからこそ、担当者が誰であろうと、また人事異動で誰に変ろうとも、まずは会社組織の一員として対します。
何より日本の場合、「○○会社という大手の社員だから信頼できる」などというように、
まずは組織そのものを信頼するという傾向が強いことが特徴です。
一方、中国人の場合、日本とは対照的です。
すなわち、中国人は担当者が変われば組織も変わると考えることが多いものです。
だからこそ、担当者が人事異動で動く際には、「あなたは今度どこに?」と聞いてくることが多いようです。
日本では「後任はどなたですか?」と次の担当者を尋ねるのが一般的だと思います。
ここからも、中国人は会社組織そのものを信頼するというよりも、
社員一人との関係を重視していることが伺え、信頼できるものは組織ではなく人であることが理解できます。
私は中国生活5年ですが、この間、自然に人と人との関係を重視する生き方を身につけていくようになっていきました。
具体的には、自身の研究支援を中国で受ける場合、誰に頼めばもっとも案件が動くか、
仕事の環境を改善する為には誰に依頼すればいいのか、など様々な問題を組織に頼らずに、
個人的に「この人だ」と考えた人に依頼をし、各問題を解決するように心がけたものです。
もちろん、このためにはきちんと日頃から多くの人間との信頼関係を築いていく事が何よりも大切です。
ともかく、この方が迅速に、かつ高い確率で物事が動くので効果的でした。
中国人との信頼関係の築くために私が気をつけたことは二つあります。
一つ:誠実に仕事に取り組み、ごまかさない。
二つ:依頼を簡単に断らずに、可能な限り引き受けて精一杯やってみる。
ということでした。
一番目は日本でも世界でも共通することだと思いますが、二番目も中国では結構重要なことだと思います。
すぐに「できない」という人間を中国人は信頼してくれません。
まずは「やってみる」という熱意、その姿勢を見せ、実際に何とかやりとげていく人間を信頼します。
もちろん無理難題は断った方がいいのかもしれませんが、大抵の要求は出来るものです。
実際、厳しい要求を引き受け見事にやり遂げた時は、相手との強い信頼が生まれます。
日本と中国、組織を信頼する国と、もう一方は個人個人を信頼する国。
本当に対照的な国だと思います。
しかし、どちらの国でも「信頼」を何よりも重視して関係が構築されているのは同じことに気づきます。
要は、国のあり方が違うために、その「信頼」の構築形態が異なっているだけにすぎないと私は思います。