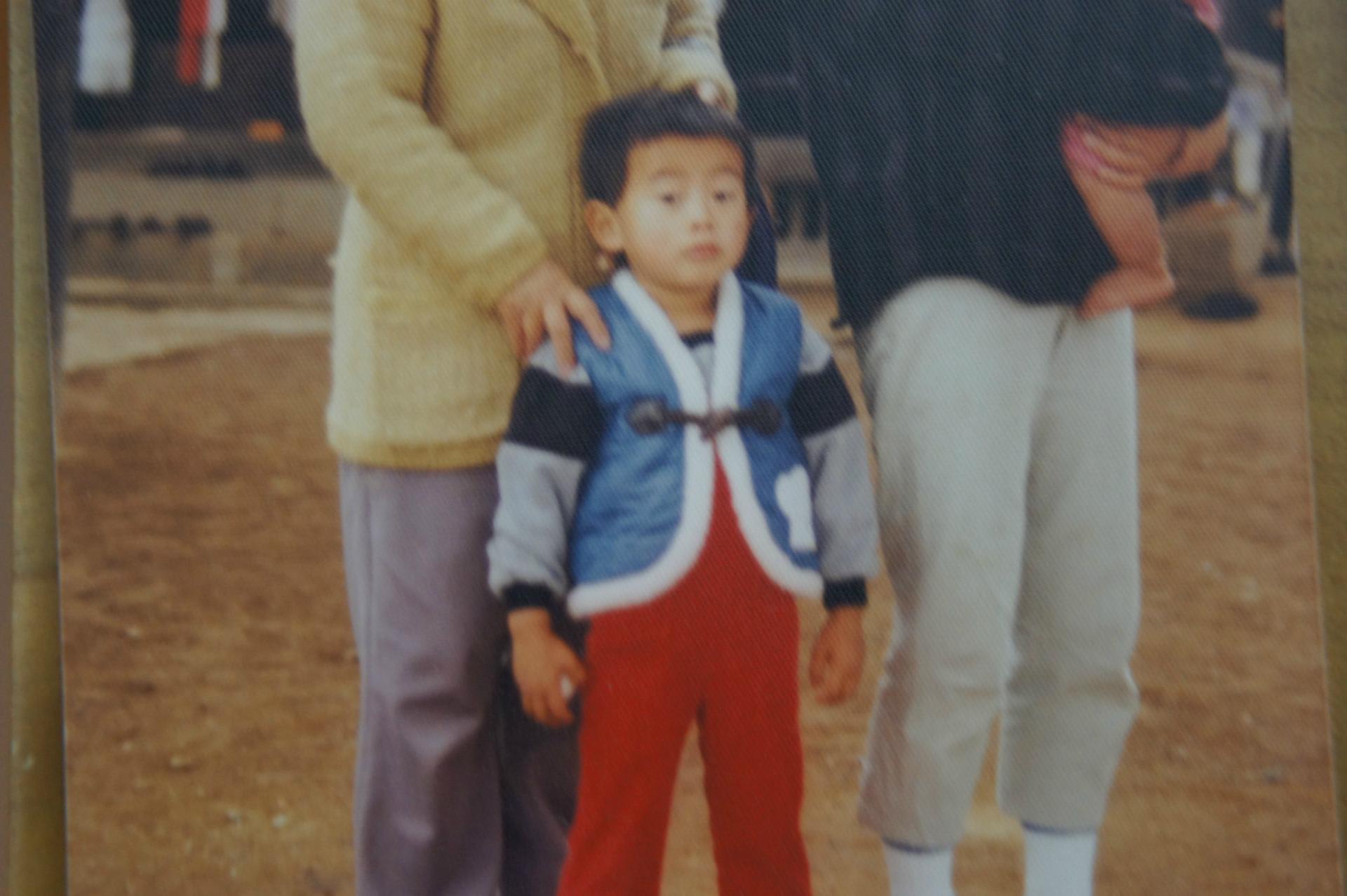今夜は18-20時半まで日本語を第二専攻とする大学生達を対象とした卒業論文の書き方をレクチャーする授業がありました。
そして明日から10月7日までは、中国の国慶節休暇(建国記念日の連休)に入ります。
この間は特に遊びに出かけたりする予定はなく、10月19、20日の学会発表準備を行う予定です。
その発表準備のため、今週は授業のない日を利用して上海档案館で資料を集めに行きました。
下の写真は現在(2013年9月)、上海市档案館で開催されている歴史展示の案内ポスター。
「外国人記者の目から見た“中国共産党人”」という展示を私も見てきました。
「中国共産党員」ではなく、「中国共産党人」という言葉を使い、国内の人々ではなく外国人記者が自分達を「客観的」にどうみたかを展示するところに、この展示の目的がよく表れているという印象を持ちました。

档案館にて目当ての資料を閲覧し、必要部分をコピー申請しようとすると新たな規則に変更されていることに気づきました。
変更された点は以下の通り。
・コピー申請は一日に一人50枚まで(※パソコンなどで手入力する場合は例外)
・各档案はその三分の一までが、当日コピー申請が可能
・その際、コピー費用は無料
このため遠方から資料収集に来た研究者などにとっては、長期滞在でもしない限りは効率的な档案収集が難しくなったといえそうです。
手入力ならば制限はかかりませんが、当然のことながら時間が膨大にかかるので効率は良くありません。
逆に上海在住の研究者の場合は何度でも通えますし、コピーのための「人材」を連れていけば一気に档案収集が可能です。
(あくまでも、「一人で一日50枚」なので…)
一気にコピーしても無料なので、中国(特に上海)在住の研究者にとっては档案収集が随分しやすくなったともいえるかもしれません。
なお、北京市档案館などでもこのケースは同様で、北京市档案館では一日にコピー申請が20枚までとなったそうです。
7月に上海市・北京市档案館を訪れた時、この規則はまだ施行前だったので、恐らく8月、9月以降に開始された模様です。
地方の档案館が全てこのような規則に変更されたのかはまだ確認していないので、次回また情報が入れば御紹介します。
明日明後日と授業準備をした後は、基本的に档案館か自宅での報告準備、論文執筆に没頭します。
中国に戻って以来、久々の研究に専念できる時期が始まりました。
そして明日から10月7日までは、中国の国慶節休暇(建国記念日の連休)に入ります。
この間は特に遊びに出かけたりする予定はなく、10月19、20日の学会発表準備を行う予定です。
その発表準備のため、今週は授業のない日を利用して上海档案館で資料を集めに行きました。
下の写真は現在(2013年9月)、上海市档案館で開催されている歴史展示の案内ポスター。
「外国人記者の目から見た“中国共産党人”」という展示を私も見てきました。
「中国共産党員」ではなく、「中国共産党人」という言葉を使い、国内の人々ではなく外国人記者が自分達を「客観的」にどうみたかを展示するところに、この展示の目的がよく表れているという印象を持ちました。

档案館にて目当ての資料を閲覧し、必要部分をコピー申請しようとすると新たな規則に変更されていることに気づきました。
変更された点は以下の通り。
・コピー申請は一日に一人50枚まで(※パソコンなどで手入力する場合は例外)
・各档案はその三分の一までが、当日コピー申請が可能
・その際、コピー費用は無料
このため遠方から資料収集に来た研究者などにとっては、長期滞在でもしない限りは効率的な档案収集が難しくなったといえそうです。
手入力ならば制限はかかりませんが、当然のことながら時間が膨大にかかるので効率は良くありません。
逆に上海在住の研究者の場合は何度でも通えますし、コピーのための「人材」を連れていけば一気に档案収集が可能です。
(あくまでも、「一人で一日50枚」なので…)
一気にコピーしても無料なので、中国(特に上海)在住の研究者にとっては档案収集が随分しやすくなったともいえるかもしれません。
なお、北京市档案館などでもこのケースは同様で、北京市档案館では一日にコピー申請が20枚までとなったそうです。
7月に上海市・北京市档案館を訪れた時、この規則はまだ施行前だったので、恐らく8月、9月以降に開始された模様です。
地方の档案館が全てこのような規則に変更されたのかはまだ確認していないので、次回また情報が入れば御紹介します。
明日明後日と授業準備をした後は、基本的に档案館か自宅での報告準備、論文執筆に没頭します。
中国に戻って以来、久々の研究に専念できる時期が始まりました。