<超心理学と懐疑論者たち(15-2)>
第15章:科学とは何か
(2)理論の役割
科学の目指すところは一言で言えば、普遍的な理論を築くこと
である。理論という言葉は日常では、現実と異なる不確かなもの
という意味合いがあるが、科学探究の文脈では、観察によって
確実になったものである。
理論は、いったん形成されると、理論に従った観察が行なわれ
検証が繰り返されていく。科学哲学者のカール・ポパーは、フロイト
の精神分析理論が、どんな患者の疾患も説明できてしまう問題を
指摘し、理論には反証可能性が必要だと主張した。相対論などの
物理理論は、未来の観測結果を予想する反証可能な理論なのだ。
ポパーは、反証可能性でもって、科学と疑似科学の境界設定を
行なう提案をした。ただし、反証可能性だけでは境界設定は完全
ではない。理論が近似である場合は反証可能にはならず、他の
理論と近似の程度を競うことになる。
形而上学的な世界観はそれ自体では検証できない。しかし、理論が
それを含意することがある。ニュートン物理学は、世界が機械仕掛け
の決定論であるという世界観をともなっていたが、量子物理学に
理論が改訂され、決定論は棄却された。
http://www.kisc.meiji.ac.jp/~metapsi/psi/8-2.htm
第15章:科学とは何か
(2)理論の役割
科学の目指すところは一言で言えば、普遍的な理論を築くこと
である。理論という言葉は日常では、現実と異なる不確かなもの
という意味合いがあるが、科学探究の文脈では、観察によって
確実になったものである。
理論は、いったん形成されると、理論に従った観察が行なわれ
検証が繰り返されていく。科学哲学者のカール・ポパーは、フロイト
の精神分析理論が、どんな患者の疾患も説明できてしまう問題を
指摘し、理論には反証可能性が必要だと主張した。相対論などの
物理理論は、未来の観測結果を予想する反証可能な理論なのだ。
ポパーは、反証可能性でもって、科学と疑似科学の境界設定を
行なう提案をした。ただし、反証可能性だけでは境界設定は完全
ではない。理論が近似である場合は反証可能にはならず、他の
理論と近似の程度を競うことになる。
形而上学的な世界観はそれ自体では検証できない。しかし、理論が
それを含意することがある。ニュートン物理学は、世界が機械仕掛け
の決定論であるという世界観をともなっていたが、量子物理学に
理論が改訂され、決定論は棄却された。
http://www.kisc.meiji.ac.jp/~metapsi/psi/8-2.htm










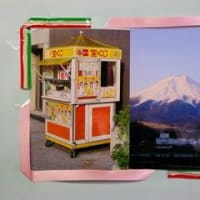
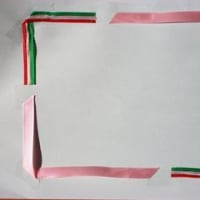


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます