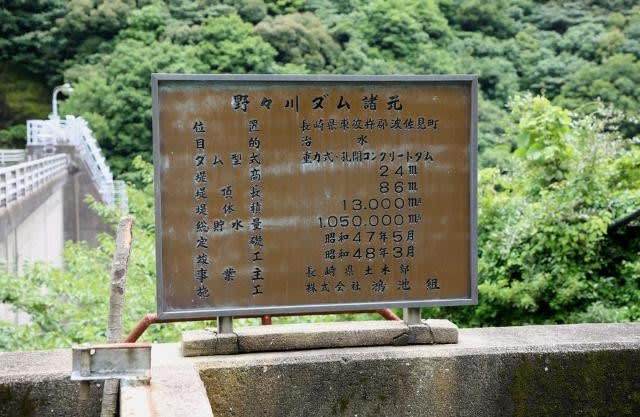2019年7月11日 繁昌ダム
繁昌ダムは佐賀県武雄市朝日町中野の六角川水系高橋川右支流繁昌川にある灌漑目的のアースフィルダムです。
農水省の補助を受けた佐賀県の事業により1973年(昭和48年)から建設がすすめられ1978年(昭和53年)に竣工しました。
運用開始後は武雄東部土地改良区が受託管理を行い、武雄市北東部の農地356.6ヘクタールに灌漑用水を供給しています。
堤高は30メートル弱ですが、かなり下流から堤体を遠望できます。

管理事務所のある左岸ダムサイトに市道が通じています。
天端も車両の通行が可能。

天端からの眺め
左下に放流設備が見えます。

総貯水容量64万5000立米の貯水池。
貯水池を周回する道路がつけられています。

左岸の斜樋。

右岸の金箔仕様の竣工記念碑が建ちます。

右岸の横越流式洪水吐。

上流面
ロック材で護岸されています。
奥の白い建屋が管理事務所。

ダム下に下りてみました。
これは放流設備。バルブが2条見えます。

草を掻き分け洪水吐減勢工から斜水路を見上げます。

(追記)
繁昌ダムは洪水調節容量を持たない利水ダムですが、治水協定により台風等の襲来に備え事前放流を行う予備放流容量が配分されました。
2536 繁昌ダム(1472)
佐賀県武雄市朝日町中野
六角川水系繁昌川
A
E
29.4メートル
156メートル
645千㎥/596千㎥
武雄東部土地改良区
1978年
◎治水協定が締結されたダム