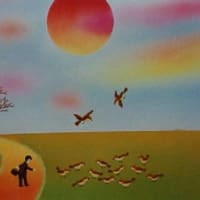(写真は「経営コンサルタント」取締役時代)
失業保険で暮らしているさなか、なんとか自分の今までの文学性の総結集とも言える「存在の彷徨」という哲学小説が完成していた。俺にとっては文学への関わりあいの遺作とも言える作品だった。埴谷雄高の「死霊」とサルトルの「嘔吐」に影響を受けた、「存在する意識」をテーマにしたものだった。俺は五木寛之審査委員長のノンフィックションの「親鸞賞」に応募した。小説だが意識というテーマではノンフィックションだったからだ。しかしあまりにも実験的な文体だったので、公募には一次予選も通過せず、落選した。しかし、世間では愚作であっても、自分には文学に対する遺書のようなものだった。それなりに満足し、俺はこれで永久に文学から足を洗おうと思った。丁度この時期に親友二人と叔父が相次いでこの世を去った。親友二人はともに高校時代からの友人だった。そして二人とも京都から東京に出てきたという縁がある。ひとりは津岡良一君。彼は一人っ子で身体が小さかったコンプレックスからか、一浪して、高崎経済大学に入ると、空手部に所属した。俺もその頃もう上京していたから、高崎まで彼に会いに行ったことがある。二年の時だったから「ポンチュ(俺のあだ名)、先輩のシゴキがきつくてのう。来年になったら先輩側になるから、なんとか頑張るワ」とこぼしていた。そして卒業後、東京の証券会社に勤めたが有価証券がなかなか売れず、やめて、京都に戻った。その後、大阪本店の宝石販売の芝カン香に入社、再び東京支店に配属された。東京に来て、俺が立会人になって結婚し、三人の男の子の父親となった。日ごろはいい男なのだが、酒好きで、酒を飲むと竹刀を持って、子供たちを追っかけまわすというから奥さんは怯えていたようだ。仕事のほうは、東急百貨店の宝石売り場など15店舗を総括する立場にまで出世した。その後バブル崩壊で、均衡縮小となり、東京店は閉鎖、女房子供を東京に置いて、単身大阪店に呼び戻された。「ポンチュ、生きるというのは辛いのう」。彼はそう言って大阪に旅立って行った。出会うといつも「まいどー」という挨拶で始める彼は、漫才のやすきよのやっさんのような性格だった。
もうひとりは新谷忍君。彼とは高校二年の時に同じクラスで意気投合した。若き日の西郷輝彦のような美男子だった。将来は学校の先生になることを夢見て、新潟大学の教育学部に入った。そこまではよかったのだが、入部した体育クラブのシゴキに遭って、耐えられず、学校を辞めてしまった。両親に学費を出してもらっていたので京都の実家には居られず、俺のいる東京のアパートに居候した。その後、銀座にある映画倫理委員会の事務局に勤めるようになったが、局内には一流大学の高学歴者ばかりで、三年くらいで辞め、建材新聞という業界紙の記者になった。そこも四年ほどで辞め、今度は田町で沖ナカシをやっていた。そしてしばらくして彼は京都に戻り、「新大阪」という夕刊紙の社会部記者になって活躍した。その後また業界紙の記者に転職し、49歳で肺がんを発病した。「ポンチュ、咳すると痰に血が混じってた」。いつも掛けてくる電話の向こうで、彼は結核を恐れていたが、肺がんだった。翌年、彼は50歳の若さでこの世を去った。そして彼の御通夜の席で「50歳か、若すぎるなあ」と言っていた津岡良一が、三ヶ月後、京都伏見の実家近くで若い暴走族らしきものに襲われ、あっけなくこの世を去った。また、読売新聞に勤めていたジャーナリストの先輩の叔父も同時期他界し、俺は僅か半年の間に最も大事な三人も弔辞を読むことになった。人生は一度っきり。そういう思いが強く心の中で渦巻いていた。
失業保険で暮らしているさなか、なんとか自分の今までの文学性の総結集とも言える「存在の彷徨」という哲学小説が完成していた。俺にとっては文学への関わりあいの遺作とも言える作品だった。埴谷雄高の「死霊」とサルトルの「嘔吐」に影響を受けた、「存在する意識」をテーマにしたものだった。俺は五木寛之審査委員長のノンフィックションの「親鸞賞」に応募した。小説だが意識というテーマではノンフィックションだったからだ。しかしあまりにも実験的な文体だったので、公募には一次予選も通過せず、落選した。しかし、世間では愚作であっても、自分には文学に対する遺書のようなものだった。それなりに満足し、俺はこれで永久に文学から足を洗おうと思った。丁度この時期に親友二人と叔父が相次いでこの世を去った。親友二人はともに高校時代からの友人だった。そして二人とも京都から東京に出てきたという縁がある。ひとりは津岡良一君。彼は一人っ子で身体が小さかったコンプレックスからか、一浪して、高崎経済大学に入ると、空手部に所属した。俺もその頃もう上京していたから、高崎まで彼に会いに行ったことがある。二年の時だったから「ポンチュ(俺のあだ名)、先輩のシゴキがきつくてのう。来年になったら先輩側になるから、なんとか頑張るワ」とこぼしていた。そして卒業後、東京の証券会社に勤めたが有価証券がなかなか売れず、やめて、京都に戻った。その後、大阪本店の宝石販売の芝カン香に入社、再び東京支店に配属された。東京に来て、俺が立会人になって結婚し、三人の男の子の父親となった。日ごろはいい男なのだが、酒好きで、酒を飲むと竹刀を持って、子供たちを追っかけまわすというから奥さんは怯えていたようだ。仕事のほうは、東急百貨店の宝石売り場など15店舗を総括する立場にまで出世した。その後バブル崩壊で、均衡縮小となり、東京店は閉鎖、女房子供を東京に置いて、単身大阪店に呼び戻された。「ポンチュ、生きるというのは辛いのう」。彼はそう言って大阪に旅立って行った。出会うといつも「まいどー」という挨拶で始める彼は、漫才のやすきよのやっさんのような性格だった。
もうひとりは新谷忍君。彼とは高校二年の時に同じクラスで意気投合した。若き日の西郷輝彦のような美男子だった。将来は学校の先生になることを夢見て、新潟大学の教育学部に入った。そこまではよかったのだが、入部した体育クラブのシゴキに遭って、耐えられず、学校を辞めてしまった。両親に学費を出してもらっていたので京都の実家には居られず、俺のいる東京のアパートに居候した。その後、銀座にある映画倫理委員会の事務局に勤めるようになったが、局内には一流大学の高学歴者ばかりで、三年くらいで辞め、建材新聞という業界紙の記者になった。そこも四年ほどで辞め、今度は田町で沖ナカシをやっていた。そしてしばらくして彼は京都に戻り、「新大阪」という夕刊紙の社会部記者になって活躍した。その後また業界紙の記者に転職し、49歳で肺がんを発病した。「ポンチュ、咳すると痰に血が混じってた」。いつも掛けてくる電話の向こうで、彼は結核を恐れていたが、肺がんだった。翌年、彼は50歳の若さでこの世を去った。そして彼の御通夜の席で「50歳か、若すぎるなあ」と言っていた津岡良一が、三ヶ月後、京都伏見の実家近くで若い暴走族らしきものに襲われ、あっけなくこの世を去った。また、読売新聞に勤めていたジャーナリストの先輩の叔父も同時期他界し、俺は僅か半年の間に最も大事な三人も弔辞を読むことになった。人生は一度っきり。そういう思いが強く心の中で渦巻いていた。