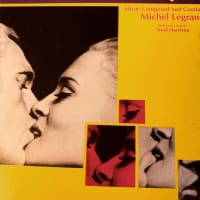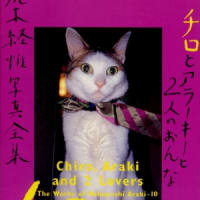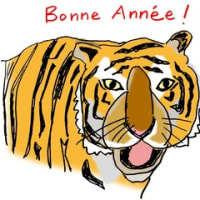音楽美学講座、楽理編曲科では
革命が起きそうな状況らしい(笑)
というのは、私が在籍する楽理初等科と
高等科の講義内容が
極めて接近し始めているようなのだ、、、
初等科の理解度が高等科を抜いてしまったら
これは革命になります、と(笑)
まあそれは冗談だとしても
双方のクラスの生徒のモチベーションを
高めるうえでも面白い展開になっているのでは
と思ってみたりも。
私見的推測をしてみると、クラス全体の
理解度にあわせて教える進度も変化するという
やり方から(高等科のクラスと授業を知らないので)
クラスの優劣とかいう事ではなく
どうやらこの初等科の生徒の面々は
(この際自分を除き)
いろいろな意味で偏差値というか水準が
高い集まりのように思う、それは出席率からみた
モチベーションからしても、一般的判断として
彼らの所属大学を聞いても。
講義のたびに先生が感心するのは
多少の遅刻はあったとしても
ほぼ毎回生徒全員が揃うという事は凄い
講義が始まる前に隣席のMちゃんに
コードを弾いてもらいルートを出題するという
プチ講義をしてもらう…何となく
娘に教えてもらっている(居ないけど)気分に(笑)
社会人で時間が無いということを理由に
しっかり復習をしていない事が
露呈してしまい焦る
と共に
わたし、脳みそのしわがホントに足りないわ、と
残念に思いつつ(笑)
本物の楽理の講義に突入した。
やっぱりどう考えても佳境に入りまくっている(笑)事を
実感する講義は
今日初めて聴いた言葉「ケーデンスライン」が
奏でる音韻情報に「…」
感嘆する私であった
<今日の教訓>
1.最も不協和(響和)である増4度(ドミナント[=D]※注1)は
2.最も協和的である長3度(トニック[=T]※注2)によって
解決(収束)する。
3.音響(音響物理学、自然物理的ーEx:吐息など・笑)と
4.音韻(言語構造的ー意味解釈的)
※注1(ドミナント)=属調
長・短音階で、主音の五度上の音。
主音の五度下の下属音と区別する場合、特に上属音ともいう。
※注2(トニック)=主調
(楽曲の中心となる主要な調。調性音楽では
一般に曲の始めと終わりは主調。基調。
全体を通しての主となる調子。)
<body>
<script type="text/javascript" src="http://www.research-artisan.com/userjs/?h=0&user_id=20060529000243138"></script><noscript>
</body>
革命が起きそうな状況らしい(笑)
というのは、私が在籍する楽理初等科と
高等科の講義内容が
極めて接近し始めているようなのだ、、、
初等科の理解度が高等科を抜いてしまったら
これは革命になります、と(笑)
まあそれは冗談だとしても
双方のクラスの生徒のモチベーションを
高めるうえでも面白い展開になっているのでは
と思ってみたりも。
私見的推測をしてみると、クラス全体の
理解度にあわせて教える進度も変化するという
やり方から(高等科のクラスと授業を知らないので)
クラスの優劣とかいう事ではなく
どうやらこの初等科の生徒の面々は
(この際自分を除き)
いろいろな意味で偏差値というか水準が
高い集まりのように思う、それは出席率からみた
モチベーションからしても、一般的判断として
彼らの所属大学を聞いても。
講義のたびに先生が感心するのは
多少の遅刻はあったとしても
ほぼ毎回生徒全員が揃うという事は凄い
講義が始まる前に隣席のMちゃんに
コードを弾いてもらいルートを出題するという
プチ講義をしてもらう…何となく
娘に教えてもらっている(居ないけど)気分に(笑)
社会人で時間が無いということを理由に
しっかり復習をしていない事が
露呈してしまい焦る
と共に
わたし、脳みそのしわがホントに足りないわ、と
残念に思いつつ(笑)
本物の楽理の講義に突入した。
やっぱりどう考えても佳境に入りまくっている(笑)事を
実感する講義は
今日初めて聴いた言葉「ケーデンスライン」が
奏でる音韻情報に「…」
感嘆する私であった
<今日の教訓>
1.最も不協和(響和)である増4度(ドミナント[=D]※注1)は
2.最も協和的である長3度(トニック[=T]※注2)によって
解決(収束)する。
3.音響(音響物理学、自然物理的ーEx:吐息など・笑)と
4.音韻(言語構造的ー意味解釈的)
※注1(ドミナント)=属調
長・短音階で、主音の五度上の音。
主音の五度下の下属音と区別する場合、特に上属音ともいう。
※注2(トニック)=主調
(楽曲の中心となる主要な調。調性音楽では
一般に曲の始めと終わりは主調。基調。
全体を通しての主となる調子。)
<body>
<script type="text/javascript" src="http://www.research-artisan.com/userjs/?h=0&user_id=20060529000243138"></script><noscript>
</body>