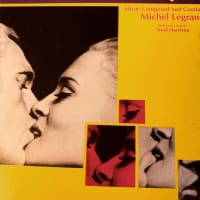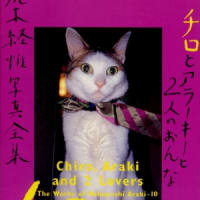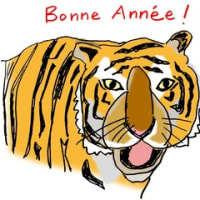ドミナントについて考えていた。
美術作家の中村ケンゴさんの日記(最近復活したそうです)
『ブログ作法』を読んでいて、作家の内田樹さんが
(私はこの方の文章がとても好きで良く日記を拝読していて
ちなみに内田さんは今月4月号のユリイカで
ブログ作法について書いてました)
よくドミナントという言葉を文中で
多用している事を想い出した。
内田さんは英語のそのままの意味で
使っているんだろうけど気になったので
改めて調べてみる、
そういえば
映画美学校の特別講義『音と映像』:岸野雄一さん編で
配られた資料にて
<映画における第四次元:エイゼンシュタイン著作集より>
ドミナントについて言及されていた事も想い出す、
面白かったので、ここに記録しておこう。
☆2
ここで使われている”ドミナント”とは
音楽用語としての意味を前提としている。
すなわち、主音(トニック=音階の中心となる第1音)に次いで
重要な音で、"調を支配する":ドミナント)
=(主音)の5度上の音、
またはその上に組み立てられた和音を指す。
エイゼンシュタインは論文中で、
必ずしも音楽用語の定義の従ってドミナント、
トニックの両用語を厳密に区分して用いてはいない。
そしてまた、この用語(ドミナント)に、
否定と肯定の二重の意味をかぶせているようだ。
一方は
「正統的で衒学的※1
(※1:学者ぶるさま。学識をひけらかすさま。ペダンチック)な
ドミナント」であり、他方は
「素材と素材のあいだに…生理学的符合を置いてしまう」という
ドミナントである。
後者の用語法は、ロシア・フォルマリズムの
主要な用語であり、V・エイヘンバウムによって
定式化された概念と共通する。
つまりフォルマリズムの詩学でいう、作品中の
「さまざまなレヴェルはその相互関係によって
一つの効果をもたらすとともに、
それ自体が独立の価値を有しドミナントとなりうる」
という考えとの共通点である。
以上
<映画における第四次元:エイゼンシュタイン著作集より>
岸野さんはエイゼンシュタインの論文は
少々怪しい部分もあって全てを信用していないと(確か)
触れていたが、資料が配られただけあって
面白い、訳がわからない部分も含め(笑)
一読の価値はある。
両義性を内包している
映像的観点から捉えたドミナント、
音楽的定義におけるドミナントと
比較してみるのは興味深い…が
また「わからない」の種が一つ、
私に植わった。
美術作家の中村ケンゴさんの日記(最近復活したそうです)
『ブログ作法』を読んでいて、作家の内田樹さんが
(私はこの方の文章がとても好きで良く日記を拝読していて
ちなみに内田さんは今月4月号のユリイカで
ブログ作法について書いてました)
よくドミナントという言葉を文中で
多用している事を想い出した。
内田さんは英語のそのままの意味で
使っているんだろうけど気になったので
改めて調べてみる、
そういえば
映画美学校の特別講義『音と映像』:岸野雄一さん編で
配られた資料にて
<映画における第四次元:エイゼンシュタイン著作集より>
ドミナントについて言及されていた事も想い出す、
面白かったので、ここに記録しておこう。
☆2
ここで使われている”ドミナント”とは
音楽用語としての意味を前提としている。
すなわち、主音(トニック=音階の中心となる第1音)に次いで
重要な音で、"調を支配する":ドミナント)
=(主音)の5度上の音、
またはその上に組み立てられた和音を指す。
エイゼンシュタインは論文中で、
必ずしも音楽用語の定義の従ってドミナント、
トニックの両用語を厳密に区分して用いてはいない。
そしてまた、この用語(ドミナント)に、
否定と肯定の二重の意味をかぶせているようだ。
一方は
「正統的で衒学的※1
(※1:学者ぶるさま。学識をひけらかすさま。ペダンチック)な
ドミナント」であり、他方は
「素材と素材のあいだに…生理学的符合を置いてしまう」という
ドミナントである。
後者の用語法は、ロシア・フォルマリズムの
主要な用語であり、V・エイヘンバウムによって
定式化された概念と共通する。
つまりフォルマリズムの詩学でいう、作品中の
「さまざまなレヴェルはその相互関係によって
一つの効果をもたらすとともに、
それ自体が独立の価値を有しドミナントとなりうる」
という考えとの共通点である。
以上
<映画における第四次元:エイゼンシュタイン著作集より>
岸野さんはエイゼンシュタインの論文は
少々怪しい部分もあって全てを信用していないと(確か)
触れていたが、資料が配られただけあって
面白い、訳がわからない部分も含め(笑)
一読の価値はある。
両義性を内包している
映像的観点から捉えたドミナント、
音楽的定義におけるドミナントと
比較してみるのは興味深い…が
また「わからない」の種が一つ、
私に植わった。