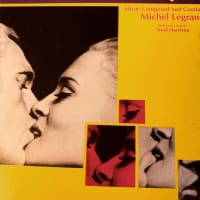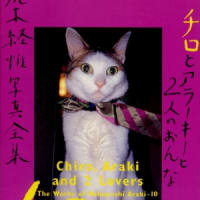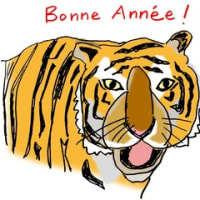2006年の今頃に備忘したこの記事に
割と多いアクセスを頂いているようなので
(美学校の初等科の記事に、ということだと思うのですが)
YouTubeの動画付きでちょっと詳細に追記してみます。
久々に坂本龍一のピアノ演奏をまとめて聴いた。
去年の22日に国際フォーラムで開催された、
<坂本龍一 PLAY THE PIANO 2005>
BSデジタルの番組をチェックしていたら偶然放送を発見。
豊かなのに余計な力が抜けていて素晴らしい演奏だった。
happyend / RyuichiSakamoto
以前雑誌を読んだとき矢野顕子が言っていた言葉を思い出す。
彼は演奏家としても素晴らしいのだけど
最近は、それを聴けなくて残念だ、と。あれから数年・・・
殊に、2台のピアノを使った(片方は自分の演奏を
記録してあるMIDIピアノ)ご本人いわく
一人時間差(笑)デュエットは圧巻。この手法で
演奏したい人って居るだろうな、フルコンサートのピアノ
2台持ってなくちゃいけないけど、、、
「Tibetan Dance」at a rehearsal(090417 Toyama)
そういえば、このコンサートが行われた
12月22日は2005年最後の映画美学校の講義だった。
あの日、事前に用があって有楽町から美学校に向かう途中、
国際フォーラムの裏手を通ったら
巨大なトラックが何台も止まっていて
ものものしかった事を思い出した。
(CO2フリーコンサートでピアノの上にはキャンドルが置かれていた)
トラックに坂本龍一の名が刻まれていて、
このコンサートに行きたいなと思っていたので
「ああ、今日がそうなんだ」と心の中で呟き、通り過ぎたのだった。
私が坂本龍一の存在を知ってから、
実に人生の半分を越えていたことに気がつく、、、(笑)
これまでも日記に何度か触れたけど、
私が『作曲/編曲』という事に具体的な関心を持ったのは
この人の存在を知ってから。
私はフツーに子供の頃から昭和歌謡(笑)や
洋楽や、イージーリスニングやディスコなどの
POPSと同様にクラシックを聴いていて、
その何れも同じくらい好きだった。
好きな音楽はカテゴリーを超えて
いつでも自然に耳に入って来たのだ。
だから、坂本龍一のような人は鮮烈だった。
クラシック畑でいて、歌謡曲の編曲もする。
そして、それが決して邪道にならなくて王道になる。
誰にでも出来る事ではないと思う。
そして日本におけるテクノポップなる音楽の創始に関わり
美しくポピュラリティーのある曲を作り
編曲もして、前衛的だったり実験的な現代音楽も、
(以前日記に書いた、「千のナイフ』に代表される)世に残している。
私はこの人が持つ和声(ハーモニー)やメロディの感覚が好きで
ピアノを弾く人ならではの編曲だ、と思う。
ピアノはオーケストラの音階を持っている。
一人でオーケストラ的な演奏をする事も可能。
彼のオーケストレーション、
特にストリングスのアレンジは秀逸だ。
10代の頃YMOのRYDEENを聴いて、
編曲の力というものを初めて知った。
(これを作曲したのは高橋幸宏だったけど
編曲をしたのは坂本龍一だった)
初めて聴いたのは、初代ウォークマンで。
初めて体験するこのデジタルな音は、
後の私に音楽的な影響を与えた。
当時、欧米では日本発の、このテクノポップを
確か「バロックテクノ」とか
呼称されていた事を記憶してる。
今でもなお後世に続く世代のミュージシャンに影響を与えていて
カヴァーされ、その音楽の魅力は常に変容し
増大して未だ衰えていない。
当時、リアルタイムに一つの『潮流』を感じた。
カノン形式と思われる、たぶんにクラシカルな構成を持った
デジタルなこの曲は、10代の私にとってかなり強烈だった。
今聴くとやりすぎなくらいの(笑)テクノで
デジタルな展開のリズムのあと、曲の後半の
3:17のあたりから、楽器が一つずつ増えていきます。
[RYDEEN〔YMO〕
(曲をご存知の方は、よければ3:18あたりから、
文面と一緒にどうぞ)
ピッコロの装飾的なフレーズが加わり、
1オクターブ下のユニゾン、3度下のコーラスが加わって
ロマンティックなピアノの伴奏が入ったところで
全てのリズムが止まる、、、
という王道的で正統派のアレンジと、
デジタルの組み合わせに当時、ぐっときた(笑)
今でも魅力的。
50代になってなお坂本龍一氏は一層、素敵で、
演奏と共に魅力的に映った。
そして、先日の映画美学校の楽曲分析の講義は
坂本龍一繋がりがあった。
待ちに待ったアントニオカルロスジョビン。
3パターンのアレンジの中、菊地さんが楽曲分析のために
メインに取り上げられたのは坂本龍一のものだった。
「お馬鹿さん」としても有名な名曲「How Insensitive」
(A DAY in new yorkより)
insensatez morelembaumx2&sakamoto
<BODY>
<script type="text/javascript" src="http://www.research-artisan.com/userjs/?user_id=20060529000243138"></script><noscript>
</BODY>
割と多いアクセスを頂いているようなので
(美学校の初等科の記事に、ということだと思うのですが)
YouTubeの動画付きでちょっと詳細に追記してみます。
久々に坂本龍一のピアノ演奏をまとめて聴いた。
去年の22日に国際フォーラムで開催された、
<坂本龍一 PLAY THE PIANO 2005>
BSデジタルの番組をチェックしていたら偶然放送を発見。
豊かなのに余計な力が抜けていて素晴らしい演奏だった。
happyend / RyuichiSakamoto
以前雑誌を読んだとき矢野顕子が言っていた言葉を思い出す。
彼は演奏家としても素晴らしいのだけど
最近は、それを聴けなくて残念だ、と。あれから数年・・・
殊に、2台のピアノを使った(片方は自分の演奏を
記録してあるMIDIピアノ)ご本人いわく
一人時間差(笑)デュエットは圧巻。この手法で
演奏したい人って居るだろうな、フルコンサートのピアノ
2台持ってなくちゃいけないけど、、、
「Tibetan Dance」at a rehearsal(090417 Toyama)
そういえば、このコンサートが行われた
12月22日は2005年最後の映画美学校の講義だった。
あの日、事前に用があって有楽町から美学校に向かう途中、
国際フォーラムの裏手を通ったら
巨大なトラックが何台も止まっていて
ものものしかった事を思い出した。
(CO2フリーコンサートでピアノの上にはキャンドルが置かれていた)
トラックに坂本龍一の名が刻まれていて、
このコンサートに行きたいなと思っていたので
「ああ、今日がそうなんだ」と心の中で呟き、通り過ぎたのだった。
私が坂本龍一の存在を知ってから、
実に人生の半分を越えていたことに気がつく、、、(笑)
これまでも日記に何度か触れたけど、
私が『作曲/編曲』という事に具体的な関心を持ったのは
この人の存在を知ってから。
私はフツーに子供の頃から昭和歌謡(笑)や
洋楽や、イージーリスニングやディスコなどの
POPSと同様にクラシックを聴いていて、
その何れも同じくらい好きだった。
好きな音楽はカテゴリーを超えて
いつでも自然に耳に入って来たのだ。
だから、坂本龍一のような人は鮮烈だった。
クラシック畑でいて、歌謡曲の編曲もする。
そして、それが決して邪道にならなくて王道になる。
誰にでも出来る事ではないと思う。
そして日本におけるテクノポップなる音楽の創始に関わり
美しくポピュラリティーのある曲を作り
編曲もして、前衛的だったり実験的な現代音楽も、
(以前日記に書いた、「千のナイフ』に代表される)世に残している。
私はこの人が持つ和声(ハーモニー)やメロディの感覚が好きで
ピアノを弾く人ならではの編曲だ、と思う。
ピアノはオーケストラの音階を持っている。
一人でオーケストラ的な演奏をする事も可能。
彼のオーケストレーション、
特にストリングスのアレンジは秀逸だ。
10代の頃YMOのRYDEENを聴いて、
編曲の力というものを初めて知った。
(これを作曲したのは高橋幸宏だったけど
編曲をしたのは坂本龍一だった)
初めて聴いたのは、初代ウォークマンで。
初めて体験するこのデジタルな音は、
後の私に音楽的な影響を与えた。
当時、欧米では日本発の、このテクノポップを
確か「バロックテクノ」とか
呼称されていた事を記憶してる。
今でもなお後世に続く世代のミュージシャンに影響を与えていて
カヴァーされ、その音楽の魅力は常に変容し
増大して未だ衰えていない。
当時、リアルタイムに一つの『潮流』を感じた。
カノン形式と思われる、たぶんにクラシカルな構成を持った
デジタルなこの曲は、10代の私にとってかなり強烈だった。
今聴くとやりすぎなくらいの(笑)テクノで
デジタルな展開のリズムのあと、曲の後半の
3:17のあたりから、楽器が一つずつ増えていきます。
[RYDEEN〔YMO〕
(曲をご存知の方は、よければ3:18あたりから、
文面と一緒にどうぞ)
ピッコロの装飾的なフレーズが加わり、
1オクターブ下のユニゾン、3度下のコーラスが加わって
ロマンティックなピアノの伴奏が入ったところで
全てのリズムが止まる、、、
という王道的で正統派のアレンジと、
デジタルの組み合わせに当時、ぐっときた(笑)
今でも魅力的。
50代になってなお坂本龍一氏は一層、素敵で、
演奏と共に魅力的に映った。
そして、先日の映画美学校の楽曲分析の講義は
坂本龍一繋がりがあった。
待ちに待ったアントニオカルロスジョビン。
3パターンのアレンジの中、菊地さんが楽曲分析のために
メインに取り上げられたのは坂本龍一のものだった。
「お馬鹿さん」としても有名な名曲「How Insensitive」
(A DAY in new yorkより)
insensatez morelembaumx2&sakamoto
<BODY>
<script type="text/javascript" src="http://www.research-artisan.com/userjs/?user_id=20060529000243138"></script><noscript>
</BODY>