少なくとも一週間に1冊くらいは何か本を取り上げようと思っていたのですが、来週の予習が追い付かなくて今週は本を一冊も読了できませんでした。
でも、だからといって今週何も書かないと、今後もずるずる行ってしまいそうなので、かなり前に読んだ本だけどものすごく感動してイギリスまで持ってきた、木寺元『地方分権改革の政治学:制度・アイディア・官僚制』(有斐閣、2012年)をご紹介しようかと思います。

本書は、従来粘着性や持続性が強調されてきた「制度」が変化するメカニズムを説明するために注目されてきた「アイディアの政治」アプローチを近年の地方分権改革の政治に適用して、①日本の中央地方関係研究に貢献し、②制度変化についての政治分析モデルへの理論的貢献をし、さらに③官僚制研究の深化への貢献を果たそう(pp.10-12)という、極めて野心的な試みです。
著者は「アイディアの政治」アプローチにおける近年の理論的発展、及び日本政治において官僚の果たす役割(政策知識を政治家に提供、政治的支持調達にかかる調整等々)の重要性を踏まえ、以下のような仮説を立てます。
①ある政策アイディアが政治アクターに受容され、そのアイディアが政策目標とされる局面(「構成的局面」)において、
(i)そのアイディアが問題となっている経済社会問題を解決でき(「必要性」;「認知的次元」)、且つ
(ii)そのアイディアが政治アクターの価値観に合致する(「適切性」;「規範的次元」)場合
においてはじめて、そのアイディアはその政策を推進しようとする「主導アクター」を獲得できる。
②政治アクターがその政策目標を主体的に実現させようとする「因果的局面」において、主導アクターが政治エリート間の合意形成を導く「専門的執務知識」を十分に有しているとき、その政策アイディアは制度変化に結びつく。(pp.55-60)
この仮説は、具体的に
・市町村合併政策(80年代まで/90年代以降)
・機関委任事務制度の廃止(80年代まで/90年代以降)
・地方財政制度改革(小泉政権における地方交付税総額削減/90年代までの交付税制度改革/00年代以降の交付税制度改革)
・第二次分権改革
においてその妥当性が検証されていきます。
これら事例は、①構成的局面における(i)認知的次元における受容の有無、(ii)規範的次元における受容の有無、②因果的局面における主導アクターの専門的執務知識の有無がそれぞれ異なっており、それぞれの要素の有無による制度変化の帰結への影響を比較検討できるようになっています。(結論としては、①(i)+(ii)+②で制度変化がもたらされるという仮説が確認されています。)
僕が特に感銘を受けたのは、上記のリサーチデザインが見事に示されている第1章でした。
第1章においては、制度変化のメカニズムを明らかにしようとした先行研究や日本の官僚制における先行研究、さらに近年の「アイディアの政治」アプローチの理論的深化の動向が詳細に検討された上で、上記の仮説及びリサーチデザインが示されます。
政治学の理論動向のレビューとしても大変勉強になるだけでなくて、研究手法としてもお手本になるような素晴らしい章だと感じました。
僕は地方政治にそこまで大きな関心を持っているわけでもないのですが、本書のような研究ができたらいいなと思って、イギリスまで持ってきてしまいました。
こちらの大学では方法論が非常に重視されていて、自分たちは科学者(scientist)なのだ、ということを最初の数回の講義において叩き込まれます。
これまで方法論にほとんど無頓着だった僕はそこに感銘を受け、またそこで苦しんでいるのですが、方法論の重要性を(なんとなくですが)理解できるにつれ、改めて本書の素晴らしさが分かってきたような気がします。
政治学の理論に関心がある方にも、近年の地方分権改革がどうだったかに関心がある方にもおすすめできる本なのではないかと思います。
また、ドラマチックな「あとがき」も、読んでいて暖かい気持ちになれました(これは読んでからのお楽しみ!)。
本書は、僕がもっと政治学を勉強してみたいと思ったきっかけの本である、Alan M. Jacobs, Governing for the Long Term(Cambridge University Press, 2011)(⇒http://blog.goo.ne.jp/latraviata0608/e/2e8088e730d7bd9d4fb6c408715ed983)とともに、いまの僕のバイブル的な存在だったりします。
本書のような研究に少しでも近づけるように、もっともっと勉強していきたいと思います。
・・・ということで、来週は、ちゃんと何か一冊だけでも英語の本を紹介できるようにします。。
(投稿者:Ren)
でも、だからといって今週何も書かないと、今後もずるずる行ってしまいそうなので、かなり前に読んだ本だけどものすごく感動してイギリスまで持ってきた、木寺元『地方分権改革の政治学:制度・アイディア・官僚制』(有斐閣、2012年)をご紹介しようかと思います。

本書は、従来粘着性や持続性が強調されてきた「制度」が変化するメカニズムを説明するために注目されてきた「アイディアの政治」アプローチを近年の地方分権改革の政治に適用して、①日本の中央地方関係研究に貢献し、②制度変化についての政治分析モデルへの理論的貢献をし、さらに③官僚制研究の深化への貢献を果たそう(pp.10-12)という、極めて野心的な試みです。
著者は「アイディアの政治」アプローチにおける近年の理論的発展、及び日本政治において官僚の果たす役割(政策知識を政治家に提供、政治的支持調達にかかる調整等々)の重要性を踏まえ、以下のような仮説を立てます。
①ある政策アイディアが政治アクターに受容され、そのアイディアが政策目標とされる局面(「構成的局面」)において、
(i)そのアイディアが問題となっている経済社会問題を解決でき(「必要性」;「認知的次元」)、且つ
(ii)そのアイディアが政治アクターの価値観に合致する(「適切性」;「規範的次元」)場合
においてはじめて、そのアイディアはその政策を推進しようとする「主導アクター」を獲得できる。
②政治アクターがその政策目標を主体的に実現させようとする「因果的局面」において、主導アクターが政治エリート間の合意形成を導く「専門的執務知識」を十分に有しているとき、その政策アイディアは制度変化に結びつく。(pp.55-60)
この仮説は、具体的に
・市町村合併政策(80年代まで/90年代以降)
・機関委任事務制度の廃止(80年代まで/90年代以降)
・地方財政制度改革(小泉政権における地方交付税総額削減/90年代までの交付税制度改革/00年代以降の交付税制度改革)
・第二次分権改革
においてその妥当性が検証されていきます。
これら事例は、①構成的局面における(i)認知的次元における受容の有無、(ii)規範的次元における受容の有無、②因果的局面における主導アクターの専門的執務知識の有無がそれぞれ異なっており、それぞれの要素の有無による制度変化の帰結への影響を比較検討できるようになっています。(結論としては、①(i)+(ii)+②で制度変化がもたらされるという仮説が確認されています。)
僕が特に感銘を受けたのは、上記のリサーチデザインが見事に示されている第1章でした。
第1章においては、制度変化のメカニズムを明らかにしようとした先行研究や日本の官僚制における先行研究、さらに近年の「アイディアの政治」アプローチの理論的深化の動向が詳細に検討された上で、上記の仮説及びリサーチデザインが示されます。
政治学の理論動向のレビューとしても大変勉強になるだけでなくて、研究手法としてもお手本になるような素晴らしい章だと感じました。
僕は地方政治にそこまで大きな関心を持っているわけでもないのですが、本書のような研究ができたらいいなと思って、イギリスまで持ってきてしまいました。
こちらの大学では方法論が非常に重視されていて、自分たちは科学者(scientist)なのだ、ということを最初の数回の講義において叩き込まれます。
これまで方法論にほとんど無頓着だった僕はそこに感銘を受け、またそこで苦しんでいるのですが、方法論の重要性を(なんとなくですが)理解できるにつれ、改めて本書の素晴らしさが分かってきたような気がします。
政治学の理論に関心がある方にも、近年の地方分権改革がどうだったかに関心がある方にもおすすめできる本なのではないかと思います。
また、ドラマチックな「あとがき」も、読んでいて暖かい気持ちになれました(これは読んでからのお楽しみ!)。
本書は、僕がもっと政治学を勉強してみたいと思ったきっかけの本である、Alan M. Jacobs, Governing for the Long Term(Cambridge University Press, 2011)(⇒http://blog.goo.ne.jp/latraviata0608/e/2e8088e730d7bd9d4fb6c408715ed983)とともに、いまの僕のバイブル的な存在だったりします。
本書のような研究に少しでも近づけるように、もっともっと勉強していきたいと思います。
・・・ということで、来週は、ちゃんと何か一冊だけでも英語の本を紹介できるようにします。。
(投稿者:Ren)










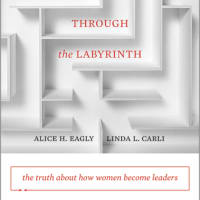









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます