Manningtreeに住んでいたとき、中のものを自由に使っていいよと言われた物置に掃除機が入っていました。
その掃除機を初めて見て衝撃を受けたのを覚えています。
どんなものだったか、言葉で説明するより、写真を見ていただいた方がいいでしょう。

掃除機に顔がついている・・・!!
ただし、これはManningtreeの家で撮った写真ではありません。
SakuraとRenが現在住んでいる部屋の中で撮った写真です。
「こんな斬新なデザインの掃除機、どこで買って来たんだろう」って思っていたら、大学の寮にもそのフロアの人たちの共有物として置いてあったんです。
まさかまったく同じ掃除機に出会うとは思っていませんでした。
もしかしたらこの掃除機、「イギリスでよくある」タイプのものなのかもしれません。
ちなみに性能ですが、重たくて音は大きくて、でもパワフルです。
かわいい顔をしていながら、そういうところはやっぱり海外の掃除機ですね。
(投稿者:Ren)
その掃除機を初めて見て衝撃を受けたのを覚えています。
どんなものだったか、言葉で説明するより、写真を見ていただいた方がいいでしょう。

掃除機に顔がついている・・・!!
ただし、これはManningtreeの家で撮った写真ではありません。
SakuraとRenが現在住んでいる部屋の中で撮った写真です。
「こんな斬新なデザインの掃除機、どこで買って来たんだろう」って思っていたら、大学の寮にもそのフロアの人たちの共有物として置いてあったんです。
まさかまったく同じ掃除機に出会うとは思っていませんでした。
もしかしたらこの掃除機、「イギリスでよくある」タイプのものなのかもしれません。
ちなみに性能ですが、重たくて音は大きくて、でもパワフルです。
かわいい顔をしていながら、そういうところはやっぱり海外の掃除機ですね。
(投稿者:Ren)






























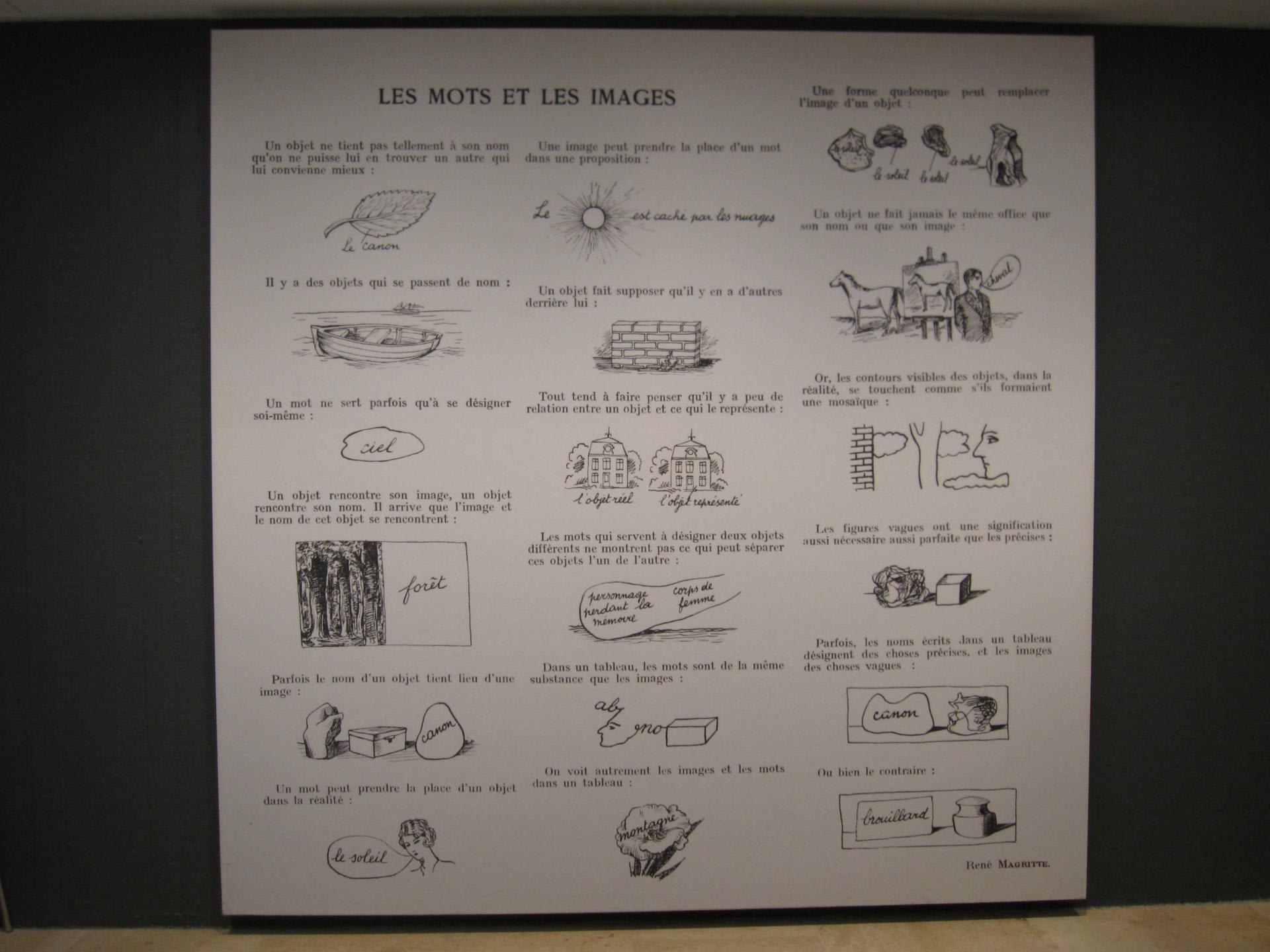


 Le Pain Quotidien(ル・パン・コティディアン)
Le Pain Quotidien(ル・パン・コティディアン)
 )
)


 この、サクッ・フワッっていうのが食べたかったんです!(イギリスではまだ未発見。アンホーチュナリーです。。)
この、サクッ・フワッっていうのが食べたかったんです!(イギリスではまだ未発見。アンホーチュナリーです。。)








