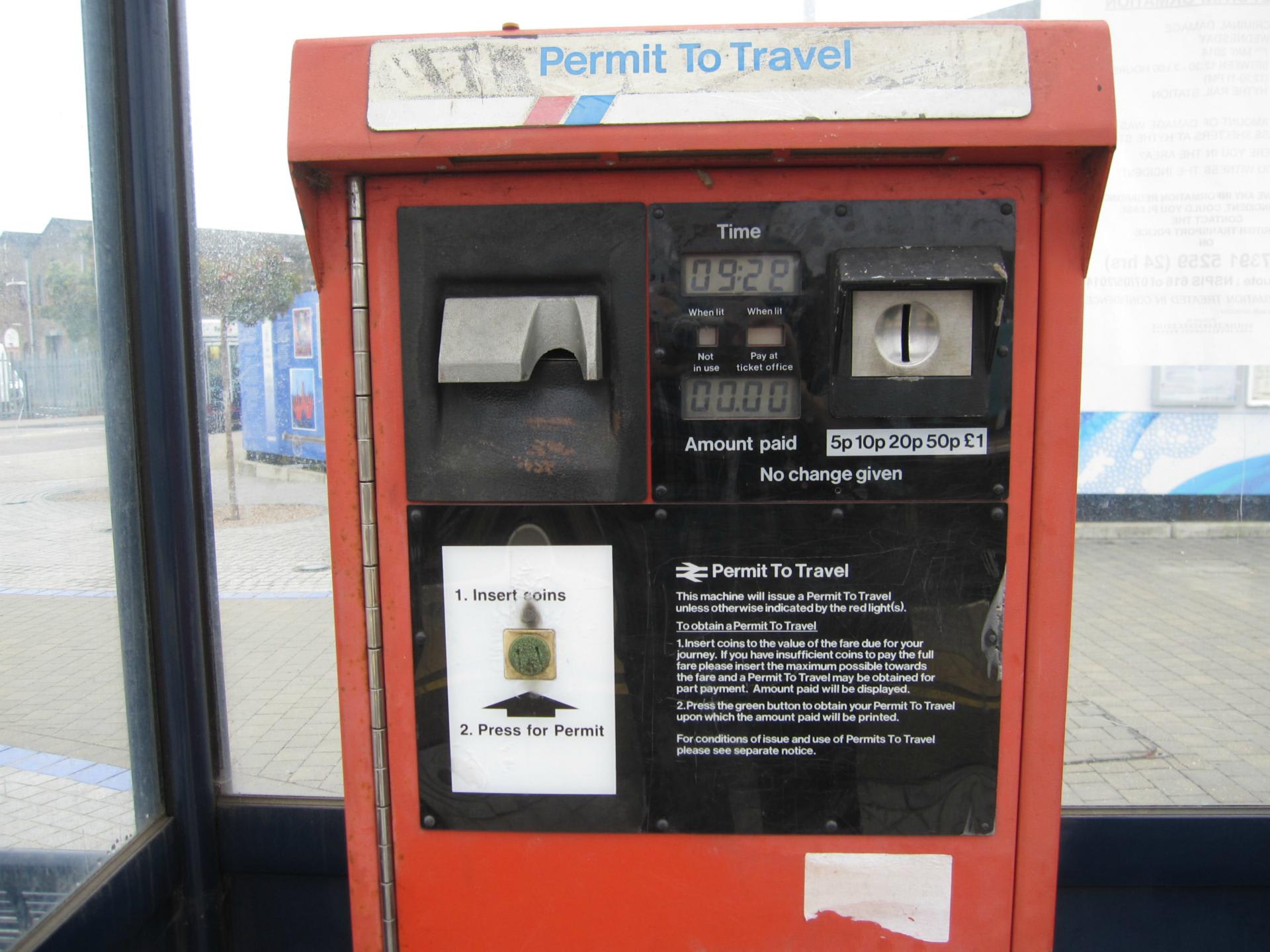Hythe駅から雰囲気のある教会が見えることを発見してからずーっと気になっていた教会についに行ってきました。

ちなみに、ここ、St Leonard-at-the-HytheはHythe駅からこんな感じに見えます。

最近教会に入るのが好きになったSakuraとRenが、このまま徒歩圏内にある教会を見逃すわけにはいきません。
なんとなくHythe駅から歩いて、だいたい5分でたどり着くことができました。(ただし、若干危険な感じもしたので、女性一人で歩くのは怖いかも。)

ここは普段は閉まっているようですが、外にあった張り紙によると、火、木、金、土のお昼くらいに来れば中に入れるようです。
Renたちが来たのは金曜のお昼。運よく入ることができました。
内部はこんな感じ。Lady Chapelもあって、結構本格的。

司祭や合唱団が座る部屋への入口のアーチには綺麗な壁画がありました。

入ってしばらくすると、どこからともなくオルガンの音が。
どうやらオルガン奏者と思われるおじさんが、練習していました。

この教会は14世紀から建てられ始めたらしく、とても価値があるので「The Churches Conservation Trust」という基金が管理しているそうです。
偶然発見して入ってみた教会でしたが、たくさんあるステンドグラスも大変美しかったし、おじさんのおかげで良質なオルガンも聴けたし、良い時間を過ごせました。
(投稿者:Ren)

ちなみに、ここ、St Leonard-at-the-HytheはHythe駅からこんな感じに見えます。

最近教会に入るのが好きになったSakuraとRenが、このまま徒歩圏内にある教会を見逃すわけにはいきません。
なんとなくHythe駅から歩いて、だいたい5分でたどり着くことができました。(ただし、若干危険な感じもしたので、女性一人で歩くのは怖いかも。)

ここは普段は閉まっているようですが、外にあった張り紙によると、火、木、金、土のお昼くらいに来れば中に入れるようです。
Renたちが来たのは金曜のお昼。運よく入ることができました。
内部はこんな感じ。Lady Chapelもあって、結構本格的。

司祭や合唱団が座る部屋への入口のアーチには綺麗な壁画がありました。

入ってしばらくすると、どこからともなくオルガンの音が。
どうやらオルガン奏者と思われるおじさんが、練習していました。

この教会は14世紀から建てられ始めたらしく、とても価値があるので「The Churches Conservation Trust」という基金が管理しているそうです。
偶然発見して入ってみた教会でしたが、たくさんあるステンドグラスも大変美しかったし、おじさんのおかげで良質なオルガンも聴けたし、良い時間を過ごせました。
(投稿者:Ren)