今日はBo Rothstein, Just Institutions Matter: The Moral and Political Logic of the Universal Welfare State (Cambridge University Press, 1998)を取り上げたいと思います。

本書は、1994年にスウェーデン語で出版された、Vad bor staten gora? Om valfardsstatens politiska och moraliska logik (SNS forlag)の英訳。
タイトルをそのまま翻訳したWhat Should the State Do?が本書全体のモチーフになっています。
本書のポイントは以下の2点にまとめられます。
(1)規範的政治理論と実証的政治科学を組み合わせたこと。
(2)制度のあり方が国民の福祉国家政策に関する選好に影響することを主張し、正義に適う制度(Just institutions)を構築することの重要性を指摘したこと。
これらにより、著者は選択的福祉国家よりも優れているものとして、普遍的福祉国家を擁護しようとします。
著者は福祉国家の将来を議論するためには、何が起こり得るか(Can)だけではなくて、何が望ましいか(Should)も考えなければならないと主張します(p.1, pp.8-9)。
ところが、著者の見るところ、政治哲学者たち(Rawls、G. A. Cohen、John Roemer、Bruce C. Ackerman、Richard J. Arnesonなどの錚々たる論者たちを参照しながら)は自分たちの提案の実現にかかる政治的及び行政上のコストをほとんど考慮しておらず、それゆえに現実の政治においてなんら使えるものではない(pp.10-14)。
著者は、政治制度がその制度の下で行動する人々にどの戦略的行動が合理的かを示すだけではなく、その社会における確立した規範を示すものであること(pp.16-17)に注目し、政治哲学と実証政治学をリンクさせるものとして、制度を研究することを目指します。
政治哲学において著者が依拠するのはリベラリズム。
主なリベラリズムの議論を参照しながら(功利主義とリベラリズムとコミュニタリア二ズムを教科書的に反駁しつつ)、国家は「equal respect and concern」をすべての構成員に確保すべきで、それを実現するために国家が介入し、市民の自律的な選択を支援するべきと主張します(第2章)。
一方で、著者は制度のあり方は国民の福祉国家政策への支持に影響することを、Margaret Leviの「contingent consent」に基づいて主張します。
すなわち、著者(というかLeviさん)によれば、人々は自分の利益を追求するけれど、同時に正しいこともしたい(pp.140-141)。
なので、道徳的価値と結びついている政策が十分な支持を得るためには以下の条件が満たされていることが必要になる。
①その政策が公正(fair)であると人々によって認識されていること
②自分だけじゃなくて他の市民たちもちゃんと公正な仕方で貢献すると信じられること
③その政策は公正に実施されること
以上の議論から、著者は普遍的福祉国家が選択的福祉国家より優れていると主張します。
たとえば、①に関して、選択的福祉政策(capabilityを欠く人たちに福祉を提供)は、(i)誰が本当に必要としていて誰が必要ないのか、(ii)必要としている人は、そうなってしまった原因が自分にあるのかそうでないのか、という2つの解決することない境界線問題に悩まされ、「undeserving poor」に議論が集中することになる。
結果、政策が公正だと受け止められることはあまりない。
また、境界線をめぐる議論の中で福祉の受給者に負の表象(スティグマ)が付されることになり、彼(女)らは自尊感情を傷つけられてしまう。
これでは自律的な市民として行動できず、equal respect and concernの原則にも抵触すると指摘されます(pp.157-160)。
一方で普遍的福祉政策では、「poorな人たちに何をするか」から「市民と国家の関係はどうすれば公正になるか」に、「彼らの問題をどうするか」から「我々の共通の課題(医療、教育、年金等)をどう解決するか」に問題が移行するために上記の問題は生じない。
著者はHugh Hecloの次の指摘を引用します。「貧乏な人たちを助ける最善の方法は、彼らについて話さないことだ。つまり、彼らを特別にターゲットにした政策を作らないことだ」。
同様に、②③に関しても「equal respect and concern」の原則及び「contingent consent」の観点からの検討が行われ、いずれの面から見ても普遍的福祉国家が優れていることを確認します(長くなりそうなので省略します)。
政治哲学が大好きな僕は本書の議論の進め方に大いに魅了されたのですが、指摘できることを2つ。
まず1点目として、本書の理論的貢献がよく分からない。
「contingent consent」論を福祉国家にも適用したところが新しいのかもしれないけど、この理論の中身はLeviさんとほとんど一緒でした。
これに関わる2点目として、「contingent consent」論による実証がstaticなものにとどまっていて、説得力が弱いように思われる。
Leviさんの税制を対象にしたOf Rule and Revenue(1988)や徴兵制を対象にしたConsent, Dissent, and Patriotism (1997)で行われているような充実したdynamicなケーススタディーが必要だったのではないかと思いました。
また、普遍的福祉国家のほうがたとえうまくいっていたとしても、それはたまたまその国がそうしやすい環境にあっただけで、それを他の国に適用できるのかどうかはそう簡単に言えることではない(なぜ規範的により望ましいはずの普遍的福祉国家が、こんなに少ない国でしか志向されていないのか?)。
重要なテーマに対する野心的な挑戦だけにいろいろと批判をすることはできるけれども、人々の規範意識に注目し、制度をどのように構築するかが重要だという本書のメッセージは直観的にすごくよく分かる(この点で、とてもpolicy relevantな重要な研究でもあると思う)。
ただ、やっぱり、以前取り上げた加藤淳子さんの「付加価値税を早くに導入した国はそれが福祉に使われるという信頼があるからその後も税金を上げやすくて、その結果福祉もさらに充実する」論(Regressive Taxation and the Welfare State, 2003)に指摘できることと同じように、すでにJustでない制度を作ってしまった普遍的福祉国家以外の国々はどうすればいいのか(もうどうしようもないのか)という悩みをどうしても抱かせられてしまう。
政治哲学と実証を橋渡ししようとする試みに心を躍らせられながら、でも、ちょっと物足りなさも感じた本でした。
(投稿者:Ren)

本書は、1994年にスウェーデン語で出版された、Vad bor staten gora? Om valfardsstatens politiska och moraliska logik (SNS forlag)の英訳。
タイトルをそのまま翻訳したWhat Should the State Do?が本書全体のモチーフになっています。
本書のポイントは以下の2点にまとめられます。
(1)規範的政治理論と実証的政治科学を組み合わせたこと。
(2)制度のあり方が国民の福祉国家政策に関する選好に影響することを主張し、正義に適う制度(Just institutions)を構築することの重要性を指摘したこと。
これらにより、著者は選択的福祉国家よりも優れているものとして、普遍的福祉国家を擁護しようとします。
著者は福祉国家の将来を議論するためには、何が起こり得るか(Can)だけではなくて、何が望ましいか(Should)も考えなければならないと主張します(p.1, pp.8-9)。
ところが、著者の見るところ、政治哲学者たち(Rawls、G. A. Cohen、John Roemer、Bruce C. Ackerman、Richard J. Arnesonなどの錚々たる論者たちを参照しながら)は自分たちの提案の実現にかかる政治的及び行政上のコストをほとんど考慮しておらず、それゆえに現実の政治においてなんら使えるものではない(pp.10-14)。
著者は、政治制度がその制度の下で行動する人々にどの戦略的行動が合理的かを示すだけではなく、その社会における確立した規範を示すものであること(pp.16-17)に注目し、政治哲学と実証政治学をリンクさせるものとして、制度を研究することを目指します。
政治哲学において著者が依拠するのはリベラリズム。
主なリベラリズムの議論を参照しながら(功利主義とリベラリズムとコミュニタリア二ズムを教科書的に反駁しつつ)、国家は「equal respect and concern」をすべての構成員に確保すべきで、それを実現するために国家が介入し、市民の自律的な選択を支援するべきと主張します(第2章)。
一方で、著者は制度のあり方は国民の福祉国家政策への支持に影響することを、Margaret Leviの「contingent consent」に基づいて主張します。
すなわち、著者(というかLeviさん)によれば、人々は自分の利益を追求するけれど、同時に正しいこともしたい(pp.140-141)。
なので、道徳的価値と結びついている政策が十分な支持を得るためには以下の条件が満たされていることが必要になる。
①その政策が公正(fair)であると人々によって認識されていること
②自分だけじゃなくて他の市民たちもちゃんと公正な仕方で貢献すると信じられること
③その政策は公正に実施されること
以上の議論から、著者は普遍的福祉国家が選択的福祉国家より優れていると主張します。
たとえば、①に関して、選択的福祉政策(capabilityを欠く人たちに福祉を提供)は、(i)誰が本当に必要としていて誰が必要ないのか、(ii)必要としている人は、そうなってしまった原因が自分にあるのかそうでないのか、という2つの解決することない境界線問題に悩まされ、「undeserving poor」に議論が集中することになる。
結果、政策が公正だと受け止められることはあまりない。
また、境界線をめぐる議論の中で福祉の受給者に負の表象(スティグマ)が付されることになり、彼(女)らは自尊感情を傷つけられてしまう。
これでは自律的な市民として行動できず、equal respect and concernの原則にも抵触すると指摘されます(pp.157-160)。
一方で普遍的福祉政策では、「poorな人たちに何をするか」から「市民と国家の関係はどうすれば公正になるか」に、「彼らの問題をどうするか」から「我々の共通の課題(医療、教育、年金等)をどう解決するか」に問題が移行するために上記の問題は生じない。
著者はHugh Hecloの次の指摘を引用します。「貧乏な人たちを助ける最善の方法は、彼らについて話さないことだ。つまり、彼らを特別にターゲットにした政策を作らないことだ」。
同様に、②③に関しても「equal respect and concern」の原則及び「contingent consent」の観点からの検討が行われ、いずれの面から見ても普遍的福祉国家が優れていることを確認します(長くなりそうなので省略します)。
政治哲学が大好きな僕は本書の議論の進め方に大いに魅了されたのですが、指摘できることを2つ。
まず1点目として、本書の理論的貢献がよく分からない。
「contingent consent」論を福祉国家にも適用したところが新しいのかもしれないけど、この理論の中身はLeviさんとほとんど一緒でした。
これに関わる2点目として、「contingent consent」論による実証がstaticなものにとどまっていて、説得力が弱いように思われる。
Leviさんの税制を対象にしたOf Rule and Revenue(1988)や徴兵制を対象にしたConsent, Dissent, and Patriotism (1997)で行われているような充実したdynamicなケーススタディーが必要だったのではないかと思いました。
また、普遍的福祉国家のほうがたとえうまくいっていたとしても、それはたまたまその国がそうしやすい環境にあっただけで、それを他の国に適用できるのかどうかはそう簡単に言えることではない(なぜ規範的により望ましいはずの普遍的福祉国家が、こんなに少ない国でしか志向されていないのか?)。
重要なテーマに対する野心的な挑戦だけにいろいろと批判をすることはできるけれども、人々の規範意識に注目し、制度をどのように構築するかが重要だという本書のメッセージは直観的にすごくよく分かる(この点で、とてもpolicy relevantな重要な研究でもあると思う)。
ただ、やっぱり、以前取り上げた加藤淳子さんの「付加価値税を早くに導入した国はそれが福祉に使われるという信頼があるからその後も税金を上げやすくて、その結果福祉もさらに充実する」論(Regressive Taxation and the Welfare State, 2003)に指摘できることと同じように、すでにJustでない制度を作ってしまった普遍的福祉国家以外の国々はどうすればいいのか(もうどうしようもないのか)という悩みをどうしても抱かせられてしまう。
政治哲学と実証を橋渡ししようとする試みに心を躍らせられながら、でも、ちょっと物足りなさも感じた本でした。
(投稿者:Ren)










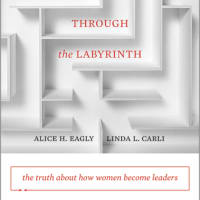









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます