Alice H. Eagly and Linda L. Carli, Through the Labyrinth (Harvard Business Review Press, 2007)
2018年08月19日 | 本
だいぶ久しぶりになってしまいましたが、今回も本の紹介です。
Alice H. Eagly and Linda L. Carli, Through the Labyrinth: The Truth About How Women Become Leaders(Harvard Business Review Press, 2007)

「Labyrinth」とは、女性が置かれている状況を表現する比喩として著者が提案するものです。
よく「ガラスの天井」(glass ceiling)という言葉が使われますが、この言葉はもう現実をうまく表現できていない、と著者は言います。
ガラスの天井とは、女性たちが順調に昇進して行っても、どこかの段階でそれまで見えなかった壁にぶち当たり、上に行けなくなることを表していましたが、いまや様々な分野でトップの地位についている女性は少なくない。
「The glass ceiling had broken」(p.6)。でも、やはり依然として女性がリーダーになるには障害がたくさんあって、成功する道を見つけることは難しい。
そこで、著者は、女性たちがリーダーになっていくために必要なルートを「迷宮」と名付けるのです。
女性がリーダーになる上での障害はいくつもある中で、本書が明確に否定するのは、一部の進化心理学者たちが主張する、男性は生まれつきリーダーに適しているから、女性よりも男性の方がリーダーになることが多い、というもの。
そのエビデンスの弱さや、それら理論の矛盾などを指摘し、リーダーとして成功する心理的な特性はいくつかあるけれど、それらは「男性的」とされているものもあるし、「女性的」なものもあることを示します。
進化心理学からの議論を丁寧に反論した上で、本書は残りのバリアーたち、すなわち家事育児への責任、女性差別、偏見、女性がリーダーになることへの拒否反応、会社組織の働き方などについて、女性がどういう状況に置かれているかを膨大な研究と、それに関わる一般書や新聞・雑誌の記事の引用を行いながら描きます。
なお、本書は、研究論文を注で説明する一方、一般書などの引用(大きな会社のCEOなどの回顧録や発言)を本文で書いてくれていることもあって、とても読みやすく、分かりやすい文章になっていると思いました。
英語の文章に拒否感がない方なら、楽しんで読み進めることができる本なのではないかと思います。
さて、本書で僕が最も意外に思ったのは、米国の企業の働き方を描く箇所でした。
著者によれば、企業には「an implicit model of an ideal employee」があるとのこと(p.139)。
それによれば、社員は長時間労働を行い、そのほか会社の利益になるために個人の犠牲を厭わないことが期待されている。
本書で引用されている社会学者のLewis Coserの1970年代の文章では、会社は労働者に「exclusive and undivide loyality」を求めていることが書かれていますが、それは最近さらにextremeになってきており、ある会社の女性幹部はこう述べているそうです。「幹部クラスになると、会社は実際にその人を所有するようになる。」(p.140)
また、昇進の条件の一つに、転勤を何度かすることがある(少なくない女性は家族との関係でそれが難しいので、昇進ができなくなる)ことも書いてあったりして、日本の会社員が置かれている状況とあまりにも似ていることに驚きました。
雇用システムは、欧米は「ジョブ型」である一方、日本は「メンバーシップ型」であり、それが日本で雇用分野における男女平等がうまく進んでいないことの理由の一つである、と濱口桂一郎さんの議論を参考に考えていたのですが、そんなに単純な話ではないということですね。
おそらく僕が濱口さんの議論を勝手に単純化して理解していただけだと思うので、もう一度丁寧に濱口さんの本を読んで、この問題を考えてみようと思いました。
現在のジェンダー差別構造を受け入れているという批判はあるかもしれないが、そんなに簡単に現実は変わらないし、女性リーダーが増えることで現実を変えることが可能だ、と主張しつつ、本書は、リーダーになろうとする女性に2つのアドバイスをします。
1つは、blending agency with communion(能動性と親しみやすさをブレンドさせること、とでも訳すのでしょうか?)。
女性リーダーは、親切さとか感じの良さ、思いやりといった、伝統的に女性に期待された特性を示すだけでは、リーダーとしての強さが欠如しているとか、自己主張が弱いとかと批判されてしまう一方で、あまりにもこうした「男性的」なリーダーシップを発揮しようとすると、今度はそれはそれで女性として期待される温かみがない、などと反発されてしまう。
男性リーダーはそういう苦労はあまりしないとのことですが、女性リーダーは特に両者の狭い道をバランスをとって進まなければならないということのようです。
アドバイスの2つ目は、ソーシャルキャピタルを築くこと。
リーダーになるためには、会社内で様々なレベルの人と積極的に雑談をしたり、交流する中で信頼され、彼らからインフォーマルな情報を集めることが有効になるそうです。
男性が支配的な職場では女性は男性たちの輪の中になかなか入れないかもしれないけど、積極的に交流をして、ネットワークを社内でに作っていくことが大切だ、と著者は主張します。
Renは男性ですが、これらのアドバイスは男性にも有益なのではないかなと思いました。
久しぶりにブログを書くとうまく文章を紡げなくて、本書の魅力を全然伝えられませんでしたが、社会における女性が置かれている状況をたくさんの論文に基づいて説明してくれる本書は、この問題にアプローチするための入門書としてとても有益でした。
文献もたくさん引用されているので、次に読むべきもののあたりをつけることができることも、初心者に嬉しいポイント。
また、本書は、様々なディシプリンから女性がリーダーになることの困難さとその理由を説明していますが、リーダーシップ論にもたくさん言及されていて、これまで1冊もこの分野の本を読んだことがなかった僕にとって、この観点でも大変勉強になりました。
(投稿者:Ren)
Alice H. Eagly and Linda L. Carli, Through the Labyrinth: The Truth About How Women Become Leaders(Harvard Business Review Press, 2007)

「Labyrinth」とは、女性が置かれている状況を表現する比喩として著者が提案するものです。
よく「ガラスの天井」(glass ceiling)という言葉が使われますが、この言葉はもう現実をうまく表現できていない、と著者は言います。
ガラスの天井とは、女性たちが順調に昇進して行っても、どこかの段階でそれまで見えなかった壁にぶち当たり、上に行けなくなることを表していましたが、いまや様々な分野でトップの地位についている女性は少なくない。
「The glass ceiling had broken」(p.6)。でも、やはり依然として女性がリーダーになるには障害がたくさんあって、成功する道を見つけることは難しい。
そこで、著者は、女性たちがリーダーになっていくために必要なルートを「迷宮」と名付けるのです。
女性がリーダーになる上での障害はいくつもある中で、本書が明確に否定するのは、一部の進化心理学者たちが主張する、男性は生まれつきリーダーに適しているから、女性よりも男性の方がリーダーになることが多い、というもの。
そのエビデンスの弱さや、それら理論の矛盾などを指摘し、リーダーとして成功する心理的な特性はいくつかあるけれど、それらは「男性的」とされているものもあるし、「女性的」なものもあることを示します。
進化心理学からの議論を丁寧に反論した上で、本書は残りのバリアーたち、すなわち家事育児への責任、女性差別、偏見、女性がリーダーになることへの拒否反応、会社組織の働き方などについて、女性がどういう状況に置かれているかを膨大な研究と、それに関わる一般書や新聞・雑誌の記事の引用を行いながら描きます。
なお、本書は、研究論文を注で説明する一方、一般書などの引用(大きな会社のCEOなどの回顧録や発言)を本文で書いてくれていることもあって、とても読みやすく、分かりやすい文章になっていると思いました。
英語の文章に拒否感がない方なら、楽しんで読み進めることができる本なのではないかと思います。
さて、本書で僕が最も意外に思ったのは、米国の企業の働き方を描く箇所でした。
著者によれば、企業には「an implicit model of an ideal employee」があるとのこと(p.139)。
それによれば、社員は長時間労働を行い、そのほか会社の利益になるために個人の犠牲を厭わないことが期待されている。
本書で引用されている社会学者のLewis Coserの1970年代の文章では、会社は労働者に「exclusive and undivide loyality」を求めていることが書かれていますが、それは最近さらにextremeになってきており、ある会社の女性幹部はこう述べているそうです。「幹部クラスになると、会社は実際にその人を所有するようになる。」(p.140)
また、昇進の条件の一つに、転勤を何度かすることがある(少なくない女性は家族との関係でそれが難しいので、昇進ができなくなる)ことも書いてあったりして、日本の会社員が置かれている状況とあまりにも似ていることに驚きました。
雇用システムは、欧米は「ジョブ型」である一方、日本は「メンバーシップ型」であり、それが日本で雇用分野における男女平等がうまく進んでいないことの理由の一つである、と濱口桂一郎さんの議論を参考に考えていたのですが、そんなに単純な話ではないということですね。
おそらく僕が濱口さんの議論を勝手に単純化して理解していただけだと思うので、もう一度丁寧に濱口さんの本を読んで、この問題を考えてみようと思いました。
現在のジェンダー差別構造を受け入れているという批判はあるかもしれないが、そんなに簡単に現実は変わらないし、女性リーダーが増えることで現実を変えることが可能だ、と主張しつつ、本書は、リーダーになろうとする女性に2つのアドバイスをします。
1つは、blending agency with communion(能動性と親しみやすさをブレンドさせること、とでも訳すのでしょうか?)。
女性リーダーは、親切さとか感じの良さ、思いやりといった、伝統的に女性に期待された特性を示すだけでは、リーダーとしての強さが欠如しているとか、自己主張が弱いとかと批判されてしまう一方で、あまりにもこうした「男性的」なリーダーシップを発揮しようとすると、今度はそれはそれで女性として期待される温かみがない、などと反発されてしまう。
男性リーダーはそういう苦労はあまりしないとのことですが、女性リーダーは特に両者の狭い道をバランスをとって進まなければならないということのようです。
アドバイスの2つ目は、ソーシャルキャピタルを築くこと。
リーダーになるためには、会社内で様々なレベルの人と積極的に雑談をしたり、交流する中で信頼され、彼らからインフォーマルな情報を集めることが有効になるそうです。
男性が支配的な職場では女性は男性たちの輪の中になかなか入れないかもしれないけど、積極的に交流をして、ネットワークを社内でに作っていくことが大切だ、と著者は主張します。
Renは男性ですが、これらのアドバイスは男性にも有益なのではないかなと思いました。
久しぶりにブログを書くとうまく文章を紡げなくて、本書の魅力を全然伝えられませんでしたが、社会における女性が置かれている状況をたくさんの論文に基づいて説明してくれる本書は、この問題にアプローチするための入門書としてとても有益でした。
文献もたくさん引用されているので、次に読むべきもののあたりをつけることができることも、初心者に嬉しいポイント。
また、本書は、様々なディシプリンから女性がリーダーになることの困難さとその理由を説明していますが、リーダーシップ論にもたくさん言及されていて、これまで1冊もこの分野の本を読んだことがなかった僕にとって、この観点でも大変勉強になりました。
(投稿者:Ren)










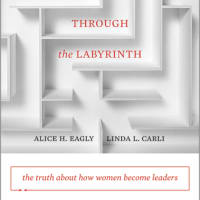









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます