「・・・翌1521年4月ルターはウォルムスの帝国議会Reichstagに呼び出される。その時ルターの脳裡に100年前のフスの運命がよぎらなかったはずもないが、ルターはおそれずにウォルムスに出かけて行く。舞台は帝国議会であるから、皇帝カール5世以下封建領主と自治都市の代表が出席して、ルターはこれらの著書を取り消すように求められる。これに対し、ルターは明確にこの要求を拒んだ。そのルターの陳述の最後にあの有名な言葉がくるのである。「教会や公会議などは、いずれも、しばしば誤りを犯し、また、相互に矛盾することは明らかであって、私はそういうものだけを信じることが出来ない。だから聖書の根拠、または明白な理性によって納得させられない限り、依然として聖書の証拠を確信している。私の良心は神の言葉に縛られている。良心に逆らって行動することは、確実でないし、正しくないから、私は何事も取り消すことは出来ないし、またそうしようとは思わない」と言い切った。・・・そして最後に、「私はここに立っている。私に他のあり方はない。Ich stehe hier. Ich kann nicht anders sein.神よ私を助けたまえ。」という言葉で結んだといわれる。そこに呼び出されているのは、身に寸鉄も帯びずまた何の権限もない、一人の学問僧、聖職者である。これに対するのは世俗の全部の権勢である。良心を根拠にして、世俗の権勢の要求を拒んだ姿は彼が自分の良心は神に縛られていると言っているように、神の奴隷であることによって、人間は世俗に対して完全に自律し、完全に自由でいるという、自らの新しい原理をそのまま象徴するような情景であった。」
(福田歓一『政治学史』(東京大学出版会、1985年)p.230。強調は引用者。))
学生時代にこの箇所を読んで、Renは衝撃のあまりしばらく動けなかったのを覚えています。
高校の世界史で宗教改革の話は習ったし、ルターの名前くらいは知っていた、その程度の認識だったのだけど、この箇所を読んだ次の瞬間から、ルターはRenの最も尊敬する人物の一人となりました。
そんなルターを主人公とする新書を、Renが読まないわけにはいきません。
というわけで、今日は特善義和『マルティン・ルター――ことばに生きた改革者』(岩波新書、2012年)をご紹介したいと思います。
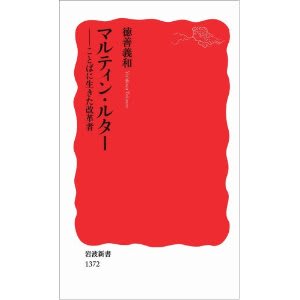
本書はルターの生涯を「ことばに生きた改革者」という視角で描き出す好著です。
ルターが修道士になったきっかけ、ルターの聖書研究の内容、あの「95箇条の提題」について、宗教改革の背景と意義について、ルターの限界(反ユダヤ主義との関わり)について等が、極めて活き活きと描かれていて、読んでいて飽きるところが全くありませんでした。
ルターの聖書研究の内容については、宗教改革がどのようなものであったかを理解する上での核心だと思います。
ルターは神に「正しい」と認めてもらうために日々努力を重ねてきたが、どんなに努力を重ねてもいっこうに神が自分を「正しい」と受け入れてくれたという確信を持つことができない。
そのために、いつしかルターの中に神への疑念が生じていった。
しかし、あるときルターは次のことに気付く。
人間の抱え込んでいる罪は、人間がどれほど真剣に心の底から正しくあろうとしても、どれほど知恵をめぐらせてみても消せるものではない。人間がこの罪から救われるためには、自分自身の中にある知恵や正しくあろうとする心を打ち壊し、神から一方的に与えられる「贈り物」、すなわちイエス・キリストを一心に信じるほかはない。(pp.49-50)
Ren自身は残念ながら信仰を持たない人間なのですが、この「答え」にはかなり共感を覚えたりします。
自分という存在に意味はあるのか、とか、苦しみばかりが続く人生は何なのか、などと問うていくと、最後にはどうしても絶望に陥ってしまいます。
ルターが苦しんだように、僕たちは、どんなに頑張っても完璧に正しくあることはできないし、また自分の存在に意味を見出すこともできない。
僕たちは結局、何かを信じるほかないのかもしれない。
Renは、ここでいきなり「よし、じゃあイエス・キリストを信じよう!」って飛躍しちゃうところがいまいち理解できなくて、ルターに最後まではついていくことができないのですが・・・。
(ちなみに、Renがこの絶望の淵から見出した答えは、「それは<愛>である」だったりします。究極的には人生に意味はないんだけれども、Sakuraを<愛する>こと、そこにかろうじて人生の意味を見出すことができる、そう信じています。とはいえ、今日は積極的に僕の答えを披瀝するのはやめておきます。)
キリスト教の信仰のあり方とヨーロッパ世界をがらりと変えてしまったルターの神学と宗教改革。
本書はこの背景(ルターの思想的な、また、当時の政治社会の)を丁寧に解き明かしてくれて、Renにとって大変勉強になりました。
また、宗教改革はReformではなくReformationであり、日本語に訳すならば「再形成化」であると筆者が述べるところは非常に興味深かったです。
宗教改革を切り拓いたルターは真剣に信仰に悩み、真摯に生きた人でした。
そうだったからこそ、四面楚歌のウォルムスの帝国議会でIch stehe hier. Ich kann nicht anders sein.なんて言い切ることができたんですね。
そんなことを改めて思ってルターのことがますます好きになり、ルターの何百分の一でもいいから真摯に誠実に生きていきたいと思ったRenでした。
あ、それはそうと、本書にはいろんなエピソードが書いてあってそれもとても楽しかったのですが、その中で、教皇からの「破門脅迫の大教勅」に対して、教皇派の多くの神学書と共に教勅と教会法を焼却し、「おまえは神のことばを汚したので、私はおまえを火中に投じる」と集まっていた学生や民衆の前で宣告したところが、なぜかかっこよく感じたので、いつかこの言葉を使ってみたいと思いました。蛇足でした。
(投稿者:Ren)









