こんにちは、Renです。
最近Sakuraが立て続けに書いていてプレッシャーを感じたので、僕も書いてみる事にします。
でも、Renの取り柄は本の紹介くらいなので、今日もまた最近読んだ本について書いてみようかと思います。
今日ご紹介するのは、Alan M. Jacobs, Governing for the Long Term, Cambridge University Press, 2011です。
(ちなみに、さっきRenがちょちょっと検索してみたところ、Jacobs先生はこんな人らしい。 →http://www.politics.ubc.ca/about-us/faculty-members/full-time-faculty/alan-jacobs.html)

この本のテーマは、著者の言葉を借りると、
"Under what conditions do democratic governments enact policies that impose costs on constituents in the short run in order to produce long-run social gains?"
つまり、民主主義国で、短期的には負担増となるものの長期的には社会に利益をもたらすような政策はどういう条件で策定されるのか、というものです。
具体的には、温暖化等の地球環境問題、年金問題、政府の財政問題といったものがこれに含まれます。
著者は、こういう、長期的な利益のために短期的な負担を国民に課す政策のことを、policy investment(政策投資)と概念化した上で、policy investmentが行われる条件を理論的に提示し、年金制度の創設・改革に関するドイツ、イギリス、アメリカ、カナダの10のケーススタディを通してその理論の妥当性を確認していきます。
policy investmentは、一般的に考えればなかなか起こりそうにないものだと思われます。
なぜなら、日本のここ何十年もの政治を見ていれば分かるとおり、政治家が再選を目指す人たちであり、有権者が負担を嫌う人たちである以上、政治家としては有権者に不人気な政策を行いたいと思わないだろうからです。
このような状況のことを、Kent Weaverさんという政治学者は、politics of blame avoidance(非難回避の政治)と呼んでいるようです。(素晴らしいネーミングだと、思う。)
ところが、そうであるにもかかわらず、policy investmentに成功した事例がいくつかの国でいくつも見られる。それは何故か。
著者は、policy investmentが行われるための必要条件を次の3つに整理します。すなわち、①Electoral Safety:その政策をしても政権を失わなさそうなこと、②Expected long-term social returns:政策を作る人たち(官僚も含む)の中で、その政策によって長期的な利得があることが強く見込まれていること、③Institutional capacity:利益団体が政治プロセスにどれだけ入り込めるか(()ほとんどの利益団体がほとんど全く入り込めないか、()ほとんど全ての利益団体がアクセス可能というときにこれが高いとされる)。
この3つの条件がどのように満たされ、満たされないかによってpolicy investmentの度合いが変わっていた、というのが著者の分析です。
詳しい内容は本書を読んでいただくとして、Renが本書を読んで最も感銘を受け、最も印象に残ったのは次の2点です。
まず1点目は、Electoral Safetyの有無にfocusing event(関係者の注目を集めるような大きな出来事)が大きな影響を及ぼす(他の要因としては、野党勢力が分裂していたりして弱い、みたいなものもあります。)こと。
本書で紹介されている年金の事例では、「年金財政がすごくピンチで、このままだともたない」ということが関係者に認識されているというようなことがfocusing eventとなっていて、そういう場合には年金給付の削減や増税についてそこまで強い反対が出ず、従って政治家のelectoral safetyが担保され、これがpolicy investmentとしての年金改革の実施に結びついていました。
ここで重要なのは、「信頼できる」情報が有権者にちゃんと提示されること。
日本で増税とか年金給付の削減とかのpolicy investmentが行われるためには、これが最も重要なんじゃないかなって思いました。
今回の社会保障と税の一体改革は、どう考えたって財政再建のためなのに、「社会保障を強化するためです」みたいなことが我々に言われている。(嘘とまでは言わないけれども。)
正直に、いまは財政がこれだけピンチで、いまの社会保障を国債発行なしに賄うこともできてなくて、そして将来はこういうふうになってしまうんです、っていうことを言ってくれないから、増税の必要性がいまいち理解されずに反対されてしまう。
政府は有権者を馬鹿にしてるんではないか?って時々思ってしまったりします。
ちゃんと現状を正直に示して欲しい。将来の姿を示して欲しい。そしてどうしたらそれが良くなるのかを責任を持って示して欲しい。
それが説得力があれば、その情報こそがfocusing eventとなるんじゃないでしょうか。
どのくらいの増税や社会保障の削減が必要か、その全体像が全然見えてこないのは不安だし、こういう状況では信頼感が生まれてくる方が難しい。
さて、本書で印象的だった2点目は、政策におけるidea(考え)の重要性を強調しているところ。
著者は、ある制度的条件の下でアクターが自分の利益を最大化するように行動するという合理的選択論のモデルでは本書の事例について説明しきれないことから、政策プロセスでは関係者のidea、問題を認知する枠組みがいかに重要であるかを論じています。
確かにちょっと立ち止まって考えれば、著者の言うとおり、"[W]e would understand institutional effects to be highly conditioned by the ideational lens through which decision makers interpret choice problems: whether a given institutional fact matters will depend on whether actors are cognitively predisposed to reason through the very problem which that institutional structure might aggravate or solve."(p.260)です。
こういう制度の下ではこういう帰結が生じる、というような研究が結構あって、ゲーム論を援用するものもあれば、歴史的制度選択論のアプローチもあって、それはすごく鋭くてクリアーなんだけど、なんとなくそんなに単純に制度で物事は決まるのかなあ、じゃあ、ダメな結果をもたらしやすい制度を持つところは諦めるしかないのか、などというような思いを抱いていましたが、著者に説得的にideaの重要性ということを言ってもらえて、なんだか安心した気持ちになりました。(ideaが重要なことは自明だし、著者が言っている事も当たり前のことだと言われればそうなんだけど・・・。)
ただ、ideaが大事なことは分かったけど、じゃあ、そのideaはどうやって出てくるのか?という疑問がすぐに浮かびます。
その点について、著者は物事を認知する枠組みは強固だけれどもそれは変わりうるんだということを主張します。
認知の枠組みは、たとえばこういうときに揺らぐみたいです。すなわち、抱かれていた信念と異なるデータが透明な形で示されたとき、こうなるだろうなと予期していたのと大きく異なる結果が出たとき、予期していたのとは違う予想外の結果が様々な文脈において続いて、「これは例外だ」とは思えなくなるようなとき。
最近の政治学の潮流の一つとしてideaに注目するものがあるということは聞いたことくらいありましたが、本書を読んで、アイディアの政治学をもっともっと勉強したいと思いました。
著者は本書をこう言って締めくくります。
"Democracy may well produce a substantial policy tilt toward the short run, but democratic politics will not always be hostile terrain for those seeking to invest in the long run."
政治学の、そして民主主義の可能性を感じさせてくれる、素晴らしい本でした。
ちなみに、この本、yahooで検索してみたら、まだほとんど日本で紹介されていないみたいです。
Renが一人で素晴らしい本だ!って興奮しただけで、実はそんなでもないのでしょうか。
前書きのところで本書の元になった博士論文を審査した人たちとして、Peter Hallさん, Torben Iversenさん, Paul Piersonさん, Theda Skocpolさんという錚々たるメンバーが挙がっているし、本書の裏を見ると、Sven SteinmoさんとかR. Kent Weaverさんが評価してるっぽいから、少なくともトンデモ本ではないと思うんだけれども。
まあ、Renが勝手に注目している立教大学の小川有美さんもこの本を取り上げていらっしゃった(http://www5.cao.go.jp/keizai2/keizai-syakai/k-s-kouzou/shiryou/wg2-2kai/pdf/4.pdf)から(というか、偶然これを見つけて、この本を読もうって思ったのでした。)、良い本なんだろうっていうことにしておきます。
不安だから、どなたか、この本を引用した学術論文を書いてください!!
論文を書くような人がこんなところを読むとは思わないけど。
(投稿者:Ren)
最近Sakuraが立て続けに書いていてプレッシャーを感じたので、僕も書いてみる事にします。
でも、Renの取り柄は本の紹介くらいなので、今日もまた最近読んだ本について書いてみようかと思います。
今日ご紹介するのは、Alan M. Jacobs, Governing for the Long Term, Cambridge University Press, 2011です。
(ちなみに、さっきRenがちょちょっと検索してみたところ、Jacobs先生はこんな人らしい。 →http://www.politics.ubc.ca/about-us/faculty-members/full-time-faculty/alan-jacobs.html)

この本のテーマは、著者の言葉を借りると、
"Under what conditions do democratic governments enact policies that impose costs on constituents in the short run in order to produce long-run social gains?"
つまり、民主主義国で、短期的には負担増となるものの長期的には社会に利益をもたらすような政策はどういう条件で策定されるのか、というものです。
具体的には、温暖化等の地球環境問題、年金問題、政府の財政問題といったものがこれに含まれます。
著者は、こういう、長期的な利益のために短期的な負担を国民に課す政策のことを、policy investment(政策投資)と概念化した上で、policy investmentが行われる条件を理論的に提示し、年金制度の創設・改革に関するドイツ、イギリス、アメリカ、カナダの10のケーススタディを通してその理論の妥当性を確認していきます。
policy investmentは、一般的に考えればなかなか起こりそうにないものだと思われます。
なぜなら、日本のここ何十年もの政治を見ていれば分かるとおり、政治家が再選を目指す人たちであり、有権者が負担を嫌う人たちである以上、政治家としては有権者に不人気な政策を行いたいと思わないだろうからです。
このような状況のことを、Kent Weaverさんという政治学者は、politics of blame avoidance(非難回避の政治)と呼んでいるようです。(素晴らしいネーミングだと、思う。)
ところが、そうであるにもかかわらず、policy investmentに成功した事例がいくつかの国でいくつも見られる。それは何故か。
著者は、policy investmentが行われるための必要条件を次の3つに整理します。すなわち、①Electoral Safety:その政策をしても政権を失わなさそうなこと、②Expected long-term social returns:政策を作る人たち(官僚も含む)の中で、その政策によって長期的な利得があることが強く見込まれていること、③Institutional capacity:利益団体が政治プロセスにどれだけ入り込めるか(()ほとんどの利益団体がほとんど全く入り込めないか、()ほとんど全ての利益団体がアクセス可能というときにこれが高いとされる)。
この3つの条件がどのように満たされ、満たされないかによってpolicy investmentの度合いが変わっていた、というのが著者の分析です。
詳しい内容は本書を読んでいただくとして、Renが本書を読んで最も感銘を受け、最も印象に残ったのは次の2点です。
まず1点目は、Electoral Safetyの有無にfocusing event(関係者の注目を集めるような大きな出来事)が大きな影響を及ぼす(他の要因としては、野党勢力が分裂していたりして弱い、みたいなものもあります。)こと。
本書で紹介されている年金の事例では、「年金財政がすごくピンチで、このままだともたない」ということが関係者に認識されているというようなことがfocusing eventとなっていて、そういう場合には年金給付の削減や増税についてそこまで強い反対が出ず、従って政治家のelectoral safetyが担保され、これがpolicy investmentとしての年金改革の実施に結びついていました。
ここで重要なのは、「信頼できる」情報が有権者にちゃんと提示されること。
日本で増税とか年金給付の削減とかのpolicy investmentが行われるためには、これが最も重要なんじゃないかなって思いました。
今回の社会保障と税の一体改革は、どう考えたって財政再建のためなのに、「社会保障を強化するためです」みたいなことが我々に言われている。(嘘とまでは言わないけれども。)
正直に、いまは財政がこれだけピンチで、いまの社会保障を国債発行なしに賄うこともできてなくて、そして将来はこういうふうになってしまうんです、っていうことを言ってくれないから、増税の必要性がいまいち理解されずに反対されてしまう。
政府は有権者を馬鹿にしてるんではないか?って時々思ってしまったりします。
ちゃんと現状を正直に示して欲しい。将来の姿を示して欲しい。そしてどうしたらそれが良くなるのかを責任を持って示して欲しい。
それが説得力があれば、その情報こそがfocusing eventとなるんじゃないでしょうか。
どのくらいの増税や社会保障の削減が必要か、その全体像が全然見えてこないのは不安だし、こういう状況では信頼感が生まれてくる方が難しい。
さて、本書で印象的だった2点目は、政策におけるidea(考え)の重要性を強調しているところ。
著者は、ある制度的条件の下でアクターが自分の利益を最大化するように行動するという合理的選択論のモデルでは本書の事例について説明しきれないことから、政策プロセスでは関係者のidea、問題を認知する枠組みがいかに重要であるかを論じています。
確かにちょっと立ち止まって考えれば、著者の言うとおり、"[W]e would understand institutional effects to be highly conditioned by the ideational lens through which decision makers interpret choice problems: whether a given institutional fact matters will depend on whether actors are cognitively predisposed to reason through the very problem which that institutional structure might aggravate or solve."(p.260)です。
こういう制度の下ではこういう帰結が生じる、というような研究が結構あって、ゲーム論を援用するものもあれば、歴史的制度選択論のアプローチもあって、それはすごく鋭くてクリアーなんだけど、なんとなくそんなに単純に制度で物事は決まるのかなあ、じゃあ、ダメな結果をもたらしやすい制度を持つところは諦めるしかないのか、などというような思いを抱いていましたが、著者に説得的にideaの重要性ということを言ってもらえて、なんだか安心した気持ちになりました。(ideaが重要なことは自明だし、著者が言っている事も当たり前のことだと言われればそうなんだけど・・・。)
ただ、ideaが大事なことは分かったけど、じゃあ、そのideaはどうやって出てくるのか?という疑問がすぐに浮かびます。
その点について、著者は物事を認知する枠組みは強固だけれどもそれは変わりうるんだということを主張します。
認知の枠組みは、たとえばこういうときに揺らぐみたいです。すなわち、抱かれていた信念と異なるデータが透明な形で示されたとき、こうなるだろうなと予期していたのと大きく異なる結果が出たとき、予期していたのとは違う予想外の結果が様々な文脈において続いて、「これは例外だ」とは思えなくなるようなとき。
最近の政治学の潮流の一つとしてideaに注目するものがあるということは聞いたことくらいありましたが、本書を読んで、アイディアの政治学をもっともっと勉強したいと思いました。
著者は本書をこう言って締めくくります。
"Democracy may well produce a substantial policy tilt toward the short run, but democratic politics will not always be hostile terrain for those seeking to invest in the long run."
政治学の、そして民主主義の可能性を感じさせてくれる、素晴らしい本でした。
ちなみに、この本、yahooで検索してみたら、まだほとんど日本で紹介されていないみたいです。
Renが一人で素晴らしい本だ!って興奮しただけで、実はそんなでもないのでしょうか。
前書きのところで本書の元になった博士論文を審査した人たちとして、Peter Hallさん, Torben Iversenさん, Paul Piersonさん, Theda Skocpolさんという錚々たるメンバーが挙がっているし、本書の裏を見ると、Sven SteinmoさんとかR. Kent Weaverさんが評価してるっぽいから、少なくともトンデモ本ではないと思うんだけれども。
まあ、Renが勝手に注目している立教大学の小川有美さんもこの本を取り上げていらっしゃった(http://www5.cao.go.jp/keizai2/keizai-syakai/k-s-kouzou/shiryou/wg2-2kai/pdf/4.pdf)から(というか、偶然これを見つけて、この本を読もうって思ったのでした。)、良い本なんだろうっていうことにしておきます。
不安だから、どなたか、この本を引用した学術論文を書いてください!!
論文を書くような人がこんなところを読むとは思わないけど。
(投稿者:Ren)










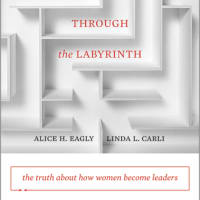









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます