世界史のことで何かわからないことがあると、吉川弘文館の「世界史年表・地図」をひも解く。年表は史実の確認に、地図はまさに国と国との支配関係、領土などの広さが色別でわかり、まさしく視覚的に世界の動きを知ることができる。目を注いでいるだけでも世界史のエッセンスが体得できそうな気がする。
イギリスは日本と同じ島国だから、他国から侵入されにくいだろうとの認識があった。歴史にしても、13世紀のマグナカルタ、無敵艦隊以降はまあまあ知っているつもりだが、それ以前のことはほとんど無知だ。せいぜい、ストーンヘンジやケルト人の神話的かつミステリアスな世界を勝手に思い描いていた。そう、ヨーロッパといえども他国の侵略は少なく、北方からのバイキングとの小競り合いを想像するのが関の山。
カズオ・イシグロの「忘れられた巨人」を読み終った今、アーサー王伝説が生まれた前後の歴史背景や、いわゆるグレートブリトン島やアイルランドがどんな民族で構成されていたか、すこぶる気になり「世界史年表・地図」で調べてみた。
紀元前には記載がなかった。紀元後の180年頃になってローマ帝国五賢帝の時代、それも「自省録」で有名なマルクス・アウレリウス帝が支配した時期に「ブリタニア」という地名が出てくる。地図上では大陸の濃い緑色ではなく、薄い黄色に染まっていて、ローマ帝国といえどもゆるい支配でしかない力関係がわかる。
(まったく小説とは関係ないが、「一本の道」をというBS番組を思い出した。スコットランドやウェールズ地方をそれぞれ採りあげて、いずれもローマ帝国時代の城、水道橋や舗装された街道などの史跡が紹介され、印象に残っている。野趣あふれる自然の景観をたのしみながら、周辺に暮らす素朴な人たちの生活、文化や各地の遺跡などを、巡礼のように歩き訪ねる好番組)
地図帳では、「ヨーロッパにおける民族大移動のはじまり」(375~450年)という囲み記事がでてきた。ローマ帝国が東と西に分裂したことが要因なのか、ブリタニアの地に多民族が侵入したことが図解されている。デンマーク方面から「ユート」、オランダ方面から「アングル」、ドイツ方面から「サクソン」それぞれの民族が侵入した。(※追記)

▲アーサー王がまだ登場する前の時代。アーサー王とは日本でいう大国主命であり、サクソン国つまり大和朝廷に国を譲ったような力関係とみると面白い。ほぼ実在に近い人物だったと私はみている。神の剣、エクスカリバー伝説など、日本の神話と読み比べても面白いのではないか・・。
そのことでケルトの末裔ブリトン人は、北のスコットランド、西部のウェールズ、フランス・ブルターニュの三方に逃げのびた(フランス語で英語のことを「アングレ」という。アングル・サクソンが語源だろうが何故だろう?)。当時はこの三地域は「ブリトン」と呼称されている。サクソン人との戦いに圧倒されていたが、ブリトン人(ケルト)としての民族的な矜持はなんとか保っている。
アーサー王の伝説はその頃の物語であり、こうした事実や伝承が混淆して12世紀頃に現在の形になったといわれる。
アーサー王伝説そのものについてここでは触れないが、「忘れられた巨人」はこのアーサー王亡き後のサクソン人とブリトン人との雌雄は決したが、緊張をのこしつつ互いの存在を認めあう時代を設定している。
場所は特定できないが、カズオ・イシグロは大学時代にグラスゴーでボランティアをしたこと、また彼の奥さんもグラスゴー出身であるので、スコットランド地方だと考えられる。平原や丘陵、湖、北部ハイランドには山々と、自然豊かな土地は、この小説にでてくるシチュエーションとしては格好の舞台であろう。(ウェールズも独特な景観をもつ土地柄であるから、こればっかりはイシグロでないと何とも言えない。)
何処にしても、先住民族としてのブリトン人と侵略者としてのサクソン人は拮抗しつつも、戦争をやめ穏和な状態を模索していた頃には間違いない。ブリトン人からすれば戦いに負け、虐げられてもサクソン人の支配地に留まる人々もいたであろう。
とまれ、今日のイギリスの人種構成を考えてみよう。ブリトン人とサクソン人は互いに行き交い混血が進んだ。現在のイギリス人は外見では、単一民族のように見える。しかし、独立運動が顕在化したようにスコットランドやウェールズでは、いまだにブリトン人由来のいわゆるケルト系の独特の言語を話す人が多い。文字もアルファベットではない。それら伝統文化として愛してやまず、次世代に継承していく草の根のような運動も盛んである。
現代では、旧植民地のインド人、ジャマイカ人、アフリカ系人種も定着して、イギリスの経済・社会に一定の影響力をもつようになった。さらにEU加盟以降、移動・就職の自由化(実質的移民)からポーランドを筆頭に東欧の人々が大挙してイギリスの主要都市に移住してきている。差別のきついドイツよりも、賃金が比較的よく自由な気風のあるイギリスが暮らしやすいらしい。人種差別があまりなく社会保障もしっかりしているのも魅力だろう。
そうしたイギリスの社会情勢のなかでスコットランドの独立騒ぎがあり、遂に昨年、ひょんなことからBREXITにも及んだ。(イシグロは、このEU離脱について激昂していたという)

▲2015年「忘れられた巨人」のPRで来日したときの特番。先日、再放送された。
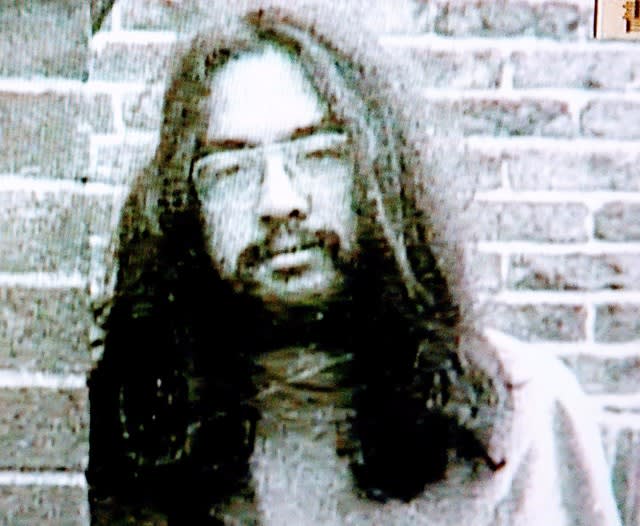
▲22歳、自称ミュージシャン。ディランのようになりたかったという・・。
日系イギリス人としてのカズオ・イシグロは、民族のアイデンティティと国としての存立をめざすが故の抗争、人種的な差別感情の噴出を世界共時の動きとしてとらえ、それらをサクソン人とブリトン人という異民族同士の闘いをメタファーとして小説の世界に展開している。
殺戮や排除、差別や遺恨、戦いで流された夥しい血の染み込んだ記憶は、敗者だけだでなく勝者にもある。そうした禍々しい記憶を消し去り、無かったことかのようにしたい。それが生きていく最善の途であり、お互いが憎みあい傷つけあうことを避ける智恵だ。それこそが集団による記憶の忘却というテーマ。「忘れられた巨人」では、クエリグという龍の大いなる眠りの呼吸が霧となって人々をつつみ、過去のことを忘れさせている。
昔の忌まわしいことだけでなく、ちょっと前の事件のこと、自分たちの息子の顔、いやどうして息子は離れてしまったのかさえ憶えていない。登場人物たちはいちように過去の記憶をなくしているが、ときおり何かを思い出す。悪いことは忘れることに限るが、大切なこと、忘れてならないことまで記憶が失われてしまったようだ。

▲角田光代が寄せている一文は、きわめて示唆的である。
ここまで書いてきて、小説の内容にまで踏み込むことに躊躇をおぼえる。ただ、主人公ともいうべきアクセルとベアトリスの老夫婦について、若干ふれておく。彼らはお互いに敬意と感謝をもって接し、深い信頼と情愛によって結ばれている。夫は妻に対して一言なにかいえば、必ず「お姫様」と呼び、妻は常にそれに答えるがごとく夫への優しい心づかいをしめす。そんな二人が、アーサー王物語においてどのような役割をもっているか、ネットで物語の概略を知る程度で、二人の重要性や夫婦関係が想定できて、人物描写の深い綾が愉しめると思う。
二人はいつも、過去の時間さえ喪失している、そのことも忘れるという理不尽さにまとわれる。息子の顔も、どこに住んでいるのかも曖昧だ。妻の方はうろ覚えに思いだすが、確信をもっている様子はない。認知症のように、昨日の出来事もすぐに忘却し、相手の言動さえも疑ってしまうことがある。ただ二人には、息子に会いに行かねばならない理由と、なにかを成し遂げたい強い意志がある。お互いを慈しみ、限りない信頼をよせながら困難を乗り越えてゆく。その主調音が最後まで途切れることはない。
ついには宗教的といっていい法悦なる高みと、人間の個として生き、老い、死んでいくであろう峻厳なる事実を受けいれる。英語ならさぞかし美しい叙述だろうと思われるが、翻訳でもそのニュアンスは充分に感じられた。
「忘れられた巨人」を読んで、小説では初めてというくらい付箋をはった。表現の巧みさというよりも、現代的状況にするどく感応する優れたメタファーの強度が凄いのだ。
物語の最初と最後に、「船頭」が登場するが、この人物はイシグロであり、神にちかい創造の存在(橋渡し)におもえる。たいへん示唆的な含蓄のある言葉を語り、「忘れられた巨人」の世界の奥行きをさらに深くしている。その「船頭」のことばや、二人をずっと守る戦士のことばを引用しようと思ったが、一切しないことにした。読む人の愉しみをうばうことになりかねない。
一気にとはいかなかったが、久しぶりに読み応えのある小説であったし、ノーベル文学賞の受賞を決定づけたのは、やはりこの作品だったという確信を抱いた。
イギリスの伝統的なファンタジーノベルに則った構成と、迷宮を探検する、わくわくするような展開。その物語としての面白さも、比類ないものだった。
(※追記)ここで何の考えもなしに「侵入」という言葉を使っているが、我ながら軽率のそしりを免れないだろう。「侵入」ではなく、「民族の移動」とあるように人間の動態を示しているだけだ。つまり「難民」ということも考えられる。アーサー王伝説時代のイギリスにおける民族間の軋轢を、侵入・支配・排除といったタームだけでなく、難民・棄民・逃亡などから読み解くことも重要であろう。カズオ・イシグロは当然のごとくこの点を踏まえて、現代に架橋する物語を紡いでいるのだから・・。(2017・11月16日 追記)





















しかし、どうにも日本語で、しっくりと訳せない部分に何度もぶつかり、現在、母が買った土屋政雄氏 翻訳の日本語版と平行して読んでいます。
母が、『 日の名残り- The Remains of the Day 』もいっしょに買ってきたので、そのあらすじを知りました。イギリスの独特な習慣や階級などについて書かれてあり、その本って、そういった事をどう日本語で表現されているのか??非常に興味深くなり、翻訳者に関して、いろいろ検索してみました。すると、山岡洋一氏が下記の通りに書いていて、「 その通り!! 」と共感しました。
【 土屋訳の「プロローグ」を読んで、これが翻訳なのかと驚いた人が少なくないのではないでしょうか。翻訳というより、土屋政雄が日本語で書いた小説なので はないかと。そういう感想をもったのであれば、土屋政雄の翻訳の特徴を正確にとらえたのだと思います。翻訳の匂いがしない翻訳、すこし角度を変えて言い換 えるなら、翻訳とはこういうものだという常識をつくがえす翻訳、これが土屋訳の特徴なのです。こうもいえます。土屋政雄は訳しているのではない、原文を読 んで原著者になりきり、日本語で小説を書いているのだと。訳すのではなく、書く。これが土屋訳の特徴です。】
なので、オリジナルを[ 堅苦しい直訳単語のまま ]あまり深く考えず、感覚的な翻訳でよいから読みきりたい!! と意気込んいます p(^_^)q
その昔、私もフランス文学を原書で読んだりしましたが、寄る年波に勝てず海外のものは翻訳に頼りきっております。
ただ、土屋政雄の訳は故山岡洋一氏がベスト5に入ると評価したごとく、流麗な日本語を駆使した名訳と評判。英米文学の大家になりつつある柴田元幸も、土屋政雄の訳を原文に忠実であるというお墨付きをあたえているようです。
ともあれ「感覚的な翻訳でよいから読みきりたい!! と意気込ん」でいるご様子なので、どうか原文で読み切った後の感想をお寄せください。
それにしても、母子でKazuo Ishiguro を読むなんて素晴らしい!
「忘れられら巨人」もいつか読んでください。