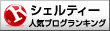今回は、サボテン(仙人掌)だ。2年前に頂いた鉢植えに花が咲いた。とても嬉しい。サボテンはサボテン科の総称で、頂いたのはエキノプシス属のオキシゴナという品種だと思う。朝に咲いて夕方に萎む「一日花」なんだって。因みに、夕方から咲き始め夜に満開となるゲッカビジン(月下美人)もサボテン科。クジャクサボテン属と“属”が違うけど、樹形はずいぶん違うねえ!
<2023年6月10日> 自宅









花は結構大きい! サボテンの勉強をしておこう
【サボテン(仙人掌)】※ Wikipedia、他
◇ サボテン科に属する植物の総称。その多くは多肉植物で、多肉植物の別名として使われることもあるがサボテン科以外の多肉植物をサボテンと呼ぶのは誤り。棘の部分は葉や茎が変化したもの考えられている。

◇ 全草に毒があり栽培する際には注意が必要だが、強心剤の薬効もあり「鬱血性心不全の特効薬」として使用されているという。
◇ 原産地はアメリカ、メキシコ、中米。日本へは江戸時代に鑑賞用として渡来したとされる。
◇ 開花時期は、品種、成熟度、大きさなどにより異なる。エキノプシス属は5月~8月に咲くものが多い。
※ エキノプシス・オキシゴナは、早朝に開花し夕方には萎む種らしいが、我が家のケースでは夕方に開花し、翌朝からはしぼみ始めていた。
【由来】
◇ 「サボテン」は、持ち込んだ南蛮人が「ウチワサボテン」の茎の切り口で畳や衣服の汚れをふき取り、樹液をシャボン(石鹸)として使ったため「石鹸のようなもの」という意味で「石鹸体(さぼんてい)」と呼ばれるようになったとする説が有力。
※ 1960年代までは「シャボテン」と表記する例もあった。
◇ 「エキノプシス(Echinopsis)」はギリシャ語で「ウニまたはハリネズミに似ている」という意味。

◇ 「仙人掌」は、中国、漢の皇帝が手のひらにお皿を乗せた仙人の像を建てたところ、その姿がさぼてんに似ており、仙人(せんにん)掌(手のひら)と書くようになったのだとかの諸説あり。
【開花の時系列】
-6月10日 7時40分-



◇ 朝の7時40分。「朝に開花」と思っていたので、明朝開花! と、思っていた。
-6月10日 19時10分-

◇ 小次郎、夕方に開花したね。

◇ ビックリ。この半日ほど、時間感覚がズレたのかな?

◇ この時がほぼ、満開!
-翌朝(6月11日)7時50分-



◇ まだ、大丈夫のようだが………。実は、“つっかい棒”をしているのだ!

◇ つっかい棒が分かるだろう?

◇ 花は大丈夫だが、花茎はぐたーっとしている。

◇ つっかい棒がないと、こんな感じ。
-翌日(6月11日)12時50分-

◇ 花びらも元気がない。洗濯バサミで支えているところ


◇ 正面からだと、まだ、頑張っている。
-翌日(6月11日)17時30分-


◇ほぼ、萎んでしまった。
-二日後(6月12日)7時00分-

◇ 完全に萎んでしまった。来年に期待しよう。
<おまけ:ゲッカビジン(月下美人)>
小次郎とのコラボの写真はないが、友人から写真を頂いたので紹介しておく、併せて勉強もしておこう。
<2022年8月25日>


◇ 「月下美人は、一年に一度しか咲かない!」とか「新月の夜にしか咲かない!」と言われが、そんなことはないそうです。このお家では、月下美人は、2022年は8月25日と10月24日の2回咲いたそうです。
【ゲッカビジン(月下美人)】
◇ サボテン科クジャクサボテン属の常緑多肉植物。別名に「ナイトクイーン(夜の女王)」の別名があり、夜の間だけに咲く。
◇ 原産地はメキシコの熱帯雨林地帯。日本へは大正末期に渡来。
◇ 日本のクジャクサボテン属には交配種が多いが、“月下美人”は原産地からそのまま導入された原種という。
◇ 開花時期は6月~11月。花は夜に咲き始め翌朝までの一晩で萎む。花冠は20~25㎝程度。
【由来】
◇「新月・満月の夜にしか咲かない」という言い伝えから、
◇「昭和天皇がまだ皇太子だった頃、台湾を訪れた際に、月下美人の花に目を奪われたそうです。 このとき、昭和天皇に連れ立っていた田氏という駐在大使に名前を聞いたところ、田氏が『月下の美人です』と答えたことから“月下美人”と名づけられた」
等、があるという。宣一くんは昭和天皇説に一票。
お終い