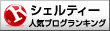今回は、マンサク(満作・万作)だ。“春を告げる花”として知られる。ほかの木々が芽吹く前に一足早く黄色の花を咲かせるという。2025年は、(我が家では)ウメ、ジンチョウゲに先駆けて,2月18日に花をつけているのに気づいた。マンサクは、葉よりも先に黄色いちぢれた花びらをつけた不思議な形の花。宮崎県の霧島では、『霧島の春はマンサクの花で始まります』といった表現で紹介される。名前の由来は諸説あるが、ボクは『「先ず咲く」から東北弁の「まんず咲く」を縮めた』説に一票。
<2025年2月18日> 自宅

◇以前、若松から頂いて挿し木していたもの。

◇ 太い木はネムノキ。その向こうにウメがあるが、まだ蕾。


◇生垣のレッドロビンに沿うように咲いている。


◇ マンサクの花は、1.5㎝程の細長い黄色の花弁で縮れており、特徴的な花びらだ。因みに、黄色の花弁の外側の赤い部位は萼(がく)という。 マンサクについて勉強しておこう。
【マンサク(満作)】※Wikipedia、他
◇ マンサク科・マンサク属の落葉小高木。漢字では、「満作」、「万作」、「金縷梅」と書く。うーん、「金縷梅」を“まんさく”とはちょっと読めない!
◇また、葉の形が左右非対称で不整なことから、カタソゲ(片削げ)の俗名があるという。

◇ 原産地:中国。日本へは古い時代(奈良時代とも)に渡来。
◇ 開花期:2月~3月。葉に先駆けて花が咲く。うむ、ウメ・サクラ・モモ・コブシ・モクレンなどと同じだ
◇ 花の形:がく、花弁と雄蕊が4個ずつ。がくは赤褐色で丸い。花弁は黄色で細長い紐状。

◇花を、観察しながらネットで調べてまとめてみた。

◇ 名前の由来(諸説あり)
・「豊年満作」から。黄金色の花を咲かせるのとイネの豊年に見立てた、説。
・早春に他の木に先駆けて花が咲くことから「先ず咲く」、東北弁の「まんず咲く」を縮めた、または「真っ先」が転訛した、説。
・花がたくさん咲くから「満咲き」からだとする説、など。
-----
若松の(咲き誇っている)マンサクも示しておく。※庭のはこの挿し木!
<2016年3月5日、2018年2月28日> 若松・高塔山

◇一枚の写真でボクのコラボは無理。ボク足元の部分だと花は見えない。
マンサクの花を探しに行ってみよう!

◇ オーイ、マンサクはどこだ?

◇ ん? この付近、(赤い実の)センリョウがあったところでは?
センリョウはこちら → Link先 小次郎と赤い実の草木 -センリョウ(千両)-

◇ この大きな葉はなんだっけ? うーん、忘れた!

◇ こちらにあるらしい?

◇ あった!! 向かって右の黄色いのが「マンサク(満作)」だ。 “あっち向いて、ホイ!” あっ、つい、反対を向いてしまった!!

全体を見よう ※建物はママの実家。その後ろは高塔山の頂上。



◇密集して咲いている。すごい!
-----
<2018年2月28日>
2月末では「枯れ葉」が残っている。

◇ 反対側に行ってみよう。

◇ うーん、木に着目するとボクが目立たない。「→」で示しておく。 併せて花の拡大も示すね。
根元に近い部分は花より(茶色の)葉が目立つ。

◇ 上の方は花があるけど、根元に近い部分は花より(茶色の)葉が目立つ。

◇ 2月末は(昨年の?)枯れ葉が、だいぶ残っている。
ーーーーーー
一部頂いて、自宅で挿し木。
<2020年3月2日>自宅の庭

◇ 挿し木だけど花が咲いた。

◇ 葉はホトトギス(杜鵑草)で、マンサクの葉は、(この時期は)ない!
ホトトギスはこちら Link先 → 小次郎と秋の草花-ホトトギス(杜鵑草)-


<2023年2月21日>自宅庭


◇枝は伸びたけど、花の付き方がイマイチ。
お終い
【写真一覧】
◇マンサク(満作)北九州市若松区高塔山 2018年2月26日、3月6日
◇小さな沈丁花 福岡県糸島市 2018年3月9日、12日
◇白のジンチョウゲ(沈丁花)福岡県糸島市 2019年2月24日、2018年3月6日
◇ジンチョウゲ(沈丁花) 福岡県糸島市 2019年2月24日、2018年3月6日。
小次郎と春の草花 ーマンサク(満作)ー