
泣くのは俺の勝手だよなあ~。
なんて思いながら読み進めた本だった。
帚木蓬生の故郷に伝わる実話を小説化したものだ。
この小説の執筆半ばで帚木蓬生は白血病の宣告をされる。
そんな事情も絡めて読むといい。
後半は、病床のベッドの上で書かれたものだ。
人に対する否定的な側面がそぎ落とされ、肯定的な面が強調されてる。
だからこれは、文学なんかじゃない。
大人の童話だ。
そして今、誰もが、大人への絵本、大人への童話に餓えている、、、。
福島原発事故を乗り越え、我々は新しい絵本、童話を紡ぎ出せるのだろうか、、、?
本日のおまけ
『水神』刊行記念インタビューより
「時代小説の呪縛」からの解放
――『水神』は、五人の庄屋が身代を擲って筑後川に堰を築いたという、史実をモチーフにしている作品です。いつ頃から、小説として描こうと構想されていたのですか?
帚木 大石堰は私の故郷からも近く、五庄屋は戦前の小学校教科書にも載っていたくらいに福岡、特に南側の筑後地方では有名な存在です。私が、実際に初めて堰を見たのは七年くらい前でした。遠くから眺めただけでしたが、そのときに、この堰を造った人間たちの肉声、嘆きや歓喜、血と汗と涙がこもった物語を書きたいと思ったのがきっかけです。五庄屋の話を単なる美談として寿ぐのではなく、実際に生きていた人間たちの物語として書きたいと。書き上げてから今度はすぐ近くまでいって、もう一度堰を見ました。私は歴史的事実との距離をある程度とった方が創造力が湧き出てくるタイプなのです。ですから、書き上げるまでは見に行かないよう、自分を律していました。
――『国銅』は奈良時代、『水神』は江戸時代初期と、舞台となっている時代は違いますが、いわゆる歴史・時代小説は『水神』で二作目となりますね。
帚木 『国銅』のときは、人名、土地の様相、衣食住、交通、信仰、迷信、貨幣、法律など二十から三十くらいの項目ごとに、必要事項を書き込んだファイルで分類していくという手法を用い、今回もそれを踏襲しました。まず最初に、生活史の全体を把握して、物語世界を構築していくというやり方です。現代小説を書くときも、たとえば生命倫理とか、先端医療など、項目がテーマに沿ったものに変わるだけで、同じようにファイルで分類して執筆準備をする方法をとっています。奈良時代に比べて、江戸時代の方が資料が多いから書きやすいかもしれないと最初は思っていたのですが、全然違いました。『水神』の主な登場人物は百姓でしょう。武士の記録はいっぱい残っているのですが、百姓についてのものはほとんどなかったのです。
これは、小説にも同じことがいえるかもしれません。小説誌でよく「時代小説特集」をやっています。掲載される小説、その大多数の舞台は江戸か上方で、登場人物は御家人や町人が主です。地方が描かれることはほとんどありません。百姓が主役となっているものもまず見当たらない。果たして、それが江戸という時代を掬い取ることになるのかなと常々感じていました。みんなが同じ方向を向いて、同じ題材を取り上げ小説を書く必要はないんじゃないかなと。いいかえれば、時代小説はこうでなければいけないという呪縛に囚われているような印象を持っていたわけです。なかなか自分たちのことを書いてくれないなあと墓の下で悔しがっている百姓たちの姿と生活を、私が描いておかなければいけないという思いも『水神』を書いた動機のひとつといえます。水を望み、水に泣かされ、ついに堰を造るにいたった百姓たちの魂の叫びを、小説に刻み込みたかったのです。
小説の絵画的な処理
――『水神』は、まさに百姓、それも農作業をしているのではなく、眼前を流れる筑後川から、毎日桶で水を汲み上げている元助が「起きろ」と呼びかけられるシーンから始まります。この元助と、元助の村の庄屋である山下助左衛門、二人の視点から一大堰渠事業が描かれていきますね。
帚木 『水神』では、百姓たちの日々の生活を百姓の目線から描きたかったのです。それで、島原の乱で父を亡くした元助の視点で、百姓の日常を地に足を着けた形で書いていきました。元助をはじめとする百姓たちは、堰渠造成の担い手として工事にも参加することになります。大工事というのは、百姓にとっては一揆と同じように非日常的な出来事です。しかし、日常生活と何の脈絡もなく生じたものではありません。堰を造らなければ、今もこれからも自分たちは泣き続けなければならない。それじゃあ、いかんという日常生活の延長線上で起こった感情の爆発、必然だったわけです。目の前に大河はあるのに、その水は村に流れてこない。百姓たちは、川の上を流れる花瓶、そこにさされた花のようなものだったのではないでしょうか。滔々と流れる水の上にいるのに、花瓶の中の水はやがて腐り、花は枯れる。あるいは、喉が渇いて彷徨っている人がやっと水のあるところに辿り着いたと思ったら、そこは海だったというような悲劇的な状況に、あの村の百姓たちはおかれ続けていた。
堰造りの推進者である五庄屋の一人、助左衛門の部分では、大きな目的に向かって矢面に立ち闘う人間たちの姿を書く。何節かごとに百姓の視点と庄屋の視点が入れ替わりつつ物語が進んでいくという構成は、一大事業の全貌を小説という形式で表現するためには必要なものだったのではないかと思います。
――元助をはじめとする百姓たちや五庄屋以外にも、彼らの情熱に心を動かされ、一大工事が実現できるよう藩に働きかける老武士、菊竹源三衛門という魅力的な男が登場しますね。
帚木 必死に、それこそ全てを擲って堰を造るべく奔走する五庄屋と、実際に工事に従事することになる百姓たち。当事者たちが、苦しいと言っているその姿だけを描写するのでは点睛を欠くように思ったのです。主体的に行動している彼らを客観的に把握する、いわば見つめる人として菊竹はいます。千枚を越える長編に物語としての緊張感をもたせるには、客観的な立場の人間がどうしても不可欠でした。もっといえば、菊竹の視線は、私の視線であるといってもいいでしょう。
――菊竹は、史実に残っている人物なのですか?
帚木 いえ、違います。他にいえば、『水神』の下巻に出てくる、工事が失敗したときに庄屋たちを吊るすための、五本の磔台が立てられた場所も史実とは異なりますし、工事の内実も少し変えているところがあります。物語が要請する形で、あえてそうしました。
日頃から絵画的な処理と小説を書くことは似ているのではないかと思っているのです。遠くにある木を見せたいのであれば画家はその木を大きく描く。枝の曲がりが悪いとなれば、キャンバスの上では美しい形に変える。そうすることで、実際に見る光景よりもさらに印象深い一枚の絵ができあがるわけです。小説も同じではないかと思うのです。ある細部を強く伝えるためには、別の細部を犠牲にしなければならないこともある。何から何までリアルさに固執すると、逆に作品内のリアリティが失われてしまうのではないかとすら思っています。
闘病生活があったからこそ
――今はお元気で本当に安心しているのですが、『水神』を執筆されていた時期は、白血病の突然の判明、そして無菌室での闘病生活という苦しい期間と重なっていましたね。
帚木 病気は、半年間のいい休養時間をいただいたという風に思っています。ちょうど半分くらい書いたところで、白血病に罹患していることが分かったのですが、闘病生活中の方が逆に書く速度があがったくらいです。下巻の部分は、全部病室で書いたことになりますね。さきほどいった項目ごとに分類したファイル、『水神』では高さ五センチくらいになりますが、それと原稿用紙を消毒して無菌室に持ち込んでいました。マスクをしてベッドで横になっていると、次から次にアイデアが浮かんでくるわけです。それでさっと起きあがってベッドの横にある文机で書く。看護師さんに見つかると「ベッドの上に寝ていてください」としかられる。その繰り返しでした。その意味では、闘病生活があったからこそ書けた作品といっていいかもしれません。書いていてとても楽しい小説でもありました。会話を方言で書けるというのが、本当に楽しかったのです。以前『閉鎖病棟』や『逃亡』で方言を使ったときもそうでしたが、今回も、正々堂々と筑後弁を書けました。誰かに、言葉の使い方があっているかどうか確認してもらうことも必要ないわけですからね。自分が小さい頃にしゃべっていた言葉を、書けばいい。本当に書き甲斐があったし、力もこもりました。
――方言だけでなく、手紙や文語調の嘆願文などでは硬質で美しい日本語も堪能できますから、その部分に着目して読んでも、楽しめますね。
帚木 確かに、いろいろな水準の日本語が『水神』にはありますね。エクリチュールの次元の違う文体を書きわけるのも喜びでした。書いているときに体はきつかったですけど、一日中書けるという状況にいるというのは本当に幸せでした。
カイロジジイのHPは
http://www6.ocn.ne.jp/~tokuch/
それと、なんでもブログのランキングというものがあるそうで、ここをクリックするとブログの作者は喜ぶらしい。

にほんブログ村

にほんブログ村
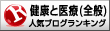
なんて思いながら読み進めた本だった。
帚木蓬生の故郷に伝わる実話を小説化したものだ。
この小説の執筆半ばで帚木蓬生は白血病の宣告をされる。
そんな事情も絡めて読むといい。
後半は、病床のベッドの上で書かれたものだ。
人に対する否定的な側面がそぎ落とされ、肯定的な面が強調されてる。
だからこれは、文学なんかじゃない。
大人の童話だ。
そして今、誰もが、大人への絵本、大人への童話に餓えている、、、。
福島原発事故を乗り越え、我々は新しい絵本、童話を紡ぎ出せるのだろうか、、、?
本日のおまけ
『水神』刊行記念インタビューより
「時代小説の呪縛」からの解放
――『水神』は、五人の庄屋が身代を擲って筑後川に堰を築いたという、史実をモチーフにしている作品です。いつ頃から、小説として描こうと構想されていたのですか?
帚木 大石堰は私の故郷からも近く、五庄屋は戦前の小学校教科書にも載っていたくらいに福岡、特に南側の筑後地方では有名な存在です。私が、実際に初めて堰を見たのは七年くらい前でした。遠くから眺めただけでしたが、そのときに、この堰を造った人間たちの肉声、嘆きや歓喜、血と汗と涙がこもった物語を書きたいと思ったのがきっかけです。五庄屋の話を単なる美談として寿ぐのではなく、実際に生きていた人間たちの物語として書きたいと。書き上げてから今度はすぐ近くまでいって、もう一度堰を見ました。私は歴史的事実との距離をある程度とった方が創造力が湧き出てくるタイプなのです。ですから、書き上げるまでは見に行かないよう、自分を律していました。
――『国銅』は奈良時代、『水神』は江戸時代初期と、舞台となっている時代は違いますが、いわゆる歴史・時代小説は『水神』で二作目となりますね。
帚木 『国銅』のときは、人名、土地の様相、衣食住、交通、信仰、迷信、貨幣、法律など二十から三十くらいの項目ごとに、必要事項を書き込んだファイルで分類していくという手法を用い、今回もそれを踏襲しました。まず最初に、生活史の全体を把握して、物語世界を構築していくというやり方です。現代小説を書くときも、たとえば生命倫理とか、先端医療など、項目がテーマに沿ったものに変わるだけで、同じようにファイルで分類して執筆準備をする方法をとっています。奈良時代に比べて、江戸時代の方が資料が多いから書きやすいかもしれないと最初は思っていたのですが、全然違いました。『水神』の主な登場人物は百姓でしょう。武士の記録はいっぱい残っているのですが、百姓についてのものはほとんどなかったのです。
これは、小説にも同じことがいえるかもしれません。小説誌でよく「時代小説特集」をやっています。掲載される小説、その大多数の舞台は江戸か上方で、登場人物は御家人や町人が主です。地方が描かれることはほとんどありません。百姓が主役となっているものもまず見当たらない。果たして、それが江戸という時代を掬い取ることになるのかなと常々感じていました。みんなが同じ方向を向いて、同じ題材を取り上げ小説を書く必要はないんじゃないかなと。いいかえれば、時代小説はこうでなければいけないという呪縛に囚われているような印象を持っていたわけです。なかなか自分たちのことを書いてくれないなあと墓の下で悔しがっている百姓たちの姿と生活を、私が描いておかなければいけないという思いも『水神』を書いた動機のひとつといえます。水を望み、水に泣かされ、ついに堰を造るにいたった百姓たちの魂の叫びを、小説に刻み込みたかったのです。
小説の絵画的な処理
――『水神』は、まさに百姓、それも農作業をしているのではなく、眼前を流れる筑後川から、毎日桶で水を汲み上げている元助が「起きろ」と呼びかけられるシーンから始まります。この元助と、元助の村の庄屋である山下助左衛門、二人の視点から一大堰渠事業が描かれていきますね。
帚木 『水神』では、百姓たちの日々の生活を百姓の目線から描きたかったのです。それで、島原の乱で父を亡くした元助の視点で、百姓の日常を地に足を着けた形で書いていきました。元助をはじめとする百姓たちは、堰渠造成の担い手として工事にも参加することになります。大工事というのは、百姓にとっては一揆と同じように非日常的な出来事です。しかし、日常生活と何の脈絡もなく生じたものではありません。堰を造らなければ、今もこれからも自分たちは泣き続けなければならない。それじゃあ、いかんという日常生活の延長線上で起こった感情の爆発、必然だったわけです。目の前に大河はあるのに、その水は村に流れてこない。百姓たちは、川の上を流れる花瓶、そこにさされた花のようなものだったのではないでしょうか。滔々と流れる水の上にいるのに、花瓶の中の水はやがて腐り、花は枯れる。あるいは、喉が渇いて彷徨っている人がやっと水のあるところに辿り着いたと思ったら、そこは海だったというような悲劇的な状況に、あの村の百姓たちはおかれ続けていた。
堰造りの推進者である五庄屋の一人、助左衛門の部分では、大きな目的に向かって矢面に立ち闘う人間たちの姿を書く。何節かごとに百姓の視点と庄屋の視点が入れ替わりつつ物語が進んでいくという構成は、一大事業の全貌を小説という形式で表現するためには必要なものだったのではないかと思います。
――元助をはじめとする百姓たちや五庄屋以外にも、彼らの情熱に心を動かされ、一大工事が実現できるよう藩に働きかける老武士、菊竹源三衛門という魅力的な男が登場しますね。
帚木 必死に、それこそ全てを擲って堰を造るべく奔走する五庄屋と、実際に工事に従事することになる百姓たち。当事者たちが、苦しいと言っているその姿だけを描写するのでは点睛を欠くように思ったのです。主体的に行動している彼らを客観的に把握する、いわば見つめる人として菊竹はいます。千枚を越える長編に物語としての緊張感をもたせるには、客観的な立場の人間がどうしても不可欠でした。もっといえば、菊竹の視線は、私の視線であるといってもいいでしょう。
――菊竹は、史実に残っている人物なのですか?
帚木 いえ、違います。他にいえば、『水神』の下巻に出てくる、工事が失敗したときに庄屋たちを吊るすための、五本の磔台が立てられた場所も史実とは異なりますし、工事の内実も少し変えているところがあります。物語が要請する形で、あえてそうしました。
日頃から絵画的な処理と小説を書くことは似ているのではないかと思っているのです。遠くにある木を見せたいのであれば画家はその木を大きく描く。枝の曲がりが悪いとなれば、キャンバスの上では美しい形に変える。そうすることで、実際に見る光景よりもさらに印象深い一枚の絵ができあがるわけです。小説も同じではないかと思うのです。ある細部を強く伝えるためには、別の細部を犠牲にしなければならないこともある。何から何までリアルさに固執すると、逆に作品内のリアリティが失われてしまうのではないかとすら思っています。
闘病生活があったからこそ
――今はお元気で本当に安心しているのですが、『水神』を執筆されていた時期は、白血病の突然の判明、そして無菌室での闘病生活という苦しい期間と重なっていましたね。
帚木 病気は、半年間のいい休養時間をいただいたという風に思っています。ちょうど半分くらい書いたところで、白血病に罹患していることが分かったのですが、闘病生活中の方が逆に書く速度があがったくらいです。下巻の部分は、全部病室で書いたことになりますね。さきほどいった項目ごとに分類したファイル、『水神』では高さ五センチくらいになりますが、それと原稿用紙を消毒して無菌室に持ち込んでいました。マスクをしてベッドで横になっていると、次から次にアイデアが浮かんでくるわけです。それでさっと起きあがってベッドの横にある文机で書く。看護師さんに見つかると「ベッドの上に寝ていてください」としかられる。その繰り返しでした。その意味では、闘病生活があったからこそ書けた作品といっていいかもしれません。書いていてとても楽しい小説でもありました。会話を方言で書けるというのが、本当に楽しかったのです。以前『閉鎖病棟』や『逃亡』で方言を使ったときもそうでしたが、今回も、正々堂々と筑後弁を書けました。誰かに、言葉の使い方があっているかどうか確認してもらうことも必要ないわけですからね。自分が小さい頃にしゃべっていた言葉を、書けばいい。本当に書き甲斐があったし、力もこもりました。
――方言だけでなく、手紙や文語調の嘆願文などでは硬質で美しい日本語も堪能できますから、その部分に着目して読んでも、楽しめますね。
帚木 確かに、いろいろな水準の日本語が『水神』にはありますね。エクリチュールの次元の違う文体を書きわけるのも喜びでした。書いているときに体はきつかったですけど、一日中書けるという状況にいるというのは本当に幸せでした。
カイロジジイのHPは
http://www6.ocn.ne.jp/~tokuch/
それと、なんでもブログのランキングというものがあるそうで、ここをクリックするとブログの作者は喜ぶらしい。
にほんブログ村
にほんブログ村











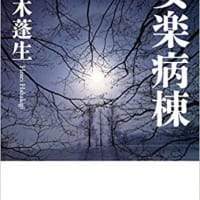
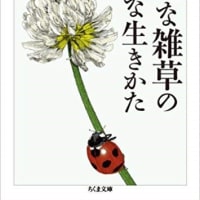
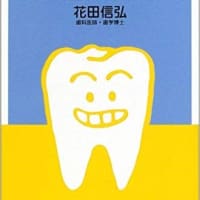

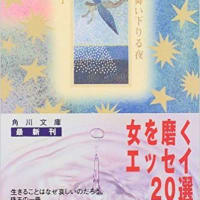
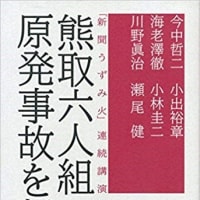

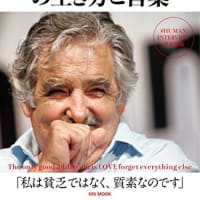

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます