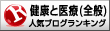とんでもない危険な本を読んでいるのではないか?
この本を読んでいる間、しばしばそんな感情に襲われた。
水俣病患者を前にして、現天皇・皇后はいくつもの天皇として守らなければならぬとされている約束事を破った。
国事としての仕事の合間に、自らの意志を表現する行動をとった。
異例づくめの、意志を通した行動をした。
国民から物を貰ってはいけないのに、緒方正美さんの創ったこけしを所望した。

水俣病患者は、国から捨てられ、地域を繁栄させた企業に歯向かう者として地域共同体から村八分の目にあい、水俣病そのもの以外の要素によっても地獄を見た人々である。
その人々が、天皇・皇后が日頃から水俣病患者に心をくだいている事を知り、カタルシスを味わう。
徳さんも、その場面では泣いてしまったが、これはかなり危険なことではないのか。
問題は、水俣病の問題を我々が放置したことである。
放置した自分、自分たちがいる。
放置したマスメディアがある。
昭和天皇は人間宣言をしたが、敗戦直後の対応はちっとも人間的じゃなかった。
平成天皇夫妻は人間であろうとして、発言の自由を奪われた中でもがき苦しんでいる。
これが、あるべき姿なのか、、、。
このあとは参考資料までに。
*****
中島岳志・評 『ふたり-皇后美智子と石牟礼道子』=高山文彦・著
毎日新聞2015年11月22日 東京朝刊より
水俣病の歴史の中の忘れられない1日
2013年10月27日。天皇皇后が水俣を訪問した。そこで水俣病患者との歴史的な対話が実現する。背後にはいったい何があったのか。著者は、水俣病をめぐる闘争の軌跡をたどりながら、その日の真相に迫る。
天皇皇后の水俣訪問は「異例づくし」だった。まず、日程にあげられていなかった胎児性患者との面会が実現する。両者を結びつけたのは石牟礼(いしむれ)道子。『苦海浄土』で水俣病を描いた作家だ。
皇后と石牟礼は鶴見和子を偲(しの)ぶ山百合(やまゆり)忌で出会い、心を通わせる。この席で、皇后が「こんど水俣に行きます」と告げると、後日、石牟礼は手紙に「水俣では、胎児性水俣病の人たちに、ぜひお会いください」と綴(つづ)った。皇后の強い意向で、急遽(きゅうきょ)、面会が実現する。ただしすべて秘密。当事者は、このことを口外しないよう、役人から強く求められた。
天皇皇后はやさしく声をかけ、苦労をねぎらった。そして患者の声を丁寧に聞いた。同席した支援施設「ほっとはうす」の加藤タケ子は、患者と共に涙を流した。「ずっと見ていてくださったんだなあ、忘れられていなかったんだなあ、といううれしさでしょうか」
面会後、役人から「夢のなかの話にしておいてくださいね」と言われたが、すぐに秘密は公然のものとなる。天皇皇后自らが、多くの人の前で患者と面会したことを話したからだ。著者はここに「秘密の話にさせたくなかった」という天皇皇后の意志を読みとく。
この後、水俣病資料館「語り部の会」会長・緒方正実が二人に向けて講話を行った。話が終わると、天皇は思いがけない行動をとった。緒方の顔をじっと見つめ、予定にはなかった「お言葉」を述べた。天皇は「今後の日本が、自分が正しくあることができる社会になっていく、そうなればと思っています」と言及した。ここには慎重な言い回しながら、国の姿勢に対する批判が込められていたと著者は見る。
この後も、異例の行動が続く。侍従が「お時間です」と声をかけても、天皇皇后は、その場を立ち去ろうとしない。その場のひとりひとりに声をかけ、耳を傾けた。患者たちは「はじめて心から救われたような気持ちに満たされた」という。著者曰(いわ)く「困窮と毒苦に出しきれぬ声であえぎつつ、心の底から彼らが求めていたのは金などではなく、真情を抱きしめてくれる人間の『言葉』だったのだ」。
人間は言葉の動物だ。言葉が人を動かし、人を形成する。そして、言葉は行動と不可分のものである。天皇皇后が患者たちの心をとらえたのは、その態度や姿勢、表情が言葉以上の言葉となっていたからである。
加害企業チッソに対して、直接交渉を求めた川本輝夫は、「サシ」で話をすることにこだわった。何とかして被害者の痛みを「わからせたい」と思っていたからだ。しかし、チッソの責任者は逃げ続けた。川本はそのたびに悔し涙を流した。
天皇皇后は、「サシ」で患者たちと向き合った。亡くなった川本の妻と息子とも言葉を交わした。ここに救いの光が射(さ)し込む。
許しとは何か。救済とは何か。天皇皇后とはいかなる存在なのか。
水俣病は終わっていない。感動的な話を、都合のいい幕引きに流用してはならない。しかし、水俣病の歴史の中で、この日は特別な意味を持ち続けるだろう。被害者たちにとって、忘れられない日となるだろう。
翌年1月、次のような天皇御製(ぎょせい)が発表された。「慰霊碑の先に広がる水俣の海青くして静かなりけり」
天皇もあの日を忘れていない。
*****
文芸評論家の富岡幸一郎氏が、天皇、皇后という存在の本質、そしてその言葉が持つ力について語る。
──本書を読むと、書名になっている「ふたり」にはいろいろな意味があることがわかります。
富岡:美智子皇后と水俣について書き続ける作家・石牟礼道子との交流によって水俣訪問が実現したわけですが、そのふたりだけでなく、天皇と皇后、石牟礼道子と長年にわたって彼女を支援し続けてきた作家の渡辺京二、そして天皇皇后と水俣病患者たちそうしたさまざまな「ふたり」の関係を描いた重層的な作品です。
──患者の代表の体験談を聞いた天皇が約1分間感想を述べましたが、異例の長さだそうですね。
富岡:〈真実に生きるということができる社会を、みんなでつくっていきたい〉〈自分が正しくあることができる社会になっていく、そうなればと思っています〉と、平易だが深い意味を持つ言葉で語ったことに感銘しました。言論の自由のない天皇は、著者が言うように〈言葉をもがれた存在〉で、ある程度自由に自分の思いを込められるのは御製(お歌)ぐらいです。それだけに、例外的に内面の思いをはっきりと表出した言葉は純度が高く、聞く者の心に響きます。
もうひとつ驚いたのは、宮内庁の求めに応じ、患者の代表が天皇皇后に話す内容の原稿を事前に提出したら、当り障りのない内容だったために両陛下から却下され、「両陛下はあなたが一番苦しかったこと、悔しかったこと、悲しかったことをお聞きになりたい」と言われた、というエピソードです。両陛下がいかに言葉を大切にしているか、そしていかに水俣に強い思いを抱いているかがわかります。
天皇皇后に会った患者の代表や胎児性患者が「この世に生まれてきてよかった」「日本人に生まれてよかった」と、著者の取材に語っていることにも驚きます。
──国家と戦ってきた人間にそう言わせる天皇とはどういう存在なのか。
富岡:歴史的に天皇は、世俗の権力を超えた聖なる権威として存在してきました。だから、水俣病患者にせよ、ハンセン病患者にせよ、原発事故の避難民にせよ、世俗の権力に見捨てられた民を慰藉し、その魂の救済に関わることができるんですね。それは政治家には絶対にできないことです。
そのことについて著者は〈貴いお方と打ち捨てられた最下層民とのあいだには、権力段階と庶民段階の膨大な地層が横たわる。貴いお方がそのようにされてしまった民に慰藉の言葉をかけたとき、これらの地層は断罪されたも同然〉と書いていますが、その通りだと思います。
みな実は今の天皇は、皇太子時代から天皇の役割を明確に意識しています。昭和61年5月26日付読売新聞で、皇室と国民の関係の理想的なあり方を質問され、文書でこう回答しているんです〈天皇は政治を動かす立場にはなく、伝統的に国民と苦楽をともにするという精神的立場に立っています〉と。さらに続けて〈このことは、疫病の流行や飢饉にあたって、民生の安定を祈念する嵯峨天皇以来の天皇の写経の精神(中略)などによっても表されている〉と述べています。そうした歴史的なあり方を水俣でも示したのです。
●インタビュー・文/鈴木洋史
※SAPIO2016年1月号より
カイロジジイのHPは
http://chirozizii.com/
そして、なんでもブログのランキングというものがあるそうで、以下をクリックするとブログの作者は喜ぶらしい。
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
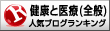
 にほんブログ村
にほんブログ村 にほんブログ村
にほんブログ村