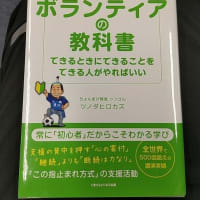こちらのサイトからの転載です。グラフや図などは転載できませんので原文をお読みください。
本当に勉強になる解析です。
ありがたいことです。
コロナウイルス arXiv*(13)2020 年 5⽉27⽇ ⿊⽊登志夫
5 ⽉ 24 ⽇までのコロナ感染を分析しました。感染者倍加⽇数、新規感染者数、患者数のどの指標をとっても、コロナが収まりつつあるのは間違いないと思います。海外からは、罰則も強制も伴わない外出⾃粛と「Stay home」の要請、極端に少ない PCR 検査にもかかわらず、⽇本がコロナを抑えこんだのは不思議のようです。われわれにとっても理解できない点があります。海外の新聞論調をご紹介します。
千葉⼤学の先進的なコロナ診療体制についてもまとめました。病院が⼀⽣懸命努⼒をしている様⼦がわかります。しかし、コロナ診療と検査に当たる医療職員の PCR 検査は、安全のために必須ですが、病院が⾃前でまかなわねばなりません。厚労省は、どうしてこの努⼒が分からないのか。私の考えを「主張」しました。参議院議員、医師、弁護⼠の三つの顔を持つ古川俊治先⽣が、医学研究者としての顔でまとめたコロナ医学論⽂解説もお届けします。
*“arXiv”(アーカイブ)は、未発表科学論⽂の投稿ネットサイトの⼀般名です。
コロナウイルス arXiv は、⼭中伸弥先⽣の「新型コロナウイルス情報発信」サイト
(https://www.covid19-yamanaka.com/index.html)に掲載されております。
バックナンバーも含めて、転送は⾃由です。
⽬次
1. 直近のコロナ感染分析
2. ⽇本の不思議
3. コロナ感染者の診療体制 (千葉⼤学附属病院)
4. 主張:PCR 検査は最も重要な院内感染対策
5. コロナ医学⽂献解説(古川俊治)
6. コロナ秀歌・秀句(略)
情報提供者
朝倉 和⼦(翻訳家)Bloomberg 通信
横⼿光太郎 (千葉⼤学附属病院⻑) コロナ診療体制
吉⽥和弘 (岐⾩⼤学附属病院⻑)院内感染対策
古川俊治 (参議院議員)コロナ⽂献解説
1.直近のコロナ感染分析
今週から⾮常事態宣⾔が解除されました。直近のコロナ解析を分析したところ、感染の状況が驚くほど好転していることがわかりました。
⽤いた指標は、次の 3 項⽬です。
① 感染者増加倍加⽇数(図 1)
② 新規感染者数 (図 2)
③ 患者数 (図 3)
データは、曜⽇バイアスを防ぐため、⽉曜から⽇曜までの週ごとにまとめました。資料は東洋経済 ON LINE『新型コロナウイルス国内感染状況』です。
(https://toyokeizai.net/sp/visual/tko/covid19/)。
図 1 は、確定感染者数の倍加⽇数です。⼀⽉前は 11.3 ⽇、すなわち、2 週間もたたずに感染者が倍増していたのに、5 ⽉ 17−24 ⽇の週は1
年以上 379 ⽇まで伸びました。
ほとんど、⽔平になったといってもよいでしょう。これは予想を上回る成績です。
図1
確定感染者数倍加時間の推移。
図2は、週ごとの新規確定感染者数です。ピークは4⽉中旬、1週間に 3600 ⼈の新規感染者がでていたのに、直近では、209 ⼈まで下がりました。
東京では、1 週間で 50 ⼈、⼀⽇平均 7 ⼈です。
図 2
新規感染者数の推移。
4 ⽉中旬から 5 週間で、18 分の 1 になった。
図 3 は患者数の推移です。今まで、このデータはとってなかったのですが、病室の状況が対策にとって重要なので、計算してみました。東洋経済のサイトにも「⼊院、治療を要する者」というデータがありますが、タイトルに違和感があるので、⾃分で計算しました。
単純に確定感染者数から退院者数と死亡者数を引いた数を患者数としたのですが、この計算にもバイアスがあります。感染者が退院あるいは死亡するまでの⽇数を計算に⼊れていないからです。いずれにしても、正確な数字は簡単にはえられないので、バイアスを含んだ数字になります。
図 3 からわかるように、患者数は、5 ⽉の連休終わり頃から急激に減少しています。現在、全国の患者数は。⼀⽉前の 5分の 1 の 2000 名にまでなりました。
図 3
コロナ患者数の推移。5 ⽉末の患者数は、全国で 2000 名程度まで少なくなった。
この 1 ヶ⽉で、⽇本のコロナ感染が収まりかけているのは、明らかです。
図 1−3 は、そのことを数字で裏付けています。われわれにとっても何故かよくわからないのですから、他の国から⾒れば、なおさら不思議なことでしょう。
Bloomberg 通信、TheGurdian 、WashingtonPost の記事をご紹介します。
2.⽇本の不思議
Did Japan Just Beat the Virus Without Lockdowns or Mass Testing?
Bloomberg は、このようなタイトルの記事を掲載しました*。Lockdown も中途半端、テストも不⼗分、加えて、CDC もなければ、⼈の⾏動を監視するハイテクも使わなかった。それなのに、何故?と⾔うのが、外から⾒た率直な疑問のようです。しかし、特別な「秘密の兵器(silver bullet)があったわけでもなく、⼀つだけの理由があるわけでもないとも⾔っています。
保健所が感染者追及に果たした役割と 5 万⼈を超える保健師の仕事、国⺠の健康についての関⼼の⾼さ、などを成功の⼀つの理由として評価しています。⽇本語の会話では、あまり唾を⾶ばさないという⽇本のテレビ局(⺠放)の実験も動画とともに紹介しています。
(https://twitter.com/i/status/1263352830225551360)。顔の前にティシューペーパーを置いて、「これはペンです」というとティシューペーパーはほとんど動きませんが、「This is apen」では、紙が⾶びそうになります。
* https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-22/did-japan-just-beat-the-viruswithout-lockdowns-or-mass-testing
From near disaster to success story: how Japan has tackled corona virus
The Gurdian も、⽇本の問題を取り上げています。握⼿でなく、お辞儀の習慣、家の中で靴を脱ぐ習慣などは、どのメディアも取り上げていることですが、免疫を⾼める納⾖を⾷べていること、肥満者が少ないことなども指摘しています(納⾖が免疫にいいとは思いませんが)。上記の⽇本⼈が唾を⾶ばさないで話す習慣は、⾮科学的な実験と⽚付けています。
https://www.theguardian.com/world/2020/may/22/from-near-disaster-to-success-storyhow-japan-has-tackled-coronavirus
Tokyo lifts state of emergency, brases for “new lifestyle” with the virus
Washington Post も、⽇本のコロナ対策を取り上げました。政府が命令もせず、罰則も設けなかった要請レベルにかかわらず、⽇本⼈はコンセンサスと社会的圧⼒に従ったと書いています。加えて、安倍総理の最初の失敗とコミュニケーション不⾜についても指摘しています。
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/tokyo-lifts-state-of-emergencybraces-for-new-lifestyle-with-the-virus/2020/05/25/7a0e5836-9b75-11ea-ad79-
eef7cd734641_story.html
お辞儀、納⾖を⾷べるといった⽣活習慣だけではなく、BCG の可能性もあります。⽇本、韓国、台湾も、ヨーロッパに⽐べると死亡者が数⼗分の⼀くらいです(前報 表 1)、東洋⼈には何か遺伝的特性があるのかも知れません。コロナウイルスのレセプターの ACEII, 感染経路、免疫系などのゲノムを調べれば何かがわかるかもしれません。研究を期待しています。
3.千葉⼤学附属病院のコロナ診療体制
前回、岐⾩⼤学附属病院と東京医科⻭科⼤病院の院内対策に続いて、千葉⼤学附属病院の診療体制をご紹介します。実は、私は千葉⼤学の経営協議会の委員を⻑い間続けております。
先週⾏われた経営協議会(ウエブ会議)で、千葉⼤学の先進的取り組みの発表を聞きましたので、横⼿光太郎病院⻑と⼭本修⼀前病院⻑に、具体的にお伺いしまとめました。
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
千葉⼤学は、COVID-19 感染発⽣当初よりに積極的に取り組み、患者を受け⼊れてきた。
・ 新型 COVID-19 ウイルス感染症が指定感染症に指定された 2020 年 2 ⽉ 1 ⽇より⼊院診療を⾏っている。
・ ダイアモンドプリンセス号が横浜港に⼊港したときには、DPAT(災害派遣精神医療チーム)1隊(4 名)を派遣し(2 ⽉ 20 ⽇-22 ⽇)、クルーズ船の患者(2 名)も受け⼊れた。
・ 2020 年4⽉後半から現在まで、⼊院患者数はのべ約 53 名。1 ⽇あたり 20〜30 名のCOVID-19 感染者が⼊院している。
・ ICU 管理患者はのべ 6 名、うち 4 名は ECMO で治療した。
診療体制
(1) 診療体制
・内科系の診療科より⼈員を提供し、COVID-19 診療チームを編成した。
・COVID-19 患者への対応は必ず 2 名以上で⾏った。
・精神神経科医師が、⼊院患者のメンタルヘルスを担当した。精神科は外来受診⼀般患者に対し、「パンデミックの不安と⾏動」に関する調査を⾏った。
(2) 外来患者
4/22 から電話診察による処⽅箋の発⾏を開始した。
4/24 から外来棟⽞関前にテントを設置し発熱/疑い患者スクリーニングを開始した。
5/11 から⼊院予定患者/外来内視鏡予定患者に対して全例 PCR 検査を開始した。
(3)検査体制
・ 放射線部に COVID-19 担当グループを置いた。
・ CT 室 1 室、⾎管造影室 3 室、透視検査室 1 室、および MRI 検査室 1 室を COVID-19に対応できるよう環境整備した。
・ ME 担当者が⼈⼯呼吸器、ECMO を運⽤した。
(4) ⼊院体制
・COVID-19 感染者のために⼀般病棟を専⾨病棟に転換した。
重症患者:24 名程度を想定。ICU 内に⽤意した。
軽症/中等症患者:最⼤ 100 名を想定し、⼀般 2 病棟(46 床 x2)を COVID-19 専⽤病棟にした。
COVID-19 専⽤病棟を⽤意するに当たっては、COVID-19 以外の病棟の稼働率を 5-10%抑制し、内科系患者を他病棟に移動させた。
・⼈⼯透析症例を 2 例受け⼊れた。
・妊婦症例を 2 例受け⼊れた。
(5)⼿術体制
COVID-19 対応診療体制の構築においては、⾮ COVID-19 患者の診療維持と医療資源配分に対するバランスを考慮した。しかし、⼿術、ICU に関しては、制限を⾏わざるを得なかった。
・緊急性レベル分類(I〜IV)に基づく⼿術の制限や⾃粛を求めた(4/20 より)
・⼿術室気管挿管時のフェイスシールドの使⽤を開始した(2/27)
・COVID-19 陽性患者の⼿術に対応するための多職種シミュレーション(対応マニュアル作成し情報共有した。
・ ⼿術室⿇酔科医と看護師は、5 ⽇サイクル再使⽤で N95 マスク使⽤開始(4/30)
・ ⼿術時のエアロゾル発⽣対策をとった(フィルター機能付き腹腔鏡装置、排煙装置付き電気メスの購⼊)
・ ⼿術室⼊室患者はサージカルマスクを装着した(4/23)
・ COVID-19 患者の緊急⼿術に対応できるように陰圧⼿術室を⽤意した。
・ 術前呼吸機能検査の原則中⽌
・ 術前⼝腔ケアの中⽌
・ 術前リハビリの中⽌
・ フロンティア医⼯学センターがフェイスシールドを作成した。
(6) ICU
術後 ICU ⼊室患者は、ICU 内 COVID-19 患者数に応じて制限した(4/6 より)
ICU は 6 名の重症患者を診療し、6 名中 4 名は、呼吸不全に対して ECMO を⾏った。
陰圧室で診療を⾏った。
院内全体の体制・ガバナンス・マネジメント
2/18 に病院⻑を本部⻑とした新型 COVID-19 感染症対策本部を設置した。
対策本部に「診療チーム」と「⽀援チーム」を設け、「診療チーム」では各診療科の医師によるチームを編成し、COVID 陽性患者の治療にあたった。また、「⽀援チーム」では患者情報、個⼈防護具の在庫状況、職員の健康チェック報告などを⾏い、検討が必要な事項は対策本部へ報告を⾏った。
・ インフェクションコントロールチームは 1 ⽉ 29 ⽇に全職員を対象に新型 COVID-19 感染症について、セミナーを開催し、現況と千葉⼤学の⽅針を説明した。
千葉県庁にリエゾンを派遣した。
マスコミにも千葉⼤学の診療体制を公開した。
院内広報を強化し技術的な⽀援をするとともに⼀体感や⼠気を醸成(例:毎週⽉曜朝に全職員へ向けて病院⻑のメッセージを配信している。)
・ 2/16 から全職員に対する健康チェックを開始した。
・ 院内出⼊り業者(院内売店など)への感染予防教育(感染制御部)をおこなった。
・ 希望者にはホテル宿泊を提供した。
・ PCR 検査や COVID 診療にあたった職員に対して、新型コロナウイルス感染症業務従事⼿当(危険⼿当)を⽀給した。
院内感染
院内感染は 1 例も発⽣していない。
PCR 検査
・2 ⽉21⽇より 5 ⽉ 25 ⽇までに 917 回の PCR 検査を⾏っている。
―陽性患者の陰性確認(治療後)と疑い症例 374 件。119 件(31.8%)が陽性であった。
―⼊院時スクルーニング検査実施 543 例は、全例陰性であった。
―費⽤は病院負担であり患者負担はない。⺠間への外注検査はない。
・医学部キャンパス内にある真菌医学研究センターの BSL3 実験室で COVID-19 の核酸抽出を⾏った後に病院検査部で PCR 検査を実施している。2 ⽉21⽇からの PCR 検査の⽴ち上げ当初は千葉市保健所、千葉県衛⽣研所と協⼒して PCR 検査の精度管理を⾏った。
経営への影響外来患者数、⼊院患者数、病床稼働率の前年度⽐(%)は、2 ⽉より減少しはじめ、4 ⽉にはマイナス 15-17%に達した。これに施設整備、危険⼿当、PCR 検査などが加わり、経営的には相当のマイナスになる。
外来患者数 ⼊院患者数 病床稼働率
2 ⽉ -3.8% -3.2% -6.5%
3 ⽉ -0.5% -7.8% -7.3%
4 ⽉ -17.7% -15.1% -15.1%
5.主張:PCR 検査は最も重要な院内感染対策
前回の岐⾩⼤学、東京医科⻭科⼤学そして今回の千葉⼤学の取り組みを調べているなかで、PCR 検査の重要性を再認識しました。院内感染を防⽌するためには、コロナ診療に関わっている医療従事者、新規患者(救急を含む)に PCR 検査を⾏い、感染の有無を確認することが重要なのです。⼀旦院内感染が起これば、病院はメガクラスターになり、病院は閉鎖され、医療崩壊につながります。事実、栄寿病院(東京都上野)では 214 名、聖マリアンヌ医⼤横浜⻄部病院からは 78 名の院内感染者を出しています。今回の緊急事態宣⾔解除にあたって、神奈川県が基準をクリア出来ませんでしたが、院内感染が⾮常に多いのが⼀つの理由です。神奈川では、調べただけでも 10 の病院で院内感染が発⽣しています。
コロナ感染を防ぐためには、感染スクリーニングとしての PCR 検査が絶対に必要です。それなのに、何故、厚労省は認めないのか、その必要性を、私の理解に基づいて、順を追って主張します。
主張:院内感染対策としての医療従事者への PCR 検査公的負担を直ぐに認めるべきである。
① 感染クラスター:病院はメガクラスターになる危険性を秘めている。
② コロナ死亡者:病院内にはコロナ死のハイリスクグループ患者がたくさんいる。
③ 医療崩壊:⼀旦、院内感染が発⽣すると、医療従事者隔離、診療制限などにより医療崩壊につながる。コロナ以外の医療にも影響が及び、地域医療は崩壊する。
④ スクリーニング検査:院内感染を防ぐためには、コロナ診療、検査関係者全員の、PCR検査によるスクリーニングが必要である。無症状の感染者が医療従事者に⼀⼈でもいると、院内で感染が拡⼤するからである。
⑤ ⼊院前検査:⼊院する患者(救急を含む)に対して PCR 検査による「⽔際スクリーニング作戦」が重要である。
⑥ PCR 検査費⽤:現在、厚労省は、コロナ感染患者と疑いのある⼈のみに PCR 検査を認めている。このため、医療従事者の感染スクリーニングは、病院が⾃前で⾏っている。⾃前で⾏えるのは、⼤学病院など⼤病院に限られている。
⑦ 公費負担:中⼩の病院は、⾃前で PCR 検査を⾏う設備もなく、財政的余裕もない。スクリーニング検査の公費負担を認めないと、病院が感染のクラスターとなる危険がある。
⑧ 費⽤対効果:PCR 検査費⽤はほぼ2万円。200 件検査でも 400 万円である。⼀⽅、院内感染、病院閉鎖になれば、その 100 倍、数億円の損失になる。これほど、費⽤対効果の良い対策はない。
同じような趣旨の要請は⽇本医学会連合などの医学会から出されていました。5 ⽉ 22 ⽇厚労省は、特定機能病院および DPC(包括診療)では、患者の⾏政検査としての PCR 検査を可能としましたが、院内感染防⽌のための医療従事者へのスクリーニング PCR 検査は含まれていません。重ねて主張しますが、患者だけでなく、医療従事者の検査が、院内感染予防のために重要なのです。
6.古川俊治先⽣による Significant Scientific Evidences about COVID-19
古川俊治先⽣は、参議院議員(⾃⺠党)、医師(慶応⼤学医学部教授)、弁護⼠(慶応⼤学法科⼤学院教授)の 3 分野で活動をしておられます。2000 年代には、TBS の報道番組「ブロードキャスター」でコメンテーターとして出演されていたのを覚えておられる⽅も多いと思います。私は、「開成医学会」その他の私的な会でご⼀緒しております。その古川先⽣が、医学研究者としてコロナに関する論⽂の詳細な解説(70 ページ)を出しておられます。感染症学会の HP にでておりますので、ご紹介します。
http://www.kansensho.or.jp/uploads/files/topics/2019ncov/covid19_sse_0513.pdf
以上、転載を終わります。
お読みいただき有難うございました。