
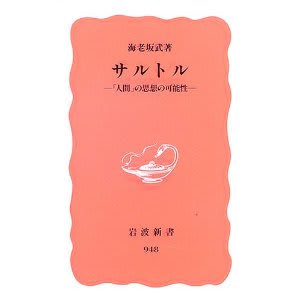

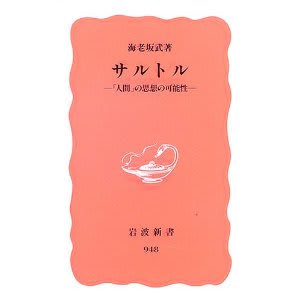
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (German: [??e???k ?v?lh?lm ?f?i?d??ç ?he???l]; August 27, 1770 ? November 14, 1831) was a German philosopher, and a major figure in German Idealism. His historicist and idealist account of reality revolutionized European philosophy and was an important precursor to Continental philosophy and Marxism.
Hegel developed a comprehensive philosophical framework, or "system", of Absolute idealism to account in an integrated and developmental way for the relation of mind and nature, the subject and object of knowledge, psychology, the state, history, art, religion, and philosophy. In particular, he developed the concept that mind or spirit manifested itself in a set of contradictions and oppositions that it ultimately integrated and united, without eliminating either pole or reducing one to the other. Examples of such contradictions include those between nature and freedom, and between immanence and transcendence.
Hegel influenced writers of widely varying positions, including both his admirers and his detractors. Karl Barth compared Hegel to a "Protestant Aquinas." Michel Foucault has contended that contemporary philosophers may be 'doomed to find Hegel waiting patiently at the end of whatever road we travel.' Hegel's influential conceptions are those of speculative logic or "dialectic", "absolute idealism". They include "Geist" (spirit), negativity, sublation (Aufhebung in German), the "Master/Slave" dialectic, "ethical life" and the importance of history.
Immanuel Kant (German: [??ma?nu?e?l kant]; 22 April 1724 ? 12 February 1804) was a German philosopher who is widely considered to be a central figure of modern philosophy. He argued that human concepts and categories structure our view of the world and its laws, and that reason is the source of morality. His thought continues to hold a major influence in contemporary thought, especially in fields such as metaphysics, epistemology, ethics, political philosophy, and aesthetics.
Kant's major work, the Critique of Pure Reason (Kritik der reinen Vernunft, 1781), aimed to bring reason together with experience and to move beyond what he took to be failures of traditional philosophy and metaphysics. He hoped to end an age of speculation where objects outside experience were seen to support what he saw as futile theories, while resisting the skepticism of thinkers such as David Hume.
René Descartes (French: [??ne deka?t]; Latinized: Renatus Cartesius; adjectival form: "Cartesian"; 31 March 1596 ? 11 February 1650) was a French philosopher, mathematician, and writer who spent most of his life in the Dutch Republic. He has been dubbed The Father of Modern Philosophy, and much subsequent Western philosophy is a response to his writings, which are studied closely to this day. In particular, his Meditations on First Philosophy continues to be a standard text at most university philosophy departments. Descartes's influence in mathematics is equally apparent; the Cartesian coordinate system ? allowing reference to a point in space as a set of numbers, and allowing algebraic equations to be expressed as geometric shapes in a two-dimensional coordinate system (and conversely, shapes to be described as equations) ? was named after him. He is credited as the father of analytical geometry, the bridge between algebra and geometry, crucial to the discovery of infinitesimal calculus and analysis. Descartes was also one of the key figures in the Scientific Revolution and has been described as an example of genius. He refused to accept the authority of previous philosophers and also refused to accept the obviousness of his own senses.
Johanna "Hannah" Arendt (14 October 1906 ? 4 December 1975) was a German-American political theorist. Though often described as a philosopher, she rejected that label on the grounds that philosophy is concerned with "man in the singular" and instead described herself as a political theorist because her work centers on the fact that "men, not Man, live on the earth and inhabit the world." Her works deal with the nature of power, and the subjects of politics, direct democracy, authority, and totalitarianism. The Hannah Arendt Prize is named in her honour.
誰からも敬愛される高名な哲学者から一転、世界中から激しいバッシングを浴びた女性がいる。彼女の名はハンナ・アーレント、第2次世界大戦中にナチスの強制収容所から脱出し、アメリカへ亡命したドイツ系ユダヤ人。
1960年代初頭、何百万ものユダヤ人を収容所へ移送したナチス戦犯アドルフ・アイヒマンが、逃亡先で逮捕された。アーレントは、イスラエルで行われた歴史的裁判に立ち会い、ザ・ニューヨーカー誌にレポートを発表、その衝撃的な内容に世論は揺れる…。
「考えることで、人間は強くなる」という信念のもと、世間から激しい非難を浴びて思い悩みながらも、アイヒマンの<悪の凡庸さ>を主張し続けたアーレント。歴史にその名を刻み、波乱に満ちた人生を実話に基づいて映画化、半世紀を超えてアーレントが本当に伝えたかった<真実>が、今明かされる─。
Simone Weil (French: [sim?n v?j]; 3 February 1909 ? 24 August 1943) was a French philosopher, Christian mystic, and political activist.
Weil's life was marked by an exceptional compassion for the suffering of others; at the age of six, for instance, she refused to eat sugar after she heard that soldiers fighting in World War I had to go without. She died from tuberculosis during World War II, possibly exacerbated by malnutrition after refusing to eat more than the minimal rations that she believed were available to soldiers at the time.
After her graduation from formal education, Weil became a teacher. She taught intermittently throughout the 1930s, taking several breaks due to poor health and to devote herself to political activism, work that would see her assisting in the trade union movement, taking the side of the left in the Spanish Civil War, and spending more than a year working as a labourer, mostly in auto factories, so she could better understand the working class.
Taking a path that was unusual among twentieth-century left-leaning intellectuals, she became more religious and inclined towards mysticism as her life progressed. Weil wrote throughout her life, though most of her writings did not attract much attention until after her death. In the 1950s and 1960s, her work became famous on continental Europe and throughout the English-speaking world. Her fame began to decline in the late 1960s and she is now rarely taught at universities. Yet her thought has continued to be the subject of extensive scholarship across a wide range of fields. A meta study from the University of Calgary found that between 1995 and 2012 over 2,500 new scholarly works had been published about her. Although sometimes described as odd, humourless, and irritating, she inspired great affection in many of those who knew her. Albert Camus described her as "the only great spirit of our times".
根をもつこと、それは魂のもっとも切実な欲求であり、もっとも無視されてきた欲求である。職業・言語・郷土など複数の根をもつことを人間は必要とする―数世紀にわたる社会的絆の破砕のプロセスを異色の文明観歴史観で辿り、ドイツ占領下の祖国再建のために起草した私的憲法案。亡命先で34歳の生涯を閉じたヴェイユ渾身の遺著。
ルソーは人間の本性を自由意思を持つものとして考え始める。自然状態では各個人は独立した存在として自己の欲求を充足させるために行動し、生存の障害が発生すればその解決のために各個人同士で協力関係を求める。こうして生じる個々人の約束は社会契約の概念として把握される。社会契約の枠組みに従って国家が正当化されるためには人間の自由な意思が社会契約の中で保障されていなければならず、本書では個人のための国家の在り方を論じている。
社会における全ての構成員が各人の身体と財産を保護するためには、各人が持つ財産や身体などを含む権利の全てを共同体に譲渡することを論じる。人びとが権利を全面的譲渡することで単一な人格とそれに由来する意思を持つ国家が出現すると考えられる。国家の意思をルソーは「一般意思」と呼んでおり、これは共同体の人民が市民として各人の合意で形成したものであると同時に、一般意思が決定されてからは臣民として絶対服従しなければならない。なぜならば一般意思とは各個人の私的利益を求める特殊意思とは反対に公共利益を指向するものであるからである。したがって一般意思をもたらす人民は主権者として見直すことが可能となる。
しかし人民主権の理念を具体化するためには多くの実際的問題が認められる。人民は主権者であり、一般意思が公共の利益を指向するとしても、人民の決議が常に正しいとは限らない。人民全員が参政することは非現実的であるばかりでなく非効率である。そこで人民に法を与える立法者の役割が導入される。立法者は制度や習俗を構築することで共同体を構築する。さらに人民の習俗が維持するための監察官を用意することで社会契約や法の絶対性を教義とする市民宗教を教育し、共同体を維持する。
A・ネグリとM・ハートによる『Empire』の日本語版がようやく発売された。あまりの厚さに驚くかもしれないが、いざ読んでみると実に分かりやすいことにすぐ気づくだろう。
本書は12年前の湾岸戦争の衝撃から生まれた。それに次ぐユーゴスラビアでの戦争、世界新秩序、そしてグローバリゼーションとその直接の帰結である国内のさまざまな改革について、それぞれ個々の議論はありながらも、ではつまるところ世界はどうなっているのかということについてははっきりした議論はなかった。とりわけ現状に対して批判的に接しようとする者にとって、決定的な理論が出ないことに対して大いに不満だっただろう。
本書は、そういった不満を一掃させてくれる、すぐれて総合的な世界の見方を大胆に示した書物だ。著者たちは本来の彼らのスタイルである難解な文体を捨て、平明な語りに終始している。まず読みとるべきは、ポストコロニアル理論、カルチュラルスタディーズ、H・アーレント、マルクス、ドゥルーズ、スピノザ等々、今まで別々に語られてきた批判理論のほとんどすべてが検討され、個々の理論がお互いどう結びつくのかといった、われわれの疑問に彼らはみごとに答えている点だ。しかも単に図式を描くだけでなく、「内在平面」とかバイオ・ポリティックスなどのキーワードを駆使して、世界の変化がわれわれ個々人の内面といかに密接に関連しあうのかを示していることも、本書の類まれな特徴の1つだ。単なる教養の域を超えて、日常の葛藤から世界認識までを描いているのだ。
この書に対して、アメリカの位置づけをめぐって批判が世界から噴出した。また頻出する「マルチチュード」という言葉に対して、具体的に何を指すのかについても曖昧(あいまい)だという弱点はある。しかし、ともかく彼らは強力な図式を提示し、われわれを豊穣な論争の世界へ誘っている。現実が見えなくなったとぼやく前に、ぜひとも読まれるべき本だろう。(池上善彦)
『全体主義の起源』(The Origins of Totalitarianism)とはハンナ・アーレントによる政治学の著作である。
アーレントは1906年にドイツのハノーファーで生まれた政治学者である。1933年にナチ党が政権を掌握してからフランスへ亡命して政治活動に関わるが、1941年にフランス進攻があるとアメリカへ亡命して大学での教育に従事する。この著作では19世紀から20世紀にかけてイタリアやドイツで出現した全体主義についての論考が行われている。この著作は1951年に発表された研究であり、第1部の『反ユダヤ主義』、第2部の『帝国主義』、そして第3部の『全体主義』の三部から構成されている。
19世紀のヨーロッパの政治秩序を構成していたのは絶対主義の王政に基づいた国民国家であった。国民国家は文化的同一性に立脚して統一的集団として確立された。この国民の枠組みとは別に成り立っていたのが階級社会である。つまり富裕層や貧困層などの諸階級から成り立っている階級社会であり、これは国民を文化的に同一だとした国民国家と本質的には矛盾するものである。当時のヨーロッパの政治秩序においてはこの国民国家と階級社会の衝突は見られることはなかったが、その中でユダヤ人は階級社会から隔絶されており、また平等な国民の一員として国家に保護されていた集団であった。そのために国家に対する不平不満が生じるとその矛先がユダヤ人に向けられるようになる。これが全体主義に向かう前段階であった。アーレントは『反ユダヤ主義』が表面化した事例としてドレフュス事件に言及している。
国民国家の体制に次第に大きな影響力を及ぼすようになったのが資本主義であり、資本家は政治への介入を積極的に行うようになる。資本主義、人種主義、そして官僚制の混合として帝国主義が出現する。帝国主義は資本主義の原理によって資本の輸出を推進しながら行政によって権力の輸出をも推進する。この帝国主義の膨張活動にとって国民国家は支障となり、階級社会から脱落した人々であるモッブが移民となって植民地化に乗り出していった。加えて人種主義は国民とは異なる外見的な差異を持つ集団を自覚させることで植民地の支配を正当化し、また官僚制は植民地の支配に適当な政令を発令することで、帝国主義の特徴である半永久的な膨張政策を進展させた。イギリスやフランスは植民地を海外に求める海外帝国主義が可能であったが、ドイツやロシアはその海外展開に遅れたために欧州大陸内方面に植民地を求める大陸帝国主義を余儀なくされた。海外への膨張を遮られた大陸帝国主義は、次第に国民国家により構成された政治秩序を超えた汎民族運動と連携しながら、人種主義(種族的ナショナリズム)の性格を強めることになる。
20世紀においては国民国家とそれに伴う階級社会が転換することになり、少数民族や人権問題の出現、大衆社会の成立が認められる。国内政治において政党が代表していた階級社会が消失したために、政党によっても代表されない孤立化した大衆が表面化したのである。ソ連について言えば、スターリンが農業集団化と有産階級の撲滅により個々を孤立無援にすることで、大衆社会を成立させたとする。この大衆は自らの政治的発言を階級政党とは別の政治勢力として集約しようと試み、プロパガンダを活用する全体主義運動を支持することになった。全体主義は大衆の支持を維持するために、また全体主義が体制として機能するためにはテロルとイデオロギーが重要である。テロルは法の支配によって確立されていた自由の領域を排除し、イデオロギーは一定の運動へと強制することで全体主義を制度化した。全体主義体制が問題であるのは、「個人性をまったく殲滅するようなシステムをつくること」にある。
Eastern philosophy includes the various philosophies of South and East Asia, including Indian philosophy, Chinese philosophy, Japanese philosophy, and Korean philosophy. Sometimes Iranian/Persian philosophy can be considered as eastern philosophy. Broadly speaking the term can also sometimes include Babylonian philosophy, Jewish philosophy, and Islamic philosophy, though some of these may also be considered Western philosophies.
中村 元(1912年(大正元年)11月28日 - 1999年(平成11年)10月10日)は、インド哲学者、仏教学者。東京大学名誉教授、日本学士院会員。勲一等瑞宝章、文化勲章、紫綬褒章受章。在家出身。
主たる専門領域であるインド哲学・仏教思想にとどまらず、西洋哲学にも幅広い知識をもち思想における東洋と西洋の超克(あるいは融合)を目指していた。外国語訳された著書も多数ある。
『中村元選集』(春秋社、1988年〈第1巻〉~1999年〈別巻4〉)