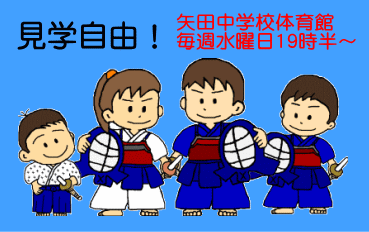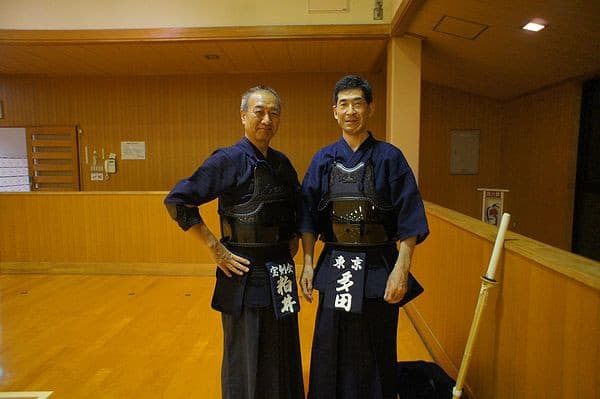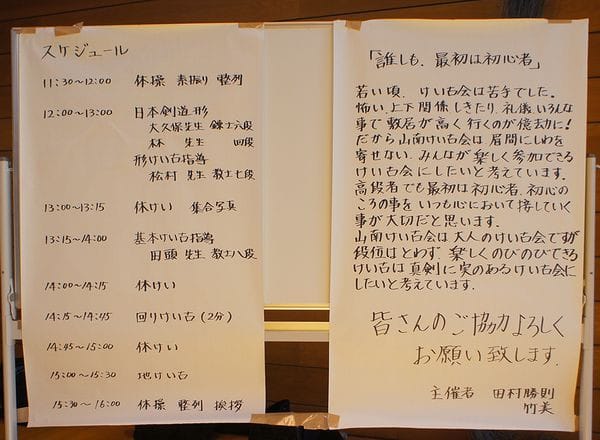2019年11月15日の、長井長正範士の遺文「No.83(昭和62年8月20日)」で、
左足の重要性のことを紹介した。
No.83(昭和62年8月20日)
https://blog.goo.ne.jp/kendokun/d/20191115/
その一部分を抜粋
------------------------
「左足は支持脚、右足は運動脚」
真っすぐ目標物に向かっているのは左足であって右足ではない。
左足は安定保持と方向性、右足はスピードコントロールと全身の器用性の役割。
------------------------
自分的に・・だが、この記述は「目からウロコ」だった。
相手と向かい合い、真っ直ぐ相手に向かって進もうとする時、
右足を真っ直ぐ相手に向かって進めようとする。
これは当たり前で間違いではない。
しかし、右足だけの意識で真っ直ぐ進もうとした場合、
体軸のブレが(ほんの僅かにだが)生じて、身体全体が捻じれたようになり、
結果として、少し不安定にブレながら前に進んでいることに気づいたのだ。
もちろん「体幹が出来ていない」ということもあるだろうが、
真っ直ぐ進むという部分で「左足の重要性」はまったく意識していなかったのだ。
-------------
そうなると、左足が外を向いている状態(撞木足)とは何なんだろうか?
どうやら左足が横を向いているときは守りの意識が強く、
前を向いている時は攻めの気勢であり体勢であるように思う。
私は過去、なかなか撞木足のクセが直らず困っていた。
稽古に夢中になると、左足先がどちらを向いているのかわからなくなる。
せめて構えた時だけは真っ直ぐ向けるようにはしようとしてきて今に至る。
「左の膝頭を相手に向ける」意識を持てと言われたことがあり、
なるほどと思い、稽古中、気が付いたら意識して修正するようにしている。
左足、左腰の大切さはよく言われることである。
しかし私の剣道ではまだ不完全で出来ていない。
前に出るには、右足で大きく前に出るのではなく、
左足で大きく前に押し出してやる・・という感じが大事なのだろう。
「真っ直ぐ進むのに大事なのは左足」ということを改めて認識し、
今後の稽古の中で「左足で前に出る」を常に意識して稽古したいものだ。