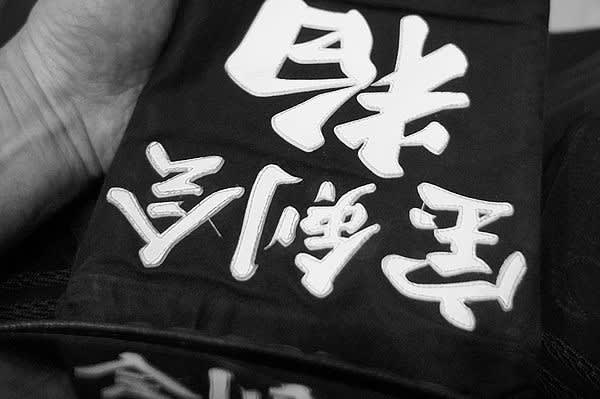大阪市東住吉区の矢田中学校の体育館で毎週水曜日19時半から。
----------------------------------------
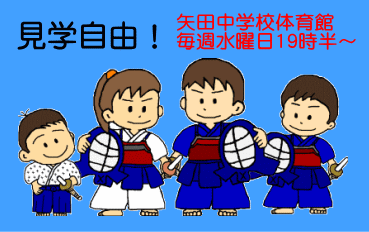
【長正館練習生募集中】
初心者、元経験者、有段者を問わず募集中。
レベルに応じて個別指導を行います。
詳しくは長正館ホームページまで。
http://doujyou.net/choseikan/
----------------------------------------
今年最後。稽古納め。
先週よりは暖かいが寒いことに変わりは無い。
人数は最終16名。うち小学生3名、中学生2名。
七段4名、六段1名、五段3名。稽古は少し大幅に長引いた。
稽古納めなので、稽古終了後に集合写真を撮る。















【感想・反省点】
道場があった頃は稽古納めは年越し稽古で、
毎年12月31日の夜に稽古して、年明け前に稽古を終了して挨拶して解散していた。
体育館ではあの雰囲気は味わえないのが残念だが、
稽古納めに大勢が集まったのでこれは嬉しいことである。
----------------------------------------
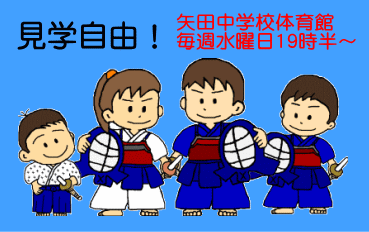
【長正館練習生募集中】
初心者、元経験者、有段者を問わず募集中。
レベルに応じて個別指導を行います。
詳しくは長正館ホームページまで。
http://doujyou.net/choseikan/
----------------------------------------
今年最後。稽古納め。
先週よりは暖かいが寒いことに変わりは無い。
人数は最終16名。うち小学生3名、中学生2名。
七段4名、六段1名、五段3名。稽古は少し大幅に長引いた。
稽古納めなので、稽古終了後に集合写真を撮る。















【感想・反省点】
道場があった頃は稽古納めは年越し稽古で、
毎年12月31日の夜に稽古して、年明け前に稽古を終了して挨拶して解散していた。
体育館ではあの雰囲気は味わえないのが残念だが、
稽古納めに大勢が集まったのでこれは嬉しいことである。