何とか台風の影響も受けずに
お彼岸のお中日の法要を勤めることができました。
最近は寺との関わり、墓の在り方、参り方、
そして弔う心までも一連のメディアに支配され、
自身が考える以前に「時代の流れ」という括りだけで
これまでの思いや歴史まで
ちょっと???な方向へ進めようとしている
そんな感じがしてなりません。
寺の営みについて20年も前から言われています。(その前から)
私もまだ若輩者であった頃(今でもバカ者 もとい 若者ですが)
研修を通して年齢や宗派関係なく夜通し論議したものです。
寺の行く末や葬儀・墓の在り方を憂いているばかりではなく、
守られる者、守る者 双方の思いを一つにして、
命の原点に立ち返ることが大切であるとおもっています。
最近は無人島を樹木葬の場所にする、海に散骨する、
夫婦や家族と一緒ではなく、
趣味が同じで気があった人とだったり、
一人が気楽と合同供養墓を希望する人がいたり、
一人身や継承する人が絶えるということで
永代供養墓を考える人も・・・
致し方ない。そういう方も少なくありません。
弔う形に正解はありません。
人生の最後は生活、思考、最終的には法律にのっとって、
人の数だけあります。
従来の考え方や生き方と同じようにいかない世の中で、
どうするべきなのか。
改めてじっくり考える時代になっている気がします。
しかし、こんな話を耳にしました。(立ち聞きではありませんよ
 )
)ある日孫と一緒に墓参りにきた方が、
「年金暮らしで生活も苦しいし、
葬儀なんかにお金をかけさせるのは申し訳ない、
とにかく死ぬときも、死んだ後も迷惑をかけたくない」
そう茶飲み話をしていました。
そして、
「お墓を維持するのも大変だから、
海や木に散骨してもらうっていうことも有りだな~」
そんな話も笑いながら皆としていました。
ひとしきりそんな話がつづき会話が途切れた時、
一緒に来ていた孫が、
「もし、おじいちゃんやおばあちゃんが海に蒔かれたら、
どこの海に行けばいいの?
おじいちゃんの骨を飲み込んだかもしれない魚が居るかもしれないから
もう魚は食べられなくなる。」
「・・・」
「じゃ 木にしよう」
「周りの木は平気なのにおじいちゃんところだけ枯れちゃったら?」
「・・・」
まだ低学年くらいのお子さんでしたが、一理あります。
おくられるひとの思いも大事ですが、
おくるひとの気持ちも無下にはできません。
【自然に還る】たしかに戦国時代など、歴史の中では
葬儀を出す、墓を作る、守る。
決まった形がなかった時がありました。
だから弔いを無かったことにしてもいいのか?
弔う気持ちがあれば無くなった場所から直ぐに火葬にして、
人知れず納骨することがいいのか?
本人の遺言で内々だけで、と親戚や兄弟に声をかけなくていいのか?
(普段は余り話をしなくても、
こういう時だけ遺言を盾に意見を通そうとしますが。。。)
究極の論議です。
現在の形式に疑問がないわけでもありません。
確かに必要以上にかかる経費、寺への布施、
どこを取っても自分の身になるものではありません。
亡き方への供養 ただその一念であるのではないでしょうか。
中には世間体、親族の手前などと考えている人もいるかしれませんが、
それでも縁あって同じ時間を過ごした者への敬いが、
葬儀という形になっていてほしいと願います。
寺を守る者としての意見もあるのですが、
その思いが相手に伝わっていないことが問題で、
伝えようとしていない独りよがりなところが、
寺側にもあるようにおもいます。
今はシビアな時代。
家族という集団から個々の集まりという形態に変わりつつあり、
気がつけば物言わぬ
 (時々音声を発しますが)
(時々音声を発しますが)何事も筒抜けで、四角い小さな物
 と過ごすだけの日々、
と過ごすだけの日々、機械を通じて繋がる。意味を知りたいです。
同じ場所にいても同じ時間を共有していない人びと。
何を持って社会というのでしょうか。。。
本当に難しい。(確かに便利ではありますが)
何事も人とひととが出会い、話、理解する・・・
その心配りが生きてる証。
死ぬまでのこと、死んだ先のことを心配することは大事ですが、
その前に意見の相違があっても相手を攻撃することなく、
揚げ足を取ることなく、黙り込むことなく、
言い過ぎたら「ごめんなさい」
良くも悪くも会話、対話を楽しむこと。
究極の人生の楽しみ方を知らずにいる人は沢山います。
「粋」な生き方を忘れた今、
所作を見直す好い機会かもしれません。
お彼岸を迎えてこんなことをおもいました。












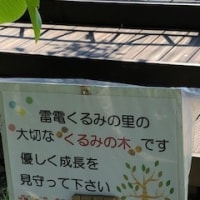







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます