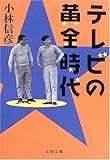昨日、8月15日は63回目の終戦(正確には敗戦)記念日だった。
63年前といわれると、「随分前」としか思えないが、私が生まれたのが昭和30年で、それは敗戦から、わずか10年後のことだ。今から10年前なら1998年、平成10年。「ほんの少し前」、「つい昨日のような」と言いたくなるほど近い過去だ。
「昭和20年代」には、まだ戦争の時代の面影があるが、わずか10年後に始まる「昭和30年代」となると、戦争や敗戦のイメージは急に薄れる。
だが、それだって2008年という現在から見ての事であり、実際、昭和30年代には、まだ町角で傷痍軍人を見かけたし、デモや社会運動のスローガンとして「戦争反対」「戦争、許すまじ」は十分に生きていた。
そんなことを思うのは、特に今年の「8月15日」が、オリンピックの最中ということもあり、テレビが「終戦記念日特番」を打つわけもなく、靖国神社に政治家の誰が行き、誰が行かないといった報道くらいしか見なかったせいだろう。
一方、衛星放送の日本映画専門チャンネルは「東宝8.15シリーズ完全放送」の看板を掲げていた。『日本のいちばん長い日』『激動の昭和史 軍閥』『連合艦隊司令長官 山本五十六』などを流し続け、NHKはともかく民放地上波より、よほど終戦記念日らしい1日にしてくれた。
昭和は、①元年から20年まで、②20年代~30年代、③40年代、④50年代~最後の63年まで、といった具合に、大きく4つのブロックに分けられそうだ。個人的な感触でいえば、すでに第3ブロックあたりまでが「歴史」の範疇になってしまっているような気がする。
2台のテレビを同時につけて、衛星の『日本のいちばん長い日』と、甲子園での慶應VS浦添商の試合を、それぞれ横目で眺めつつ、秋山真志さんの新著『昭和~失われた風景・人情』(ポプラ社)を読んだ。
フリーランスのライター&エディターである秋山さんには、寄席を支える様々な仕事師たちを取材した『寄席の人たち―現代寄席人物列伝』(創美社)などの著書がある。
今回の本のテーマは、昭和30~40年代の、まさに”失われた風景”。主な舞台は東京だ。
手塚治虫、藤子不二雄、石森章太郎、赤塚不二夫といった漫画家が暮らしていた伝説のアパート「トキワ荘」。今は高層ビルが林立する新宿副都心にあった巨大な人工池「淀橋浄水場」。それから「丸ビル」や「玉川電車」も。
秋山さんは、東京の「かつてそれがあった場所」を訪ね、歩き回り、当時を知る人に話を聞いていく。
それだけではない。私のような「地方在住の子ども」にとっても、同じように懐かしい風景も登場する。デパートの屋上にあった楽園「屋上遊園地」。その店先に立つだけでわくわくした「駄菓子屋」などだ。
この本全体は、もちろん懐かしさにあふれているが、単なる懐古趣味ではない。丹念なフィールドワークによって、徐々に甦る「昭和の記憶」と「昭和の風景」は、ほとんど消えかけている「街と時代」の貴重な記録であり、資料だといえるだろう。
 | 昭和―失われた風景・人情秋山 真志ポプラ社このアイテムの詳細を見る |
この本の表紙で、女の子たちがキメているのは、もちろん「シェー!」のポーズだ。