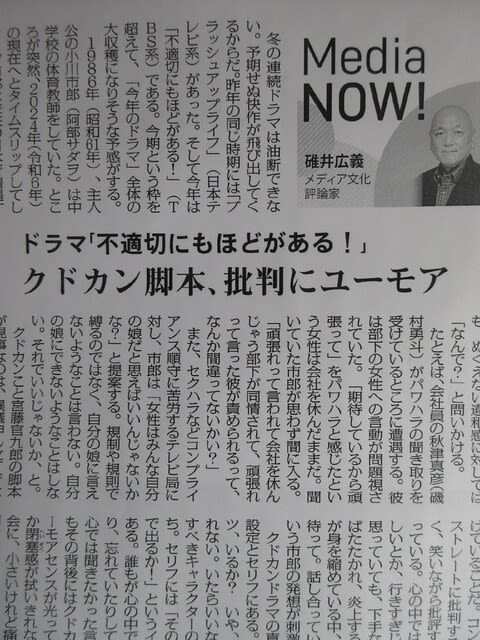〈Media NOW!〉
「新宿野戦病院」突然の終盤展開
クドカンならではの離れ業
クドカンこと宮藤官九郎が脚本を手掛けたドラマでは、特定の街・地域が背景となることが多い。「池袋ウエストゲートパーク」(TBS系)や「木更津キャッツアイ」(同)、そして岩手県の北三陸が登場したNHK連続テレビ小説「あまちゃん」もそうだった。
先日幕を閉じた「新宿野戦病院」(フジテレビ系)もまた、東京の新宿・歌舞伎町に焦点を当てた“地元ドラマ”と言えるだろう。しかし前記3作と異なるのは、軽妙なコメディータッチのドラマでありながら、「命」という重いテーマに正面から挑んでいたことだ。
物語の舞台は歌舞伎町の片隅にある「聖まごころ病院」。ヒロインは元軍医の日系アメリカ人、ヨウコ・ニシ・フリーマン(小池栄子)だ。外科医を探していたこの病院で働くことになった。「目の前の救える命を救うために軍医になった」とヨウコは言う。
アメリカでは患者の貧富の差が受けられる医療の差となっている。だが、戦地では男も女も善人も悪人も命に区別はない。「平等に雑に助ける、それが医者!」が信条だ。ドクターXならぬドクターY、手術は雑だが腕はいい。
日系アメリカ人っぽい英語と、岡山生まれの日本人である母親(余貴美子)から受け継いだ岡山弁が入り交じるヨウコの語り。それは見る者を引き込む独特の迫力と説得力があった。
「(英語で)私は見た。負傷した兵士、病気の子供。運ばれて来る時は違う人間、違う命。なのに死ぬとき、命が消えるとき、(岡山弁で)皆、一緒じゃ!」と力を込める。
続けて、「(英語で)心臓が止まり、息が止まり、冷たくなる。(岡山弁で)死ぬときゃ、一緒。それがつれえ。もんげえつれえ」と嘆く。もんげえつれえ(すごくつらい)からこそ、平等に雑に助けるのだ。そんなヨウコの存在は聖まごころ病院の医師たちを含め、周囲を少しずつ変えていく。
驚かされたのは終盤の展開だ。突然、物語の時間軸が2025年という近未来へと移り、新型コロナとは異なる新種のウイルス「ルミナ」の感染が拡大する事態を現出させたのだ。しかも、そこには見過ごせないリアリティーがある。
行政の機能不全。医療現場の混乱。SNS(ネット交流サービス)などによる誤った情報の拡散。ウイルスが海外から入ったことによる外国人への不当な抗議や排斥。そんな中、一人でも多くの命を救おうとヨウコらは奮闘する。未来の出来事の形を借りて過去と現在の状況を批評的に描く、クドカンならではの見事な離れ業だった。
(毎日新聞 2024.09.21 夕刊)