
■■■■■■■■■■■■能楽を嗜む■■■■■■■■■■■
北条俊彦
経営コンサルタント・前 住友電工タイ社長
■■「能楽 事始め」
●私は学生時代に能を少しかじった。流派は観世流である。
友人に能楽師の子息もおり、特に謡いには性根を入れて互いに
鍛えあったものである。おかげで今も声は良く出る。
時代劇などでサムライが夜道に悠然と謡う姿を見た方もおられ
るだろうが、我が学生時代も友人と夜、大学からの帰り道、扇
を手に謡いに興じることが多々あったがご近所から苦情を言わ
れることはなかったと記憶している。今と違い世の中いたって
おおらかだった。
学生時代の自演会では「小鍛冶」を演能したことは今も強く記
憶に残っている。
“蛙の子は蛙“ 友は今能楽師になっているが、学生時代に黒澤明
監督映画「影武者」で能のシーンに出演したのが プロになろう
としたきっかけのようだ。
能の演目は「田村」で武田信玄が野田城攻めの陣で薪能を鑑賞
するシーンであったと記憶する。
能の演目の多くは前場と後場の二部構成になっており、前半部
分の静かな雰囲気と後半部分の激しい動きの差を楽しむことが
できる。
前場では主役(シテ)はあまり動かず、語りが先立ち謡いの聴
かせどころが多く、ゆっくりしたリズムを奏でる囃子は心地良
いが、未熟な私はよく心地良い眠りに誘われた(笑)。
前場は全体として静かで哀しい雰囲気を醸成している。
後場は主役(シテ)の動きが激しく、力強い謡いとテンポの速
い囃子に合わせた主役(シテ)の舞は躍動感あり見どころも多
い。
“静から動(破)“その変化の醍醐味は中々のものである。
船弁慶、土蜘蛛は変化の醍醐味を楽しめる演目である。

●私は「俊寛」が特に好きである。
「俊寛」は「平家物語」に描かれた俊寛僧都の悲劇を舞台化し
た能である。俊寛は平家打倒の陰謀が密告により露見し鹿ヶ谷
で捉えられ、藤原成経、平康頼と共に異界の地鬼界ヶ島に配流
となる。
流人生活に打ち沈む日々の中、俊寛は同志の存在だけが心の拠
り所となっていた。京の都を懐かしみ赦免の日を心待ちに、水
を酒になぞらえ同志と酌み交わす俊寛は、配流地での悲惨な日
々の中にわずかながらも心のゆとりを見出すのであった。
ある日、待ちに待った赦免船が都から使わされてきた。赦免と
都への帰還を期待した俊寛であったが、瞬時にしてその期待は
裏切られた。赦免状には彼の名前だけが記されていなかったの
である。
何度も赦免状を読み返すが、やはりどこにも彼の名は無く俊寛
はただただ悲しみに打ち震えるばかりであった。

やがて、同志とも別れ孤島に独り取り残され、絶望の淵に突き
落とされた俊寛の究極の哀れさは、我々観るものの心を深く打
つ演目である。
主役(シテ)の被る能面は俊寛の心の全てを映し出しており、
また その静かな主役(シテ)の動作ひとつひとつに寂寥、孤独、
疑心、期待、悲しみ、絶望といった 心の変化が象徴的に表現さ
れている。是非、ご鑑賞頂きたい。

■■「風姿花伝」
●能楽とは式三番(翁) 能と狂言を包含する総称であるが、
能楽は江戸時代迄猿楽と呼ばれていた。その源流は奈良時代に
遡り、大陸から渡来した「散楽」が多様な芸能として進化し、
日本風に「猿楽/申楽(さるがく/さるごう)」と呼ばれるよう
になり時代の変化のもと世相を捉えた風刺笑劇として発達、後
々狂言に発展していった。
一方、鎌倉時代に農村部から生まれた「田楽」が流行し、猿楽
と互いに影響しあってきたが、室町時代に観阿弥・世阿弥親子
の登場により、より芸術性の高い舞台芸能へと大成されたので
ある。
特に世阿弥は、将軍足利義満の庇護も受け、父の志した「幽玄」
を理想とする歌舞主体の芸能に磨き上げ「複式夢幻能」という
スタイルを完成させている。
●観阿弥がこころざし、世阿弥が完成させた「幽玄(ゆうげん)」
とは“物事の趣が奥深くはかりしれないこと。
またその様(さま)を表現する言葉として文芸・絵画・芸能など
日本文化の基層となる理念の一つで、日本人の精神的支柱とな
っていることは 周知の認めるところである。
本来は仏教や老荘思想で用いられた漢語であったようだが、歌人
藤原俊成により、和歌を批評する用語として、有心(うしん)とと
もに歌道の理念として用いられた。
その後、能楽・禅・連歌・茶道・俳諧など中世・近世以降日本の
芸術文化に影響を与え続けている。
●世阿弥元清は、観阿弥の息子として生まれ、才能豊かな能役
者として、また作者として幽玄の美を追求する優れた演目を 数
多く世に残している。世阿弥が生み出した「複式夢幻能」 形式
は、時間が過去と現在に自在に交差しうる高度な作劇法である。
世阿弥は、政治的権力に翻弄され 後に佐渡へ配流となり悲運な
晩年をおくるが 「風姿花伝」「花鏡」「申楽談義」など多くの
伝書を残している。
「風姿花伝」は世阿弥が記した能楽の理論書で世阿弥の残した
21種の伝書のうち最初の作品である。父観阿弥の教えを基に能の
修行法・心得・演技論・演出論・歴史・能の美学など 世阿弥が
会得した芸道の視点から解釈を加えた著述になっており 「幽玄」
「花」「物真似」といった能の神髄を語る表現はここにその典拠
がある。
●能は演劇として現在も演じられる世界で最も古い舞台芸能と
して現在、ユネスコ無形文化遺産に登録されているが その典拠
には「源氏物語」「平家物語」「義経記」「伊勢物語」「大和
物語」「今昔物語」「曽我物語」等がある。また、主役(シテ)
の役柄によって能は大きく、
「神(しん)」
「男(なん)」
「女(にょ)」
「狂(きょう)」
「鬼(き)」
の5つに分類される。
●能舞台でのもう一つの主役「能面」は曲の演出を左右する重
要な存在で、能役者は「おもて」と呼び大切に扱う。
面をつけるのは主役(シテ)の特権である。素顔で演じる曲もあ
るが、その場合では「直面(ひためん)」と呼び役者は面をつけた
つもりで演じる。面は 生きた人間の表情を表現し、人間の魂と心
が宿っていると考えられている。


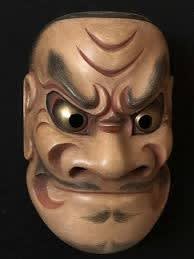

面は大きく7種類に分けられるが、細分すると200種にものぼる
そうだ。
●また、能囃子を構成する四種楽器の役割も大きい。


「能笛(のうてき、能管ともいう)」は、唯一のメロデイ楽器で吹
く強さによってオクターブの音階がでる。
「小鼓(こつづみ)」は、その日の天気で音が変わるデリケート
な楽器で馬の皮と櫻の胴で出来ている。
「大鼓」は、小鼓と同じ材料でできているが、周りをリードする
男性的な楽器で大皮(おおかわ)とも呼ばれる。
「太鼓」は、ここ一番で登場し曲のクライマックス部分に活躍、
他の打楽器と違い牛の皮を使用している。この四種楽器を「四
拍子(しびょうし)」という。
■■「幽玄に浸る」
●能楽堂は演能の舞台として、独特の雰囲気を醸し出し観客を
「幽玄」の世界へ誘ってくれる。屋内でも屋根があり、舞台の
大きさは6m四方で、大きく張りだした舞台と廊下のような「橋
がかり」の部分からなっており、主人公の登場のときなど 遠近
感がより出し易くなっている。
観客席を見所(けんしょ)といい舞台を正面・脇・斜めからの3
方で取り囲む独特の造りとなっている。


外国要人(国賓・公賓等)の接遇に日本文化の粋を集めた“おも
てなし”で能や歌舞伎などを催すことが多いが、タイのプミポン
前国王夫妻が1963年に国賓として我が国を訪問されたとき薪能
を鑑賞されたと記録にある。
● タイの伝統芸能にも、仮面を被って踊りつつお芝居をする
仮面舞踏劇(コーン)があり、古くから王室の重要な催しで
演じられてきた。
神、王、女性の役以外は仮面を被り、その豪華絢爛な衣装と眩
いばかりの金の冠(仏塔を表現)は実に美しい。

また「指先の技術」と言われ指や指先の繊細な動きはタイ舞踏
の大きな特徴の一つであり、美しい指先と身体全体の曲線美で
あらゆるものを表現するのである。
●代表的な作品にはインドの叙事詩「ラーマーヤナ」を題材に
した「ラーマキエン物語」が有名である。
新型コロナウイルス感染拡大の影響はタイの芸術文化にも及んで
おり、伝統舞踏劇を観劇しながらデイナーを楽しめた「サイアム
ニラミット」が昨年、残念ながら完全閉鎖になってしまったよう
だ。

























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます