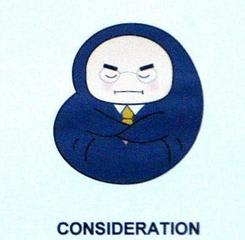日本のSPAは下記に大別される。
1)大手百貨店アパレルのSPA業態(ワールド、樫山、サンエイ、イトキン、ファイブフォックス等)
2)小売業出身のSPA業態(ユニクロ、シマムラ)
3)109系のSPA業態
4)専門店アパレルのSPA業態(マツオインター、ジオン商事、ハヴァナイストリップ等)
5)セレクト&SPA(ビームス、UA、パル、リステア、ザ・ファースト等)
6)形だけのSPA=売場を自社ブランドで固めたもの(社名は秘す)
7)海外からの進出組みのSPA(Gap、ZARA、
国内のSPAの夫々にマーケティング、MD、生産、ロジステッゥスや販売、VMD等の手法が異なっている。
これらを一律にSPAとすることには無理が有るのではないかという疑問がある。
アパレル系のSPAは、旧来の委託的な条件から進化させたものであると言えよう。
生産面や販売面での脆弱さは真のSPAと言えないと考える。
ロジスティックスや管理面においても従来の卸型のシステムや規範を改変しないままでの多店舗展開が規模の拡大とともにその矛盾が露呈しつつあるように見える。
SPA化により、POSシステムにだけ頼る傾向が強く、アパレルの本来の強みであった企画機能を○投げ、半投げと言われるアウトソーシング化が横行した。
その結果として、ブランドロイヤルティー(ショップロイヤルティー)を無くし、同質化の要因となった。
マーケティングの面からも、その出店が、百貨店からSC、路面店、ファッションビル、専門店とのFC契約等の無秩序なものであった。
その無秩序な出店は、後にMD面での混乱の要因となった。
アパレルのSPAは旧来の委託取引からの脱却の手段としては、販売利益率のアップと言う一定の効果はあったが、一方では経費の増加、販売ロスの増加、キャッシュフローの低下等の問題を抱えることになった。
大手アパレルの多ブランドによるSPAは、今後見直しが迫られてくる考えられる。
1)大手百貨店アパレルのSPA業態(ワールド、樫山、サンエイ、イトキン、ファイブフォックス等)
2)小売業出身のSPA業態(ユニクロ、シマムラ)
3)109系のSPA業態
4)専門店アパレルのSPA業態(マツオインター、ジオン商事、ハヴァナイストリップ等)
5)セレクト&SPA(ビームス、UA、パル、リステア、ザ・ファースト等)
6)形だけのSPA=売場を自社ブランドで固めたもの(社名は秘す)
7)海外からの進出組みのSPA(Gap、ZARA、
国内のSPAの夫々にマーケティング、MD、生産、ロジステッゥスや販売、VMD等の手法が異なっている。
これらを一律にSPAとすることには無理が有るのではないかという疑問がある。
アパレル系のSPAは、旧来の委託的な条件から進化させたものであると言えよう。
生産面や販売面での脆弱さは真のSPAと言えないと考える。
ロジスティックスや管理面においても従来の卸型のシステムや規範を改変しないままでの多店舗展開が規模の拡大とともにその矛盾が露呈しつつあるように見える。
SPA化により、POSシステムにだけ頼る傾向が強く、アパレルの本来の強みであった企画機能を○投げ、半投げと言われるアウトソーシング化が横行した。
その結果として、ブランドロイヤルティー(ショップロイヤルティー)を無くし、同質化の要因となった。
マーケティングの面からも、その出店が、百貨店からSC、路面店、ファッションビル、専門店とのFC契約等の無秩序なものであった。
その無秩序な出店は、後にMD面での混乱の要因となった。
アパレルのSPAは旧来の委託取引からの脱却の手段としては、販売利益率のアップと言う一定の効果はあったが、一方では経費の増加、販売ロスの増加、キャッシュフローの低下等の問題を抱えることになった。
大手アパレルの多ブランドによるSPAは、今後見直しが迫られてくる考えられる。