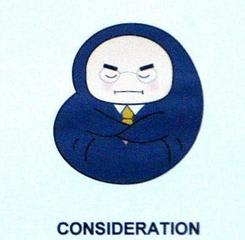先日の百貨店部門に続き第二弾です。
今後専門店、通信販売、生地問屋(テキスタイルコンバーター)部門と掲載されていくと思います。
興味深いデーターで、貴重な資料と思っています。
先の投稿にも書きましたが、繊維・アパレル・小売・流通の総合的なデーターで、業界がどのように盛衰し、どのように移行し、新しいチャネルが誕生ししているかの全体像が掴めて、今後の方向性を考える上で貴重な資料となります。
研究レポートで百貨店同様に1990年を基点として2006年のデーターを分析しました。
1990年は、全てのアパレルが「製造卸型」で、SPA(企画・製造小売型)がアパレルや専門店業界に取り入れられた年度と位置づけました。
1990年以降アパレル業界に大きな変化が起こりました。
A)ワールド、イトキン、サンエー、ファイブフォックス、JAVA、フランドルなどが脱卸を行いSPA型に移行しました。
B)一方、レナウン、三陽商会、東京スタイル、レナウンルック、ナイガイ、樫山などの百貨店老舗アパレルは樫山を除き百貨店中心のアパレルの座標を守りました。
C)かたくなに旧態の製造卸型に固執した、キング、キャングループ、ピアジェ(ライカ)、ラピーヌ、赤川英、コロネット紹介
D)クロスプラス、サンラリー、ジュニア、シンガポール、小泉アパレル等の量販店アパレル
A)~D)の1990年の経年比較により、それぞれのビジネスモデルがどのように盛衰、移行して言ったかを考察しました。
その変化を分析し、百貨店や専門店、通信販売、生地問屋などの経年比較を行なうことで、小売、流通の変化や生産の変化、空洞化などの効果と問題点が浮かび上がってくると考えています。
今後の専門店や生地問屋(テキスタイルコンバーター)、通信販売店などのランキングが発表を楽しみにしています。
1990年以前の川上→川中→川下の垂直的な河流型の繊維・アパレル・小売の業界構造が、SPAを中心とした水平的な流れに変化し、海外メガブランドやユニクロを始めとするしまむら、大手アパレルなどの海外グローバル化や、中小アパレル・小売(むしろ零細アパレル)によるBtoBやBtoCによるニュービジネスへの期待や“マンガ”に代表されるローカルローカル文化がアジアを中心としたリージョナル文化の勃興などが予測されます。
これらの潜在的なマーケットが生まれていることが予測されます。
これからの課題は、これらの潜在的な市場(消費者が真に受け入れらている)のマーケットにスポットを当て、醸成していくことも重要と思います。
私は、先の研究レポートで、繊維・アパレル・流通小売業界は川上→川中→川下の「河流型」から、生産から流通・小売・情報がグローバルにリージョナルにローカルに注ぎ合い、交流していく時代になっていると考えてて、「河流型」ではなく、「大洋型」と提唱しました。
そんな観点から、今日の繊研新聞のデーターを私のパソコンに入力して、分析してみたいと思います。