週末息抜きシリーズ。今週は、今年私が購入したJazz Albumでは恐らく最高と思われる、Ambrose Akinmusireの"When the Heart Emerges Glistening"に参加してピアノを弾いていた、Gerald Claytonの作品です。
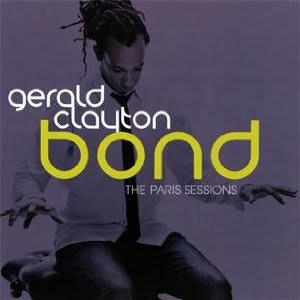
Bond: Paris Sessions 。購入前の期待が高かったのですが、それに見合う内容だと思います。
。購入前の期待が高かったのですが、それに見合う内容だと思います。
リーダーのClaytonをはじめ、BaseのJoe Sanders、ドラムズのJustin Brownの3人とも、若手の黒人プレイヤーです。
3人で相当に緻密にテーマを練り上げているのだと感じましたが、演奏そのものはジャズ的な即興性に満ちているので、押し付けがましい感じはしません。
むしろ爽快。
静かにピアノが語り始める曲が多いですが、リズム陣が意外と強力かつ主張が強く、中盤から終盤にかけて大きな盛り上がりを見せます。
そのリズムに応えるClaytonのピアノも若々しく、同時に知的な冷たさを湛えており、よく言われる表現を使うと"都会的な"空気が感じられます。
まあ、現代的で格好いいと言ってしまうとチープに聞こえますが、そういうアルバムです。ただし、内容はよろしい。楽曲、演奏、構成すべてレベル高い。
4分前後の比較的短めの曲が多いですが、それもある意味都会的なイメージにつながっていると思います。
10分近くの大きな曲だと力が入ってくるところも、短い曲だとある程度まとまりがよくなるのでしょう。
ある意味で抑制が効いたというか、エレガンスとかバランスとかいう表現で評価される部分につかがるのだと思います。
これはこれで無難なのですが、あえて欲を言うと、私としてはまだ20代のアメリカの(元々はオランダ出身らしいが)ピアニストにはもっとリスクをとってもらいたいと感じました。
才能は豊かな感じなので、どうせなら思い切り爆発させると楽しそうなのに。自分のリーダー作だと守りに入るんですかね。
ライブで聴いてみたいものです。おそらく、このアルバムの評価もそれなりに高いと思いますが、ライブで弾けた方がおもしろいプレイヤーだと思います。
相当に緊張感のある"When the Heart Emerges Glistening"で堂々たる演奏ができているのですから、もっと高みを目指してもいいと思いますね。
それにしても、やはりアメリカのジャズはよろしい。なぜかヨーロッパのジャズよりも自然に聴くことができるような気がしますね。
自由なんですかね。
↓記事がおもしろかったら、投票していただけるとありがたいです
 にほんブログ村
にほんブログ村
↓お勧めの本のリストを作りました。
冷たい風のような火を燃やすものたち
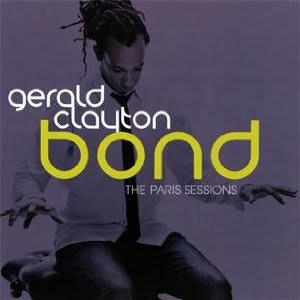
Bond: Paris Sessions
リーダーのClaytonをはじめ、BaseのJoe Sanders、ドラムズのJustin Brownの3人とも、若手の黒人プレイヤーです。
3人で相当に緻密にテーマを練り上げているのだと感じましたが、演奏そのものはジャズ的な即興性に満ちているので、押し付けがましい感じはしません。
むしろ爽快。
静かにピアノが語り始める曲が多いですが、リズム陣が意外と強力かつ主張が強く、中盤から終盤にかけて大きな盛り上がりを見せます。
そのリズムに応えるClaytonのピアノも若々しく、同時に知的な冷たさを湛えており、よく言われる表現を使うと"都会的な"空気が感じられます。
まあ、現代的で格好いいと言ってしまうとチープに聞こえますが、そういうアルバムです。ただし、内容はよろしい。楽曲、演奏、構成すべてレベル高い。
4分前後の比較的短めの曲が多いですが、それもある意味都会的なイメージにつながっていると思います。
10分近くの大きな曲だと力が入ってくるところも、短い曲だとある程度まとまりがよくなるのでしょう。
ある意味で抑制が効いたというか、エレガンスとかバランスとかいう表現で評価される部分につかがるのだと思います。
これはこれで無難なのですが、あえて欲を言うと、私としてはまだ20代のアメリカの(元々はオランダ出身らしいが)ピアニストにはもっとリスクをとってもらいたいと感じました。
才能は豊かな感じなので、どうせなら思い切り爆発させると楽しそうなのに。自分のリーダー作だと守りに入るんですかね。
ライブで聴いてみたいものです。おそらく、このアルバムの評価もそれなりに高いと思いますが、ライブで弾けた方がおもしろいプレイヤーだと思います。
相当に緊張感のある"When the Heart Emerges Glistening"で堂々たる演奏ができているのですから、もっと高みを目指してもいいと思いますね。
それにしても、やはりアメリカのジャズはよろしい。なぜかヨーロッパのジャズよりも自然に聴くことができるような気がしますね。
自由なんですかね。
↓記事がおもしろかったら、投票していただけるとありがたいです
↓お勧めの本のリストを作りました。
冷たい風のような火を燃やすものたち













