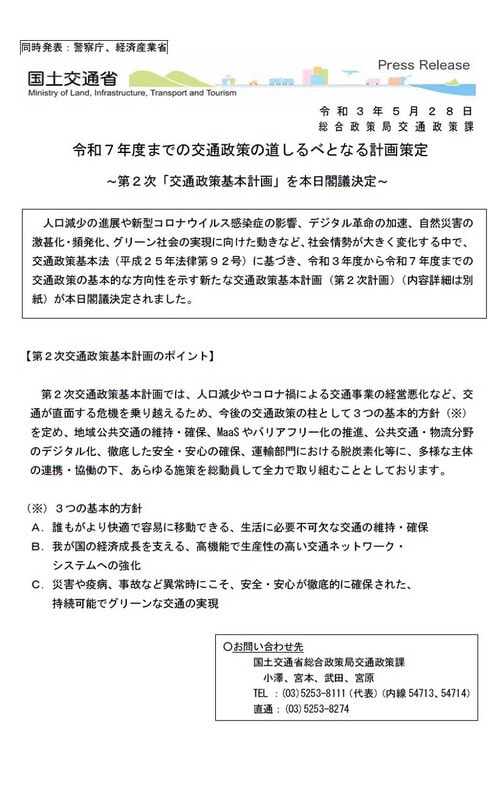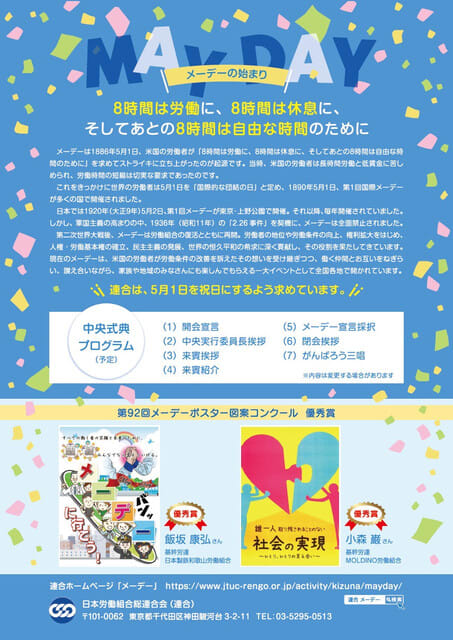第3回労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会ハイヤー・タクシー作業部会(議事録 全文はこちらから)
1 日時 令和3年10月8日(金)13時59分~15時45分
2 場所 労働委員会会館 講堂(東京都港区芝公園1-5-32 7階)
3 出席委員
公益代表委員
東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科教授 寺田一薫
慶應義塾大学法務研究科教授 両角道代
労働者代表委員
日本私鉄労働組合総連合会社会保障対策局長 久松勇治
全国自動車交通労働組合連合会書記長 松永次央
使用者代表委員
西新井相互自動車株式会社代表取締役社長 清水始
昭栄自動車株式会社代表取締役 武居利春
4 議題
(1)改善基準告示の見直しについて
(2)その他
資料
【次第】第3回労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会ハイヤー・タクシー作業部会
【資料1】改善基準告示見直しの方向性について
【参考資料1】改善基準告示見直しについて(参考資料)
【参考資料2】改善基準告示の内容(一覧表)

○両角部会長 どうもありがとうございました。ただいま事務局から見直しの方向性について御提案を頂きましたので、資料1の項目順に労使双方の見解を確認していきたいと思います。それぞれの論点ごとにお聞きしますので、まず冒頭で労側、そして使側の御意見を述べていただいて、それを確認した後に自由に御議論をお願いしたいと思います。なお、本日の会合の目的は、この場で改正案を決定することではありません。本日は、労使がそれぞれの立場から率直な御意見を発言いただいて、年度末の取りまとめに向けて議論を深めることになります。寺田委員や私も公益委員として質問や意見を述べるかもしれませんが、今日の主たる目的は、労使双方の率直な御意見を十分に伺うことであります。皆様、積極的に御議論のほどよろしくお願いいたします。
それでは、早速1つ目の項目として、日勤の1か月間の拘束時間について伺いたいと思います。このことについて事務局案では、1か月の拘束時間、日勤で288時間という提案がありました。この点について御意見を確認したいと思います。それでは、労側から先にお願いいたします。
○久松委員 久松です。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。働き方改革関連法によりまして、罰則付きの時間外労働の上限規制が原則45時間、年360時間。ただし、例外的に720時間というものが決まりましたが、その際に自動車運転者が適用除外となり、最終的に960時間という数字が2024年から施行されることになりました。そのとき、私たちの職場の組合員からは、脳・心臓疾患の労災認定基準が発症前1か月、単月で100時間、2か月ないし6か月で平均80時間を超える場合は、過労死認定ラインになるにもかかわらず、自動車運転者は12か月平均で80時間の働き方をさせるということは、私たちは国から見捨てられたのか、見殺しにされるのかというような、非常に憤った怒りの声がたくさん私どものほうにも寄せられております。その点を踏まえた上で、今回事務局から提示された日勤の1か月の拘束時間というのは、173時間の1か月の所定内労働に22時間の休憩時間を載せた195時間に、93時間までの時間外労働を認めるというものですので、2か月ないし6か月の80時間を更に上回る93時間を上限とするような数字ですので、到底承服できるものではないと思っています。以上です。

○両角部会長 ありがとうございます。それでは、この点について自由に御議論いただきたいと思います。御発言がある方は、挙手をお願いします。久松委員。
○久松委員 武居委員の御主張も理解できるところではあります。ただし、1か月の拘束時間で288時間でありましても、例えば年間的な考え方とか、例えば月少なくとも80時間を考慮した一定の数字、それが年間の上限とか何らかのところにその数字がきちんと入るような考え方は必要ではないかと思います。
○両角部会長 今、松永委員、久松委員がおっしゃられた趣旨を確認したいと思います。月の上限が288時間であるとしても、それとは別に、例えば年間の上限があって、12か月全部が288時間まで認められるわけではないような形であれば考えることができる、そういう趣旨の御意見ですか。
○久松委員 そのとおりで、柔軟に考えていきたいと思っています。ただし、タクシーの日勤の年間の拘束時間、今最大で3,588時間ですから、288時間ということは、3,456時間では132時間の短縮しかできていないということ。あと貨物とバスの議論がどうなっていくか、まだよく分かりませんが、それでも突出したものになるのではないかという懸念も持っているということも、よろしくお願いしたいと思います。
○両角部会長 ほかになければ、続いて隔勤の1か月の拘束時間について御意見を伺いたいと思います。事務局からの提案は、現行維持で適切な運用を促すということです。この点についての御意見はいかがですか。まず労側からお願いします。
○久松委員 次の項目になりますが、拘束時間、休息期間についても隔勤は現状維持ということで、事務局から数字を示されております。この3つが密接に絡まってくる話かと思いますので、次の項目のときに隔勤については議論させていただきたいと思います。
○両角部会長 これは非常に重要な点かと思いますので、積極的に御議論いただければと思います。どちらからでも結構です。
○久松委員 今回、2024年施行の改善基準告示の見直しの議論をしています。前回からの見直しのスパンを考えていきますと、相当先までこれが波及していく基準になっていくかと思います。法律のほうでも、勤務間インターバルが努力規定になっておりまして、以前も発言しましたが、助成金のところでは9時間から11時間未満についてと、11時間から、それぞれ助成金が出ますが、11時間以上の場合は満額の助成金が出るということで、今後の社会の動向として、そういった11時間という数字が基準となって労災認定基準も含めてされていくのだろうと思いますと、今回の改善基準告示の改正については、そこもきちんと抑えた上で結論を出していくべきだと思います。松永委員からもありましたが、一定繁忙期などの対応もあるということで、例外を作るという点ですが、睡眠時間がどうしても短い状態で働くということが、利用者の安全も含めて考えていきますと、やはり重要な観点であるということで、ある一定制限をかけた上での特例も含めて、9時間という数字は妥当ではないか。3回は多い感じもするのですが、9時間という数字は私は妥当だと思っております。
○久松委員 先ほど言い忘れたので。清水委員が先ほど地方部においては16時間の日勤拘束でやっているところが多いということでしたが、確かにそうですが、16時間拘束でダイヤを組んでいるところについては、大体2勤1休なのです。2日勤務して1日休日、2日勤務して1日休日で公休日というサイクルで回しているところが多いので、ベタで日勤22日働いたら月の拘束時間は絶対に突き抜けてしまいますので、そういうわけにはいきませんので。大体そういう勤務シフトが多いと思いますので、少し趣旨が違う点もあるので押さえておいていただきたいと思います。
○久松委員 2日乗って1日休みというのは、2台の車を3人で回すというイメージなのです。今日乗って、同じ車を1人の人が乗って、もう1台の車を同じ人が乗って、空いた日が2日出ますので、もう一人の人が乗ったらちょうどうまく車が100%動くという形なのです。これは運転手が充足していた時代では、地方では主流の勤務体系だと私は覚えているのですが、今は運転手が足りないので、ほぼほぼ日勤に寄った勤務体系になっているところが多いのです。私も地方で聞きましたが、16時間あれば使い勝手がいいというイメージの声はよく聞きますが、実際、今、16時間働かせているかと言ったら、大分減っていると私は理解しています。
○久松委員 今、松永委員がおっしゃったとおりで、少なくとも休息期間については、24時間に改善してほしいという考え方です。今、隔日勤務の拘束時間については、年間で合計しても3,144時間ということで、他の業種、他の勤務体系と比べても相当程度短いということがありまして、過酷という点に十分重視した議論をお願いしたいと思います。したがいまして、今、実態を見ても2暦日の拘束時間の21時間、1か月の拘束時間262時間について、時間いっぱいに仕事をしているような実態は、かなりかけ離れた実態で仕事をしているところですので、ここは現状どおりでも一定の理解が得られるかと思いますが、やはり休息期間についてはこだわりたいと思います。
○久松委員 武居委員がおっしゃっていることもそうですが、実際、2暦日の48時間の中で、拘束時間は21時間でいいではないですかと申しておりますから、引けば本来では27時間あるから27時間休息期間にしてと言いたいのですが、そこはある程度バッファの部分も必要なのではないかと思いまして24時間。タクシーは隔日勤務で乗れば、1日乗ったら次の日24時間のお休みを保障していると。これは求人にとっては良いアピールになるのではないかと思います。その辺は考えていただけたらいいと思います。
先ほどから松永委員も私も触れていませんでしたが、年6回労使協定がある場合について、270時間までの延長を廃止しろというところまでは言うつもりはありません。やはり反感もありますし、利用者の利便性の問題もありますので、これについては維持されてもいいのではないかと思っています。
○久松委員 恐らく、隔日勤務のシフトで、例えば月水金で非番公休という勤務を組んだときに、1勤務目は6時出勤、2勤務目は8時出勤、3勤務目は10時出勤という勤務を組んでいて、3勤務終わって、次はまた月曜に戻りますから、そのときに24時間の休日とプラス休息期間を乗せたときに、次は6時の出勤にもしかしたら影響するかもしれない。そういう変則的な勤務を組んでいる場合、休息期間によって、公休明けの1勤務目に影響があるかもしれないと思います。ただし、24時間ではほぼ大丈夫だろうとは思っています。

○久松委員 車庫待ちに関して、松永委員とは少し考え方が違うのかもしれませんが、私どもも所属の組合で、明らかに車庫待ちの営業をしているようなところで、これも事業者の協力を得ましてヒアリングをしたところ、車庫待ち特例を使っている事例がないと、原則の範囲内で十分仕事ができていると、そこまでお客さんもないということで、やっているという方向でお聞きしています。ですので、私はこの際、この車庫待ちの特例を廃止したらいかがかと思いますので、その意見表明をさせていただきます。
私の出身が阪急タクシーというところなのですが、大阪の私鉄で、京都・大阪・兵庫の沿線営業をやっている阪急電鉄の駅の車庫待ちの営業が主体です。27通達ができました昭和55年なのですが、それまではそれぞれの駅のタクシー乗場の車庫には、休憩所と仮眠施設を全部設置して、1人の方が週に1回は必ず宿直勤務をして、早朝のお客さん対応に当たっていたということをやっていたのですが、私のところの阪急タクシーの沿線では、当時5つの営業区域、営業エリアがありました。全ての地域に人口30万人以上の自治体を含むということで、当時は大阪の労働局とも何度も相談したのですが、車庫待ち特例の対象にはならないということで、勤務体系を変更して宿直勤務を廃止して今に至っているというところがあります。
そういう典型的な、私の出身のところでもそうですし、特にもっと地方に行けば、それほどお客様のニーズがないという点から見ても、これだけの上限時間を延長する必要はないと思いますので、車庫待ち等については、この際に廃止したらどうかと思います。
○久松委員 いえ、駅待ちも含めてです。
○両角部会長 寺田委員、お願いします。
○寺田委員 私は久松委員が特に主張されている、車庫待ち特例自体の廃止というのは、「あり」のように思います。特にその実態があまりないという割には追加の時間が非常に長いので、設ける場合は慎重なほうがいいかなと思っています。
次に質問ですけれども、資料の7ページの一番下のところに日勤も隔勤もプラス4時間というものがあります。「4時間の仮眠」というのですか。ここの部分もなくしてしまうということなのですよね。恐らくバスなどの分割特例みたいな意味もあるのだと思うのですけれども、そこも含めて全くなくしてしまうということを御提案というか、そのようにとってよろしいのでしょうか。
○久松委員 この4時間以上の仮眠付与というのは条件なのです。4時間以上の仮眠付与を確保しないと、車庫待ち特例に該当しないという条件です。
○寺田委員 だから当然なくなってしまうというか、全部なくしてしまうということですか。
○久松委員 車庫待ちの実態はあるのですが、実際にここまでの上限をいっぱいいっぱい使ってやっているところはないので、もうこの車庫待ちの特例というものをなくしたらいいのではないかということです。
一方で、この車庫待ちの特例を残すということで、時間をどうするかという議論をしていくとすれば、私は以前からも言っていますが、車庫待ちの定義については、しっかりと明確なものにしていただきたい。参考資料1の16ページに、前回の作業部会で提示された内容でありますが、「車庫待ち等の自動車運転者」とは、ということで記載されています。この下の○の一般的には人口30万人以上うんぬんというところ、ここが少し曖昧なので、ここの30万が妥当かどうかは別として、特にこの3行の文章をもう少し明確に、うちはそうだ、そうじゃないということが明確に判断できるものにしておけば、この車庫待ち特例を残すとすれば、必要なことではないかなと思います。

○両角部会長 はい、ありがとうございました。それではハイヤーについてはよろしいでしょうか。それでは最後に、特例その他について伺いたいと思います。特例その他のところでは、まず休日労働について、事務局案は2週間に1回という現行を維持。それから新しく加えることとして、予期しない事象による遅延について、例外的な取扱いを認める。それから適用除外業務、大規模災害等に伴う緊急輸送など、適用除外業務について、タクシーも対象に含めるという御提案がありました。
これらについて3つ内容がありますけれども、これらについて御意見をお願いします。では、まず労側から。
○久松委員 久松です。休日労働2週間に1回現行どおり、これは是非このとおりでお願いしたいと思います。新たに出されました予期しない事象による遅延というところでは、客観的な記録が認められる場合ということで、濫用防止をするためにこういった条項を入れることは必要であろうと思います。
ただし休息期間は拘束時間の延長に伴い短縮というのは、これはないでしょうと思っています。例えば11時間という休息期間になるかどうか分かりませんけれども、道路の封鎖が11時間続いた時に、やっと入庫したらまた次の仕事に行けという話になりかねないので、この休息期間は拘束時間の延長に伴い、当然スライドするものであるべきだと思いますので、ここは削除すべきだと思います。また適用除外業務については異存はありません。
○両角部会長 ありがとうございました。では使側お願いします。
○寺田委員 途中で引き返すとか、そういう意味ですか。ならば関係ないような気がしますが。
○久松委員 客を乗せてフェリーで離島まで送って、帰りにフェリーで帰ってこようと思ったら、そのフェリーが悪天候とかで出航しなかった、向こうの島で足止めを食らうというようなことがないこともないです。
○両角部会長 ありがとうございました。この特例その他について、ほかに御意見は。
○久松委員 すみません、今回の事務局案には入っていないのですが、以前から意見として言わせてもらっている、改善基準告示にあります累進歩合制度の禁止について、定義を再度検討してもらいたいという点については、次回以降また取り上げていただきたいと思っています。累進歩合制度という賃金体系については、長時間労働やスピード違反を極端に誘発するおそれがあり、交通事故の発生も懸念されることから、改善基準告示では廃止すべきとされています。
更に2014年に改正タクシー適正化活性化特別措置法というものができた際に、衆議院参議院両院において、附帯決議でこの累進歩合の廃止について再度触れられたということもありまして、厚生労働省からは2014年1月24日付けで、廃止に係る指導等の徹底について通達が出されています。また1月27日には国土交通省からも廃止の徹底についての通達が出されているということがあります。
この間何が起こっているかと言いますと、月例賃金における累進歩合制度については厚生労働省等の指導などによって、ずいぶん改善がなされてきたと思うのですが、それを臨時給、半年に1回支払うボーナスであったり臨時給であったり、4か月に1回かもしれませんが、そちらのほうで累進歩合制度を導入して、結果的にスピード違反ですとか長時間労働を誘発するような現状が起こっています。
さらに、年次有給休暇の5日間の取得義務がなされたのですが、この臨時給、ボーナスなどにおける累進歩合がネックになって、年次有給休暇の消化がなかなか進まないという現状がありますので、改善基準告示の今回の見直しの際には再度累進歩合制度の定義について、議論をしていきたいと思いますので、できましたら事務局におかれましては、次回一定の考え方を出していただければと思います。
○両角部会長 はい、ありがとうございます。それではほかに、ここの部分について御意見ありますでしょうか。
○久松委員 一応、改善基準告示の中の項目の1つということでもありますので、是非やるのであればこの場でしかないと思いますし、少なくとも考え方を出せということではなくて、累進歩合制度というものが改善基準告示でどうされていて、実際に現場の監督の場所ではどういった指導・摘発とか、その実態の資料を次回御掲示いただいて、公益委員の先生方も含めて一度見つめてほしい。まずは見つめてほしいと思います。それ以降また議論が必要でしたら、意見したいと思います。よろしくお願いします。お任せします。
○監督課長 どういったものが出せるかは検討させていただきます。現状は通達に基づいて累進歩合の廃止を指導していますので、そうした内容や現状についてお出しすることも含めて検討させていただければと思います。ありがとうございます。
○両角部会長 それではよろしいでしょうか、ほかに御意見は何かありますか。積極的に御議論いただいてありがとうございました。ちょっと時刻は早いですが、本日はここまでとさせていただきます。次回の作業部会では、本日の御意見を踏まえて、更に議論を深めたいと思います。最後に次回の日程等について、事務局からお願いします。…(議事録 全文)





















![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2233fbe2.1a4da6c3.2233fbe3.fd69b9ba/?me_id=1247055&item_id=10067069&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdlx-girl%2Fcabinet%2Fimages14%2Fzzlpjp.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/18bfa755.bb912127.18bfa756.dcb862a9/?me_id=1224379&item_id=10002101&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdarkangel%2Fcabinet%2F2021_newitem%2F202110%2F2792-1104-09.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)