
新幹線総合車両センター(利府町)に静態保存されている車両を見てきました。
7月24日に基地祭りでE5系が一般公開されますが、仕事を休めない為ズ~ッと気になっていた
展示車両を見てきました。
今回はその中からSLをご紹介します。
D51-1108号 デゴイチ

D51-1108号の経歴
製造年月日: 昭和19年7月
主な性能: 重 さー125t 馬 力ー1280PS 長 さー19,7m
最高速度ー85km/H 車直経ー1,4m
新製後新潟鉄道局新津機関区に配置され、羽越本線、信越本線を走り、昭和25年10月に秋田鉄道管理局に転配となって奥羽線、羽越本線の主として日本海縦幹線を約20年間で160万キロを走行した。
この形式は全国のあらゆる幹線、亜幹線の貨物列車牽引と勾配線区での旅客列車牽引に活躍した。
日本一顔が広く人気ものでSLの代表的な機関車であり、昭和11年~昭和20年まで1115両が製造された。



四輪駆動こそDたる由縁だ!
東北本線 山王駅~国府多賀城間 2008年9月28日 D51-498です

C11-351号 Cのチョンチョン

製作年月日:昭和21年8月
主な性能: 重 さー68t 馬 力ー610PS 長 さー12.6m
最高速度ー85km/H 車直径ー1.52m
新製後仙台鉄道局仙台機関区に配置され構内入換機として活躍し、昭和36年末に会津若松機関区に転配、10年間構内入換、会津、只見、日中等ローカル線の客車貨車を牽引して会津地方の発展に大きく貢献、約26年間で100万キロを走行した。
この形式は小型SLの代表的な新型タンク機関車で後部の見通しもよく、バック運転が前進と同じ速度で出来た。
小型の割りに力のある機関車で昭和7年~昭和22年まで881両が製造された。




3軸ですね。Cである由縁です。
C11 351 1968.04.28. 会津若松所属 只見線 滝谷 ( 福島県 河沼郡 )

C58-365号 シゴハチ

1944年(昭和19年)製造


C58 365 小牛田所属 1972.08.18. 仙台駅百周年記念展示

みんな現役を引退しましたが、その存在感は堂々たるものです。ゆっくり休んで下さい。
7月24日に基地祭りでE5系が一般公開されますが、仕事を休めない為ズ~ッと気になっていた
展示車両を見てきました。
今回はその中からSLをご紹介します。
D51-1108号 デゴイチ

D51-1108号の経歴
製造年月日: 昭和19年7月
主な性能: 重 さー125t 馬 力ー1280PS 長 さー19,7m
最高速度ー85km/H 車直経ー1,4m
新製後新潟鉄道局新津機関区に配置され、羽越本線、信越本線を走り、昭和25年10月に秋田鉄道管理局に転配となって奥羽線、羽越本線の主として日本海縦幹線を約20年間で160万キロを走行した。
この形式は全国のあらゆる幹線、亜幹線の貨物列車牽引と勾配線区での旅客列車牽引に活躍した。
日本一顔が広く人気ものでSLの代表的な機関車であり、昭和11年~昭和20年まで1115両が製造された。



四輪駆動こそDたる由縁だ!
東北本線 山王駅~国府多賀城間 2008年9月28日 D51-498です

C11-351号 Cのチョンチョン

製作年月日:昭和21年8月
主な性能: 重 さー68t 馬 力ー610PS 長 さー12.6m
最高速度ー85km/H 車直径ー1.52m
新製後仙台鉄道局仙台機関区に配置され構内入換機として活躍し、昭和36年末に会津若松機関区に転配、10年間構内入換、会津、只見、日中等ローカル線の客車貨車を牽引して会津地方の発展に大きく貢献、約26年間で100万キロを走行した。
この形式は小型SLの代表的な新型タンク機関車で後部の見通しもよく、バック運転が前進と同じ速度で出来た。
小型の割りに力のある機関車で昭和7年~昭和22年まで881両が製造された。




3軸ですね。Cである由縁です。
C11 351 1968.04.28. 会津若松所属 只見線 滝谷 ( 福島県 河沼郡 )

C58-365号 シゴハチ

1944年(昭和19年)製造


C58 365 小牛田所属 1972.08.18. 仙台駅百周年記念展示

みんな現役を引退しましたが、その存在感は堂々たるものです。ゆっくり休んで下さい。










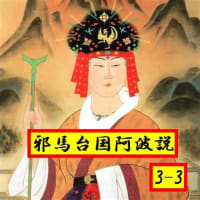

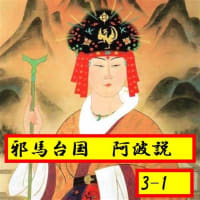


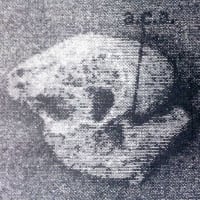











電車のゆっくり旅なので
車両に興味を持つことで
旅行の楽しさが深まります
これもひーさんブログのおかげです
最近は鉄道の写真もやって見ようかと考えています。
今の無機質な電車とは違った武骨な姿、味わいがありますね。
見とれそうです。
ドームがカマボコのような形状で横がストンと切れています。
東北本線を力走している写真のドームみたいに丸っこい形状にする余裕のない時代でした。
高崎水上間の動態保存機があちこちに出張して運転されています。
C11は動態保存されている形式で1番多いですね。あの大井川鉄道の主力のカマです。
バック運転に加え、軸重が軽いためローカル線にも入れ、重宝な存在でした。
C58は秩父鉄道で動態保存され首都圏の人間には馴染み深い形式です。
どの保存機にも屋根とか覆いがないため、かなり傷んでいるのが痛々しいです。
子供の頃は、これがほとんどだったから~
利府を東北線が走っていたころ、だいぶ煤でな悩まされたのでしたね~
御召し列車を牽引するとなると、
電気機関車やディーゼル機関車と違って
磨き方が半端でなかったそうです。
傷み方といえば、西公園のC60(C61)だったでしょうか)が残念でなりません。
宮城県では陸羽東線沿いの駅(岩出山よりは小牛田寄り)と岩出山の城跡(車道で登る途中です)に
C58型が静態保存してあります。
クロンシュタットさんのコメントにもありましたが、
C11型はバック運転がしやすい設計になっています。
短い線区でよく使われていましたね。
宮城県では石巻線で走っていました。
C58型は
地方交通線で客車でも貨物車でも牽けるように設計された万能機関車と聞いています。
東北地方では陸羽東線と同西線、八戸線などで走っていたはずです。
私が意識して見たのは陸羽東線のC58型と石巻線のC11型。
多分、宮城県内で蒸気機関車が就役していた最後の頃だと思います。
D51型といえば、やはり御堂・奥中山間の貨物特急の三重連ですね。
写真でしか見たことがありませんが・・・
今回の写真のD51が戦時型だというのは頷けます。
クロンシュタットさんんが指摘しなければ、
カマの形は見落してしまったと思います。
戦時中であればなおのこと、
工事期間の短縮と効率化が求められます(量産化ということも含めて)。
海で言えば海軍の松型駆逐艦や戦時量産型の海防艦、戦時標準型貨物船も
直線的なデザインが目立ちます。
工数の削減と工程の短縮、量産化が目的だったと思います(米国のリバティ型貨物船も)。
蒸気機関車ではD52の戦時型ですが、
デフレクターや炭水車の石炭搭載部分が木製だったと聞いております。
これは明らかに金属の不足によるものですね。
幹線が真っ先に電化され、
地方交通線では使えぬ大型機がいち早く引退せざるを得なくなったことは何とも皮肉なこと。
残念でなりません。
この間気づいたのですが、小牛田駅と郡山駅の転車台は健在のようです。
陸羽東線や磐越西線で今なおテンダ型の蒸気機関車が運行できる所以ですね。
只見線のSLとか臨時列車など撮ろうかと思いまして。
以前の記事に子供時に列車内で撮った写真をアップしてあります。
SLの記憶がありますよ。
利府街道を通ると線路の名残がわかりますよね。
その本の中に…西古川にC58の表記がありました。
また、郡山総合車両センター会津若松派出所の転車台の写真もありましたよ。
デゴイチの三重連…奥中山の勾配も写真に取りたいと思っています。
次回は、続きのディーゼルアップします。