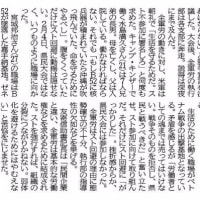80歳近いおじいさんが、ひとりで水田を耕している。その水田は、おじいさんのおじいさんが、子孫たちが食べるものに困らぬよう、狭く、急な斜面ばかりの島で30年もかけて石を積み上げて作った棚田だ。子どもたちは都会へ出てゆき、ひとり残されたおじいさんが、それでも米を作るのは、子どもや孫に食べさせるためだ。息が止まるほど美しい空や海に囲まれた水田の傍らでおじいさんが話している。次の代で田んぼはなくなるだろう。耕す者などいなくなるから。
「田んぼも、もとの原野へ還(かえ)っていく」といって、おじいさんは微笑(ほほえ)む。そして、曲がった腰を伸ばし、立ち上がる。新しい苗代を作るために。
山口県上関町の原発建設に30年近く反対し続けている祝島(いわいしま)の人たちを描いた映画「祝(ほうり)の島」(〈1〉)の一シーンだ。
人口500人ほどの小さな島には、ほとんど老人しか残っていない。その多くは一人暮らしの孤老だ。彼らは、なぜ「戦う」のか。彼らが何百年も受け継いできた「善きもの」を、後の世代に残すために、だ。では、その「善きもの」とはなんだろうか。汚染されない海、美しい自然だろうか。そうかもしれない。
だが、その「善きもの」を受け取るべき若者たちが、もう島には戻って来ないことを、彼らは知っているのである。
四国電力伊方原発の出力調整実験への反対闘争について記した中島眞一郎(〈2〉)、新潟県巻町(当時)の原発建設の是非をめぐる住民投票について記した成元哲(〈3〉)、そして、祝島について報告した姜誠(〈4〉)。都会から遠く離れた場所での、孤独な「戦い」を記述した彼らの報告を読みながら、ぼくの脳裏には、映画で見た祝島の風景が蘇(よみがえ)った。
受け取る者などいなくても、彼らは贈り続ける。「戦い」を通じて立ち現れる、大地に根を下ろしたその姿こそが、ひとりで「原野へ還っていく」老人たちから、都会へ去っていった子どもたちへの最後の贈りものであることに、ぼくたちは気づくのである。
おそらく、世界中に「祝島」はあって、そこから、「若者」たちは「外」へ出てゆくのだ。では、「外」へ出ていった「若者」たちは、どうなったのか。
「こんなデモは今までに見たことがない」
9月18日夜、米ウォール街から北に200メートルばかり離れた広場に出向いた津山恵子は、まずこんな風に書いた(〈5〉)。
「参加者のほとんどは、幼な顔の10代後半から20代前半。団塊の世代や、1960~70年代の反戦運動を経験した世代など、『戦争反対』『自治体予算削減反対』『人種差別反対』などのデモで毎度おなじみの顔は全くない。いや、彼らは今までデモに参加したことすらないのだ」
世界を震撼(しんかん)させることになる「Occupy Wall Street」デモが始まった翌日の光景だ。いったい、彼らは、なんのためにどこから現れたのか。
肥田美佐子(〈6〉)は、豊かな社会の中で劇的に広がる「格差」が、彼らを、まったく新しいやり方で、街頭に繰り出させたと報告し、さらに、瀧口範子はリポート(〈7〉)にこう書いている。
「自然発生的に広がっていったOccupy Wall Streetは、まるで新しい共和国のような様相を呈している。最初は失業者やホームレスたちの集まりと見られていたが、そのうち若者や学生も加わり、整然と組織化されていった。組織といっても、弱肉強食のウォール街の流儀とは正反対のもの。話し合いを通じて、合意形成を図り、それを実践していくというものだ」
10月6日。『ショック・ドクトリン』の著者で、反グローバリズムの代表的論客、ナオミ・クラインは、彼らが占拠する広場で演説した。そこで、彼女は、一つの「場所」に腰を下ろした、この運動の本質を簡潔に定義している(〈8〉)。
「あなたたちが居続けるその間だけ、あなたたちは根をのばすことができるのです……あまりにも多くの運動が美しい花々のように咲き、すぐに死に絶えていくのが情報化時代の現実です。なぜなら、それらは土地に根をはっていないからです」
かけ離れた外見にかかわらず、「祝の島」のおじいさんとニューヨークの街頭の若者に共通するものがある。「一つの場所に根を張ること」だ。そして、そんな空間にだけ、なにかの目的のためではなく、それに参加すること自体が一つの目的でもあるような運動が生まれるのである。
上野千鶴子は大著『ケアの社会学』で、ケアの対象となる様々な「弱者」たちの運命こそ、来るべき社会が抱える最大の問題であるとし、「共助」の思想の必要性を訴えた(〈9〉)。
「市場は全域的ではなく、家族は万全ではなく、国家には限界がある」
背負いきれなくなった市場や家族や国家から、高齢者や障害者を筆頭とした「弱者」たちは、ひとりで放り出される。彼らが人間として生きていける社会は、個人を基礎としたまったく新しい共同性の領域だろう、と上野はいう。
それは可能なのか。「希望を持ってよい」と上野はいう。震災の中で、人びとは支え合い、分かちあったではないか。
その共同性への萌芽(ほうが)を、ぼくは、「祝の島」とニューヨークの路上に感じた。ひとごとではない。やがて、ぼくたちもみな老いて「弱者」になるのだから。
---------
たかはし・げんいちろう 1951年生まれ。明治学院大学教授。新作小説『恋する原発』の単行本が近日発売予定。写真は鈴木好之撮影。
--------
〈1〉纐纈(はなぶさ)あや監督(2010年)
〈2〉「いかたの闘いと反原発ニューウェーブの論理」(現代思想10月号)
〈3〉「巻原発住民投票運動の予言」(同)
〈4〉「マイノリティと反原発」(すばる11月号=連載中)
〈5〉「立ち上がった『沈黙の世代』の若者」(http://jp.wsj.com/US/node_315373)
〈6〉「若者の『オープンソース』革命は世界を変えるか」(http://jp.wsj.com/US/Economy/node_320632/?tid=wallstreet)
〈7〉「全米に広がる格差是正デモの驚くべき組織力」(http://diamond.jp/articles/-/14428)
〈8〉「aliquis ex vobis」掲載の邦訳から(http://beneverba.exblog.jp/15811070/)
〈9〉8月刊行
〈ネットからの引用は執筆時点のものです。一定時間後、読めなくなる場合があります〉
*2011.10.27 朝刊
-----------------------
〈あすを探る〉公共事業と原発、日本の縮図/小熊英二(慶応大学教授)
「138億円かけて街を壊すだけ」といわれる公共事業がある。東京都世田谷区の下北沢駅周辺の再開発だ。
下北沢は演劇と音楽の街として知られ、東京観光の名所でもある。鉄道交通が至便だが、大きな道路が駅前周辺に通っておらず、いつも歩行者天国状態が保たれ、身体障害者が駅前周辺を電動車イスで自由に散歩している。道路幅が狭く大きなビルが建たないため、古着屋や雑貨店など個性的で小さな店が集まっていることが、この街の特色と活力源だ。
この街の中心に大規模道路を通す計画が決定されたのは2003年である。もっとも栄えている小売店密集地を幅26メートルの大型道路に変え、街を分断する無謀な計画に、反対と行政訴訟がおきた。その過程で、これがいかにずさんな計画であるかが明らかになった。
開発計画の原型は、東京が焼け野原だった1946年のものである。この65年前の計画が、小田急線の複々線化と地下化に伴う駅舎改築を契機に、抱きあわせで浮上したのだ。しかも1期工事で駅周辺の商店地区を道路にしても、計画通り幹線道路まで連結するのに、2期・3期工事で住宅密集地をさらに大規模買収するのに約200億円かかるとの試算もあり、全くめどが立たない。要するに、特色と活力ある商店地区を100億円かけ立ち退かせ、巨大な袋小路状の更地にするだけの事業だ。
行政側は、駅前に消防車両が入れないことなどを道路開発理由に挙げている。だがそれは、線路の地下化後、線路跡地だけを道路にすれば解決する。しかも03年以前は区も歩行者優先ゾーンにする計画だったこと、26メートルという道路幅は線路との立体交差を前提として拡幅した旧計画が地下化決定後も変更されていないだけであることなど、多くの矛盾が行政訴訟の場で問われ、行政側は回答に窮した。区によるアンケートでも、地域住民の7割が「歩行者中心の駅前広場」を望むと回答している。
まさに「止まらない無駄な公共事業」の典型だが、地権者との交渉は着手段階で、立ち退き料と補助金なしには住民がやっていけないといった末期的状態には至っていない。また4月の選挙で、大型公共事業見直しを掲げた区長が当選し、再検討のための円卓会議を提案している。しかし少数与党であるため、区長の力だけでは動きがとれない。
こうした風景は日本のどこでも見慣れたものだ。ダム、道路、そして原発。その弊害を多くの人が感じたからこそ、「コンクリートから人へ」を掲げた民主党に政権を託した。脱原発の世論とデモが高まっているのも、放射能への恐れもさることながら、原発をめぐる構図が現代日本の諸問題の縮図と認識されたからだ。
だが民主党政権は、そうした期待に応えていない。その一因は民主党の見通しの甘さだが、主な理由は複雑な利権構造や利害調整に足を取られているからだと、多くの人は理解している。この国に生きる人びとは、たとえ財政やマクロ経済やエネルギーの専門知識はなくとも、現代日本の問題の根源がどこにあるかを、日常の生活から肌身にしみて知っている。それを変えてくれると期待した政権が、期待に応えようとしないとき、失望と「支持政党なし」が増加するのは当然ではないか。
下北沢の再開発計画は地域住民でも詳細を知らない人が多いが、計画を知った人に多かった反応は、「なんて無茶な」と、「でもそういう事業は止まったためしがないんだよね」だった。一昔前ならこうした無力感とニヒリズムに身を任せていても、豊かさと安全がいつまでも続いてくれると、多くの人が思っていた。だがもはや、この国にそんな余裕はない。いまならまだ変えられる。私たちはいま、いやおうなく、「あすを探る」ことを求められている。そして「あすを探る」こと、「あすを創る」ことは、じつは誰もが望んでいる、楽しい経験であるはずなのだ。
(おぐま・えいじ 62年生まれ。慶応大学教授・歴史社会学)
ブログ内・関連記事
よろしければ、下のマークをクリックして!

よろしければ、もう一回!

「田んぼも、もとの原野へ還(かえ)っていく」といって、おじいさんは微笑(ほほえ)む。そして、曲がった腰を伸ばし、立ち上がる。新しい苗代を作るために。
山口県上関町の原発建設に30年近く反対し続けている祝島(いわいしま)の人たちを描いた映画「祝(ほうり)の島」(〈1〉)の一シーンだ。
人口500人ほどの小さな島には、ほとんど老人しか残っていない。その多くは一人暮らしの孤老だ。彼らは、なぜ「戦う」のか。彼らが何百年も受け継いできた「善きもの」を、後の世代に残すために、だ。では、その「善きもの」とはなんだろうか。汚染されない海、美しい自然だろうか。そうかもしれない。
だが、その「善きもの」を受け取るべき若者たちが、もう島には戻って来ないことを、彼らは知っているのである。
四国電力伊方原発の出力調整実験への反対闘争について記した中島眞一郎(〈2〉)、新潟県巻町(当時)の原発建設の是非をめぐる住民投票について記した成元哲(〈3〉)、そして、祝島について報告した姜誠(〈4〉)。都会から遠く離れた場所での、孤独な「戦い」を記述した彼らの報告を読みながら、ぼくの脳裏には、映画で見た祝島の風景が蘇(よみがえ)った。
受け取る者などいなくても、彼らは贈り続ける。「戦い」を通じて立ち現れる、大地に根を下ろしたその姿こそが、ひとりで「原野へ還っていく」老人たちから、都会へ去っていった子どもたちへの最後の贈りものであることに、ぼくたちは気づくのである。
おそらく、世界中に「祝島」はあって、そこから、「若者」たちは「外」へ出てゆくのだ。では、「外」へ出ていった「若者」たちは、どうなったのか。
「こんなデモは今までに見たことがない」
9月18日夜、米ウォール街から北に200メートルばかり離れた広場に出向いた津山恵子は、まずこんな風に書いた(〈5〉)。
「参加者のほとんどは、幼な顔の10代後半から20代前半。団塊の世代や、1960~70年代の反戦運動を経験した世代など、『戦争反対』『自治体予算削減反対』『人種差別反対』などのデモで毎度おなじみの顔は全くない。いや、彼らは今までデモに参加したことすらないのだ」
世界を震撼(しんかん)させることになる「Occupy Wall Street」デモが始まった翌日の光景だ。いったい、彼らは、なんのためにどこから現れたのか。
肥田美佐子(〈6〉)は、豊かな社会の中で劇的に広がる「格差」が、彼らを、まったく新しいやり方で、街頭に繰り出させたと報告し、さらに、瀧口範子はリポート(〈7〉)にこう書いている。
「自然発生的に広がっていったOccupy Wall Streetは、まるで新しい共和国のような様相を呈している。最初は失業者やホームレスたちの集まりと見られていたが、そのうち若者や学生も加わり、整然と組織化されていった。組織といっても、弱肉強食のウォール街の流儀とは正反対のもの。話し合いを通じて、合意形成を図り、それを実践していくというものだ」
10月6日。『ショック・ドクトリン』の著者で、反グローバリズムの代表的論客、ナオミ・クラインは、彼らが占拠する広場で演説した。そこで、彼女は、一つの「場所」に腰を下ろした、この運動の本質を簡潔に定義している(〈8〉)。
「あなたたちが居続けるその間だけ、あなたたちは根をのばすことができるのです……あまりにも多くの運動が美しい花々のように咲き、すぐに死に絶えていくのが情報化時代の現実です。なぜなら、それらは土地に根をはっていないからです」
かけ離れた外見にかかわらず、「祝の島」のおじいさんとニューヨークの街頭の若者に共通するものがある。「一つの場所に根を張ること」だ。そして、そんな空間にだけ、なにかの目的のためではなく、それに参加すること自体が一つの目的でもあるような運動が生まれるのである。
上野千鶴子は大著『ケアの社会学』で、ケアの対象となる様々な「弱者」たちの運命こそ、来るべき社会が抱える最大の問題であるとし、「共助」の思想の必要性を訴えた(〈9〉)。
「市場は全域的ではなく、家族は万全ではなく、国家には限界がある」
背負いきれなくなった市場や家族や国家から、高齢者や障害者を筆頭とした「弱者」たちは、ひとりで放り出される。彼らが人間として生きていける社会は、個人を基礎としたまったく新しい共同性の領域だろう、と上野はいう。
それは可能なのか。「希望を持ってよい」と上野はいう。震災の中で、人びとは支え合い、分かちあったではないか。
その共同性への萌芽(ほうが)を、ぼくは、「祝の島」とニューヨークの路上に感じた。ひとごとではない。やがて、ぼくたちもみな老いて「弱者」になるのだから。
---------
たかはし・げんいちろう 1951年生まれ。明治学院大学教授。新作小説『恋する原発』の単行本が近日発売予定。写真は鈴木好之撮影。
--------
〈1〉纐纈(はなぶさ)あや監督(2010年)
〈2〉「いかたの闘いと反原発ニューウェーブの論理」(現代思想10月号)
〈3〉「巻原発住民投票運動の予言」(同)
〈4〉「マイノリティと反原発」(すばる11月号=連載中)
〈5〉「立ち上がった『沈黙の世代』の若者」(http://jp.wsj.com/US/node_315373)
〈6〉「若者の『オープンソース』革命は世界を変えるか」(http://jp.wsj.com/US/Economy/node_320632/?tid=wallstreet)
〈7〉「全米に広がる格差是正デモの驚くべき組織力」(http://diamond.jp/articles/-/14428)
〈8〉「aliquis ex vobis」掲載の邦訳から(http://beneverba.exblog.jp/15811070/)
〈9〉8月刊行
〈ネットからの引用は執筆時点のものです。一定時間後、読めなくなる場合があります〉
*2011.10.27 朝刊
-----------------------
〈あすを探る〉公共事業と原発、日本の縮図/小熊英二(慶応大学教授)
「138億円かけて街を壊すだけ」といわれる公共事業がある。東京都世田谷区の下北沢駅周辺の再開発だ。
下北沢は演劇と音楽の街として知られ、東京観光の名所でもある。鉄道交通が至便だが、大きな道路が駅前周辺に通っておらず、いつも歩行者天国状態が保たれ、身体障害者が駅前周辺を電動車イスで自由に散歩している。道路幅が狭く大きなビルが建たないため、古着屋や雑貨店など個性的で小さな店が集まっていることが、この街の特色と活力源だ。
この街の中心に大規模道路を通す計画が決定されたのは2003年である。もっとも栄えている小売店密集地を幅26メートルの大型道路に変え、街を分断する無謀な計画に、反対と行政訴訟がおきた。その過程で、これがいかにずさんな計画であるかが明らかになった。
開発計画の原型は、東京が焼け野原だった1946年のものである。この65年前の計画が、小田急線の複々線化と地下化に伴う駅舎改築を契機に、抱きあわせで浮上したのだ。しかも1期工事で駅周辺の商店地区を道路にしても、計画通り幹線道路まで連結するのに、2期・3期工事で住宅密集地をさらに大規模買収するのに約200億円かかるとの試算もあり、全くめどが立たない。要するに、特色と活力ある商店地区を100億円かけ立ち退かせ、巨大な袋小路状の更地にするだけの事業だ。
行政側は、駅前に消防車両が入れないことなどを道路開発理由に挙げている。だがそれは、線路の地下化後、線路跡地だけを道路にすれば解決する。しかも03年以前は区も歩行者優先ゾーンにする計画だったこと、26メートルという道路幅は線路との立体交差を前提として拡幅した旧計画が地下化決定後も変更されていないだけであることなど、多くの矛盾が行政訴訟の場で問われ、行政側は回答に窮した。区によるアンケートでも、地域住民の7割が「歩行者中心の駅前広場」を望むと回答している。
まさに「止まらない無駄な公共事業」の典型だが、地権者との交渉は着手段階で、立ち退き料と補助金なしには住民がやっていけないといった末期的状態には至っていない。また4月の選挙で、大型公共事業見直しを掲げた区長が当選し、再検討のための円卓会議を提案している。しかし少数与党であるため、区長の力だけでは動きがとれない。
こうした風景は日本のどこでも見慣れたものだ。ダム、道路、そして原発。その弊害を多くの人が感じたからこそ、「コンクリートから人へ」を掲げた民主党に政権を託した。脱原発の世論とデモが高まっているのも、放射能への恐れもさることながら、原発をめぐる構図が現代日本の諸問題の縮図と認識されたからだ。
だが民主党政権は、そうした期待に応えていない。その一因は民主党の見通しの甘さだが、主な理由は複雑な利権構造や利害調整に足を取られているからだと、多くの人は理解している。この国に生きる人びとは、たとえ財政やマクロ経済やエネルギーの専門知識はなくとも、現代日本の問題の根源がどこにあるかを、日常の生活から肌身にしみて知っている。それを変えてくれると期待した政権が、期待に応えようとしないとき、失望と「支持政党なし」が増加するのは当然ではないか。
下北沢の再開発計画は地域住民でも詳細を知らない人が多いが、計画を知った人に多かった反応は、「なんて無茶な」と、「でもそういう事業は止まったためしがないんだよね」だった。一昔前ならこうした無力感とニヒリズムに身を任せていても、豊かさと安全がいつまでも続いてくれると、多くの人が思っていた。だがもはや、この国にそんな余裕はない。いまならまだ変えられる。私たちはいま、いやおうなく、「あすを探る」ことを求められている。そして「あすを探る」こと、「あすを創る」ことは、じつは誰もが望んでいる、楽しい経験であるはずなのだ。
(おぐま・えいじ 62年生まれ。慶応大学教授・歴史社会学)
ブログ内・関連記事
よろしければ、下のマークをクリックして!
よろしければ、もう一回!