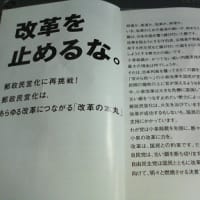「夫は外、妻は家庭」に反対、半数超える・内閣府世論調査
内閣府が29日発表した男女共同参画社会に関する世論調査によると、「夫は外
で働き、妻は家庭を守るべきだ」との考えに反対する人の割合が52.1%と1992
年の調査開始以来、初めて半数を超えた。賛成は44.8%。内閣府では「男女の
役割分担を固定的に考える傾向に変化がみられる」(男女共同参画局)と分析
している。
ただ現実の家事分担では、妻の仕事として「食事の支度」を挙げたのが
85.6%、「掃除」も75.6%と高い。仕事と家庭のどちらを優先するかでも「仕
事を優先する」は女性の17.3%に対し、男性は40.2%。男女の仕事と家庭に対
する考え方には依然開きがある。
一方、結婚観や家庭観では「結婚しても必ずしも子どもを持つ必要はない」と
の考えに反対の人が59.4%と2004年の前回調査に比べ8.1ポイント上昇。「結
婚しても相手に満足できないときは離婚すればよい」との考えに反対の人も
47.5%と同7.4ポイント上昇し、賛成の46.5%(同4.6ポイント低下)を逆転し
た。
えー、個人的に偏った考え方を持っているようなので、参考にならないと思いますが。
この「家庭を守る」ってなんでしょう。
こういった調査で、必ず項目に入ってくる「家庭を守る」という文言。
この仕事だ、家庭だという「くくり」に、
夫婦間の、人間としての関係が、よく見えてきません。
もう極端なことを言えば、人間観関係は、ある意味大なり小なりの
利害関係で成立していると考えております。
もちろん、純粋な気持ち、例えば好き、愛しているなど、
こういう普遍的な心を否定するつもりはさらさらありません。
ただ、生きていく中で、それぞれのタイミングで、
どうあがいても、大なり小なりの「ミッション」をこなしていくのが人生です。
自分で見つける方もいますし、そして、結果を出せなくて、魂消るような一瞬を
迎える、とほほな私みたいな人間もおりますし、
もちろん、やむなく、降りかかってくる案件を処理しなければならない事も
当然ありますし。
こういうの、一言で言うならば、たった一人では「成立」しない。
全てが、あらゆる人間関係性の中で、起こりうるものだ。
因果関係を含めて。
そういうものだと、理解しております。
で、そういう中で、人それぞれでしょうが、自分は、
人生と言うミッションをこなす上で、パートナーが必要だし、
後出しかもしれないが、
パートナーの存在を、日々、この上なくありがたいものだと、痛感しているわけです。
手近な話で申し訳ないですが、
子を育てるということも、生き物が抱えるミッションですし、
望む、望まないは別に、そういう価値観をここで問わなければ、
夫婦として普通迎える、最初の共同作業であることは間違いないです。
当たり前ですが、その共同作業の中で、
この地域コミュニティーが、ほぼ全壊してしまっている都会エリアでは、
当然、昔よりは、過酷な作業になっているのは自明です。
さらに、様々に紹介されている情報は、
どう考えても、企業マーケティングの一環として、提供される情報が過半で、
経済的な格差を、もろに受けてしまう種類のもが多いことも事実で、
それを「緩衝」してくれる、両隣の「知恵袋」は、
昨今の環境では、死滅している状態です。
なもので、家庭という単語よりは、個人的には、
子育てをする、「共同作業体の場」として考えており、
具体的で、リアリティーのない、イメージできないものを
あえて「家庭」とくくる考え方には、
昨今、どうも「負」のイメージが強くなってきております。
本来であれば、そういうんでなくて、
生産的で、ポジティブなイメージを、せっかくやるんだったら考えるべきで、
家庭というよりは、別の考え方があってしかるべきなんじゃないかなぁ、
と思うようになりました。
当然ですが、男女の役割分担は、時代時代の「要請」にしたがって、
むしろ流動的であるのは、大きな歴史の流れの中で、実証済みで、
何が効率がよいのか、それぞれの事情で、これが効率的なのかが問題であって、
これだけ、「餌場」も「餌」も、複雑で、あらゆる手段が講じれる現在、
むしろ、それぞれが、まさに、計画的に、得意な分野でやればいい話で、
今更、家庭に縛り付けるという考え方が、
何を、どう、縛り付けているのかすら、自分は理解しかねます。
好きだから、愛しているからという、いずれは、多分、一方的な思いに
なってしまいがちな、この感情によって、
それが、パートナーの生産性に「効果的」であるならば、
むしろ、家庭に「いる」ことの重要度が高いという判断でしょうし、
まるで逆に、「私が食べさせてあげる」という世界も、
承認しがたいですが、もちろん、それでその関係性が、
生産的で、効率的であるならば、もちろん可でしょう。
そういうことをとっぱずして、家庭に対する考え方。
こういう発想。
前にも言いましたが、共同作業の場ですから、
これを一般論として、男女の役割分担として、
どうしても、考えたくなる気持ちもわかりますが、
もう、さすがに、古い、マッチィングしていない。
ええ、こういう調査事態が、むしろ、マイナスです。
だって、家庭というより、最近は、ファミリーって言うほうが、
何だか、ぱっと、明るい感じがするでしょ?
こういうところから、システムを支えていかなければ、
少子化を考えすぎて、むしろ、少子化に拍車をかける、
いつもの悪い「役人」のあり方が、露になると思いますが。
内閣府が29日発表した男女共同参画社会に関する世論調査によると、「夫は外
で働き、妻は家庭を守るべきだ」との考えに反対する人の割合が52.1%と1992
年の調査開始以来、初めて半数を超えた。賛成は44.8%。内閣府では「男女の
役割分担を固定的に考える傾向に変化がみられる」(男女共同参画局)と分析
している。
ただ現実の家事分担では、妻の仕事として「食事の支度」を挙げたのが
85.6%、「掃除」も75.6%と高い。仕事と家庭のどちらを優先するかでも「仕
事を優先する」は女性の17.3%に対し、男性は40.2%。男女の仕事と家庭に対
する考え方には依然開きがある。
一方、結婚観や家庭観では「結婚しても必ずしも子どもを持つ必要はない」と
の考えに反対の人が59.4%と2004年の前回調査に比べ8.1ポイント上昇。「結
婚しても相手に満足できないときは離婚すればよい」との考えに反対の人も
47.5%と同7.4ポイント上昇し、賛成の46.5%(同4.6ポイント低下)を逆転し
た。
えー、個人的に偏った考え方を持っているようなので、参考にならないと思いますが。
この「家庭を守る」ってなんでしょう。
こういった調査で、必ず項目に入ってくる「家庭を守る」という文言。
この仕事だ、家庭だという「くくり」に、
夫婦間の、人間としての関係が、よく見えてきません。
もう極端なことを言えば、人間観関係は、ある意味大なり小なりの
利害関係で成立していると考えております。
もちろん、純粋な気持ち、例えば好き、愛しているなど、
こういう普遍的な心を否定するつもりはさらさらありません。
ただ、生きていく中で、それぞれのタイミングで、
どうあがいても、大なり小なりの「ミッション」をこなしていくのが人生です。
自分で見つける方もいますし、そして、結果を出せなくて、魂消るような一瞬を
迎える、とほほな私みたいな人間もおりますし、
もちろん、やむなく、降りかかってくる案件を処理しなければならない事も
当然ありますし。
こういうの、一言で言うならば、たった一人では「成立」しない。
全てが、あらゆる人間関係性の中で、起こりうるものだ。
因果関係を含めて。
そういうものだと、理解しております。
で、そういう中で、人それぞれでしょうが、自分は、
人生と言うミッションをこなす上で、パートナーが必要だし、
後出しかもしれないが、
パートナーの存在を、日々、この上なくありがたいものだと、痛感しているわけです。
手近な話で申し訳ないですが、
子を育てるということも、生き物が抱えるミッションですし、
望む、望まないは別に、そういう価値観をここで問わなければ、
夫婦として普通迎える、最初の共同作業であることは間違いないです。
当たり前ですが、その共同作業の中で、
この地域コミュニティーが、ほぼ全壊してしまっている都会エリアでは、
当然、昔よりは、過酷な作業になっているのは自明です。
さらに、様々に紹介されている情報は、
どう考えても、企業マーケティングの一環として、提供される情報が過半で、
経済的な格差を、もろに受けてしまう種類のもが多いことも事実で、
それを「緩衝」してくれる、両隣の「知恵袋」は、
昨今の環境では、死滅している状態です。
なもので、家庭という単語よりは、個人的には、
子育てをする、「共同作業体の場」として考えており、
具体的で、リアリティーのない、イメージできないものを
あえて「家庭」とくくる考え方には、
昨今、どうも「負」のイメージが強くなってきております。
本来であれば、そういうんでなくて、
生産的で、ポジティブなイメージを、せっかくやるんだったら考えるべきで、
家庭というよりは、別の考え方があってしかるべきなんじゃないかなぁ、
と思うようになりました。
当然ですが、男女の役割分担は、時代時代の「要請」にしたがって、
むしろ流動的であるのは、大きな歴史の流れの中で、実証済みで、
何が効率がよいのか、それぞれの事情で、これが効率的なのかが問題であって、
これだけ、「餌場」も「餌」も、複雑で、あらゆる手段が講じれる現在、
むしろ、それぞれが、まさに、計画的に、得意な分野でやればいい話で、
今更、家庭に縛り付けるという考え方が、
何を、どう、縛り付けているのかすら、自分は理解しかねます。
好きだから、愛しているからという、いずれは、多分、一方的な思いに
なってしまいがちな、この感情によって、
それが、パートナーの生産性に「効果的」であるならば、
むしろ、家庭に「いる」ことの重要度が高いという判断でしょうし、
まるで逆に、「私が食べさせてあげる」という世界も、
承認しがたいですが、もちろん、それでその関係性が、
生産的で、効率的であるならば、もちろん可でしょう。
そういうことをとっぱずして、家庭に対する考え方。
こういう発想。
前にも言いましたが、共同作業の場ですから、
これを一般論として、男女の役割分担として、
どうしても、考えたくなる気持ちもわかりますが、
もう、さすがに、古い、マッチィングしていない。
ええ、こういう調査事態が、むしろ、マイナスです。
だって、家庭というより、最近は、ファミリーって言うほうが、
何だか、ぱっと、明るい感じがするでしょ?
こういうところから、システムを支えていかなければ、
少子化を考えすぎて、むしろ、少子化に拍車をかける、
いつもの悪い「役人」のあり方が、露になると思いますが。