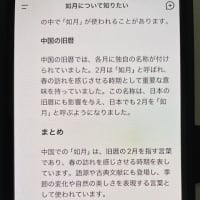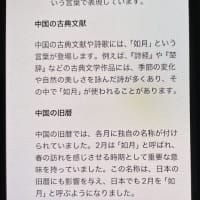進化生物学の枠組み
https://bsd.neuroinf.jp/wiki/%E3%82%A8%E3%83%94%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%8D%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%B9
エピジェネティクス
>
英語名:epigenetics 独:Epigenetik 仏:épigénétique
エピジェネティクスとは、DNAの配列変化によらない遺伝子発現を制御・伝達するシステムおよびその学術分野のことである。すなわち、細胞分裂を通して娘細胞に受け継がれるという遺伝的な特徴を持ちながらも、DNA塩基配列の変化(突然変異)とは独立した機構である。このような制御は、化学的に安定した修飾である一方、食事、大気汚染、喫煙、酸化ストレスへの暴露などの環境要因によって動的に変化する。言い換えると、エピジェネティクスは、遺伝子と環境要因の架け橋となる機構であると言える[1][2]。主なメカニズムとして、DNAメチル化とヒストン修飾がある。
http://10mtv.jp/pc/content/detail.php?movie_id=1619
進化生物学から見る「母親の子殺し」
進化生物学から見た少子化問題(1)近代以前の嬰児殺
長谷川眞理子 長谷川眞理子総合研究大学院大学長
>
誰が生まれてきた子どもの世話をするのか
総合研究大学院大学の長谷川眞理子です。今日は進化生物学から見た親の配偶と繁殖、子育てを土台に、現代社会の虐待や子殺しを普通とは違った目で分析してみたいと思います。動物一般の配偶や子育ての理論的な枠組みに、人間の配偶行動、子育て行動を乗せて考えていきます。
動物は次の瞬間に何をするか、次の一歩をどう踏み出すかを常に選択し、決めなくてはなりません。その意味で、その動物がどう思っているかどうかは別として、全ての動物は意思決定者です。動物の脳は、外部のさまざまな情報を取り入れ、さらに体内の情報も参照して、今何ができるのか、何をすればうまくいくのかを、あるアルゴリズムで判断し、いくつかの選択肢から最適だろうと思われる行動を決めています。誰が生まれてきた子どもの世話をするのかということも、一種の意思決定と考えられます。
もちろん、子育てをまったくしない動物はたくさんいますし、多くの哺乳類のように雌親だけが子育てをして、雄親は何もしないという種も普通にあります。また、受精卵が雌の体から産み落とされて、目の前に卵がある場合、雌だけでも雄だけでも育てることができます。そこで雌がどこかに行ってしまえば、雄親が育てるのです。魚やカエルなどでそうしたケースがよく見られます。両親がともに子育てをするのは、スズメやツバメなどの鳥で有名ですが、キツネやタヌキなど哺乳類の一部にもいます。それから、これは以前に10MTVでお話ししましたが、親だけでなく、血縁があってもなくても周囲の個体が一緒に子育てをする、共同繁殖の種が少しだけ存在します。
ごく一部の動物だけは自分の子どもを殺すことがある
自分の子どもを殺すという行動は、生物学的にはあまり見られません。なぜなら、わが子を殺してしまうことは、自分の遺伝子の継承者を消してしまうことだからです。ただし、よその子を殺すことはしばしば起こります。よその子は自分の遺伝子とは無関係ですから、自分や自分の子とコンフリクトすれば、殺してしまうのです。
例えば、ライオンの雄は群れを乗っ取ったときに、前のライオンの雄が残した個体を全てかみ殺してしまいます。同じように、サルも一夫多妻の雄が追い出されて、新たな雄が妻たちの中に収まるとき、新たな雄は前の雄が残した乳児を殺してしまいます。それは、前の雄の子を育てている間、雌が発情しないからです。新たな雄には雌が離乳するまで繁殖を待っているような暇はありません。自分もいつ新たな雄に追い出されるか分からないからです。短い時間の中で自分の遺伝子を何とかして残すためには、前の雄が残した乳児を殺し、すぐに雌を発情させることが適応的な戦略なのです。それはもちろん、雌や子どもにとっては大迷惑なことですが、雄にとっては進化的に見て広がりをもたらすことになるのです。
例外として、ごく一部の動物だけは、自分の子どもを殺すことがあります。多数回繁殖することができる寿命の長い動物で、次の子育てのチャンスがまだ残されている場合、そのときの子育てがうまくいきそうになければ、子育てをやめることができます。もちろん、子どもができたけれども今はうまく育てられないから捨てようかということは、人間社会の倫理では許されないことですが、生物の行動選択としてはあり得るのです。実際に、子どもを捨てたり、流産したり、子どもを殺したりして、子育てをやめる例があることが知られています。
以下は、ウイキペディアによる。
進化論
>こうした新たな学問分野の確立や研究の進展によって、ダーウィンの自然選択説を基本にしつつ、集団遺伝学、系統分類学、古生物学、生物地理学、生態学などの成果を取り入れて生物の形質の進化を説明することが主流になった。これを総合説(ネオダーウィニズム)と呼ぶ。
>進化論(しんかろん、英: evolution theory)とは、生物が進化したものだとする提唱、あるいは進化に関する様々な研究や議論のことである。
生物は不変のものではなく長期間かけて次第に変化してきた、という仮説(学説)に基づいて、現在見られる様々な生物は全てその過程のなかで生まれてきたとする説明や理論群である。進化が起こっているということを認める判断と、進化のメカニズムを説明する理論という2つの意味がある。なお、生物学における「進化」は純粋に「変化」を意味するものであって「進歩」を意味せず、価値判断について中立的である。
進化は実証の難しい現象であるが(現代では)生物学のあらゆる分野から進化を裏付ける証拠が提出されている。
^ リドレー, マーク 「だれが進化を疑うのか」『生物の進化 最近の話題』 チャーファス, ジェレミー編、松永俊男、野田春彦、岸由二訳、倍風館〈ライフサイエンス教養叢書9〉、1984年(原著1982年)。ISBN 4563039276。
^ Ridley, Mark (2004). Evolution. Blackwell Publishing. ISBN 1405103450.
^ Barton,Nikolas H., Briggs,Derek E.G., Eisen,Jonathan A., Goldstein,David B. & Patel,Nipam H. 『進化 分子・個体・生態系』 宮田隆、星山大介訳、メディカル・サイエンス・インターナショナル、2009年(原著2007年)。ISBN 9784895926218。
^ ドーキンス, リチャード 『進化の存在証明』 垂水雄二訳、早川書房、2009年(原著2009年)。ISBN 9784152090904。
>進化思想、進化理論、進化生物学の歴史、社会や宗教との関わりについて概説する。
なお、生物学において「進化論」の名称は適切ではないため、「進化学」という名称に変更すべきだとの指摘がある。
「進化」「evolution」という語
英語の evolution という語は元来ラテン語起原で、内側に巻き込んでおいたものを外側に展開することを意味しており、現在でも「展開」の意味で使われる。最初にこの概念が生物学に援用されたのは、発生学の前成説においてであり、個体発生に際して「あらかじめ用意された個体の構造が展開生成する」プロセスを指していた。今日の日本語で「進化」と翻訳されるような系統発生のプロセスを指す語としての evolution は、個体発生のこの概念を系統発生に対して援用したものである。みずからの進化論において定められた方向への「進歩」を意図していなかったチャールズ・ダーウィンは、当初かれ自身はこの語を積極的に採用していない。
進化発生生物学
1980年代と1990年代には総合説は詳細な研究に注目した。進化生物学への構造主義的な視点はスチュアート・カウフマンやブライアン・グッドウィンのような生物学者からもたらされた。彼らはサイバネティクスと一般システム理論からアイディアを取り入れて、発生過程における自己組織化機構を強調し、進化にも直接作用する要因であると述べた。スティーヴン・ジェイ・グールドは発達過程における器官ごとの成長率の相対的な差が、進化における新しいボディプランの起源となるのではないかと考え、初期の進化理論の概念であったヘテロクロニーを甦らせた。遺伝学者リチャード・ルウォンティンはある生物の適応が最初から最後まで同じ選択圧の産物として誕生するのではなく、他の適応の偶然の産物として誕生することがあるのではないかと考え1979年に影響力のある論文を書いた。そのような構造の付帯的な変化を彼らはスパンドレルと呼んだ。のちにグールドとヴルバはそのような過程で得られる新しい適応構造を外適応と呼んだ。
>