今日はスタンダードなやつとの味の違いがよくわからないペプシのソルティライチ味です。

本日は第16回私が好きなマンガの話。今回取り上げるのは土田世紀の『編集王』(全16巻・小学館)です。
これはあしたのジョーに憧れてプロボクサーになった青年が、網膜剥離によりライセンスを停止され、どうしていいかわからなくなっていたところを、兄貴分の勧めによって編集者の頂点、“編集王”を目指すことになる・・・という話。マンガ家の裏方である編集にスポットを当てた作品なのですね。
土田さんは熱い男を描くのを得意とされてまして、本作の主人公カンパチこと桃井環八もまた熱血漢。しかしその熱い男をむやみに美化したり、完璧な人間として造形することはなく、情けないところも愚かしいところも含めて描かれています。親しみやすい等身大のキャラを目指したというより、リアリティを追求したのでしょう。
たしか「BSマンガ夜話」だったと思いますけど、ひとつのマンガ作品を徹底的に語りつくすという番組の『編集王』の回で、出演してた大槻ケンヂが、「僕は『編集王』のことを「逆まんが道」と呼んでいる。『まんが道』を読むとマンガ家を目指したくなるけど、『編集王』を読むとやめとこうってなるから」って話してたんですよね。これまさにその通りで。マンガ家ってなんて嫌な仕事なんだろって気分になっちゃうのが『編集王』なんですね。だからね、むしろマンガ家になりたいって人は全員『編集王』を読むべきなんですよ。『まんが道』よりもね。『編集王』を読んで、それでもマンガ家になりたいって人だけが目指すべきなんじゃないかと思います。
僕のお気に入りキャラはマンボ好塚のマネージャーの仙台さん。不遇の身に共感しちゃうというか、仙台さんの若いころのエピソードは一番繰り返し読みました。
作中には見開きで『キャンディキャンディ』が引用されてる箇所があるのですが、ご存じの通り水木杏子さんといがらしゆみこさんが著作権をめぐって争いになり、『キャンディキャンディ』が絶版状態になったために、本作のワイド版と文庫版では当該箇所がまっちろなページになっちゃってます。これもまたマンガをめぐるひとつの事件。完璧な状態を求めるならビッグコミックス版で読みましょう。
『編集王』はドラマ化もされてますが、カンパチ役が原田泰造と聞いたときには思わず膝を打ちました。まさにはまり役。泰造以上にカンパチに似ている芸能人はほかにいませんからね。
作者の土田世紀さんは、2012年に43歳の若さでお亡くなりになりました。もしご存命であったら、あとどれだけの作品を世に送り出すことができたか・・・。合掌。
ここで新型コロナウイルス関連身辺ニュース、および雑感。
セブンイレブンのレジが、自分でお金を投入するタイプに変わっていました。バーコードの読み取りと袋詰めは店員さんがやってくれるんですけど、支払いはセルフレジと同じで、「半セルフレジ」みたいなかんじです。皆さんの近所のコンビニもそうなってますか?たしかロイヤルホストではコロナ以前からそうなってましたけどね。
もちろんこれはコロナ感染防止のために、「非接触」の割合を増やす目的で導入されたものですが、それだけではなく、ボタン押してトレーがチーンって出てくるタイプのレジと違って、お金が取り出しにくくなっているので、強盗しにくいレジ、つまり防犯対策の面でも望ましいレジなのですね。あとお釣りを間違えることがないってのもありますね。
コロナの影響で「非接触」のサービスが拡大しています。感染防止のために、できるだけ人同士が、あるいは店員と客が接触しないで売買を行えるシステムが理想とされており、そのシステムを導入するための技術もすでに確立されているため、いろんなところに非接触型のサービスが普及しつつあるのです。
人と人とのかかわりが希薄になってしまうのは寂しいなあ、なんてジジイみたいな感慨にふけってしまいますけど、この流れはもう不可逆でしょうね。一度導入したシステム・インフラは、コロナが終息したとしても撤去されずに使われ続けるでしょうし、人々の意識の上でもそれが当たり前のものという理解になっていくはずです。非接触型サービスは、コロナ終息後も残るのです。
コロナは人と人の距離を遠ざけ、終息後もなお影響を及ぼし続ける。だとしたら、我々はそれに対抗すべく、距離を近づけるための手段を講じなければならないでしょう。
人付き合いがより希薄になり、少子化がさらに加速するアフターコロナにおいて、拡がってしまった人の間の距離をどう縮めるか。それこそが、「コロナとの闘い第2ラウンド」なのかもしれません。

本日は第16回私が好きなマンガの話。今回取り上げるのは土田世紀の『編集王』(全16巻・小学館)です。
これはあしたのジョーに憧れてプロボクサーになった青年が、網膜剥離によりライセンスを停止され、どうしていいかわからなくなっていたところを、兄貴分の勧めによって編集者の頂点、“編集王”を目指すことになる・・・という話。マンガ家の裏方である編集にスポットを当てた作品なのですね。
土田さんは熱い男を描くのを得意とされてまして、本作の主人公カンパチこと桃井環八もまた熱血漢。しかしその熱い男をむやみに美化したり、完璧な人間として造形することはなく、情けないところも愚かしいところも含めて描かれています。親しみやすい等身大のキャラを目指したというより、リアリティを追求したのでしょう。
たしか「BSマンガ夜話」だったと思いますけど、ひとつのマンガ作品を徹底的に語りつくすという番組の『編集王』の回で、出演してた大槻ケンヂが、「僕は『編集王』のことを「逆まんが道」と呼んでいる。『まんが道』を読むとマンガ家を目指したくなるけど、『編集王』を読むとやめとこうってなるから」って話してたんですよね。これまさにその通りで。マンガ家ってなんて嫌な仕事なんだろって気分になっちゃうのが『編集王』なんですね。だからね、むしろマンガ家になりたいって人は全員『編集王』を読むべきなんですよ。『まんが道』よりもね。『編集王』を読んで、それでもマンガ家になりたいって人だけが目指すべきなんじゃないかと思います。
僕のお気に入りキャラはマンボ好塚のマネージャーの仙台さん。不遇の身に共感しちゃうというか、仙台さんの若いころのエピソードは一番繰り返し読みました。
作中には見開きで『キャンディキャンディ』が引用されてる箇所があるのですが、ご存じの通り水木杏子さんといがらしゆみこさんが著作権をめぐって争いになり、『キャンディキャンディ』が絶版状態になったために、本作のワイド版と文庫版では当該箇所がまっちろなページになっちゃってます。これもまたマンガをめぐるひとつの事件。完璧な状態を求めるならビッグコミックス版で読みましょう。
『編集王』はドラマ化もされてますが、カンパチ役が原田泰造と聞いたときには思わず膝を打ちました。まさにはまり役。泰造以上にカンパチに似ている芸能人はほかにいませんからね。
作者の土田世紀さんは、2012年に43歳の若さでお亡くなりになりました。もしご存命であったら、あとどれだけの作品を世に送り出すことができたか・・・。合掌。
ここで新型コロナウイルス関連身辺ニュース、および雑感。
セブンイレブンのレジが、自分でお金を投入するタイプに変わっていました。バーコードの読み取りと袋詰めは店員さんがやってくれるんですけど、支払いはセルフレジと同じで、「半セルフレジ」みたいなかんじです。皆さんの近所のコンビニもそうなってますか?たしかロイヤルホストではコロナ以前からそうなってましたけどね。
もちろんこれはコロナ感染防止のために、「非接触」の割合を増やす目的で導入されたものですが、それだけではなく、ボタン押してトレーがチーンって出てくるタイプのレジと違って、お金が取り出しにくくなっているので、強盗しにくいレジ、つまり防犯対策の面でも望ましいレジなのですね。あとお釣りを間違えることがないってのもありますね。
コロナの影響で「非接触」のサービスが拡大しています。感染防止のために、できるだけ人同士が、あるいは店員と客が接触しないで売買を行えるシステムが理想とされており、そのシステムを導入するための技術もすでに確立されているため、いろんなところに非接触型のサービスが普及しつつあるのです。
人と人とのかかわりが希薄になってしまうのは寂しいなあ、なんてジジイみたいな感慨にふけってしまいますけど、この流れはもう不可逆でしょうね。一度導入したシステム・インフラは、コロナが終息したとしても撤去されずに使われ続けるでしょうし、人々の意識の上でもそれが当たり前のものという理解になっていくはずです。非接触型サービスは、コロナ終息後も残るのです。
コロナは人と人の距離を遠ざけ、終息後もなお影響を及ぼし続ける。だとしたら、我々はそれに対抗すべく、距離を近づけるための手段を講じなければならないでしょう。
人付き合いがより希薄になり、少子化がさらに加速するアフターコロナにおいて、拡がってしまった人の間の距離をどう縮めるか。それこそが、「コロナとの闘い第2ラウンド」なのかもしれません。










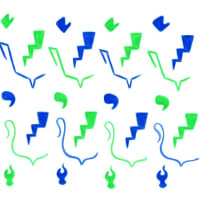

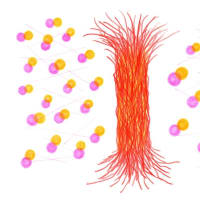





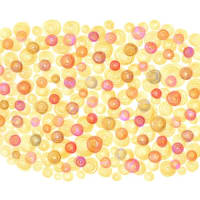

あ、コミックスは3巻ぐらいで読むのやめましたけど(もっと読んだかな???つまらなすぎてやめたけど)
まあ、一つのウイルスで騒いでるような社会なら、いっそアレしたほうがいいのかもしれないとも思いますね
映像化もされてますけどそんなにつまんないんですか?
コミックは、とにかく毎回悩んで、描いて、人気が出て、描いて、悩んで・・・で、ちょっとしたトラブルがあって・・・
の繰り返しで飽きました
そういうマンネリズムがいいって人もいますけどね。
それでずっと続いてるマンガもありますし。