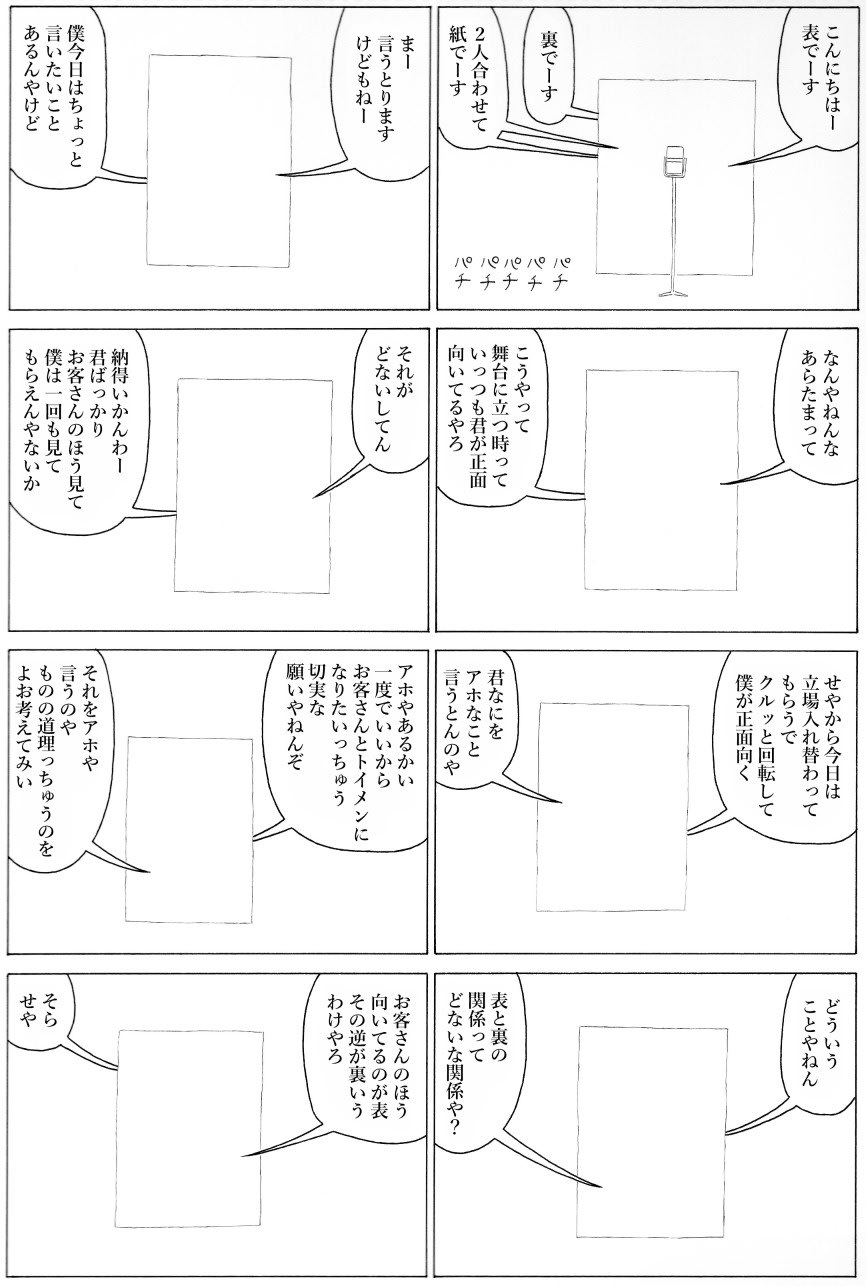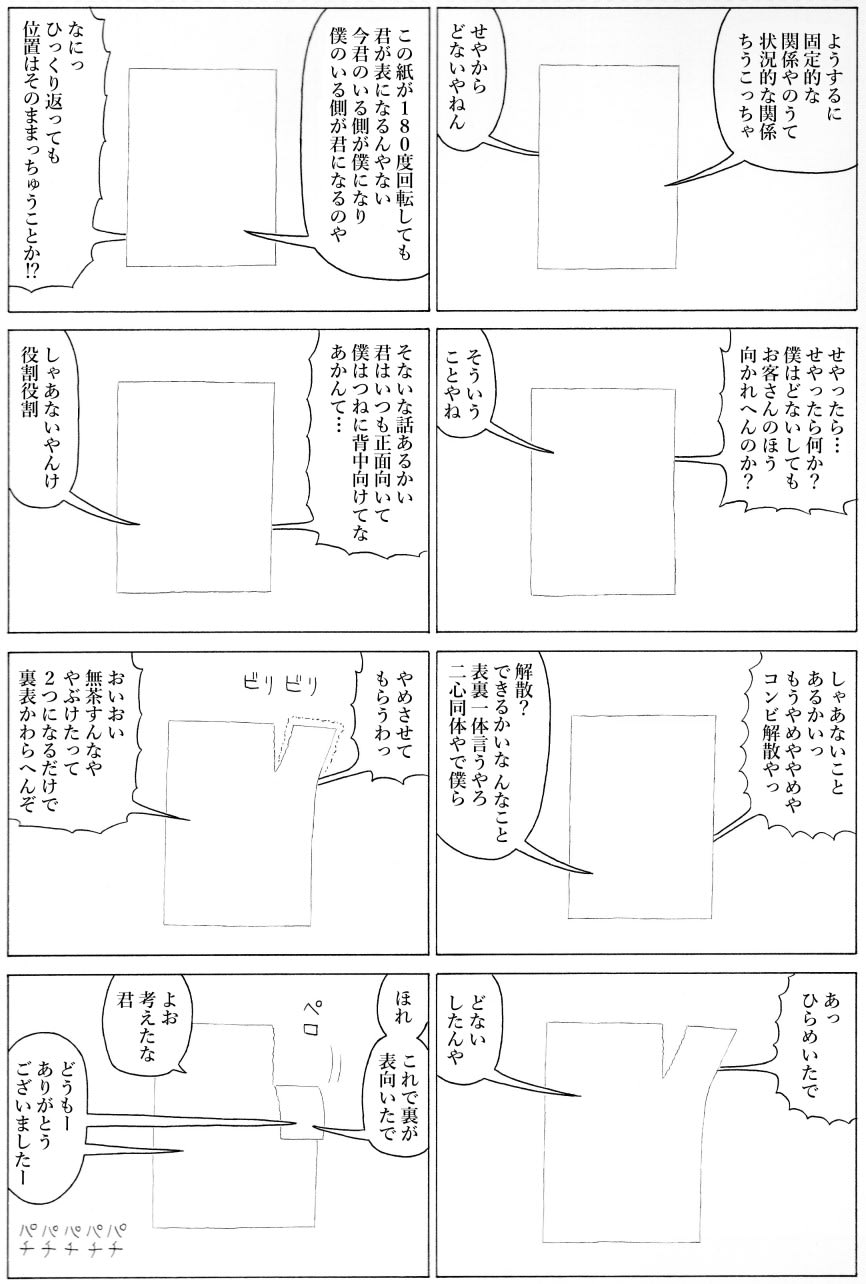新しいカテゴリー「雑考」始めます。これはどんなジャンルなのかといいますと、「雑文未満の思考の記録」です。雑文はひとつの読み物として、起承転結や序破急といった全体性、完結したまとまりをもった文章になるよう仕上げているのですが、何かしらのアイディアがあったとしても、そのような文章のかたちをとるまでには至らない細かいものもあるのです。
なので、それらの断片的な思考を記録してとどめておこう、というのがこの「雑考」なのです。
自身にとっては備忘録として、皆様におかれましては考えるヒントになれば、と考えております。
それでは第一回目、始まります。
金成陽一の『誰が「赤ずきん」を解放したか』(大和書房)を読んでの気付き。
これは、グリム童話の「赤ずきんちゃん」がどのように語られてきたか、物語が書かれた時代背景がどのように反映されているか、類似の童話(物語)との相違点は何か、といったことが書かれた本である。頭巾の赤い色は初潮の比喩であることや、狼とは性的に誘惑する男の象徴であること、狼に食べられてその後お腹から出てくるというのは、性体験を経て大人の女性として生まれ変わることを意味しているなど、興味深い分析が盛り込まれている。
その中で特に印象に残ったのが次の箇所。狼は夜の象徴でもあるという説を紹介したあとの発言。引用文中に引用文が含まれているので少しややこしいことをお詫びしておく。
つまり、狼は「薄暗がりの狩人」であり、闇と光の中間、暁と黄昏時に出現するのだ。フランス語には、黄昏時を「イヌとオオカミの間」(Entre Chien et loup.)とよぶ面白い表現があるという。
林勝一氏は『ゴールの雄鶏』の中で、「『イヌとオオカミの間』という奇妙な表現が生まれたのも、かつてオオカミが山や森に数多く潜んでいた時代には、あたりが暗くなってきて、ふと現れた動物がイヌなのかオオカミなのか見分けがつかなくなるとき、それは人間にとっては、きわめて危険な、それこそ運命の『分かれ道』となるときだったからだろう。この表現はすでに紀元前二世紀のヘブライ語の文献に『人間がイヌとオオカミを区別できなくなる時』というかたちで記録されている」と述べている。
日本でも夕暮れ(薄暮)を「逢魔が時」と呼ぶ。それは人間の視認能力が曖昧になり、交通事故が起きやすい時間帯でもある。「魔と出逢う」などと言えば単なる迷信とか、前近代的だなどと思われがちだが、もっと具体的で現実的な、危険な野生生物に遭遇しかねない時間帯だという教訓であったのだろう。過去の日本において、狼――かつて生息していたニホンオオカミ――や熊といった野生生物と接触する確率がどれくらいのものであったかはわからない。だが狼や熊のような特別な動物のみならず、ごく普通の犬であっても人間にとっては危険な生物であった。今日の日本ではすっかり忘れられてしまったことだが、かつて狂犬病という病気があり、ワクチンが開発される以前、野犬に噛まれるということは、極めて致死率の高い病に侵されるということであったからだ(今はもう野良犬すらいないからね。90年代ぐらいまではいたかな)。あるいは、野生生物のみならず、借金取りのような好ましくない人物に捕まってしまう恐れがある、という意味合いもあったのかもしれない。
魔というのは、わりと身近に潜んでいるものなのである。