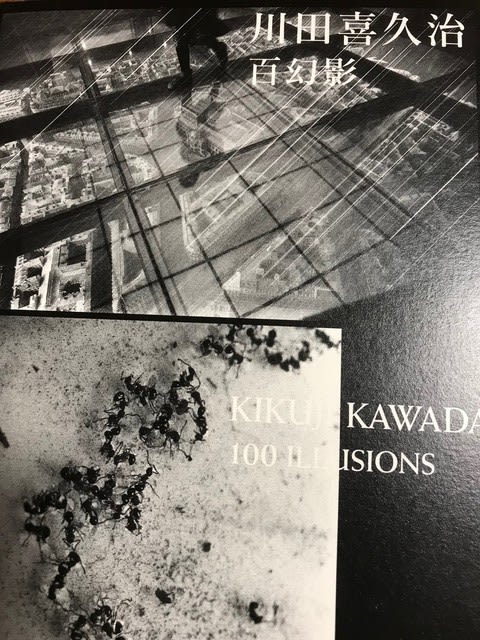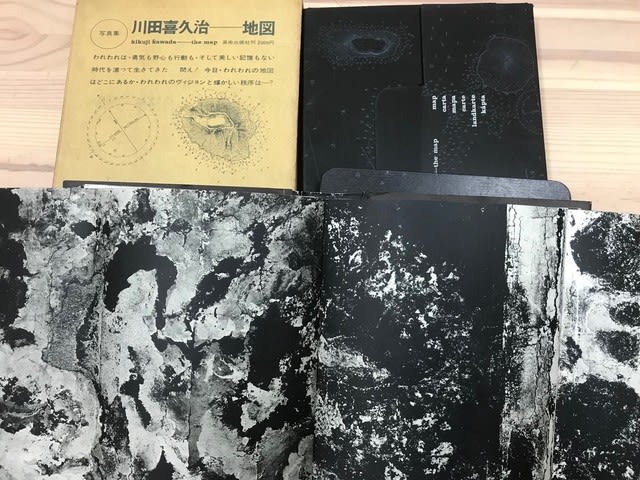11月11日から20日にかけてパリを訪れた。ヨーロッパの旅は初めてで不安もあったが、幸い友人のS氏がパリに長期滞在していて案内をしてくれるというので、半年以上前からの計画を実行することになった。S氏は7年前にもヨーロッパに1年間滞在したことがあり、パリにも半年いてパリのことをよく知っている。今回は約1ヶ月の滞在で、前と同じモンマルトルの中腹にあるアパルトマンを借りて生活しているという。
S氏とは到着の翌日に落ち合い、早速アパルトマンを訪ねることになった。モンマルトルというとパリ有数の観光地でおしゃれな名前と思われるかも知れないが、その名の由来はMont des Martyrs(殉教者の丘)で、キリスト教受難の歴史を物語る。
モンマルトルは19世紀から20世紀にかけて一大歓楽街となり、ムーラン・ルージュ(今も健在である)などのキャバレーや、シャ・ノワール(カフェだったという)に、退廃的な芸術家達が集うようになる。ロートレックの描いたあの世界である。
モンマルトルに登るにはケーブルカーもあるが、標高がたった130メートル(それでもパリで一番高い)しかないので、歩いて登る。S氏の案内で途中、ピカソやモジリアーニなどが住んだBateau-Lavoir(洗濯船)の跡やゴッホ兄弟が住んだ建物などを見学しながら、モンマルトル美術館へ。19世紀のモンマルトルの文化や歴史を紹介するその美術館は古い邸宅を改造したもので、偉大な作品はないが、古き良き時代の雰囲気を濃厚に伝えている。

頂上のサクレ・クール寺院を目指す。寺院脇に小さな広場があり、その周りを土産物店やカフェなどが取り囲んでいる。公園には似顔絵描きの芸術家達が観光客を捕まえている。似顔絵ではなく風景画で勝負の本格派もいるが、中には「おれは土産物の風景画なんか描かないぞ」といった感じで、抽象画とすれすれの表現をねらっている自己主張派もいた。

サクレ・クール寺院は美しい教会である。1914年に完成したまだ新しい建物のせいもあるが、遠望もきれいだし、近くで見てもその均整の取れた構造に魅せられてしまいそうになる。正面に展望台があって、パリ市街を一望できる。観光客はここで記念写真を撮ることになっている。私は近くの空き地の切り株に巨大なマスタケを見つけたのでカメラに納めた。パリのキノコ好きなら大喜びするだろうに。

ここにサルバドール・ダリの美術館があり、S氏の目的の一つがそれであった。正式名称はエスパス・ダリ・モンマルトル。小さな館だが、展示作品は意外に多く、彫刻から絵画、ポスター、イラストなど収蔵品も幅広い。そして一番特徴的なのはダリの狂気の世界を濃厚に示しているところだろうか。
そこでリトグラフ作品に見とれていると、若い美人の館員がファイルに納められた原画の数々を見せてくれるというのである。巨大なファイルに入った作品を一枚一枚開いて、場合によってはファイルから取り出してまで見せてくれた。どこの美術館がこんなサービスをしてくれるというのだろう。ダリに関しては油絵以外の絵画は未見の世界であり、とても嬉しかった。
S氏の目的はもう一つ。モンマルトルの麓に美術館があり、そこで日本人のグループが面白そうな展覧会をやっているからそれを観に行こうというのである。私はそれがいったい何であるのかまったく分からずに、その美術館の前に立つことになった。

サクレ・クール寺院を正面から見上げる麓の街並みの一角に、円形の建物があり、Halle Saint Pierreの名前がある。そして正面の看板にはArt brut Japonaisの文字が。私は思わず絶句してしまった。「これがあのアル・サン・ピエール美術館か。でもなんで今頃日本のアール・ブリュットをここでやっているんだろう」。
実はここは8年前の2010年、「アール・ブリュット・ジャポネ展」が開かれたその場所であったのだ。私はタイムスリップにでも巻き込まれたような奇妙な感覚に捕らわれてしまっていた。(柴野)
S氏とは到着の翌日に落ち合い、早速アパルトマンを訪ねることになった。モンマルトルというとパリ有数の観光地でおしゃれな名前と思われるかも知れないが、その名の由来はMont des Martyrs(殉教者の丘)で、キリスト教受難の歴史を物語る。
モンマルトルは19世紀から20世紀にかけて一大歓楽街となり、ムーラン・ルージュ(今も健在である)などのキャバレーや、シャ・ノワール(カフェだったという)に、退廃的な芸術家達が集うようになる。ロートレックの描いたあの世界である。
モンマルトルに登るにはケーブルカーもあるが、標高がたった130メートル(それでもパリで一番高い)しかないので、歩いて登る。S氏の案内で途中、ピカソやモジリアーニなどが住んだBateau-Lavoir(洗濯船)の跡やゴッホ兄弟が住んだ建物などを見学しながら、モンマルトル美術館へ。19世紀のモンマルトルの文化や歴史を紹介するその美術館は古い邸宅を改造したもので、偉大な作品はないが、古き良き時代の雰囲気を濃厚に伝えている。

下から見上げたサクレ・クール
頂上のサクレ・クール寺院を目指す。寺院脇に小さな広場があり、その周りを土産物店やカフェなどが取り囲んでいる。公園には似顔絵描きの芸術家達が観光客を捕まえている。似顔絵ではなく風景画で勝負の本格派もいるが、中には「おれは土産物の風景画なんか描かないぞ」といった感じで、抽象画とすれすれの表現をねらっている自己主張派もいた。

広場の絵描き達
サクレ・クール寺院は美しい教会である。1914年に完成したまだ新しい建物のせいもあるが、遠望もきれいだし、近くで見てもその均整の取れた構造に魅せられてしまいそうになる。正面に展望台があって、パリ市街を一望できる。観光客はここで記念写真を撮ることになっている。私は近くの空き地の切り株に巨大なマスタケを見つけたのでカメラに納めた。パリのキノコ好きなら大喜びするだろうに。

これがマスタケ
ここにサルバドール・ダリの美術館があり、S氏の目的の一つがそれであった。正式名称はエスパス・ダリ・モンマルトル。小さな館だが、展示作品は意外に多く、彫刻から絵画、ポスター、イラストなど収蔵品も幅広い。そして一番特徴的なのはダリの狂気の世界を濃厚に示しているところだろうか。
そこでリトグラフ作品に見とれていると、若い美人の館員がファイルに納められた原画の数々を見せてくれるというのである。巨大なファイルに入った作品を一枚一枚開いて、場合によってはファイルから取り出してまで見せてくれた。どこの美術館がこんなサービスをしてくれるというのだろう。ダリに関しては油絵以外の絵画は未見の世界であり、とても嬉しかった。
S氏の目的はもう一つ。モンマルトルの麓に美術館があり、そこで日本人のグループが面白そうな展覧会をやっているからそれを観に行こうというのである。私はそれがいったい何であるのかまったく分からずに、その美術館の前に立つことになった。

アル・サン・ピエールの外観
サクレ・クール寺院を正面から見上げる麓の街並みの一角に、円形の建物があり、Halle Saint Pierreの名前がある。そして正面の看板にはArt brut Japonaisの文字が。私は思わず絶句してしまった。「これがあのアル・サン・ピエール美術館か。でもなんで今頃日本のアール・ブリュットをここでやっているんだろう」。
実はここは8年前の2010年、「アール・ブリュット・ジャポネ展」が開かれたその場所であったのだ。私はタイムスリップにでも巻き込まれたような奇妙な感覚に捕らわれてしまっていた。(柴野)