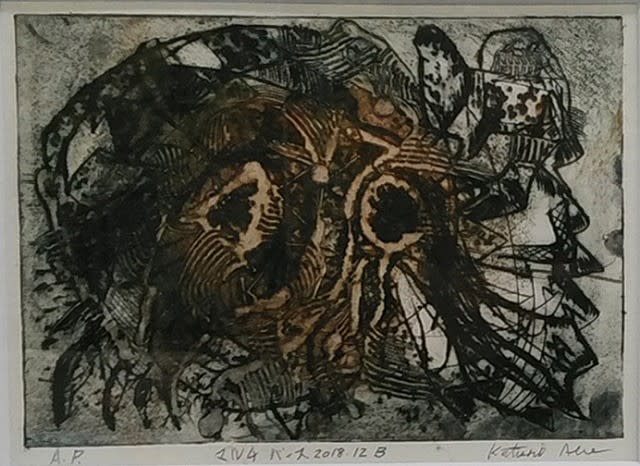ユベール・ロベール「ローマのパンテオンのある建築的奇想画」(1763)
東京渋谷区の松濤美術館「終わりのむこうへ 廃墟の美術史」展。ピラネージにユベール・ロベール、ポール・デルボー、片や日本の野又穣や元田久治――「廃墟」といえば真っ先に思い浮かぶこれらの作家たちが一堂に会するらしい。これは見逃すわけにはいかないと思いつつ、ようやく観ることが出来たのは最終日だった。案の定カタログは完売だった。
コンパクトにまとまった、静かな落ち着いた展覧会であった。それもまた「廃墟」がもたらすのであろう。しかしそれだけではない。どこか既視感がある。作品は全て国内にあるものばかり、しかも別々のテーマ展で観たものも多数含まれている。もちろんそれでがっかりしたということではない。ピラネージもデルボーも何度観ても見飽きることなく、その都度発見させられることもある。
やはり国内にある作品ということで、日本の作家については「こんな人まで」と思うものまで、よく集められていた。亜欧堂田善や歌川豊春に始まり、藤島武二や難波田龍起、シュルレアリスムの作家たちを経て、大岩オスカールや野又穣、元田久治といった現代画家まで見比べていくと、日本の廃墟の「とらえ方」の系譜が一望できる。すなわち、西欧の廃墟画のイメージを借りたり、海外で見た廃墟を写生したり、といったことから始まり、現代は、ほとんど空想的な崩壊感覚、あるいは未来の終末的な光景として描かれているのである。
ここで見えてくるのは、廃墟の持つ歴史的時間感覚の決定的な欠如ではないか。紀元前からの石の建造物が遺る西欧と違って、日本には廃屋こそあれ、廃墟の歴史は皆無と言ってよい。少年期に敗戦を体験した建築家・磯崎新は「廃墟とはすぐれて西欧的な概念である」とし、その異質性を自覚しつつ、焼け野原の「空虚」を「廃墟」と結びつけ、「建築」がそもそも内包する「廃墟」を見据えながら建築家としてスタートした。廃墟ブームと言われる昨今だが、大岩も野又も元田も、震災後の茫漠たる荒野を連想させたり、未完の巨大な建築物や現存の都市を崩壊させているのだ。シャトーブリアンは廃墟を「時の仕業」と「人間の仕業」に二分し、後者には前者のような「特殊な美」がなく虚無的なだけだと言っている。シャトーブリアン流に言えば、日本では「人間の仕業」としての廃墟の方がイメージしやすかったということだろうか。それも、都市や建造物が巨大になればなるほど、まるで臨界に達したかのようにほころび、崩壊していく様は、何かしら予兆的で無気味でさえある。
一方、廃墟の歴史や時間を体感してきた西欧では、廃墟画の歴史も古く、表象としてだけでなく、内面的に深く掘り下げられ様々に展開させてきた。前述の通り、別の切り口で観てきた作品が多いということは、それだけ廃墟のとらえ方も多様だということでもあるが、今展ではその多様性のままに拡散し、枝葉は全て中途半端なところで断ち切られている感が否めない。国内作品に限られていることの限界でもあるが、「廃墟の美術史」と銘打っているからには物足りなさを禁じ得ない。期待していたユベール・ロベールはチラシ掲載の一点だけだったし、時代的には20世紀は、デルボー以外はマグリットとキリコが一点ずつで、こちらも日本とのバランスを欠く。
不染鉄の作品は廃墟ならぬ「廃船」(1969)だ。画面上部に巨大な赤錆た船、下方に貧しい民家の家並み。直接の影響関係は不明だがカスパー・ディービッド・フリードリッヒの「氷海」を思い出す。フリードリッヒは、時代の裂け目をのぞき込み、自らの孤独を託したような廃墟画を描く、やはり重要な作家だ。また元田久治の、植物が繁茂し始めた国会議事堂の鳥瞰図など、ジョセフ・マイケル・ガンディを連想せずにはいられないし、野又穣や元田久治の想像世界が巨大化するほどに、ジョン・マーティンの作品をみたくなる。また、彼らと同時代の、即ち現代の海外作家の「廃墟」と並べてみたい。これらの作家の出展は、ない。

フリードリッヒ「氷海」(1823,24頃)

ピラネージ『ローマの古代遺跡』より「古代アッピア街道とアルデアティーナ街道の交差点」(1756)
私にとってはそうした未完の展覧会ではあったが、改めてピラネージの圧倒的な存在感、真の廃墟の作家たるところを感じる展覧会となった。『ローマの古代遺跡』より「古代アッピア街道とアルデアティーナ街道の交差点」、『ローマの景観』より「シビラの神殿、ティヴォリ(背後から)」など合わせて5点の展示だが、壮大で壮麗、記憶の奥底を揺さぶる空虚と退嬰。語りかけてくる歴史の時間。剥がし、抉り、腑分けする解剖学のような精緻にしてグロテスクな視線。ビジョンとしての廃墟。―小さな画面には「廃墟」がもたらすあらゆるイメージが詰まっている。(霜田文子)