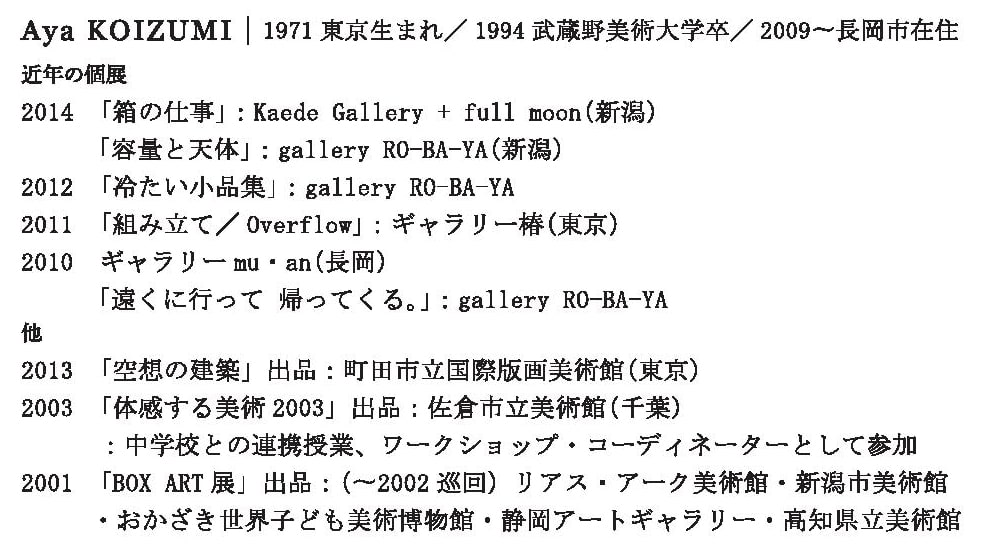游文舎七周年記念企画のコイズミアヤ展「充満と空虚」では、9つの白い箱形の作品が並んだ。すべて揃えたのは2005年の初展示以来とのこと。10年ぶりの再展示にあたり、コイズミさんはそれぞれのイメージからのドローイングを添えた。言葉と立体とを往還しつつ構築していくようなコイズミさんの造形世界に、さらに平面作品が加わり、ギャラリーは重層的な思考空間へと変貌した。
初めて実物を見たときのことを思い出す。不思議な体験だった。それまで写真でしか見たことがなく、螺旋階段は天空へ向かうようだし、大気の塊が家を蔽っていくようで、大きな楼閣のような作品をイメージしていたが、実は40㎝四方、高さ35㎝ほどの箱の内部だったのである。具象的な椅子や階段や家を実際の比例を無視して配し、さらに抽象的な形も組み合わせることによって錯覚させられていたのだった。それらは周到な設計図によって作られているのだが、そうした作為を感じさせない、静穏で、既視感を伴う、白日夢のような世界でもあった。
箱の四辺それぞれの中央に、下方から、あるいは上方から切り込みのような細い長方形の開口部がある。門を思わせる。箱の中に入り込み、夢想を妨げることのない入り口としての門。さらにはそこを通り抜け、次の箱へと誘う門。もちろんあくまでも視覚と意識だけをくぐらせるものではあるけれど。それぞれタイトルを付された9つの箱の中央は「聖なる山」。マンダラのように配された箱を逍遙していくと、いつしか内部と外部(見る人)は一体となり、原初的で普遍的な祈りや瞑想の空間にいるような感覚を覚える。
1996年の初個展からの制作ファイルを見る。展示の度に、テキストも添えられている。コイズミさんにとって、作品とテキストは不即不離なのだ。
「私は世界を箱にしまい込もうとしている。・・・箱に直接手を触れて開いてもらうことによって、具体的で個人的な出会いの場と時間を共有することができるように。そして箱は普段は閉じられていることによって、世界はいつも内側に在ることを表していた。」(初個展の時のテキストより)
このとき「小さな門(とびら)」という作品も出品されている。テキストを読むうち、「門」「開いて」「時間」「閉じられ」等、「もんがまえ」の文字が多いことに気がついた。さらに読み進むと「門」「開」「閉」「間」「閃」「関」「闇」「聞」・・・と、「もんがまえ」の文字だけが、文脈や言葉から独立し、意味から離れて紙面から浮き上がり、箱形の立体物のように立ち上がって来るのだった。


初めて実物を見たときのことを思い出す。不思議な体験だった。それまで写真でしか見たことがなく、螺旋階段は天空へ向かうようだし、大気の塊が家を蔽っていくようで、大きな楼閣のような作品をイメージしていたが、実は40㎝四方、高さ35㎝ほどの箱の内部だったのである。具象的な椅子や階段や家を実際の比例を無視して配し、さらに抽象的な形も組み合わせることによって錯覚させられていたのだった。それらは周到な設計図によって作られているのだが、そうした作為を感じさせない、静穏で、既視感を伴う、白日夢のような世界でもあった。
箱の四辺それぞれの中央に、下方から、あるいは上方から切り込みのような細い長方形の開口部がある。門を思わせる。箱の中に入り込み、夢想を妨げることのない入り口としての門。さらにはそこを通り抜け、次の箱へと誘う門。もちろんあくまでも視覚と意識だけをくぐらせるものではあるけれど。それぞれタイトルを付された9つの箱の中央は「聖なる山」。マンダラのように配された箱を逍遙していくと、いつしか内部と外部(見る人)は一体となり、原初的で普遍的な祈りや瞑想の空間にいるような感覚を覚える。
1996年の初個展からの制作ファイルを見る。展示の度に、テキストも添えられている。コイズミさんにとって、作品とテキストは不即不離なのだ。
「私は世界を箱にしまい込もうとしている。・・・箱に直接手を触れて開いてもらうことによって、具体的で個人的な出会いの場と時間を共有することができるように。そして箱は普段は閉じられていることによって、世界はいつも内側に在ることを表していた。」(初個展の時のテキストより)
このとき「小さな門(とびら)」という作品も出品されている。テキストを読むうち、「門」「開いて」「時間」「閉じられ」等、「もんがまえ」の文字が多いことに気がついた。さらに読み進むと「門」「開」「閉」「間」「閃」「関」「闇」「聞」・・・と、「もんがまえ」の文字だけが、文脈や言葉から独立し、意味から離れて紙面から浮き上がり、箱形の立体物のように立ち上がって来るのだった。