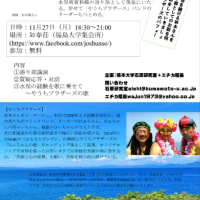國分功一郎さんがソウル大学のドゥルーズワークショップで発表した論文「How to read Deleuze」
を読んだ。まず驚いたのはGoogle翻訳の読みやすさ。翻訳ソフトが進化してることを実感した。
しかし一方、これはもしかすると 「國分功一郎的なことば」
が持つ圧倒的な読みやすさの効果なのかもしれない。Google翻訳にとっても國分さんの文章は読みやすい、のだとしたら、これはスゴいことですね(^_^)
http://www.academia.edu/35744293/How_to_read_Deleuze_neurosis_schizophrenia_and_autismhttp://www.academia.edu/35744293/How_to_read_Deleuze_neurosis_schizophrenia_and_autism
内容は、19世紀を象徴する 「病い」が神経症(フロイトによる)であり、20世紀を象徴するそれが統合失調症(ラカン←ドゥルーズ=ガタリが前景化した)であったとするなら、21世紀を象徴する「障害」は自閉症(ドゥルーズによる)である、という枠組みが作業仮説として成立するのでは?というお話。
(フロイトはいいとして)もちろんラカンの 「原抑圧」とかドゥルーズの 「無人島」とか理解しなければならない概念はあるけれど、とても興味深い。
ちなみに、もう少し正確に言えば
神経症→フロイト
統合失調症→ガタリ(ラカンから別れての)
自閉スペクトラム症→ドゥルーズ
という感じになる(読み返してみたら)。
フロイトからラカン、
ラカンからガタリ、
ガタリとドゥルーズ
という流れはもちろん切断されつつもつながっているから、そのあたりの丁寧な表現の機微は直接本文を当たってほしい。
ガタリとドゥルーズの分離は國分さんがいつもちょっと触れていた話だが、ここではよりはっきりと示されている印象を持った。
千葉雅也『動きすぎてはいけない』
國分功一郎『ドゥルーズの哲学原理』
村上靖夫『自閉症の現象学』を
復習読みしたくなった。
を読んだ。まず驚いたのはGoogle翻訳の読みやすさ。翻訳ソフトが進化してることを実感した。
しかし一方、これはもしかすると 「國分功一郎的なことば」
が持つ圧倒的な読みやすさの効果なのかもしれない。Google翻訳にとっても國分さんの文章は読みやすい、のだとしたら、これはスゴいことですね(^_^)
http://www.academia.edu/35744293/How_to_read_Deleuze_neurosis_schizophrenia_and_autismhttp://www.academia.edu/35744293/How_to_read_Deleuze_neurosis_schizophrenia_and_autism
内容は、19世紀を象徴する 「病い」が神経症(フロイトによる)であり、20世紀を象徴するそれが統合失調症(ラカン←ドゥルーズ=ガタリが前景化した)であったとするなら、21世紀を象徴する「障害」は自閉症(ドゥルーズによる)である、という枠組みが作業仮説として成立するのでは?というお話。
(フロイトはいいとして)もちろんラカンの 「原抑圧」とかドゥルーズの 「無人島」とか理解しなければならない概念はあるけれど、とても興味深い。
ちなみに、もう少し正確に言えば
神経症→フロイト
統合失調症→ガタリ(ラカンから別れての)
自閉スペクトラム症→ドゥルーズ
という感じになる(読み返してみたら)。
フロイトからラカン、
ラカンからガタリ、
ガタリとドゥルーズ
という流れはもちろん切断されつつもつながっているから、そのあたりの丁寧な表現の機微は直接本文を当たってほしい。
ガタリとドゥルーズの分離は國分さんがいつもちょっと触れていた話だが、ここではよりはっきりと示されている印象を持った。
千葉雅也『動きすぎてはいけない』
國分功一郎『ドゥルーズの哲学原理』
村上靖夫『自閉症の現象学』を
復習読みしたくなった。